 |
意見書
私的録音録画小委員会
主査 中山 信弘 様
2007年6月25日
日本音楽作家団体協議会
常任理事 小六 禮次郎
2007年6月15日開催の私的録音録画小委員会配付資料1について以下のとおり意見を申し述べます。
パソコンやポータブル・オーディオ・レコーダが私的録音録画の主流となりはじめてからこれまでの間、私たちが心をこめて創った音楽は、大量に且つ無償で私的録音録画されてきました。
こうした実態を背景に、2005年度の法制問題小委員会以降、一日も早く実際に私的録音録画に供される機器・記録媒体を私的録音録画補償金支払いの対象としていただくよう要望してきたわけですが、なかなか具体的な制度の話までたどり着くことができませんでした。
それでも漸く資料1のような私的録音録画補償金制度(以下「補償金制度」といいます)の制度設計が示され、具体的な検討ができる状態になったことについては、非常に大きな一歩であると評価しております。
しかし、内容を細かくみてまいりますと、私たちへの補償がより適切になされるよう検討いただきたい点が多々あります。特に今回の制度の見直しに当たって大切なことは、わが国の私的録音録画の規模に応じて適切な権利保護が行われることです。
この趣旨に基づき、資料に沿って意見を申し述べさせていただきます。
| 1 |
|
前提条件の整理について
アについては、ベルヌ条約9条2項のスリーステップテストにおいても、著作物の通常の利用を妨げているといえるので、著作権法30条の範囲から除外すべきです。
イについては、除外された後のルール作りが円滑に整うかどうかについて若干懸念されるところがありますので、関係者の理解を十分得たうえで除外していただきたいと考えます。
| ○ |
|
著作権保護技術の進展により補償金制度が不要となるのは、著作権保護技術により私的複製がすべて禁止される場合か、すべてに課金できるようになる場合のいずれかだけです。 |
著作権保護技術が一体いつ効果的な進展を示すのでしょうか。私には全く予想がつきません。
ただ、そうだとしても著作権保護技術と補償金制度が併存可能であることは、これまでの検討からも明らかですし、むしろ併存すべきものであることはなんら否定するものではありません。そして、補償金は前提ですが、大量の私的録音録画が短時間に可能なデジタルの世界では、一定の回数等に関する秩序、即ち30条の範囲内の複製に留めるための上限ルールは不可欠であると考えております。
さらにいえば、その場合においても、嘗てパソコンの登場によってSCMSが無効化されてしまった経験に鑑み、上限ルールとしての著作権保護技術が勝手に無効化されてしまわないよう法律で規定する等保証が必要であると考えます。
|
| 2 |
私的録音録画補償金制度の基本的なあり方について
| ○ |
|
制度設計の大枠としては、(1)アの「録音録画機器・記録媒体の提供という行為に着目した制度設計」を採用すべきです。 |
イについては、「私的録音録画問題の本質」に立ち返って検討し直さなければならないものと考えますが、制度の見直しは緊急を要しており、現段階でこうした根本の転換を図ることは現実的ではありません。現段階ではやはり、既に長期にわたる運用実績のある文化先進諸外国の例に倣い、(1)アを採用することが望ましいと考えます。
| ○ |
|
対象機器・記録媒体の範囲は見直し、私的録音録画に供される機器・記録媒体の全てが対象となるような制度設計とすべきです。 |
今回の見直しの最も重要な点は、従来の補償金制度が専用機器・記録媒体のみを対象としていたことが問題であったことを認識し、この状況を改善することです。
TVの「6つのチャンネルを連続録画できるAVサーバー」機能付パソコンや、「新しい音楽ライフ HDオーディオコンピューター」等、大容量を武器に大量の私的録音録画行為が可能であることを売り物にしているパソコン、音楽ケータイ等は音楽の利用を重要な前提としている点で専用機器・記録媒体となんら変わりありません。
さらに、資料1にいう「汎用機器(録音録画が主たる用途)」も「汎用機器(録音録画が主たる用途でない)」も、そのような区別をする意味がわかりません。どちらの機器を用いても、私的録音録画した場合の利用の実態は同じです。もはや専用と汎用を区別することに意味がなくなってきているのです。
以下の私的録音の関係を示した図をご覧ください。
図
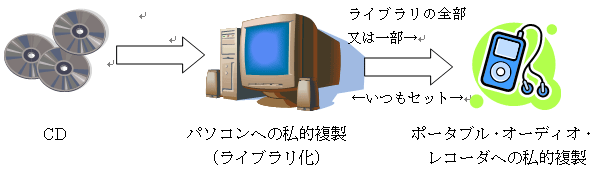
現在ポータブル・オーディオ・レコーダで行われている私的録音は、普通まずパソコンに私的録音され、ライブラリ化されます。そのライブラリの全部又は一部がポータブル・オーディオ・レコーダに私的録音されるのです。つまり、私的録音の量で比較すると、
パソコン ポータブル・オーディオ・レコーダ ポータブル・オーディオ・レコーダ |
という式が成り立つ関係にあります。
この場合、パソコンとポータブル・オーディオ・レコーダが私的録音補償金の対象となる、ならないで違いがあるのはおかしい、ということがおわかりいただけると思います。
こうした現実を踏まえ、公平な取扱いを実現するのであれば、どんな用途に用いられるものも、私的録音録画に用いることができるものは私的録音録画補償金の対象としておいて、補償金の額の設定において実態を反映すべきである、と考えます。
参考までに、補償金制度を有する文化先進諸国における音楽用CD-R/RWと代表的な汎用媒体であるデータ用のCD-R/RWについて興味深いデータ(収集できた国のみ)がありますので、ここに掲載します。
| 2006年度各国音楽用・データ用CD-R/RW補償金入金実績 (単位:千円) |
| 国名 |
音楽用 |
データ用 |
合計 |
比率(注1) |
備考 |
| フランス |
312,393 |
8,756,591 |
9,068,984 |
3.4パーセント |
|
| イタリア |
185,838 |
3,923,766 |
4,109,604 |
4.5パーセント |
|
| ドイツ(注2) |
303,743 |
3,456,193 |
3,759,936 |
8.1パーセント |
音楽用はデータ用以外全て |
| スペイン |
53,087 |
3,043,400 |
3,096,487 |
1.7パーセント |
|
| カナダ |
78,308 |
2,346,077 |
2,424,385 |
3.2パーセント |
|
| オランダ |
82,237 |
1,820,981 |
1,903,218 |
4.3パーセント |
音楽用はデータ用以外全て |
| オーストリア |
37,968 |
1,006,738 |
1,044,706 |
3.6パーセント |
|
| ベルギー |
77,765 |
945,089 |
1,022,854 |
7.6パーセント |
音楽用にはMDを含む |
| スウェーデン |
5,408 |
693,167 |
698,575 |
0.8パーセント |
|
| ハンガリー |
3,956 |
552,902 |
556,858 |
0.7パーセント |
|
| スイス |
64,324 |
362,636 |
426,960 |
15.1パーセント |
音楽用はデータ用以外全て |
| フィンランド |
4,974 |
394,438 |
399,412 |
1.2パーセント |
|
| |
1ユーロ 165.8円 1カナダドル 115.3円 |
| (注1) |
合計に対する音楽用CD-R/RWによる収入の比率 |
| (注2) |
ドイツのみ2006年度実績資料が入手できなかったため、2005年度実績 |
ちなみに、わが国の音楽用CD-R/RWから得られている補償金額は、2006年度でおよそ1億円です。
なぜ、各国がデータ用CD-R/RWも対象としているのでしょうか、なぜデータ用に比べて音楽用は多くの国で5パーセントにも満たない程度の補償金収入でしかないのでしょうか。このことは、どの国においても、いかにデータ用CD-R/RWが大量に私的録音のために使用されているか、ということを物語っていると思います。
このデータ用CD-R/RWのように、これまで「汎用」という言葉を隠れ蓑にしていたものを、今後はすべて対象にし、わが国の著作者がこのような不利益を受けないよう、制度設計を行っていただきたいと考えます。
そのためには、補償金の支払い義務者が非常に重要な意味を持つことになりますので、資料1とは前後しますが、次に支払い義務者について述べることとします。
| ○ |
|
全ての機器・記録媒体を補償金の対象とする場合、消費者を支払い義務者とするのは難しいと考えます。 |
補償金の支払い義務者の考え方については、これまでの検討の経緯があることは承知しております。
しかし、私的録音録画を取り巻く環境の中で、補償金制度導入当時と最も大きく変化したのが、前述のとおり専用機器・記録媒体以外の機器等による私的録音録画の台頭です。
このような状況であるにもかかわらず、支払い義務者を消費者のままとしておくと、実際に私的録音録画に供されている機器・記録媒体を広く補償金の対象とする場合に生じる課題(返還制度や特定の機器等が私的録音録画に供される割合等の補償金への反映等)が解消されないこととなり、制度設計が困難であることは明らかです。
実は、こうした変化はどの国にも起こっている現象ですが、文化先進諸国の中でわが国の補償金制度だけが機能不全に陥ったのは何故でしょうか。私はその最も大きな原因が、支払い義務者の違いであると強く感じております。
| ○ |
|
対象機器・記録媒体の決定及び補償金の額の決定方法については、フランスの例に倣い、公的な「評価機関」によることが合理的であると考えます。 |
フランスが採用している、消費者、製造業者・輸入業者、権利者及び政府関係者により構成される公的な「評価機関」による私的録音録画補償金制度は、これまで大変良く機能していると感じます。ぜひわが国においてもこの好例に倣うべきと考えます。
ただし、公平且つ適正な結論を導くためには、当該評価機関の構成人数、人選、議決の要件等につき最大限の配慮が必要と考えます。
| ○ |
|
補償金の管理については、可能な限り合理性、効率性、管理経費の節減を考慮して検討されるべきであると考えます。 |
私的録音録画は、消費者個々のプライベートな空間で行われていることであり、今後も私的録音録画補償金を100パーセント正しく分配できるようにするためには相当な困難が伴うと考えます。この状況が続く限り、共通目的事業を導入した当時の理由である間接分配の必要性は失われることはありません。
こうした理由から、共通目的事業は今後も存続させることが望ましいと考えます。
ただし、これまでの二割という比率等については再検討が必要であるという認識です。
| ○ |
|
補償金制度の広報のあり方については、義務化の必要はなく、利害関係者がそれぞれ努力することで足りると考えます。 |
補償金制度の普及啓蒙のための広報を行うことは当然のことであり、利害関係者である消費者団体、製造業者・輸入業者団体、権利者団体等が、それぞれ、又は協力して実施すればそれで済むことであると考えます。
| ○ |
|
私的録音録画補償金制度に代わることができる優れた方法は現時点では見当たりません。 |
消費者の私的録音録画の自由度を一定程度確保し、製造業者・輸入業者が私的録音録画のための機器・記録媒体を提供し、権利者等に対価が還元される、三者の利害関係を適切に調整できる仕組みは、現時点においても私的録音録画補償金制度をおいて他にはありません。
|
| 以上 |
|
 |