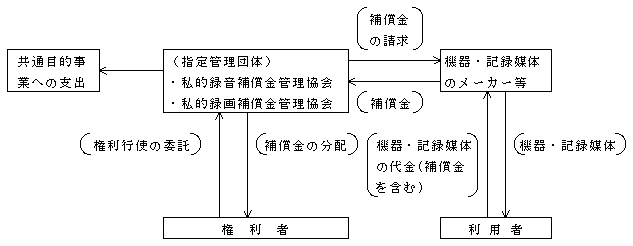私的使用のための複製に関する制度の概要
平成18年4月6日
文化庁著作権課
 .私的使用のための複製に係る権利制限 .私的使用のための複製に係る権利制限
|
権利の目的となっている著作物又は実演等について、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、原則として、その使用する者が複製することができる(第30条第1項及び第102条第1項)。
 .私的録音録画補償金制度 .私的録音録画補償金制度
|
| 1. |
補償金の原則 |
| |
私的使用のための複製のうち、政令で定める機器及び記録媒体(以下、「特定機器」及び「特定記録媒体」という。【資料1】参照)による録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を権利者に支払わなければならない(第30条第2項及び第102条第1項)
|
| 2. |
指定管理団体による権利の行使 |
| |
補償金を受ける権利は、文化庁長官がその同意を得て指定する団体(【資料2】参照)がある場合には、その団体によってのみ行使することができる(第104条の2第1項)。
(関連する主な規定)
| ア) |
指定要件
文化庁長官による指定にあたっては、 公益法人であること、 公益法人であること、 各権利者を代表する又は相当数を構成員とする団体を構成員としていること、 各権利者を代表する又は相当数を構成員とする団体を構成員としていること、 構成員たる団体が非営利であり、団体内の手続きが民主的であること、 構成員たる団体が非営利であり、団体内の手続きが民主的であること、 的確な業務遂行能力を具備していること、が要件となる(第104条の3)。 的確な業務遂行能力を具備していること、が要件となる(第104条の3)。 |
| イ) |
補償金の額の認可
指定管理団体が補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は補償金の額を定め、文化庁の認可を受けなければならない(第104条の6)(【資料3】参照)。 |
|
| 3. |
補償金の支払方法の特例 |
| |
特定機器又は特定記録媒体を購入する者は、購入時に、指定管理団体から補償金の支払の請求があった場合には、補償金を一括して支払わなければならない(第104条の4第1項)(【資料4】参照)。
(関連する主な規定)
| ア) |
補償金の返還
特定機器又は特定記録媒体の購入時に補償金を支払った者は、指定管理団体に対し、当該機器又は記録媒体を専ら私的録音録画以外の用に供することを証明して、補償金の返還を請求することができる(第104条の4第2項)。 |
| イ) |
製造業者等の協力義務
指定管理団体がこの方法により補償金の支払を請求する場合には、特定機器又は特定記録媒体の製造業者等は、当該補償金の支払の請求及びその受領に関し協力しなければならない(第104条の5)。 |
| ウ) |
補償金の分配
指定管理団体の業務の執行に関する規程には、この方法により受け取った補償金の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第30条第2項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない(第104条の7第2項)(【資料5】参照)。 |
|
| 4. |
著作権等の保護に関する事業等のための支出 |
| |
指定管理団体は、3.の方法により受け取った補償金の額の2割以内で政令で定める割合(2割)に相当する額を、権利の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のために支出しなければならない(第104条の8第1項)(【資料6】参照)。 |
 .技術的保護手段の回避による私的使用のための複製 .技術的保護手段の回避による私的使用のための複製
|
私的複製であっても、技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになった複製を、その事実を知りながら行う複製については、権利制限規定の対象とならない(第30条第1項第2号及び第102条第1項)。
※制定の理由等
著作権審議会マルチメディア小委員会WG(技術的保護・管理関係)報告書では、権利制限規定の趣旨の1つとして、「(a)著作物等の利用の性質からして著作権等が及ぶものとすることが妥当ではないもの」を挙げ、「そもそも私的使用のための複製を認めている趣旨は、上記(a)に該当し、個人や家庭内のような範囲で行われる零細な複製であって、著作権者等の経済的利益を害しないという理由によるものと考えられる。一方、技術的保護手段が施されている著作物等については、その技術的保護手段により制限されている複製が不可能であるという前提で著作権者等が市場に提供しているものであり、技術的保護手段を回避することによりこのような前提が否定され、著作権等が予期しない複製が自由に、かつ、社会全体として大量に行われることを可能にすることは、著作権者等の経済的利益を著しく害するおそれがあると考えられるため、このような、回避を伴うという形態の複製までも、私的使用のための複製として認めることは適当ではないと考えられる。」としている。
 .公衆向けに設置された自動複製機器を用いた複製 .公衆向けに設置された自動複製機器を用いた複製
|
私的複製であっても、公衆による使用を目的として設置されている自動複製機器を用いて行う複製については、権利制限規定の対象とならない(第30条第1項第1号及び第102条第1項)。
| ※ |
ただし、当分の間、ここでいう自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製のために使用されるものを含まない(附則第5条の2)。 |
(別添)
【資料1】 政令により指定されている機器及び記録媒体
| 録音 |
機器 |
DAT(デジタル・オーディオ・テープ)レコーダー |
| DCC(デジタル・コンパクト・カセット)レコーダー |
| MD(ミニ・ディスク)レコーダー |
| CD-R(コンパクト・ディスク・レコーダブル)方式CDレコーダー |
| CD-RW(コンパクト・ディスク・リライタブル)方式CDレコーダー |
| 記録媒体 |
上記の機器に用いられるテープ,ディスク |
| 録画 |
機器 |
DVCR(デジタル・ビデオ・カセット・レコーダー) |
| D-VHS(データ・ビデオ・ホーム・システム) |
| MVDISC(マルチメディア・ビデオ・ディスク)レコーダー |
| DVD-RW(デジタル・バーサタイル・ディスク・リライダブル)方式DVDレコーダー |
| DVD-RAM(デジタル・バーサタイル・ディスク・ランダム・アクセス・メモリー)方式DVDレコーダー |
| 記録媒体 |
上記の機器に用いられるテープ,ディスク |
【資料2】 指定されている管理団体
| 録音: |
社団法人私的録音補償金管理協会(SARAH) |
| 録画: |
社団法人私的録画補償金管理協会(SARVH) |
【資料3】 特定機器及び特定記録媒体に係る補償金の額
(録音)
| (1) |
特定機器・・・基準価格(注)の2パーセント
(上限:シングルデッキは1,000円、ダブルデッキは1,500円) |
| (2) |
特定記録媒体・・・基準価格(注)の3パーセント |
(録画)
| (1) |
特定機器・・・基準価格(注)の1パーセント(上限:1,000円) |
| (2) |
特定記録媒体・・・基準価格(注)の1パーセント |
| (注)基準価格 |
|
特定機器・・・カタログに表示された標準価格の一定割合(65パーセント)
特定記録媒体・・・カタログに表示された標準価格の一定割合(50パーセント) |
|
【資料4】 補償金の徴収及び分配の流れ
【資料5】 指定管理団体に支払われた補償金は、次の関係団体を通じて、権利者に分配されている。
(録音)
| ○ |
社団法人日本音楽著作権協会 |
| ○ |
社団法人日本芸能実演家団体協議会 |
| ○ |
社団法人日本レコード協会 |
(録画)
| ○ |
私的録画著作権者協議会(会員11団体)
| ・ |
社団法人日本民間放送連盟 |
| ・ |
日本放送協会 |
| ・ |
社団法人全日本テレビ番組製作社連盟 |
| ・ |
社団法人日本映画製作者連盟 |
| ・ |
有限責任中間法人日本動画協会 |
| ・ |
社団法人日本映像ソフト協会 |
| ・ |
協同組合日本映画製作者協会 |
| ・ |
社団法人日本音楽著作権協会 |
| ・ |
協同組合日本脚本家連盟 |
| ・ |
協同組合日本シナリオ作家協会 |
| ・ |
社団法人日本文藝家協会 |
|
| ○ |
社団法人日本芸能実演家団体協議会 |
| ○ |
社団法人日本レコード協会 |
|
【資料6】 共通目的事業の主な内容
 |
著作権及び著作隣接権の保護に関する事業
| ・ |
新聞・雑誌等への広告掲載 |
| ・ |
著作権教育用の小冊子・パンフレット等の作成・配付 |
| ・ |
広報誌の作成・配付 |
| ・ |
イベントへのブース出展 |
| ・ |
著作権普及啓発活動(教材開発,セミナー・シンポジウムの開催等)への助成 |
| ・ |
国際協力事業(国際セミナー,研修プログラム)への助成 |
| ・ |
著作権等に関する調査・研究事業(私的録音等実態調査,海外における侵害実態調査 等)の実施 等 |
|
 |
著作物の創作の振興及び普及に資する事業
| ・ |
コンサート,講演会等への助成 |
| ・ |
新人芸術家の育成活動(作品の公募・発表等)への助成 |
| ・ |
海外への日本音楽に関する情報の提供活動への助成 |
| ・ |
国際文化交流事業への助成 等 |
|
|