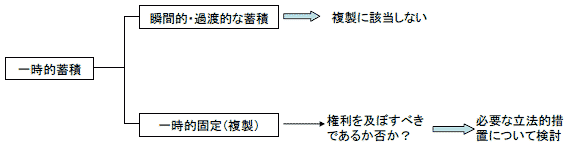平成20年5月22日
デジタル対応ワーキングチーム
機器利用時・通信過程における蓄積(以下、総称して「一時的蓄積」という。)については、平成17年度のデジタル対応ワーキングにおいてその取り扱いについて議論がなされ、平成18年1月の著作権分科会報告書(以下「18年報告書」という。)では、「・・・法的予測可能性を高め、萎縮効果を防止することにより、権利者や利用者が安心して著作物を流通・利用できる法制度を構築する観点から、今後も立法措置の必要性について慎重な検討を行い、平成19年を目途に結論を得るべきとした。」とされている。
これを踏まえ今般、新たな技術動向も見極めつつ、機器利用時、通信過程における一時的蓄積の著作権法上の取扱いに関し、立法措置のあり方について検討を行った。
2.本年度の検討方針
18年報告書においては、(1)機器等を用いて著作物の視聴等を行う場合に機器内部で技術的に生じる一時的蓄積行為と、(2)情報通信過程において送信の効率化等のために蓄積装置等を設置して行う一時的蓄積行為を、包括的に「一時的固定」の問題として整理し、権利を及ぼすべきでない範囲の要件が検討された。
この結果、18年報告書では「技術の進展に伴い、様々な形態の一時的固定が出現しており、また今後も出現することが予想されるため、上記 〜
〜 の要件では、権利を及ぼすべきではない場合のすべてを対象とすることは困難である(注1)と考えられる」ことから、「必要な場面を想定し、個別に別個の権利制限規定を設けるなど、必要な措置を追加して検討する必要があると考えられる」とされている。
の要件では、権利を及ぼすべきではない場合のすべてを対象とすることは困難である(注1)と考えられる」ことから、「必要な場面を想定し、個別に別個の権利制限規定を設けるなど、必要な措置を追加して検討する必要があると考えられる」とされている。
しかしながら、実際の状況に鑑みると、(1)と(2)では、蓄積行為の目的や態様など検討の前提が異なっているため、結果として本来権利を及ぼすことが適当でないと考えられる行為の全てが捕捉できていなかったものと考えられる。
具体的には、(2)の一時的蓄積行為は、技術的な過程において付随的又は不可避的に生じるものとして位置づけるというよりは、むしろ情報伝達の効率化や通信伝達の信頼性確保などの理由に伴い蓄積装置を設置して行う積極的な行為としての観点から、権利を及ぼすべきでないとする場合の要件を検討することが適当な場合が多いと考えられる。
他方、(1)の一時的蓄積行為については、18年報告書の基本的枠組において議論することが適切であるが、立法措置を講じるに当たっては、技術動向等に左右されないようなものとすべく、権利を及ぼすべきではない行為が満たすべき3要件(2項参照)を再度詳細に検討すべきであると考えられる。
以上を踏まえ、本報告書では、(1)の一時的蓄積行為についての論点のみを取り上げ、(2)の一時的蓄積行為については、別途検討することとする。
- (注1) 例として、通信の効率性を高めるために行われるミラーサーバにおける蓄積や、災害時等のサーバの故障に備えたWebサイトのバックアップサービスなどは、要件から外れてしまうが、通信の効率性や安全性の観点から、権利を及ぼすべきではないとする社会的な要請が強いと考えられるとされている。
3.18年報告書の要件の再検証
18年報告書の3要件について再検証をしてみると、18年報告書で権利を及ぼすべきではないと整理されている行為類型であっても、例えばブラウザキャッシュの蓄積やRAMへの蓄積などの事例については、3要件のうち、 の「合理的な時間の範囲内」という定量的な時間の要素に基づく要件には必ずしも該当しない場合がありうるといえる(注2)。
の「合理的な時間の範囲内」という定量的な時間の要素に基づく要件には必ずしも該当しない場合がありうるといえる(注2)。
以下では、こうした状況を踏まえ、18年報告書の要件である 「合理的な時間の範囲内」について更なる検証を行い、技術動向に左右されないような修正の方向について検討することとする。
「合理的な時間の範囲内」について更なる検証を行い、技術動向に左右されないような修正の方向について検討することとする。
- (注2) 例えばブラウジングの際のブラウザキャッシュは、ユーザー側の設定次第ではかなり長い期間残存しうることから、必ずしも客観的に「合理的な時間の範囲内」にとどまるかは明瞭でないと考えられる。また不揮発性のRAMに蓄積された情報は、電源を切ることで消去が予定されているわけではないため、ハードディスクと同様に使用されるような場合もありえるが、同様に「合理的な時間の範囲内」にとどまるかは不明瞭であると考えられる。
4.要件の考え方について
(1)「合理的な時間の範囲内」という要件の含意
18年報告書において、一時的蓄積が「合理的な時間の範囲内」であることという要件が検討された背景としては、結局のところ、利用者にとって著作物等の実質的な価値は視聴等により生じるものであるが、一方で視聴等の行為を排他的権利の対象とすることは現実的ではないことなどから、半永続的に反復継続される視聴等の行為の『元栓』として複製行為に関して対価回収機会を設けることを複製権の重要な趣旨の一つであるとする観点を踏まえつつ、
- −機器等により著作物等の蓄積がなされている間は、当該蓄積を利用して一度ないし複数回(注3)にわたり当該著作物等の視聴等(注4)が行われることが予定されている。
- −しかし、この蓄積が「合理的な時間の範囲」で消去されるのであれば、視聴等の行為も長期的には反復されることはない。
- −すなわち、この蓄積は、独立した複製物としての価値を持たず、複製権を及ぼすには値しない。
という考え方があったといえる。
利用者の適法な機器利用の確保と権利者の権利の適切な保護の双方を踏まえれば、この含意に基づき、仮に長時間に渡って蓄積が残存したとしても、実質的に当該蓄積を「複製」として利用したと評価するには及ばない程度であれば、複製権の対象とならないようにするというように要件を再検討することが適切と考えられる。
- (注3) RAMへの蓄積やブラウザキャッシュ等は頻繁な処理を高速化するための蓄積である。
- (注4) ここでは、支分権が及ばない行為であるという意味で「視聴等」(ただし、特にプログラムを明示する場合は「使用」)と呼称することとする。
(2)複製権を及ぼすべきでない範囲
上記の考え方を踏まえれば、「合理的な時間の範囲内」という定量的な時間の要素ではなく、むしろ、より一般化した形でその含意を要件化することが適切であると考えられる。具体的には、
 視聴等行為に合目的な蓄積であること
視聴等行為に合目的な蓄積であること 上記蓄積を伴う視聴等行為が合理的な範囲内のものであること
上記蓄積を伴う視聴等行為が合理的な範囲内のものであること
- −蓄積が、合理的な範囲内での視聴等行為に合目的なものとして行われること
- −蓄積後において、視聴等行為が合理的な範囲内で行われること
とすることにより、18年報告書の際に想定されていた複製権の対象とすべきではない範囲を蓄積の定量的時間に左右されずに担保できるものと考えられる(注5)(注6)。
なお、視聴等行為が「合理的な範囲」内か否かは、所与の技術体系下において社会に一般的と認められる機器利用の態様から客観的に判断されるべきである(注7)(注8)。すなわち、定量的な時間の要素は「合理的な範囲内」を図る尺度の一表現ではあるが、必要条件とはならない。
- [要件適用の具体的イメージ例]
ブラウザキャッシュの例では、一般に行われている視聴方法でブラウザによりオンラインの著作物等を視聴している限りにおいては、その際に生じる蓄積(ブラウザキャッシュ)は、本要件に該当すると考えられるが、例えば、ユーザーが設定を変更して、ブラウザで予定されている範囲を超えて視聴等を行うことを意図して蓄積する場合や、蓄積後に他のアプリケーションを用いて視聴等を行うなどしてこの蓄積をいわば独立した複製物として視聴に供するような場合には、本要件には該当しないものと考えられる(ただし、このような場合であっても、私的使用目的の場合(第30条)など、他の権利制限規定の対象となる場合はありうる)。
- (注5) 支分権が及ぶ行為(複製、公衆送信、演奏、上映等)でも支分権が及ばない視聴等行為でも、機器を利用してそれらの行為を行う際に付随的又は不可避的に生じる蓄積の技術的態様は同様と考えられるため、機器利用の円滑化の観点から、当該要件のもとで同様に複製権が及ばないものとすべきである。支分権が及ぶ行為が違法に行われる場合も同様である。
- (注6) なお、本要件を満たさず、権利を及ぼさないこととならない場合であっても、別の権利制限規定が適用される場合がありうる(例えば、私的使用目的であれば第30条、自ら複製物を所有しているプログラムの場合であれば第47条の2など)。
- (注7) 現行法下でも、RAMへの蓄積について、「前記(説明略)のような一時的・過渡的な性質故に、著作権法にいう「有形的な再製」というに至らないものと解すべきである」とした裁判例(平成12年05月16日東京地裁、事件番号平成10(ワ)17018)がある。本件は「複製ではない」と規範的に解釈することにより複製権が及ばないものとしているが、本規定案の解釈の参考になる事例であると考えられる。
- (注8) プログラムについては、業務上の使用が多く、他の著作物等より一度の使用時間が比較的長い場合も多いと考えられること、業務上使用される場合のプログラムの公衆送信の態様は様々なものがあると考えられることから、プログラムの使用にかかる「合理的な範囲」は、利用態様毎の技術的背景に照らして柔軟に判断すべきであると考えられる。
(3)関連する論点
このような要件とした場合、利用者が当該蓄積を利用して行う視聴等行為が、合理的な範囲を超える場合であっても、それが意図せずにたまたま行われたものであるならば、利用者保護の観点から、複製権を及ぼさないよう整理すべきである。
また、一意には定まらない「合理的な範囲」という要件を採用することは、複製権が及ぶべき範囲とそうでない範囲の判別の曖昧さは残るため、現実の条文の検討に際しては、要件の意図をより明確に表現することに留意が必要であるほか(注9)、18年報告書の の要件中「行為主体の意思に基づかない」については、行為主体が技術的に蓄積が生じることを認識している場合に不安定性が生じることから、同じく曖昧さを避けるべく見直すことが適当である。
の要件中「行為主体の意思に基づかない」については、行為主体が技術的に蓄積が生じることを認識している場合に不安定性が生じることから、同じく曖昧さを避けるべく見直すことが適当である。
- (注9) たとえば、利用者が蓄積を独立した複製物として利用する場合や、当該蓄積を再度複製するような場合(ブラウザキャッシュを別途複製して保存するような場合)は対象外となることを一般的に明示するなどが考えられる。
5.結論
以上を踏まえれば、機器利用時の一時的蓄積については、次の
 著作物等の視聴等に係る技術的過程において生じる、
著作物等の視聴等に係る技術的過程において生じる、 付随的又は不可避的で、
付随的又は不可避的で、 視聴等に合目的な蓄積であって、当該技術及び当該技術に係る一般的な機器利用の態様に照らして合理的な範囲内の視聴等行為に供されるものであること、
視聴等に合目的な蓄積であって、当該技術及び当該技術に係る一般的な機器利用の態様に照らして合理的な範囲内の視聴等行為に供されるものであること、
を満たすものについて、権利を及ぼさないよう立法的措置を講ずることによって、機器の通常の利用における法的予測性を高め、萎縮的効果を防止することができるものと考えられる。