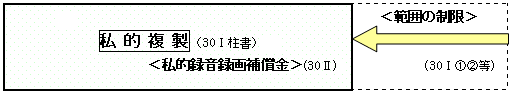ここからサイトの主なメニューです
|
| 1. | 問題の所在 |
| 個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする複製(以下「私的複製」という。)については、実際上家庭内の行為について規制することは困難である一方、零細な複製であり、著作権者等の経済的利益を不当に害することがないと考えられたため、著作物を複製することができるとされている(第30条第1項及び第102条第1項)。(注1) 著作権法は他方において、昭和45年の現行法の制定以降、技術革新を踏まえ、私的複製の範囲として権利制限を認めておくことが不適切と考えられるものについては、上記の趣旨も踏まえながら、私的複製の範囲を制限し(第30条第1項第1号及び第2号)、あるいは、私的複製の範囲内において行われる私的録音録画については、一定の条件の下で補償金を課すことにより(第30条第2項)、権利の保護と公正な利用とのバランスを図ってきたところである(【別添】参照)。なお、その際の考慮要素としては、上記の趣旨とあわせて、個人的かつ家庭内の複製について個別に権利を行使しようとする場合の費用(トランザクションコスト)の存在も含めて考えられるものといえる。 |
|
| (注1)ただし、私的使用のために一旦複製したものを、その後公衆に頒布又は提示する場合は、目的外使用として、原則に戻り許諾が必要である(第49条第1項第1号及び第102条第4項第1号)。 |
|
|
|
| 複製・通信技術の発達は目覚ましく、私的領域においても、大量かつ広範に高品質の複製物が作成されうる状況である。特に、インターネットを通じた著作物等の交換・共有は、大量かつ広範な複製を可能にしている。しかし、技術革新は、複製の拡大ということだけではなく、同時に、私的領域であっても、契約や著作権保護技術を通じて、権利者の利益を確保することも可能性となしうるものである。 このため、現行法の制定当初は予定していなかったと考えられるこのようなデジタル化・ネットワーク化等の急速な技術革新に対応して、私的複製に関する適切な権利保護の在り方について検討を行うことが必要となっている。 私的複製における権利保護の在り方については、上記のとおり、立法措置としては、これまで、私的複製の範囲から除外し、又は補償金を課することにより対応してきたところである。しかし、私的複製をめぐっては、立法措置以前に、関係者間の契約や著作権保護技術を通じて、私的複製の範囲を事実上制限することが可能になりつつあることから、まずは、このような場合における契約の有効性や権利者が被る不利益との関係について、整理が必要となる。 その上で、そのような私的複製の範囲を前提として、問題とされる私的複製について、私的複製の範囲から除外する必要があるのか、あるいは補償金を必要とすると考えるべきか等、立法措置の必要性の有無について、私的複製についての立法趣旨も踏まえながら、検討することが必要となる。 |
| 2. | 検討課題 |
| (1) | 解釈上の検討課題
|
||||||||
| (2) | 立法上の検討課題
|
| 3. | 検討結果 |
| (1) | 解釈上の検討課題
|
||||||||
| (2) | 立法上の検討課題
|
||||||||
| (3) | まとめ 私的複製の範囲にかかる立法上の検討課題については、私的録音・録画の在り方にかかる検討を避けては通ることはできないが、私的録音・録画の在り方は、私的録音録画補償金の在り方と密接に関係する課題である。すなわち、私的録音・録画の在り方については、私的録音・録画の現状を踏まえ、私的領域における複製に関し、権利の保護と著作物等の公正な利用とのバランスを図る方策として、いずれの部分を補償金で対応し、著作権保護技術等で対応し、あるいは私的複製の範囲としておくことが適切なのかといったことについて、一体的な議論が必要となる。 したがって、法制問題小委員会としては、私的録音・録画に関する私的録音録画小委員会における検討の状況を見守り、その結論を踏まえ、必要に応じて、私的複製の在り方全般について検討を行うことが適当である。 |
| 【別添】 | 私的複製に関するこれまでの改正 |
| (1) | 昭和59年改正〔公衆向けに設置された自動複製機器を用いた複製〕 |
| 私的複製であっても、公衆による使用を目的として設置されている自動複製機器を用いて行う複製については、権利制限規定の対象とならない(第30条第1項第1号及び第102条第1項)。また、このような自動複製機器を営利を目的として、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者に対しては刑罰が科せられる(第119条2号)。 ただし、当分の間、ここでいう自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製のために使用されるものを含まない(附則第5条の2)。 |
| 【趣旨】 公衆の利用に供することを目的として設置された自動複製機器を用いた私的複製については、家庭のような閉鎖的な私的領域における零細な複製を許容する趣旨を逸脱すると考えられることから、権利制限規定の対象から除外したもの。 なお、文献複写の分野については、必ずしも権利の集中処理の体制が整っていないことから、附則第5条の2において、当分の間の措置として、権利制限の対象から除外される自動複製機器には文献複写機は含まないとされている。 |
| (2) | 平成4年改正〔私的録音録画補償金制度〕 |
| 私的複製のうち、デジタル方式の私的録音録画については、政令で定める機器及び記録媒体による録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を権利者に支払わなければならないとされた(第30条第2項及び第102条第1項)。 |
| 【趣旨】 デジタル方式の私的録音録画については、広範かつ大量に行われ、さらに市販のCD等と同等の高品質の複製物を作成しうるものであることから、そのような私的録音録画を自由とする代償として、政令で定める機器及び記録媒体による録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を権利者に支払わなければならないとしたもの。 |
| (3) | 平成11年改正〔技術的保護手段の回避による私的複製〕 |
| 私的複製であっても、技術的保護手段(第2条第1項第20号)の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになった複製を、その事実を知りながら行う複製については、権利制限規定の対象とならない(第30条第1項第2号及び第102条第1項)。 |
| 【趣旨】 技術的保護手段が施されている著作物等については、その技術的保護手段により制限されている複製が不可能であるという前提で著作権者等が市場に提供しているものであり、技術的保護手段を回避することによりこのような前提が否定され、著作権者等が予期しない複製が自由に、かつ、社会全体として大量に行われることを可能にすることは、著作権者等の経済的利益を著しく害するおそれがあると考えられることから、権利制限規定の対象から除外したもの。 |
| 前のページへ | 次のページへ |
| ページの先頭へ | 文部科学省ホームページのトップへ |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology