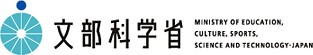2 �������e |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@ | �i�A�jUCITA�̐����o�� �@�č��ɂ����ẮA�_��@�̈�ʓI�ȋK�����s�����̂Ƃ��āAUCC�iUniform Commercial Code�G���ꏤ���@�T�j�����邪�A����͌����Ƃ��ėL�̕��i���邢�͗L�̕��Ɩ̍����j�̎�����K��������̂ł���B��L�̕��ɉ��̂��Ď�������ȏ�́AUCC�̓K�p���F�߂���i����ProCD�����Ŗ��ƂȂ����̂́A���ꏤ���@�T�̑�2�҂ł������j���A��ꎩ�̂�����̑ΏۂƂȂ錻��Љ�ɂ����āA���̖@�I�K�����s����ʓI�Ȑ���@���K�v�ł���Ƃ����F�������܂�A�����́AUCC�̑�2�҂���������Ƃ����`�ŗ��@��Ƃ��J�n���ꂽ�B�@���̉�����Ƃ́ANCCUSUL�iNational Conference of Commission on Uniform States Laws�G�S�ē���B�@�ψ���S����c�j�y��ALI�iAmerican Law Institute�G�č��@������j�Ō������i�߂�ꂽ���A���@�ߒ������]�Ȑ܂��ɂ߁A�ŏI�I�ɂ�UCC�ɐ��荞�ނ��Ƃ͒f�O����AUCC�Ƃ͓Ɨ�����UCITA�iUniform Computer Information Transactions Act�G����R���s���[�^������@�j�Ƃ���NCCUSUL�Ő��������B���݁A�B���x���ō̑����i�݂���B |
| �i�C�jUCITA�ɂ�����_�_ �@UCITA�ɂ����ċ����[���̂́A�}�X�}�[�P�b�g�E���C�Z���X�iMass-Market License�j�ɂ��ċK�肵����209���A�����āu��{�I�Ȍ�������iFundamental Public Policy�j�v�ɔ�����_��������邱�Ƃ��K�肵����105���ł���B��209���ł́A�_����������C�Z���X�̈ꕔ�ɂȂ�Ȃ��ƌf�����Ă���Ƃ���́u��ǐS�I�iunconscionable�j�Ȍ_������A���͑�105���ia�j�i�A�M�@�ɂ����iPreemption�j�̏ꍇ�j�Ⴕ���́ib�j�i��{�I�Ȍ�������iFundamental Public Policy�j�ɔ�����ꍇ�j�Ɋ�Â����{�ł��Ȃ��_������v�����ƂȂ�B �����Ȃ�_��������A�L�����͖����Ƃ����\��������̂��Ɋւ��A�I�t�B�V�����E�R�����g�i |
�i
�i
�i
�i
�i
�@���̂悤�ɁA�I�t�B�V�����E�R�����g�ɂ����ẮA����̗ތ^�ɂ��ċ�̓I�ɗL�����͖����ƂȂ�_�����������Ă�����̂́A�����̗ތ^�ɑ��Ă��A�u�ʏ�̏ꍇ�ɂ́iordinarily�j�v�Ƃ����������ĎO�ɓn���ėp�����Ă���A��ɖ����ƂȂ�Ƃ܂ł͌������Ă��Ȃ��B�Ȃ��A�����@�[�X�E�G���W�j�A�����O�Ɋւ��ẮA�J��Ԃ��q�ׂ��Ă��邱�Ƃ���A��ʓI�ɂ���𐧌�����_������͖����Ƃ����ׂ��Ȃ̂��낤�Ƃ������Ƃ͊Ŏ悵����B
�@�E���B�̓���
�@���B�ɂ����ẮA1991�N�̃R���s���[�^�E�v���O�����w�߁A1996�N�̃f�[�^�x�[�X�w�ߓ����A�����̖@���F�߂���̗��p�s�ׂɔ�����_��͖����ł���inull and void�j�Ɛ����i�Ⴆ�A�O�҂ɂ����ẮA�����@�[�X�E�G���W�j�A�����O�̍ۂɖ��ƂȂ�t�R���p�C��������ɓ�����i�R���s���[�^�E�v���O�����w�ߑ�6���j�j���A�e���������@������ߒ��ɂ����đΉ��ɈႢ�������Ă���悤�ł���B
�@���̓_�A�f�[�^�x�[�X�w�߂ɑΉ�����`�ʼn������Ȃ��ꂽ�x���M�[���쌠�@���A����ړI��Ȋw�����A�s���葱��i�@�葱���ł̕������ɂ��ċ��s����F�߂�Ή����s���Ă���_�����ڂ����i��23����2�j�B���̑��A�h�C�c���쌠�@���A�u�Ɨ����č쐬���ꂽ�R���s���[�^�E�v���O�����Ƒ��̃v���O�����Ƃ̌݊������m�ۂ��邽�߂ɕs���ȏ��邽�߂ɂ́v�Ƃ����������ŁA�t�R���p�C�������e���闧�@���s���Ă���i��69e���j�B
�@
�@�č��ɂ�����c�_���T�ς���������A����̗ތ^�������ƂȂ�Ƃ�����`�I�w�j�邱�Ƃ͂ł����A���̖����䂪���ɂ����ċc�_����ɓ������āA�䂪�����쌠�@�̐����K��͋��s�K�肩�ۂ��Ƃ������ݒ���s�����Ƃɂ͍�����\�z�����B�����Ƃ�,���B�ɂ�����R���s���[�^�E�v���O�����w�߁A�f�[�^�x�[�X�w�߂ɂ�����c�_�ł́A�������̗ތ^�����s����L����ƋK�肳���P�[�X�������A�č��ɂ�����c�_���������ՓI�ł���ƍl����̂ɂ͗��ۂ��K�v�ł���B
�@���i�K�ŏd�v�Ȃ��Ƃ́A�č��ɂ�����c�_�ɂ���A���[���b�p�ɂ�����c�_�ɂ���A������c�_���{�i�I�ɂȂ���Ă��Ȃ��䂪���ɂ����ẮA�ȉ��ɏq�ׂ��Ƃ𒅎��ɍs�����Ƃł���Ǝv����B���̉ߒ��ɂ����āA�������̗��p�ތ^�ɂ��ċ��s�K��Ƃ��ׂ��ƍl������Ȃ�A���̎|�𗧖@���邱�ƂőΉ����ׂ��ł���B
�@����A�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��_�́A���앨�̗��p�Ɋւ��A�����̌_��͖����Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����A���̗v�f�Ƃ��Ă͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��l�����邩�Ƃ������Ƃł���B�č��ł́AUCITA��105���ɁA�_���̗L�����Ɋւ����ʏ���������A����ɂ�薳���ƂȂ�_��̗ތ^���A���쌠�@�̍l������1�̔��f�v�f�Ƃ��ċc�_���Ă���B�ȉ��A�����̏�����3�̒i�K�ɕ����Ę_���邱�ƂƂ���B
�@��1�ɁA���̖����u�����K�肪���s�K�肩�ۂ��Ƃ������v�Ƃ��ċc�_�����ꍇ�A���_�Ƃ��Ă��鐧���K�肪���s�K��ł���Ƃ����ꍇ�ɂ́A�_��ɂ����鑼�̗v�f����؍l�����邱�ƂȂ��A���Y���s�K��ɔ�����_��͖����ƂȂ�̂����A�ǂ̂悤�ȏꍇ�ɂ����Ă���ɖ����ł���ƌ�����悤�Ȑ����K�肪���쌠�@�ɉʂ����Ă��邾�낤���Ƃ����_�ł����i![]() 68�j�B�Ƃ�킯���B�̋c�_����f����悤�ɁA�����K��ɂ��ČʂɌ������A���s�K��ł��鐧���K��𒊏o�����Ƃ��s�����Ƃ��\�ł���_�͑O�q�̂Ƃ���ł��邪�A���̐o����Ƃ��s���ɂ́A����Ȃ錟�����K�v�ł���i
68�j�B�Ƃ�킯���B�̋c�_����f����悤�ɁA�����K��ɂ��ČʂɌ������A���s�K��ł��鐧���K��𒊏o�����Ƃ��s�����Ƃ��\�ł���_�͑O�q�̂Ƃ���ł��邪�A���̐o����Ƃ��s���ɂ́A����Ȃ錟�����K�v�ł���i![]() 69�j�B
69�j�B
�@��2�ɁA�{���̑�O��Ƃ��āA���앨�̗��p�Ɋւ��āA�����̌_��͖����ƂȂ�ׂ��ł͂Ȃ����Ƃ������ӎ������݂���̂ł���A�]���Ă��̖��́A�����K�����̌_���f����v�f�Ƃ��A�������̗v�f���画�f���āu��ʓI�Ɂv�����ƂȂ�ƍl����ׂ��_��Ƃ��Ăǂ̂悤�Ȃ��̂����邩�A�܂��A�����K��ȊO�̔��f�v�f�Ƃ��Ăǂ̂悤�Ȃ��̂��l�����邩�Ƃ����_���猟�����Ȃ����ׂ��ł���B
�@��3�ɁA�����̏��v�f���m�肳������ŁA�_��̗L�����Ɋւ��锻�f�ɂ��Ă̗��@�I�Ή����K�v���i���@��90���A���邢�͏���Ҍ_��@��10���őΉ�����̂��A���ꂾ���ł͑���Ȃ��Ƃ��Ē��쌠�@�Ɍ_���Ɋւ��鉽�炩�̈�ʏ�����u���̂��j���������ׂ��ł���B
�@�Ȃ��A�����K��Ƃ̊W�ړI�ȗv�f�Ƃ͂��Ȃ����̂́A�ی���Ԃ̖����������앨�A�앨�̗��p�_��ɂ��Ă��A����̍�Ƃ̌��ʂ��̂��߂Ɏ�L�q����B
�@�ی���Ԃ̖����������앨���_��ɂ���ė��ʂ���`�Ԃ́A���݂ɂ����Ă��A�ی���Ԃ̖��������f��≹�y�̕��������̗��ʂ�G�擙�̃A�[�J�C���Ƃ������̈�Ō�����Ƃ���ł���A�܂��앨�Ɋւ��Ă���ʂɌ_���ʂ������p���Ȃ���Ă��邱�Ƃ���A���̂悤�ȏ�̗��p�Ɋւ���@�I�K���ɂ��Č������邱�Ƃ��K�v�ł���Ǝv����B�Ȃ��A�f�[�^�x�[�X����ʂ������p���Ȃ���Ă���Ƃ����ꍇ�ɂ́A�X�̏��̗��p�Ɋւ���@�I�K���̌����ɉ����ăf�[�^�x�[�X�̖@�I�ی�Ƃ̊W�Ƃ����������O���ɒu�����������Ȃ����ׂ��ł���i![]() 70�j�B
70�j�B
�i
�i
�i
�y�Q�l�����z
�E�R���s���[�^�E�v���O�����ɌW�钘�쌠���Ɋւ��钲���������͎҉�c�� �������v���O�����̒����E��͓��ɂ��Ą� ����6�N5��������
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�E���쌠�R�c��}���`���f�B�A���ψ���[�L���O�E�O���[�v�i�Z�p�I�ی�E�Ǘ��W�j���@����10�N12��10��
��5�߁@�K���̑ΏۂƂ��ׂ��s�� |
�i2�j���쌠�@��63���2���̉��߂ɂ��āi�����ɌW�闘�p���@�y�я����̐����j
�@���쌠�҂́A���l�ɑ��A���̒��앨�̗��p���������邱�Ƃ��ł��i��63���1���j�A�@�������҂́A���̋����ɌW�闘�p���@�y�я����͈͓̔��ɂ����āA���̋����ɌW�钘�앨�𗘗p���邱�Ƃ��ł���i��63���2���j�B
�@���앨�̗��p�����i���C�Z���X�j�_��ł́A�����A�㉉�A�ݗ^�A�������́A���쌠�@������҂ɔr���I�ȗ��p��F�߂Ă��闘�p�`�Ԃ̂��������������̂��m�ɂ��Ă�������̑��A���p�����A���t�A���p�ꏊ�A���p���ԁA�Ή��̊z���₳��Ɋe���p�`�Ԃ��ו��������������l�X�Ȏ������߂邱�Ƃ���ʓI�ł���B
�@���쌠�@��63���2���́A�u�������҂́A���̋����ɌW�闘�p���@�y�я����͈͓̔��ɂ����āA���̋����ɌW�钘�앨�𗘗p���邱�Ƃ��ł���v�ƋK�肵�Ă��邪�A���̓_�ɂ��ĉ��߂����m�łȂ��Ƃ�����肪����Ƃ����i![]() 71�j�B
71�j�B
| ��63���2���́u���p���@�y�я����v�ɂ́A���p�����_��Œ�߂��Ă���S�Ă̏������Y������̂��B | |
| ��63���2���́u���p���@�y�я����v�͈̔͂ɔ����Ē��앨�𗘗p�����ꍇ�A���C�Z���V�[�́A���쌠�N�Q������̂��B | |
| ����ɕt�����āA���C�Z���V�[�̌_��ᔽ�𗝗R�Ɍ_������������ꍇ�A�����O�ɍs�������p�͒��쌠�N�Q�ƂȂ�̂��B |
�i
�@�E�����쌠�@�y�ђ��쌠���x�R�c��\�i���a41�N�j
�@�����쌠�@�́A���앨�̗��p�̋����ɂ��Ă̋K���u���Ă��Ȃ��B
�@���쌠���x�R�c��\�ɂ����Ă��A���p�̋����Ɋւ��铚�\�͂Ȃ��A���\���č쐬���ꂽ�����Ȏ������ǎ��āi���a41�N10���j�ɂ����Ă��A���p�̋����Ɋւ���Ă͂Ȃ��B
�@�������Ȃ���A���̌�̌����ɂ����āA�u�����s�g�̍ł����ՓI�����ʂ̑ԗl�ł��闘�p�����̋K�肪�Ȃ��Ƃ������Ƃ͓K���ł͂Ȃ��v�Ƃ���A���s���쌠�@��63���1�������4���Ɠ��l�̏Ă��쐬���ꂽ�B�������A��1���y�ё�2���ɂ��ẮA������O�̂��Ƃ��m�F�I�ɋK�肵�����̂Ƃ��ė�������Ă����悤�ł���A���Y�����ɂ��Ă̋c�_�͌�������Ȃ��B
�@�E���쌠�@�����i����9�N�j
�@��2���Ɋ֘A����K��Ƃ��āA��63���5��������9�N�̒��쌠�@�����Œlj�����Ă���B��5���́A���M�\���̋����ɂ����闘�p���@�y�я����̂����A���M�\���̉A���͑��M�\���ɗp���鎩�����O���M���u�ɌW����̂ɂ��ẮA����ɔ����Ă����O���M���̐N�Q�ƂȂ�Ȃ��ƋK�肵�Ă���B
�@�E�l�����̐���
�@��63���2���̍l�����Ƃ��ẮA��1�ɁA�i�A�j�u���p�����_��Œ�߂鎖���͑S�đ�2���́u�����ɌW�闘�p���@�y�я����v�ł���Ƃ���l�����v�����蓾��B���̍l�����́A����Ɏ���2�ɕ�������B
�i![]() �j�u�����ɌW�闘�p���@�y�я����i�����p�����_��Œ�߂������j�v�Ƀ��C�Z���V�[���ᔽ�����ꍇ�A�S�Ē��쌠�N�Q�ƂȂ�B
�i
�j�u�����ɌW�闘�p���@�y�я����i�����p�����_��Œ�߂������j�v�Ƀ��C�Z���V�[���ᔽ�����ꍇ�A�S�Ē��쌠�N�Q�ƂȂ�B
�i![]() �j�u�����ɌW�闘�p���@�y�я����i�����p�����_��Œ�߂������j�v�Ƀ��C�Z���V�[���ᔽ���Ă��A���쌠�N�Q�ɂȂ�ꍇ�ƂȂ�Ȃ��ꍇ������B
�j�u�����ɌW�闘�p���@�y�я����i�����p�����_��Œ�߂������j�v�Ƀ��C�Z���V�[���ᔽ���Ă��A���쌠�N�Q�ɂȂ�ꍇ�ƂȂ�Ȃ��ꍇ������B
�@�i![]() �j�ɂ��Ă͔ے�I�Ȍ����������B�Ⴆ�A�o�ŕ���^�����̏��n�����n�ꏊ�����肷�鎖���ɂ��ẮA���n���̋K��̎�|������A���ꂪ���쌠�N�Q�ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ����������ʓI�ł���B
�j�ɂ��Ă͔ے�I�Ȍ����������B�Ⴆ�A�o�ŕ���^�����̏��n�����n�ꏊ�����肷�鎖���ɂ��ẮA���n���̋K��̎�|������A���ꂪ���쌠�N�Q�ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ����������ʓI�ł���B
�@�i![]() �j���̂�ꍇ�A��2���́u���p�҂͌_������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ�����ʓI�Ȃ��Ƃ��m�F�I�ɋK�肷������ɉ߂��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B
�j���̂�ꍇ�A��2���́u���p�҂͌_������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ�����ʓI�Ȃ��Ƃ��m�F�I�ɋK�肷������ɉ߂��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B
�@��2�̍l�����́A�i�C�j�u���p�����_��Œ�߂鎖���̂����A���C�Z���V�[���ᔽ����ƒ��쌠�N�Q�ɂȂ���̂������A��2���́u�����ɌW�闘�p���@�y�я����v�ł���Ƃ���l�����v�ł���B���̍l�������̂�ƁA��2���́A�u�����ɌW�闘�p���@�y�я����v�ɔ����Ē��앨�𗘗p���邱�Ƃ͒��쌠�N�Q�ł���ƋK�肷������Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�������A���̏ꍇ�A�����_��Œ�߂鎖���̂����A�������쌠�N�Q�ƂȂ鎖���ł��邩�A�܂�A�����u�����ɌW�闘�p���@�y�я����v�ł��邩���A���Ȃ��Ƃ��㖾�m�ł͂Ȃ��Ƃ�����肪����B
�@�]���āA�i�A�j�i![]() �j�̍l�������̗p���Ȃ�����ɂ����ẮA��2���ɋK�肷��u�����ɌW�闘�p���@�y�я����v�̕��������߂��邱�ƂɎ����I�ȈӖ��͂Ȃ��A�ނ���A��2���Ɋւ��ẮA���p�����_��Œ�߂鎖���̂����A�u�ᔽ����ƒ��쌠�N�Q�ɂȂ鎖���v�Ɓu�ᔽ���Ă��P�Ȃ�_��ᔽ�ɂ����Ȃ�Ȃ������v�����m������邱�ƂɈӖ�������B
�j�̍l�������̗p���Ȃ�����ɂ����ẮA��2���ɋK�肷��u�����ɌW�闘�p���@�y�я����v�̕��������߂��邱�ƂɎ����I�ȈӖ��͂Ȃ��A�ނ���A��2���Ɋւ��ẮA���p�����_��Œ�߂鎖���̂����A�u�ᔽ����ƒ��쌠�N�Q�ɂȂ鎖���v�Ɓu�ᔽ���Ă��P�Ȃ�_��ᔽ�ɂ����Ȃ�Ȃ������v�����m������邱�ƂɈӖ�������B
�@�E���p�����_��̉����Ƃ��̌���
�@���p�����_��ɂ����Ē�߂������̈ᔽ�����쌠�N�Q�ƂȂ�Ȃ��Ƃ��Ă��A���Y�����Ɉᔽ�������Ƃ������Ē��쌠�҂����p�����_��������ł���ꍇ�ɂ́A�����̌��ʂ������O�ɍs�������p�s�ׂɂ��đk�y����i�Ⴆ�A�_��W���������瑶�݂��Ȃ��������ƂɂȂ�j�Ƃ���A���Y���p�s�ׂ͌��ǒ��쌠�N�Q�ƂȂ�Ƃ��l������B
�@�����āA���̏ꍇ�ɂ́A���p�����_��ɂ����Ē�߂������̈ᔽ���A���쌠�N�Q�ƂȂ邩�Ȃ�Ȃ����ɊW�Ȃ��A���p�����_��̉����ɂ���ė��p�҂̒��쌠�N�Q��₤���Ƃ��ł��邱�ƂƂȂ�̂ŁA�i4�j![]() �ɂ����镪�ނ͈Ӗ����Ȃ��Ȃ��Ȃ�A�ނ���A���p�����_��������ł���_��ᔽ�Ƃ��āA�ǂ̂悤�Ȃ��̂��F�߂��邩���d�v�ƂȂ�B
�ɂ����镪�ނ͈Ӗ����Ȃ��Ȃ��Ȃ�A�ނ���A���p�����_��������ł���_��ᔽ�Ƃ��āA�ǂ̂悤�Ȃ��̂��F�߂��邩���d�v�ƂȂ�B
�@��5���ɂ��Ă��A�u���M�\���̉v�Ɓu���M�\���ɗp���鎩�����O���M���u�v�ɌW�闘�p���@�y�я����ɂ��Ă̌_��ᔽ�𗝗R�ɗ��p�����_��������ł���̂ł���A�����̌��ʂɂ���ẮA�K��̎����I�ȈӖ����Ȃ��Ȃ邨���ꂪ����B
�@�]���āA����A�ǂ̂悤�ȏꍇ�ɗ��p�����_��������ł���̂��A���p�����_��̉������ǂ̂悤�Ȍ��ʂ����̂��ɂ��Č�������K�v������B�Ⴆ�A�p���I���p�����_��̉����̌��ʁA���p�ɂ��쐬���ꂽ���앨�̕��������w��������O�҂ւ̌��ʁA�Y�����̓K�p�Ȃǂɂ��Đ������K�v�ł���B
�@��ʓI�Ȓ��앨�̗��p�����_��ł́A�����A�㉉�A�ݗ^�A�������̒��쌠�@������҂ɓƐ��F�߂����p�`�Ԃ̂��������������̂��m�ɂ��Ă�������̑��A���p�����A���t�A���p�ꏊ�A���p���ԁA�Ή��̊z���₳��Ɋe���p�`�Ԃ��ו��������������l�X�Ȏ�������߂��Ă���B
�@���̂����A�Ή��̊z���₳��Ɋe���p�`�Ԃ��ו��������������ɂ��ẮA�����̏����Ɉᔽ��������Ƃ����Ē��쌠�N�Q�Ƃ͂������A�]���āA�ʏ�̗��p�����_��ɂ͒��쌠�҂����쌠�Ɋ�Â����~���������s�g���Ȃ��|���߂����앨���p�K�@�������ƁA�Ή��̊z���̌_��������R�ɂ����Ȃ�Ȃ��P�Ȃ�_��������Ƃ�����B
�@��63���1���́u�����v�́A�_��̑��ɒP�ƍs�ׂɂ���Ă��\�ł���Ɖ�����Ă���B�]���āA��62���2���ł����u�����ɌW�闘�p���@�y�я����v�쌠�҂��P�ƍs�ׂŌ��߂��邱�ƂɌ��肵�A���쌠�҂����~���������s�g���Ȃ��͈݂͂̂���63���2���́u�����ɌW�闘�p���@�y�я����v�ł���A����ȊO�͒P�Ȃ���s���s�̖��ł���ƍl���Ă��s���R�ł͂Ȃ��B
�@�������A��L�i4�j![]() �l�����̐����ŏq�ׂ��悤�ɁA�ǂ̗�����x�����邩�͏d�v�ł͂Ȃ��A�����I�ȈӖ��́u�ᔽ����ƒ��쌠�N�Q�ɂȂ鎖���v�Ɓu�ᔽ���Ă��P�Ȃ�_��ᔽ�ɂ����Ȃ�Ȃ������v�̏s�ʂł���B
�l�����̐����ŏq�ׂ��悤�ɁA�ǂ̗�����x�����邩�͏d�v�ł͂Ȃ��A�����I�ȈӖ��́u�ᔽ����ƒ��쌠�N�Q�ɂȂ鎖���v�Ɓu�ᔽ���Ă��P�Ȃ�_��ᔽ�ɂ����Ȃ�Ȃ������v�̏s�ʂł���B
�@��63��2���̖��́A�����@�Ɠ��l�A�����_�ł͒��ړI�ɗ��@�I������}��K�v���ɖR�����A�_��̉����̌��̖͂����܂߂āA���ߘ_�ɔC����ׂ������ł���ƍl����B
�@�������A����ŗ��p�����_��ɂ����闘�p�҂̕ی�̖��ɂ����āA���쌠�҂̔j�Y��A���쌠�҂���O�҂ɒ��쌠�����n�����ꍇ�ɗ��p�҂̒��앨���p��ی삷�鐧�x�̓����ɂ��Č������s���Ă���B�����ł́A���p�����_��̌_���̒n�ʂ̏��p�̖��ƁA�����̑R�̖�����ׂ��ł���Ƃ̋c�_������B����A���̋c�_�ɍۂ��A��L�́u�ᔽ����ƒ��쌠�N�Q�ɂȂ鎖���v�Ɓu�ᔽ���Ă��P�Ȃ�_��ᔽ�ɂ����Ȃ�Ȃ������v�̏s�ʂ��K�v�ɂȂ��Ă���\��������̂ň����������ӂ��ׂ������ł���Ƃ�����B
�i3�j���쌠�̏��n�_��̏��ʉ��ɂ���
�@���쌠�́A���쌠�҂ɂ��C�ӂ̈ړ]���\�ł���i��61��1���j�B�����āA���쌠�̈ړ]�́A���L�����̑��̕����̈ړ]�Ɠ��l�A�����҂̈ӎv�\���݂̂ɂ���Č��͂���B���Ȃ킿�A���쌠�̔����A�����A���^�A�M�����̌_��i���n�_��j�����ɂ��ړ]����B�������A���쌠�̈ړ]�́A�o�^���Ȃ���Α�O�҂ɑR���邱�Ƃ��ł��Ȃ��i��77���j�B
�@�䂪���ɂ����ẮA��ʓI�ɔ������̌_��͓����҂̈ӎv�̍��v�Ő������A�_�̍쐬�͌_���̗v���ł͂Ȃ��B
�@���쌠�̏��n�ɂ��ď��ʂɂ�蓖���҂̈ӎv�����m�Ɋm�F����Ȃ����Ƃɂ��A����A���̌_��̉��߂ɂ��Ė��ƂȂ邱�Ƃ������Ƃ����B�����āA���̖��͎���2�ɏꍇ�������邱�Ƃ��ł���B
�E���n���ꂽ�����͈͓̔��̖��m���̖��
�@��1�ɁA�_���n�_��ł���Ƃ������Ƃɂ��Ă͑������Ȃ����A���n�������쌠�͈̔͂�������ɂ��Ď���ɑ���������ꍇ�ł���B
�@����́A�A�D���n�ɍۂ��Ă̒��쌠�̍ו������������x���R�ɔF�߂��Ă��邱�Ƃ�A�C�D���앨�̗��p���Z�p�̐i����Љ�̕ω��ɂ�葽�l�����邽�ߓ����_��Ɋ܂܂�Ă������̔��f������V�������p�i�}�́E�`�ԁj�̓o�ꂪ�������Ȃ����Ɠ��ɋN��������ł���Ǝv����B�������A����͏��n���L�̖��ł͂Ȃ��A���p�����ɂ����Ă����l�̖�肪�������i![]() 72�j�B
72�j�B
�i
�E�_���n�_��ł��������ǂ����̖��
�@��2�ɁA�_���n�_��ł��������ǂ����𑈂��ꍇ�ł���B
�@�Ⴆ�A���앨�̐�����O�҂Ɉϑ����鐧��ϑ��̏ꍇ�̒��쌠�̋A���������肪����B���앨�̐���ϑ��_��ɂ����āA�ϑ��҂Ǝ���҂��A�_�ɒ��앨�̒��쌠�̋A���m�����Ȃ����Ƃɂ��A�ϑ����ɗ������҂����m�ɔF�����Ă������p�ɂ��Ắi���Ȃ��Ƃ����p�����͔F�߂��邾�낤����j�����͐����Ȃ����A����������p���s���ꍇ�Ɍ��݉�������ł���B
�@�܂��A�o�ŋƊE���ɂ�����u����_��v�ƌĂ��_����A���e�A�ʐ^�A�C���X�g���̒��쌠�̏��n�_��ł������̂��ǂ��������ƂȂ�₷���B
�@�����̖��́A���n�ɓ��L�̖��ł���Ǝv����B
�@�܂��A�����̌_��̉��߂Ƃ������̑��ɁA���܂�_�����邱�Ƃ͂Ȃ��������A���n�_�̎�ҕی�̕K�v���⏔�O���Ƃ̖@���x�̒��a�Ƃ�����������Ǝv����B
�E�_�쐬�̌��ʓ�
�@��̓I�����ɐ旧���A�_�쐬�̌��ʂƓ����҂Ɍ_���쐬�����闧�@��i�����Ă݂����B
�@�_����邱�Ƃ̌��ʂƂ��ẮA��ʓI�ɂ́A�_���҂̈ӎv�m�ɂ�����ʁA�_��������ɓ����҂ɐT�d�Ȕ��f�𑣂����ʁA�i�ד��̑����ɂȂ����ꍇ�̏؋��Ƃ��Ă̌��ʁA�_����邱�Ƃŏ���l����O�҂ɑ����炪�����҂ł��邱�Ƃ�����������ʓ�������ƍl������B�܂��A�����҂Ɍ_���쐬�����闧�@��i�Ƃ��ẮA�ȉ��̂悤�ȕ��@���̂蓾�邾�낤�B
�@�A�D�v���_��Ƃ���i�_���Ȃ���Ό_��͐������Ȃ��Ƃ���B�j�B
�@�C�D�����_��ł��邪�A���ʍ쐬�`�����͏��ʌ�t�`�����A�������Җ��͈���ɉۂ��B
�@�E�D�_���Ȃ��ꍇ�A�ٔ������_��̑��݂��݂Ƃ߂Ȃ��B
�@�A�D�ɂ��ẮA�_��͓����҂̈ӎv�\���̍��v�ɂ�萬������Ƃ���������ύX���āA�v���_��Ƃ��邱�Ƃɂ͑����̗��R���K�v�ł��邵�A�_���Ȃ���Ό_��̐������݂Ƃ߂Ȃ��Ƃ��邱�Ƃ܂ŕK�v���ǂ����̌������s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�C�D�ɂ��ẮA���̂悤�ȗ��@��́A���Ɏ��ƋK���Ƃ��ĉ䂪���ɂ�������Ƃ���ł��邪�A������ɂ���K�v���ɂ��ď\���Ȍ������s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�E�D�ɂ��ẮA�䂪���̑i�ׂɂ����鎩�R�S�؎�`�̗�O�Ƃ��āA���؎�`���Ƃ邱�ƂɂȂ�̂ŁA�A�Ɠ��l�ɑ����̗��R���K�v�ł��낤�B
�E�ߋ��̌����̐���
�@�ߋ�2��̌����́A��������_��̗v�����ɂ��Č������Ă��邪�A���쌠���x�R�c��ł͏��n�_��݂̂��A���쌠�R�c��}���`���f�B�A���ψ���[�L���O�E�O���[�v�ł͗��p�����_����܂ޒ��앨�ɌW�闘�p�_��S�ʂ�ΏۂƂ��Ă���B
�@�]���āA���ɒ��쌠�R�c��}���`���f�B�A���ψ���[�L���O�E�O���[�v�ɂ�����c�_�́A�i2�j![]() �̖��ɂ��Ă̋c�_�ł������ƍl����ׂ��ł��낤�B����A���쌠���x�R�c��ɂ�����c�_�ł́A�v���_�̈Ӌ`���A�����ҊԂ̊W�m�ɂ��ď����ɂ����镴�c��������A�܂��A�������������ꍇ�ɂ����鎖���F���e�Ղɂ��铙�̓_�ɔF�߂Ă����悤�ł���A���ꂪ�i2�j��
�̖��ɂ��Ă̋c�_�ł������ƍl����ׂ��ł��낤�B����A���쌠���x�R�c��ɂ�����c�_�ł́A�v���_�̈Ӌ`���A�����ҊԂ̊W�m�ɂ��ď����ɂ����镴�c��������A�܂��A�������������ꍇ�ɂ����鎖���F���e�Ղɂ��铙�̓_�ɔF�߂Ă����悤�ł���A���ꂪ�i2�j��![]() ��
��![]() �̂ǂ����O���ɂ����Ă����̂��͖��炩�ł͂Ȃ����A�����炭���҂���ʂ����ɋc�_���Ă������̂Ǝv����B�������A�u���ʂɂ��_������҂��邱�Ɓv���ł��Ȃ����n�_��̎��ԂɌ��y���Ă���_�́A���
�̂ǂ����O���ɂ����Ă����̂��͖��炩�ł͂Ȃ����A�����炭���҂���ʂ����ɋc�_���Ă������̂Ǝv����B�������A�u���ʂɂ��_������҂��邱�Ɓv���ł��Ȃ����n�_��̎��ԂɌ��y���Ă���_�́A���![]() ��O���ɂ��Ă����Ǝv����B
��O���ɂ��Ă����Ǝv����B
�@�܂��A������̋c�_�ɂ����ʂ��邱�Ƃ́A�v���_�i���Ȃ킿�A�_�̂Ȃ��_��̐�����F�߂Ȃ����ƁB�j�ɂ��āA�����܂ł̕K�v����F�߂Ă��Ȃ��Ƃ������ƁA�����Ē��쌠�����̓��ʂȃ��[������邱�Ƃɂ��Ă͏��ɓI�ł������Ƃ������Ƃł���B
�@�䂪���ł́A�Ⴆ�Εs���Y�̏��L���̏��n�_��ɂ��Ă������E�s�v���_��ł��邵�A�������̏��n�_��ɂ��Ă��A�o�^���Ȃ���Έړ]�̌��͂��Ȃ����A�����̏��n�_��ł����Ă������ł͂Ȃ��A���n�l�́A����l�ɑ��Ĉړ]�o�^�葱���s���ׂ��_���̋`�����B��������ƁA�Ȃ����쌠�̏��n�_��ɂ��Ă̂ݏ��ʂ�v�����A�v���_��Ƃ��闝�R�̐����͓���B�����Ƃ��A�s���Y�ɂ��Ă͓o�L���邱�Ƃ���ʓI�ł��邵�A�������ɂ��Ă͓o�^���Ȃ���Γ��������ړ]���Ȃ����A�_�̂̐����Ƃ͕ʂ̖ʂœ����ҍ��ӂ̏��ʂɂ�閾�m�����}����d�|���ƂȂ��Ă���i���ʂ��Ȃ���Γo�L���͓o�^���s�����Ƃ��ł��Ȃ��j����A���쌠�͓o�^����O�ґR�v���ƂȂ��Ă��邪�قƂ�Ǔo�^�����p����Ă��炸�A�⊮�I������S���Ă��Ȃ��Ƃ����Ⴂ������B
�@�܂��A���앨�̐���ϑ����̌_����s���ۂɂ́A�_����e�̋�̓I�ȏ����̋l�߂��s���O�ɁA����҂����앨�̐���Ɏ�肩����ꍇ���������A���̂悤�Ɍ_��̗��s�s�ׂ��_�̍쐬�ɐ�s����Ƃ������Ƃ́A���앨�̐���ϑ��Ɍ��炸�䂪���̌_����ԂƂ��Ă����Ό�����Ƃ���ł���B
�@�䂪���̌_��@�͂��̂悤�Ȏ��ԂƂ����݊W�ɂ��邽�߁A���쌠�̏��n�����ɓ��ʂ̃��[����������ꍇ�A���앨�̐���ϑ����̎��ԓ�������ɑΉ��ł��邩�ǂ����͋^�₪����A���Ȃ��Ƃ����̂��߂ɂ͑傫�ȓw�͂�K�v�Ƃ���Ǝv����B
�@�Ȃ��A�_���쐬�����邱�Ƃŏ��n�l�ł��钘��҂ɐT�d�Ȕ��f�𑣂��Ƃ���������ҕی�̔��z�́A�ߋ��̌�������͖����I�ɂ͓ǂݎ��Ȃ��B�܂��A���O���Ɩ@���x���قȂ邱�Ƃɂ��A���ʂȂ��O�����쌠�̏��n�̗L������i�ד��̏�ʂɂ����鈵���ɌW�鍑�ێ��@��̖��̋c�_�͈�؍s���Ă��Ȃ��B
�@�E��1�̖��_�u���n���ꂽ�����͈͓̔��̖��m���̖��v�̌���
�@�u���n���ꂽ�����͈͓̔��̖��m���̖��v�́A���p�����ɂ�����u���p�����_��ɂ����闘�p���͈̔͂̉��ߖ��v�Ƃ����ʂ���_��̉��ߖ��ł���B�����҂͌_��̑��ݖ��͗L�����𑈂��Ă����ł͂Ȃ��̂ŁA�ߋ��̋c�_�Ɠ��l�ɁA�_���Ȃ���Ώ��n�_��̐�����F�߂Ȃ��Ƃ���Ή��ɂ���ĉ������͂��낤�Ƃ���͓̂K���ł͂Ȃ��Ǝv����B
�@�������A���̑��̎�i�ɂ��_�쐬���������邱�ƂŁA�����x�̌_����e�̖��m���̌��ʂ͊��҂ł��邪�A�_���쐬�����Ƃ��Ă������҂̈ӎv�\�������ʏ�s���m�ł���Ή��̖������ɂ��Ȃ�Ȃ����A�_�������Ă����߂ɂ��Ă̑������N���Ă�����Ԃɂ��݂�A�v���_���̑��̌_�쐬�̋����́A���ɑ��銮�S�ȉƂ͂Ȃ�Ȃ��B
�E��2�̖��_�u�_���n�_��ł��������ǂ����̖��v�̌���
�@�_���n�_��ł��������ǂ��������ꍇ�ɁA���̉�����Ƃ��ď��n�_��̗v���_�y�т��̑��̌_�쐬�̋����𐧓x���i�؋����[�����j���邱�Ƃɂ���āA����������e�Ղɂ��邱�Ƃ͉\�ł��邪�A����́A�u���쌠�̏��n�ɂ��ď��ʂňӎv�\�����Ȃ����Ɓv�ɂ��āu�_���̗L������F�߂Ȃ��v�Ƃ����y�i���e�B��^���鐧�x�ł���A���̃y�i���e�B���ۂ�����̂͒��쌠�̏��n�����Ǝ咣���鑤�ƂȂ�B
�@�������A���̖��́A�u�����҂����쌠�̋A���ɂ��Ė��m�Ɏ�茈�߂����Ȃ��i���쌠�̏��n�ɂ��ď��ʂňӎv�\�����Ȃ��j�v���Ƃ������ł���Ȃ�A���̉����@�Ƃ��Ē��쌠�̏��n�����Ǝ咣���鑤�������y�i���e�B�����x�ɂ͋^�₪����B
�@�������A�K���I�Ȏ��_��Ɛ�֎~�@�I�Ȏ��_����A�Ⴆ�A�l�̒���҂�����ϑ��_��ɂ����āA���Ƃł���ϑ��҂������I�ɒ��ꂽ����ϑ��_����ɒ��쌠�̋A���ɂ��Ĉ�ؐG����Ă��Ȃ������悤�ȏꍇ�ɁA�����ҊԂŒ��쌠�̏��n�����������ǂ����������ƂȂ����Ƃ���A�ٔ������u�\���g�p�҂ɕs���ɉ��߁v���ď��n�_��̑��݂�ے肷��Ƃ������Ƃ����邩������Ȃ��B�������A�u���쌠�̏��n�ɂ��ď��ʂňӎv�\�����Ȃ����Ɓv��ʂɂ��āA���̗v�f���l�������ɁA���쌠�̏��n�����Ǝ咣���鑤�ɕs���ɔ��f���邱�Ƃ͓K���ł͂Ȃ��B
�@�Ȃ��A���̂悤�Ȗ��ɑ��锻�Ⴉ������Ɋ�͒��o�ł��Ȃ��B�Ⴆ�A����Č��ɂ��āA�����R�Ə㋉�R�ŁA�����F�肪�قȂ�ꍇ��������i![]() 73�j�B
73�j�B
�E��������x���x�����h�~�@�̎{�s
�@�Ȃ��A��ҕی�̊ϓ_����̑Ή��Ƃ��ẮA����16�N4��1������{�s���ꂽ���������@�ɂ��A�V���Ƀv���O������f��E�����ԑg���̏�ʕ��̍쐬�ɌW�鉺����������K���ΏۂƂȂ��Ă���B���@�ł́A��������̌�������}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�������ł���e���Ǝ҂ɑ��A�����̓��e�A��������̊z�A�x�������y�юx�����@�����L�ڂ������ʁi3�����ʁj�̉������Ǝ҂ւ̌�t�`�����ۂ��Ă���A����ɂ���āA���앨�̐���ϑ��_��Ɋւ���_��̖��ɂ��Ă��A�����x�̎蓖���s���Ă��邱�Ƃɂ����ӂ��ׂ��ł���i![]() 74�j�B
74�j�B
�@���O���̗��@����݂�ƒ��쌠�̏��n�ɂ��ď��ʂ̍쐬��v�����闧�@��͑����B�������A�䂪���ɂ����ē��l�̗��@���s�����Ƃ́A�K�������K�ł���Ƃ͌����Ȃ��B
�@���̗��R�Ƃ��āA
![]() �j�@�s���Y�̏��L�����̑��̕����̏��n�_���ʂ��v���_��Ƃ���Ă��Ȃ��䂪���̖@���x�̒��ŁA���쌠�̏��n�_��ɂ��Ă̂ݗv���_��Ƃ��邾���̏\���������I�ȗ��R�����������Ȃ����ƁA
�j�@�s���Y�̏��L�����̑��̕����̏��n�_���ʂ��v���_��Ƃ���Ă��Ȃ��䂪���̖@���x�̒��ŁA���쌠�̏��n�_��ɂ��Ă̂ݗv���_��Ƃ��邾���̏\���������I�ȗ��R�����������Ȃ����ƁA
![]() �j�@���쌠�̏��n�ɂ��ď��ʂ̍쐬��v�����鍑�ɂ́A���쌠�Ɍ��炸�A�s���Y�̏��L�����艿�l�ȏ�̌����̏��n�ɂ����ʂ����߂铙�̖@���x���̂��Ă���A����Ƃ͈قȂ�@���x���̂�䂪���ɂ����ē��l�ɍl����ׂ��K�R���͂Ȃ����ƁA
�j�@���쌠�̏��n�ɂ��ď��ʂ̍쐬��v�����鍑�ɂ́A���쌠�Ɍ��炸�A�s���Y�̏��L�����艿�l�ȏ�̌����̏��n�ɂ����ʂ����߂铙�̖@���x���̂��Ă���A����Ƃ͈قȂ�@���x���̂�䂪���ɂ����ē��l�ɍl����ׂ��K�R���͂Ȃ����ƁA
![]() �j�@�䂪���̖����i�ׂł́A���쌠�̏��n�ɂ�����������ꍇ�ɂ́A���쌠�̏��n���������Ǝ咣����҂����̓_�ɂ��Ď咣�E���ؐӔC���Ƃ���A�_�ʂ��Ȃ��ꍇ�ɂ́A����ȊO�̏؋����@�ɂ���ď��n�_��̑��݂��F�肳��Ȃ�����A���쌠�̏��n�͂Ȃ��������̂Ɣ��f�����B�]���āA�_�ʂ̂Ȃ����Ƃɂ��s���v�́A���s�@���x�̂��Ƃł����n���咣���鑤�ɔ������Ă���A�_�ʈȊO�̕��@�ɂ�蒘�쌠���n�𗧏�����ꍇ�ɂ������ے肷��@���x�̕K�v���E�Ó����ɂ��ċ^�₪���邱�ƁA
�j�@�䂪���̖����i�ׂł́A���쌠�̏��n�ɂ�����������ꍇ�ɂ́A���쌠�̏��n���������Ǝ咣����҂����̓_�ɂ��Ď咣�E���ؐӔC���Ƃ���A�_�ʂ��Ȃ��ꍇ�ɂ́A����ȊO�̏؋����@�ɂ���ď��n�_��̑��݂��F�肳��Ȃ�����A���쌠�̏��n�͂Ȃ��������̂Ɣ��f�����B�]���āA�_�ʂ̂Ȃ����Ƃɂ��s���v�́A���s�@���x�̂��Ƃł����n���咣���鑤�ɔ������Ă���A�_�ʈȊO�̕��@�ɂ�蒘�쌠���n�𗧏�����ꍇ�ɂ������ے肷��@���x�̕K�v���E�Ó����ɂ��ċ^�₪���邱�ƁA
![]() �j�@�ނ��뎩�R�S�؎�`�̂��Ƃōٔ������ʎ��Ăɉ������K�Ȏ����F��y�ь_����߂��s�����Ƃɂ��A�����I�������Ȍ��_����Ɗ��҂ł��邱�ƁA
�j�@�ނ��뎩�R�S�؎�`�̂��Ƃōٔ������ʎ��Ăɉ������K�Ȏ����F��y�ь_����߂��s�����Ƃɂ��A�����I�������Ȍ��_����Ɗ��҂ł��邱�ƁA
�������邱�Ƃ��ł���B
�@�܂��A���ԂƂ��Ă��A
![]() �j�@���앨�̒��ɂ͉f���Q�[���\�t�g�̂悤�Ɍo�ϓI���l�̑傫�����̂�A������|�p�ʐ^�̂悤�ɍ��x�̐��_�I�����̏��Y�ł�����̂��܂܂�锽�ʁA�Ɩ�����X�i�b�v�ʐ^�̂悤�ɂ�������I�ɍ쐬�������̂������܂܂�A�����̒��쌠�̏��n�Ɉꗥ�Ɍ_�ʂ�v������͕̂K�������K�ł͂Ȃ��Ǝv����B
�j�@���앨�̒��ɂ͉f���Q�[���\�t�g�̂悤�Ɍo�ϓI���l�̑傫�����̂�A������|�p�ʐ^�̂悤�ɍ��x�̐��_�I�����̏��Y�ł�����̂��܂܂�锽�ʁA�Ɩ�����X�i�b�v�ʐ^�̂悤�ɂ�������I�ɍ쐬�������̂������܂܂�A�����̒��쌠�̏��n�Ɉꗥ�Ɍ_�ʂ�v������͕̂K�������K�ł͂Ȃ��Ǝv����B
�Ȃ��A��ҕی�̌����̕K�v���ɂ��ẮA�ȉ��̗��R����A���쌠�̏��n�_��Ɋւ��ĉ��炩�̎蓖���K�v�ȍ����������ɂ͂Ȃ��ƍl����B
![]() �j�@���n�I���쌠�҂ɂ͗�ׂȌl�̒���҂݂̂Ȃ炸�A��K�͂ȃ\�t�g�E�F�A��ЁE�f�搻��ғ��̖@�l��A�l�ł����Ă�����ȗ����L���钘��҂�����A���n�I���쌠�҂��K�������Љ�I�E�o�ϓI��҂ł���ƒf���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����ƁA
�j�@���n�I���쌠�҂ɂ͗�ׂȌl�̒���҂݂̂Ȃ炸�A��K�͂ȃ\�t�g�E�F�A��ЁE�f�搻��ғ��̖@�l��A�l�ł����Ă�����ȗ����L���钘��҂�����A���n�I���쌠�҂��K�������Љ�I�E�o�ϓI��҂ł���ƒf���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����ƁA
![]() �j�@�Љ�I�E�o�ϓI��ҕی�̖@���x�Ƃ��ẮA����ϑ��_��ɔ������쌠���n�̃P�[�X�ɑΏۂ�������Ǝv���邪�A���ɉ����@�ɂ��K�������݂��Ă���A���쌠�@�Ƃ͈قȂ�@���x�̂��ƂŎЉ�I�E�o�ϓI��҂ł��钘��҂̕ی��}��]�n�����邱�ƁA
�j�@�Љ�I�E�o�ϓI��ҕی�̖@���x�Ƃ��ẮA����ϑ��_��ɔ������쌠���n�̃P�[�X�ɑΏۂ�������Ǝv���邪�A���ɉ����@�ɂ��K�������݂��Ă���A���쌠�@�Ƃ͈قȂ�@���x�̂��ƂŎЉ�I�E�o�ϓI��҂ł��钘��҂̕ی��}��]�n�����邱�ƁA
�@�������A���O���̖@���x�Ɣ�r�����ꍇ�A�䂪���̖@���x�����Ȃ����ł��邱�Ƃ���A����A���ɉ䂪���ɂ����Ē��쌠�̏��n�_���v���_�����ꍇ�ɂǂ̂悤�ȕs�s���������邨���ꂪ���邩�ɂ��āA����ɋc�_��[�߂�K�v������B
�@�܂��A���ۉ��̐i�W�ɔ����A���쌠�����ێ���ɂ���ď��n�����ꍇ�������Ȃ��Ă��邪�A�䂪���̖@���x�����쌠���n�ɂ��Č_�ʂ̍쐬��v�����Ȃ��Ƃ���A���O���ł͌_�ʂ�v������邱�Ƃ��������Ƃ���A
![]() �j�@�䂪���̒��쌠�����n����_��̏����@���_�ʂ�v�����鍑�̖@���ł������ꍇ�A
�j�@�䂪���̒��쌠�����n����_��̏����@���_�ʂ�v�����鍑�̖@���ł������ꍇ�A![]() �j�@�t�ɁA���쌠���n�Ɍ_�ʂ�v�����鍑�ɂ����钘�쌠���A�䂪���̖@���������@�Ƃ���_��ɂ���ď��n����ꍇ�A�̂��ꂼ��ɐ����鍑�ێ��@��̖��i
�j�@�t�ɁA���쌠���n�Ɍ_�ʂ�v�����鍑�ɂ����钘�쌠���A�䂪���̖@���������@�Ƃ���_��ɂ���ď��n����ꍇ�A�̂��ꂼ��ɐ����鍑�ێ��@��̖��i![]() 75�j���������Ă����K�v������B
75�j�������������K�v������B
�@
�@�܂��A�O���̍ٔ����ő���ꂽ�ۂɂǂ̂悤�Ȍ��_�ɂȂ�̂��ɂ��Ă��A���ӂ��K�v�ł���B
�i
�i
�i
�y�Q�l�����z
�E���쌠���x�R�c��\�i���a41�N4���j
|
|||||||||
�E���쌠���x�R�c��\������
|
||||||
�E���쌠�R�c��}���`���f�B�A���ψ���[�L���O�E�O���[�v�����o�ߕi����7�N2���j
|
||||||||||||||||||
�y�O���̗��@��z
�E��i
��204���@���쌠�̈ړ]�̎��s�i
| �@ | �ia�j | �@���쌠�̈ړ]�́A�@�̍�p�ɂ����̂������A���n�؏��܂��͈ړ]�̋L�^�������͊o�������ʂɂč쐬����A���A�ړ]����錠���ۗ̕L�҂܂��͂��̓K�@�Ɏ������ꂽ�㗝�l���������Ȃ���Ό��͂�L���Ȃ��B |
| �ib�j | �� |
�E�p��
�i���n�y�ы����j
��90���i
| �@ | �i1�j | �i2�j�� |
| �i3�j | �@���쌠�̏��n�́A���n�l�ɂ��A���͂��̎҂̂��߂ɏ������ꂽ���ʂɂ��Ȃ�����A�L���ł͂Ȃ��B | |
| �i4�j | �� |
�E�t�����X
| �@��131��2���i |
||
| 2 | ���̑��̂�����̏ꍇ�ɂ��A���@�T��1341�������1348���܂ł̋K�肪�A�K�p����顁i |
|
�Ȃ��č��ł͌_���ʖ@���Ƃ��ā@UCC��201���E��202��������A���ȏ�̎���ɂ��Ă̏��ʂ̍쐬��v������ƂƂ��Ɍ����؋��r�����K�肵�Ă���B
�i
�i
�i
�i
�i4�j���쌠�@��61���1���̉��߂ɂ��āi�ꕔ���n�ɂ����錠���̍ו����̌��E�j
�@���쌠�́A���̑S�����͈ꕔ�����n���邱�Ƃ��ł���i��61���1���j�B
�@���쌠�@�́A���쌠�̈ꕔ�����n���邱�Ƃ��ł���Ƃ��Ă��邪�A�����ł����ꕔ�Ƃ͂ǂ̂悤�ȒP�ʂ��w���̂��A���p�`�ԁA���ԁA�n��ɂ��ו������F�߂���̂��ɂ��Ă͖��炩�ł͂Ȃ��B
�@�����쌠�@��2���́A�u���쌠�n�V�����n�X���R�g�����v�ƒ�߂Ă������A���a9�N�@����48���ɂ��A�o�Ō��̑n�݂Ɠ����Ɂu���쌠�n���m�S�����ꕔ�����n�X���R�g�����v�Ɖ������ꂽ�B���s���쌠�@�́A���̋K������̂܂܈����p���ł���B
�@�E�����쌠�@���@���i����32�N�j
�@���쌠�̏��n�ɂ��ẮA����32�N���莞����A�o�^���R�v���Ƃ���Ă������i��15���3���j�A�����炭��q���鏺�a6�N���쌠�@�{�s�K���̐���܂ł́A�u���s���݂̂̏��n�v��u�N�������肵�����n�v��o�^�ł��鐧�x�͗p�ӂ���Ă��Ȃ������悤�ł���B
�@�E���쌠�@�������āi�吳15�N�j
�@�������O�Y���O���̋c�����A������t�������쌠�̏��n���\�ł���|���K�肷��āi![]() 81�j���܂ށu���쌠�@�������@���āv�i�吳15�N��51�c��j���o�������A�R�c�����ɂ��s�����ɏI����Ă���B
81�j���܂ށu���쌠�@�������@���āv�i�吳15�N��51�c��j���o�������A�R�c�����ɂ��s�����ɏI����Ă���B
�@�E���쌠�@�{�s�K���i���a6�N�j
�@�����Ȃ́A���a6�N7��28������̒��쌠�@�{�s�K����3���ɂ����āA�ꕔ���n�E�����t�ړ]�̓o�^�葱���߂Ă���i![]() 82�j�B���̎{�s�K������ɂ��Ẳ���͌�����Ȃ��������߁A���̎����ɂ��̂悤�ȉ������Ȃ��s�����̂��͕s���ł���B�܂��]�O����s���Ă����o�^�����𖾕����������̂��A�ύX�������̂����s���ł���B�������Ȃ���A���Ȃ��Ƃ����NJ�����������Ȃ̍l���Ƃ��ẮA�ꕔ���n����t���n���\�ł���Ƃ̗����ɗ����Ă������Ƃ͊m���ł���B
82�j�B���̎{�s�K������ɂ��Ẳ���͌�����Ȃ��������߁A���̎����ɂ��̂悤�ȉ������Ȃ��s�����̂��͕s���ł���B�܂��]�O����s���Ă����o�^�����𖾕����������̂��A�ύX�������̂����s���ł���B�������Ȃ���A���Ȃ��Ƃ����NJ�����������Ȃ̍l���Ƃ��ẮA�ꕔ���n����t���n���\�ł���Ƃ̗����ɗ����Ă������Ƃ͊m���ł���B
�@�E�����쌠�@�̈ꕔ�����i���a9�N�j
�@�o�Ō��̑n�݂ɔ����A���쌠�̈ꕔ���n���\�ł��邱�Ƃ��m�F�I�ɋK�肷��������s��ꂽ�i![]() 83�j�B
83�j�B
�@�Ȃ��A�{�����̋N���S���҂ł��������ѐq�����́A���̉����͑吳15�N�����Ă̑�2���y�ё�2����4�̉����ĂƁu�S�������|�ɑ��������́v�ł���Ƃ��Ă���i![]() 84�j�B
84�j�B
�@�E���쌠���x�R�c��\�E���\�������i���a41�N�j
�@���a9�N������A���ߏ�y�ю����㒘�쌠�̉����͈̔͋y�я��n�̍ۂɕt�����鐧���͈̔͂��s���m�ł���Ƃ�����肪�����A����͒��쌠���x�R�c��ɂ����錟���������F������Ă������ł������B�Ⴆ�A���\�R�c�̒i�K�ɂ����āA���܂�ɂ��ו������ꂽ���쌠�̕������n�̓o�^�͕����ȁi�����j�ɂ����Ď��Ȃ��悤�ɑ[�u���邱�Ƃ��]�܂����Ƃ̎w�E���ꕔ�̈ψ����炠�����Ƃ����B
�@�������Ȃ���A���쌠���x�R�c��\�͂��̖��ɂ��Ă͐G�ꂸ�A���\�������ɂ����āA���쌠�̑S�����͈ꕔ�����n���邱�Ƃ��ł���Ƃ��鋌���쌠�@���ێ�����Ɛ�������ɗ��܂��Ă���B
�i
| �@ | �����@���쌠�n�������t�V���n�t�Z�X�V�e�V�����n�X���R�g���� | |
| �����m�l�@���쌠���n�m�ꍇ�j���e���m�s�׃��׃X�����n�ʒi�m�_��i�L�����ړ]�Z�U�����m�g�X | ||
| �@ | ��`�l�@�i���j | |
��O���@���쌠�m�ꕔ�ړ]���n�����t�ړ]�m�o�^���\���X���ꍇ�j���e �n�ړ]�X�x�L������ �n�������o�^�\�����j�L�ڃX�x�V���쌠���n�V���ړI�g�X�������m���p�l�K�����i���ꍇ�j���e�o�^�����j�����m��A���g�L���m�����j�t�����W �i
�i
�@�E�ꕔ���n��F�߂�Ӌ`
�@�䂪�����쌠�@�́A���쌠�̏��n���͏o�Ō��̐ݒ�ȊO�ɁA��O�҂����앨�̗��p�ɂ��Ắu�����I�Ȍ����v�邽�߂̐��x��L���Ă��Ȃ��B���s���x�ł́A�����͑S�č��I�����ł���A�틖���ҁi���C�Z���V�[�j�́A�Ɛ藘�p�����_������Ƃ��Ă����Y�Ɛ萫�͍��I���͂����L���Ȃ����ߑ�O�҂����p���邱�Ƃɂ��ē��R�ɂ͍����~�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B����ɁA���p�����ɂ��đR�v�����x�����݂��Ȃ����߁A���쌠�ҁi���C�Z���T�[�j���j�Y�����ꍇ���O�҂ɒ��쌠�����n���ꂽ�ꍇ�A�����������Y���앨�𗘗p���邱�Ƃɂ��Ă��A�j�Y�Ǎ��l�����l�ɑR���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ɖ�����Ă���B
�@���앨�ɂ͑��l�ȗ��p�`�Ԃ����݂��A���p�`�Ԃ��ƂɓƗ��̌o�ϓI���p�����҂�����B���앨�̗��p�ɌW��u�����I�Ȍ����v���A��O�҂ɗ^����ɍۂ��A���쌠�̑S�������n���邩���͑S�����n���Ȃ����̓�ґ��ꂵ���Ȃ��Ƃ���A���쌠�ҋy�ї��p�҂̑o���ɂƂ��ĕs�ւł���A�����ɒ��쌠�̈ꕔ���n��ϋɓI�ɔF�߂�Ӌ`������B�@�E���쌠�̉����̌���
�A�D���쌠�@�ɋ�̓I�ɋK�肳��Ă���ʓI�ȗ��p�ԗl�ʂ̌����̏��n
�@���쌠�@��21�������28���܂łɋK�肷�镡�����A�㉉���A���t���A��f���A���O���M�����ɂ��ẮA�����̒P�ʂł̏��n���F�߂���Ƃ����̂��ʐ��ł���B��61���2���̋K�肩����A���Ȃ��Ƃ��A��27���ɋK�肷�錠���A��28���ɋK�肷�錠�����������Čʂɏ��n�ł��邱�Ƃɂ��Ă͋^�����Ȃ��B�������A�@�����ɂ�蒘�쌠�@�̋K�肪�ς�������́i�Ⴆ�A�������ƌ��O���M���Ȃǁj�����邱�Ƃɂ͗��ӂ���K�v������B
�@�������Ȃ���A���쌠�@�ɋ�̓I�ɋK�肳��Ă���ʓI�ȗ��p�ԗl�ʂ̌����̏��n�ɂ��Ă��A�������Ə��n���̏��n��ʁX�ɔF�߂�K�v�������邩�ǂ����i�Ɨ��̌o�ϓI���p�����҂ł���ƌ����邩�j�A�܂��A�������ƌ��O���M���Ⴕ���͌��Ȃ��N�Q�K�蓙�ɂ����錠���Ԃ̏d���Ƃ�����肪����B
�@�Ȃ��A�u���쌠�@�ɋ�̓I�ɋK�肳��Ă���ʓI�ȗ��p�ԗl�ʂ̌������ƂɕʁX�ɏ��n�ł���v�Ƃ̉��߂́A�������āu���쌠�S���̏��n�v��������\��������B�Ⴆ�A�j�Y��������҂̒��쌠�ɂ��Ĕj�Y���c�ɋA�����邱�ƂƂȂ邪�A�j�Y�葱���̏I����ɁA�V���������i�Ⴆ�Αݗ^���j�����쌠�@�ɋK�肳�ꂽ�ꍇ�A����҂͐V����������L����Ƃ̉��ߘ_�����݂����邱�ƂƂȂ�B����́A���ӂɂ����n�ɂ��Ă����l�ł���B
�C�D�X�ɍו������ꂽ���p�ԗl�ʂ̌����̏��n
�@���쌠�@�ɋ�̓I�ɋK�肳��Ă���ʓI�ȗ��p�ԗl�ʂ̌��������ו������ꂽ�����A�Ⴆ�A���앨���p��ɖ|�ďo�ł��錠���A���y�̒��앨�����R�[�h�ɘ^�����錠���������f�扻���錠���Ƃ������A��������ʌ̌����Ƃ��ċ�ʂ���Ă���A���Љ�I�ɂ��̂悤�Ȏ�舵��������K�v�����������̂ɂ��ẮA�ו������\�Ƃ��錩������ʓI�ł��邪�A���̌��E�͖��m�ł͂Ȃ��B
�@����ɂ́A���쌠�@�ɋ�̓I�ɋK�肳��Ă���ʓI�ȗ��p�ԗl�ʂ̌��������ו������ꂽ�����P�ʂŏ��n�ł��邱�Ƃ�O��Ƃ��������i![]() 85�j������B
85�j������B
�E�D�����t�����n�i���ԓI�Ȍ����t�������n�j
�@�����t�����n�́A���n�Ƃ��Ă̌��͔͂F�߂���Ƃ���l��������ʓI�ł���B������T�_�ł��邪�u���ԓI�ꕔ�̏��n�v��F�߂����̂�����i![]() 86�j�B�����t�����n�ɂ��ẮA���ԓI�ɕ������ꂽ���쌠�̏��n�Ƃ���i
86�j�B�����t�����n�ɂ��ẮA���ԓI�ɕ������ꂽ���쌠�̏��n�Ƃ���i![]() 87�j�i�����t�����n���ꕔ���n�Ƃ��ĔF�߂�j�l�����ƁA���������t���̏��n�_��┃���߂�����t���̏��n�_��Ƃ���i�ꕔ���n�Ƃ��Ă̊����t�����n�͔F�߂Ȃ��j�l����������B
87�j�i�����t�����n���ꕔ���n�Ƃ��ĔF�߂�j�l�����ƁA���������t���̏��n�_��┃���߂�����t���̏��n�_��Ƃ���i�ꕔ���n�Ƃ��Ă̊����t�����n�͔F�߂Ȃ��j�l����������B
�@���҂̍l�����̈Ⴂ�́A�����̓����O�ɏ��n�l�E����l���j�Y�����ꍇ���Ɍ����B���Ԍ�������������A���ߓ���t�̏��n�Ɖ�����ꍇ�A���Ԃ̌��肪�o�^��Ɍ�������Ă��Ă��i���̗��ꂩ��͖{���������ׂ��łȂ����ƂɂȂ邪�j�A�����쌠�҂͏���l�̔j�Y���Ɋ��Ԑ����̑��݂��O�҂Ɏ咣�ł��Ȃ��\��������B�����t���n���ꕔ���n�Ƃ��ĔF�߂錩������́A���Ԃ����肳��Ă��邱�Ƃ���������Ă���Ό����쌠�҂͑�O�҂Ɋ��Ԃ̐������咣���邱�Ƃ��ł���B
�G�D�n������肵���ꕔ���n
�@�n������肷����n�͔F�߂���Ƃ���l��������ʓI�����A�ΊO�I�Ȍ����W���s���m�ɂȂ�A��������ꍇ�ɂ��Ă͌��͂��ے肳���\��������Ƃ��錩����A���E���ׂ����������̗��ʂ�j�~�ł���悤�ȉ��ߘ_�܂ł͋��e����Ȃ��Ƃ��錩��������B
�@�܂��A���ꍑ���i����@�̈�j�ɂ�����n��I�������\�ł��邩�ɂ��Ă͍��ۓI�ɂ��c�_�̂���Ƃ���ł���B
�i
�i
�i
�@�E���̍��Y���Ƃ̔�r
�A�D���L���̏ꍇ
�@���̎g�p�A���v�y�я������Ȃ����錠���Ƃ��ď��L�������邪�A���L���͂��̈ꕔ�����n���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��i���L�����̏��n�͏����j�B�Ⴆ�A���L�������ԓI�ɕ������đ�O�҂ɏ��n���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@���L���҂́A�����I�ɖ��͈����ԂɎx�z�����^�I�ȓ��e�̐����������O�҂ɐݒ肷�邱�Ƃ��ł���B�Ⴆ�A�y�n�̏��L���҂͒n�㌠�i���@��285���j��ݒ�ł���B
�@�n�㌠�҂́A���̒n�㌠���i�����̏ꍇ�H�앨�Ƌ��Ɂj���҂ɏ��n���邱�ƁA�y�ѓy�n�𑼎҂ɒ��݂��邱�Ƃ��ł���Ɖ�����Ă���i�i���쌠�ɂ��Ă͖��@��272���Ŗ�������Ă���j�B�n�㌠�̐ݒ�ɂ���āA���L���̔r���I�x�z�͂͐ݒ肵���͈͂ɂ��Đ�������邪�A�ݒ肵�����Ԃ��I������ΐ��������͏��ł��A���L���͎����I�Ɍ��̔r���I�x�z�͂�����B
�C�D�������̏ꍇ
�@���s�@��A�������͂��̈ꕔ�����n���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�������Ȃ���A��O�҂ɓ������̈ꕔ�̗��p�ɂ��āu�����I�Ȍ����v��ݒ肷�邱�Ƃ��ł����p���{�����x��L���Ă���B�����@�̐�p���{���́A�������@���́u�������̐����t�ړ]�i����Έꕔ���n�j�v�Ɓu�Ɛ�I���p�����v�̑o���ɑΉ�������̂Ƃ��đn�݂��ꂽ���̂ł���A�o�^���Ȃ���Ό��͂��Ȃ��B�Ȃ��A�����I�ɁA���ԁA���{�ԗl�A�n�擙�̐�����t�����o�^���\�Ƃ̎����^�p���Ȃ���Ă���B
��p���{���́A�������҂̏����Ȃ���A��O�҂ɏ��n���邱�Ɓi�����@��77��3���j��A��O�҂ɒʏ���{�����������邱�Ɓi�����@��@77��4���j���ł��Ȃ��B��p���{���ݒ莞�ɂ�����A�������҂̐N�Q�҂ɑ��鍷�~�������ɂ��ẮA�Ŕ�����17�N6��17������16�N�i��j��997����������m�肵�Ă���B
�@�o�^�����͔����v���Ƃ������߂ɁA�u�o�^�ɂ���p���{���v�͂��܂�p�����Ă��炸�A�����I�ɂ́A�u�_��ɂ��Ɛ�I�ʏ���{���v���p�����邱�Ƃ������i���ɁA��\���������������L���A��ЂɎ��{�����Ă��鎖�Ăɂ��ẮA��Ђɖَ��̓Ɛ�I�ʏ���{�����F�肳��邱�Ƃ������j�B�����āA�������̐N�Q�҂ɑ���Ɛ�I�ʏ���{���҂ɂ�鑹�Q���������ɂ��ẮA��ʘ_�Ƃ��Ĕے肷�锻��͑��݂��Ȃ��i�唼�̔���ł͌��_�Ƃ��Ă��F�e�j�B���~�����ɂ��ẮA�i�ג�N�̒i�K�ł͐�p���{���o�^���ς܂��Ă���ꍇ��A�������҂����~���������鎖�Ă��������߁A�ŋ߂̔���ł͗]�葈�_�ƂȂ��Ă��Ȃ��B
![]() ��������
��������
�@�E���s���x�̕]��
�A�D�ꕔ���n�̈Ӌ`�E�@�\
�@���앨�̗��p�s�ׂɂ��A���e�I�E���ԓI������t���ĕ����I������ݒ肷����ۏ�̕K�v�������݂��A���Ɉꕔ���n���p�����Ă���B���ۓI�ɂ��A���e�I�E���ԓI������t���ꂽ���쌠�̏��n�i�ꕔ���n�j���邢�͔r���I�������L���Ƃ���Ă���B�䂪���̒��쌠�@�́A�@��̓��e��L����o�Ō��Ƌ��ɁA�����҂����n����錠���͈̔͂�����ł���ꕔ���n�̐��x��݂��Ă���B����ɂ��A���쌠�҂͏_��ȓ��e�̔r���I�����𑼎҂Ɉړ]���邱�Ƃ��ł��A�܂����n���ꂽ�������ꕔ�ɉ߂��Ȃ����Ƃ�o�^���Ă����A��O�ҁi���n���ꂽ�����̓]���ҁj�ɑR�ł���B
�܂��ו������ꂽ�ꕔ���n��F�߂邱�Ƃ́A����҂����n���������͈̔͂�����I�ɉ��߂���]�n���L����@�\���ʂ����Ă���B
�C�D�u�ꕔ���n�̖��_�v�̌���
�@���쌠�̈ꕔ�����n���邱�Ƃɂ��ẮA���L���Ƃ̑Δ�ɂ����ė��_�I�ɖ�肪����Ƃ̎w�E������A���Ɋ��Ԃ����肳�ꂽ���쌠�̏��n�͈ꕔ���n�Ƃ͔F�߂�ׂ��łȂ��Ƃ̈ӌ�������B�������A���ۓI�ȓ����ɂ��ӂ݂�ƁA���L���Ƃ̑Δ�ɂ����Ę_���ׂ���肩�ǂ����͋c�_�̂���Ƃ���ł���A����̌������҂���悤�B�����������쌠�@�E���s���쌠�@�����쌠�̈ꕔ���n���I�ɒ�߂Ă������ƁA�܂��A�����t���n�ɂ��Ă͗��@�S���ғ����ꕔ���n�Ɋ܂܂��Ɖ����Ă������ƁA����ɃA�D�ŏq�ׂ��ꕔ���n�̋@�\���l����ƁA�ꕔ���n�̌��E�m�����闧�@���ɍs���K�v�͂Ȃ��Ɖ������B
�����A�ꕔ���n��F�߂邱�Ƃ̎����I�Ȗ��_�Ƃ��āA�@���W�̕��G���ɂ�錠���W�̍������w�E����Ă���B�������A���̌����W�̍����́A��ɓ����ҊԂ̌_�邢�͓o�^�ɂ����āA���n�͈̔́i���ɗ��p�ԗl�j���\���ɓ��肳��Ă��Ȃ����Ƃɂ���Đ�������Ǝv����B�]���āA���m�ɗ��p�ԗl�����肳�ꂽ��ł��ꂪ��������Ă���ꍇ�ɂ܂ōו������ꂽ�ꕔ���n�̌��͂�ے肷�鍪���Ƃ��Ă͏\���łȂ��B�ނ����̓I�ȏ��n���ƂɁA�_��ѓo�^�̕����ɏƂ炵�ď��n�͈͂̓���E�����̉��߂ɂ����������ׂ����ł��낤�B
�E�D��ֈĂƂ��Ă̐�p���p�����x
�@�C�D�ŏq�ׂ����_�I�Ȗ��_�Ɋӂ݁A�����@�ɂ����ē������̐����t�ړ]��p����p���{����n�݂����悤�ɁA���쌠�@�ɂ����Ă���p���p���i![]() 88�j���x��n�݂��邱�Ƃ��l������B�������A�����I�Ȗ��_�Ƃ��Ă̌����W�̕��G���́A��p���p�����x�ɂ����Ă����ʂ̖��ƂȂ�i
88�j���x��n�݂��邱�Ƃ��l������B�������A�����I�Ȗ��_�Ƃ��Ă̌����W�̕��G���́A��p���p�����x�ɂ����Ă����ʂ̖��ƂȂ�i![]() 89�j�B�܂��A���쌠�̈ꕔ���n��O��Ɏ����������Ȃ���Ă��邱�Ƃ��l����ƁA�p��̕ύX�A�f�t�H���g���[���̕ύX�ɂ�薳�p�̍��������������������B
89�j�B�܂��A���쌠�̈ꕔ���n��O��Ɏ����������Ȃ���Ă��邱�Ƃ��l����ƁA�p��̕ύX�A�f�t�H���g���[���̕ύX�ɂ�薳�p�̍��������������������B
�@�E����̗��@�Ή���
�@�ꕔ���n�̌��E�m�����邽�߂����̗��@�𑁋}�ɍs���K�v�͂Ȃ��B
�������A���C�Z���V�[�ی�̗��@�y�ѓo�^���x�̌������Ƃ̊W�ňꕔ���n�̖����Č�������K�v���o�Ă���\��������B�Ⴆ�A�R�v��������邱�Ƃɂ��A�Ɛ�I�ȗ��p���������҂��Ɛ萫���O�ҁi���쌠�̏���l�A�y�ђ��쌠�҂����ɋ��������ҁj�Ɏ咣�ł���Ƃ̐��x�v���s�����ꍇ�ɂ́A�r���I�ȗ��p�����͈ꕔ���n�Ɠ��l�̕����I���͂�L���邱�Ƃɂ��Ȃ�B�܂��A���쌠�ړ]�̑R�v���Ƃ��Ă̓o�^���x���������ꍇ�ɂ́A���n�͈͂��ꕔ�ł��邱�Ƃ̌������@�ɂ��Ă����������K�v�ƂȂ낤�B
�ȏ�̂��Ƃ���A�ꕔ���n�̖��́A���C�Z���V�[�ی�̐��x�E�o�^���x�̌����̒��ŁA���쌠�҂������I�������O�҂ɐݒ�E�ړ]���邽�߂̐��x�v�̖��i��^�I�ȓ��e�݂̂�F�߂�̂�����Ƃ������҂̍��ӂɈς˂�̂��A�R�v���͂ǂ�����̂����j�Ƃ��āA��p���p�����x���܂ޒ��앨�́u���p���v�ɌW�鐧�x�̑n�݂�����ɋc�_�����ׂ����̂Ǝv����B
�i
�@(1)��p���p���̏��n�C��p���p���҂ɂ�闘�p�̋����ɒ��쌠�҂̏������K�v�ƂȂ�i�A���C���s�@�̈ꕔ���n�ł������̓���E����сu�����̐����v�Ƃ��Ă̓o�^���\�ł��邩��C�����̓f�t�H���g���[���̕ύX�ɂƂǂ܂�j�B
�@(2)��p���p���̐ݒ�͈͓��ł̐N�Q�s�ׂɑ��C��p���p���ҁE���쌠�ҋ��ɍ��~�E���Q������������L����B (3)��p���p���̓o�^�ɂ��C��p���p���҂͐�p���p���̐ݒ���O�҂ɑR�ł���B��p���p���̓��e�ɐ���������ꍇ�ɂ́C���̓o�^�ɂ�蒘�쌠�҂͑�O�ҁi���p���̏���l���j�ɂ��̐����̑��݂��咣���邱�Ƃ��ł���B
�i
�y�Q�l�����z
�E����B���Y�w���쌠�@�v�`�x�i�L��t�A1899�N�j19�ňȉ�
| �@�����@�ɉ��͐�������͕��������ď��n�����Ƃ]�X�Ƃ������������͕������邱�Ƃ͓��ɖ�������̕K�v�Ȃ��A䑂����n���邱�Ƃ�ȏ�͑��̑S������ƈꕔ����ƁA��������������ƔۂƂ͖@�̖����Ȃ����Đ��ӂɈׂ������邱�Ƃɂ��Ċ������@��̖}�Ă̌����̏��n�ɍ��邱�Ƃ�������Ɠ���Ȃ�A�̂ɖ����Ȃ������쌠�͑��̈ꕔ����|�����s���݂̂����n�����͔N�����ĔV�����n���邱�Ƃ��ܘ_�Ȃ� |
�E���ѐq�����u���s���쌠�@�̗��@���R�Ɖ��߁|���쌠�@�S�������̎����Ƃ��ā|�v�i���a33�N�����ȁj
��́@���쌠�i���Y���j�̓��e |
�E��65��鍑�c��M���@�o�Ŗ@�������@���ē��ʈψ���c�����L�^ ���{�ψ����c�i�g�i�����ȎQ�����j�ɂ���|�v�j�̐���
| �@�u�����������������܂��āA���쌠�͑��S�����͈ꕔ�����n������|�m�ɒv���܂����B���s�@�����́A�P�ɒ��쌠�͔V�����n������|���K�肵�ċ���̂ł������܂�����A�ʂ��đ��ꕔ�A��ւΖ|�݂̂Ƃ��A���͋��s���݂̂����n�����邩�ۂ������ĂłȂ��̂ł������܂��A����̖@����̖��m�ɁA���쌠�̈ꕔ�����n������|���K�肢�����܂��āA���쌠�̍��Y�I���l�̑�����͂������̂ł������܂��B�v |
�E�ꕔ���n�����鏺�a9�N3��19���̋c�_
����c�����c�� |
�E���쌠���x�R�c��\�������i���a41�N�j
�攪�@���쌠�̏��n�E���� |
�y�O���̗��@��z
�E��i
��201���@���쌠�̋A��
| �ia�j | �`�ic�j�� | |
| �id�j | ���쌠�̈ړ]�i |
|
| �i1�j | �@���쌠�́A�������i�ɂ����n�܂��͖@�̍�p�ɂ���āA���̑S���܂��͈ꕔ���ړ]���邱�Ƃ��ł��A�܂��A�⌾�ɂ���Ĉ②���܂��͖��⌾�����@�ɂ���Đl�I���Y�Ƃ��Ĉړ]���邱�Ƃ��ł���B | |
| �i2�j | �@��106���ɗ��錠�����܂ށA���쌠�Ɋ܂܂�邢���Ȃ�r���I�������A��L��i1�j���ɋK�肷��Ƃ���ړ]���A�܂��A�ʂɕۗL���邱�Ƃ��ł���B����̔r���I�����ۗ̕L�҂́A�����錠���͈͓̔��ŁA�{�҂����쌠�҂ɑ��ĔF�߂�S�Ă̕ی삨��ы~�ς��邱�Ƃ��ł���B | |
��204���@���쌠�̈ړ]�̎��s
| �ia�j | �@���쌠�̈ړ]�́A�@�̍�p�ɂ����̂������A���n�؏��܂��͈ړ]�̋L�^�������͊o�������ʂɂč쐬����A���A�ړ]����錠���ۗ̕L�҂܂��͂��̓K�@�Ɏ������ꂽ�㗝�l���������Ȃ���Ό��͂�L���Ȃ��B |
| �ib�j | �� |
�E�p���i
�i���n�y�ы����j
��90��
| �i1�j | ���쌠�́A�l�I���Y���͓��Y�Ƃ��āA���n�A�⌾�ɂ�鏈�����͖@���̍�p�ɂ��A�ړ]���邱�Ƃ��ł���B |
| �i2�j | ���쌠�̏��n���̑��̈ړ]�́A1�����Ƃ��邱�ƁA���Ȃ킿�A���̂��̂ɓK�p�����悤�Ɍ��肷�邱�Ƃ��ł���B |
| �ia�j�@���쌠�҂��s���r���I������L���鎖����1����2�ȏ�ł����đS���łȂ����� | |
| �ib�j�@���쌠���������ׂ����Ԃ�1�����ł����đS�̂łȂ����� | |
| �i3�j | �� |
| �i4�j | �@���쌠�҂ɂ��t�^����鋖���́A�Ή����x�������P�ӂ̍w���҂ł����ċ����̒ʒm�i�����̖��͐���ɂ��j���Ă��Ȃ��Җ��͂��̂悤�ȍw���҂��猠���Ă���҂������A���쌠��̗��v�ɂ��Ă̂��ׂĂ̌������p�l���S������B�܂��A���̕��ɂ����钘�쌠�҂̋����Ė��͓����ɂ����ꂩ�̂��Ƃ��s�����Ƃւ̌��y�́A����ɏ]���ĉ��߂���� |
�i�r���I�����j
��92��
| �i1�j | �@���̕��ɂ����āA�u�r���I�����v�Ƃ́A���쌠�҂��ʓr�r���I�ɍs�g���邱�Ƃ��ł��錠�����s�g���邱�Ƃ��A������t�^����҂��܂ޑ��̂��ׂĂ̎҂�r�����āA�������҂ɋ����鋖���ł����āA���쌠�҂ɂ�薔�͂��̎҂̂��߂ɏ������ꂽ���ʂɂ����̂������B |
| �i2�j | �@�r���I�����Ɋ�Â��ċ������҂́A������^����҂ɑ��ėL����Ɠ���̌������A�����ɂ��S������錠�����p�l�ɑ��Ă��L����B |
�i�r���I�������҂̌����y�ы~�ρj
��101��
| �i1�j | �r���I�������҂́A���쌠�҂ɑ���ꍇ�������A�����̕t�^�̌�ɐ����鎖���ɂ��āA���������n�ł��������̂Ƃ��āA����̌����y�ы~�ς�L����B |
| �i2�j | ���̎҂̌����y�ы~�ς́A���쌠�҂̌����y�ы~�ςƕ�������B�܂��A���̕��̊W�K��ɂ����钘�쌠�҂ւ̌��y�́A����ɏ]���ĉ��߂����B |
| �i3�j | �r���I�������҂����̏��Ɋ�Â��Ē�N����i�ׂɂ����āA�퍐�́A�i�ׂ����쌠�҂ɂ���N���ꂽ�Ȃ�Η��p���邱�Ƃ��ł���������̍R�ق������p���邱�Ƃ��ł���B |
���t�����X�i
��131��3���@����҂̌����̈ړ]�́A���n�����e���������n�؏��ɂ����Čʂ̋L�ڂ̑ΏۂƂȂ�A���A���n����錠���̗��p���삪���͈̔́A�p�r�A�ꏊ�y�ъ��ԂɊւ��Č��肳���Ƃ��������ɏ]���
2�`4�@��
��131��4���@����҂ɂ�邻�̒��앨�ɂ��Ă̌����̏��n�́A�S�����͈ꕔ�Ƃ��邱�Ƃ��ł��顏��n�́A�̔����͗��p���琶��������̔��z����҂̂��߂ɔ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��
2�E3�@��
��131��7���@�ꕔ���n�̏ꍇ�ɂ́A��������l�́A�_��ɒ�߂�����y�ѐ����ɏ]���A�_��ɒ�߂���Ԃ̊ԁA�y�ѕ̋`���������Ƃ��āA���n���������̍s�g�ɂ����Ē���҂�㗝����
�E�h�C�c�i
��31���@���p���̋��^
| 1 | �@����҂́A���앨���ʓI���p���@���͂��ׂĂ̗��p���@�ɂė��p���錠���i���p���j�𑼎҂ɋ������邱�Ƃ��ł���B |
| 2 | �� |
| 3 | �@�r���I���p���́A���̂��ׂĂ̐l�X��r���āA���ۗ̕L�҂ɑ��āA���앨���������ꂽ���@�ɂ�藘�p���錠���y�ї��p�������^���錠����^����B����҂ɂ�闘�p�͗��ۂ���Ă���Ɩ�肷�邱�Ƃ��ł���A��35���́A����ɂ��e�����Ȃ��B |
| 4,5 | �� |
�i
�i
�i
�i
�i
��34���@���p���̏��n
1�@���p���́A����҂̓��ӂ�����ꍇ�ɂ̂݁A���n���邱�Ƃ��ł���B����҂́A�M�`�����ɔ����A���̓��ӂ����ނ��Ƃ��ł��Ȃ��B
2�`5��
��35���@����Ȃ闘�p���̋��^
1�@�r���I���p�҂́A����҂̓��ӂ�����ꍇ�ɂ̂݁A���p��������ɋ��^���邱�Ƃ��ł���B�r���I���p��������҂̗��v���Ǘ����邽�߂ɂ̂��^�����ꍇ�ɂ́A���ӂ͗v���Ȃ��B
2��
�i5�j���쌠�@��61���2���̑��u�̕K�v���ɂ���
![]() ���s���x
���s���x
�@���쌠�����n����_��ɂ����āA��27�͑�28���ɋK�肷�錠�������n�̖ړI�Ƃ��ē��f����Ă��Ȃ��Ƃ��́A�����̌����́A���n�����҂ɗ��ۂ��ꂽ���̂Ɛ��肷��Ƃ��Ă���i��61���2���j�B�����āA���f�̗v���������߂ɂ́A�P�Ɂu�S�Ă̒��쌠�����n����v�Ƃ����\���ł͑���Ȃ��Ɖ�����Ă���B
�܂��A�{���ɂ�鐄��́A�����A���^�A�����A�M�����̂�������n�_��ɋy�сA�����s���쌠�@�{�s�O�ɂȂ��ꂽ�_��ɂ��K�p�����B
![]() ���̏���
���̏���
�@���̂悤�ȋK��̑��݂́A���n�_��̉��߂ɂ��Ď���I�ɓ����ҊԂ̃g���u�������������ɂȂ肩�˂Ȃ��Ƃ����ӌ�������A���쌠�@�̒P�����̊ϓ_����p�~���邱�Ƃ̐���������Ă����B���Ƀv���O�����̒��앨�̒��쌠�̏��n�ɂ��ẮA���̗��p�̎��Ԃ��瓖�Y�K���K�p���ׂ��łȂ��Ƃ������쌠�@�����v�]���o����Ă���Ƃ���ł���B
�X�ɁA��27���y�ё�28���ɋK�肷�錠���݂̂����n�ɂ�������f���邱�Ƃ����߂��Ă��邱�Ƃ́A���̑��̒��쌠�@�ɋ�̓I�ɋK�肳��Ă���ʓI�ȗ��p�ԗl�ʂ̌����ƈ������قɂ��A���x����A���o�����X�Ȃ��̂ƂȂ��Ă���Ƃ̎w�E������B
![]() ���@��|
���@��|
�@���쌠���x�R�c��́A�u���쌠�̏��n�Ɋւ��ẮA�`���I�ɂ͏��n����錠���͈̔͂̌��肪�����ꍇ�ɂ����Ă��A��̓I�ɉ����Ă��͈̔͂����肳�����̂ł���Ƃ����|�̉��ߋK���݂��邱�Ƃ��K���v�ł���Ɠ��\���Ă���i���a41�N4���j�B���̂悤�ȓ��\���o���ꂽ�̂́A�o�ŎГ��ɂ�錜������W�̂悤�Ȗɂ�钘�쌠���n�ւ̑Ή����K�v�ł���Ƃ̔F�����������Ƃ����i![]() 95�j�B
95�j�B
�i
�@���\���č쐬���ꂽ�����ȕ����ǎ��āi���a41�N10���j�ł́A���쌠���n�Ɋւ��A�u�_���\�z����Ȃ����@�ɂ�蒘�앨�𗘗p���錠���v�����n�l�ɗ��ۂ��鐄��K���u���Ă������A���̌�̌������o�āA���s��61���2���Ɠ��l�̏Ă��쐬���ꂽ�B
�@�Ȃ��A�Č����̉ߒ��ŁA���ۂ����肳��錠�������肵���m���������R�Ƃ��ẮA��1�ɁA�u�\�z����Ȃ����@�v�Ƃ����ꂪ�A���������u�_�ɑ��݂��Ȃ��������m�̗��p���@�v���܂ނ��̂ł���Ƃ�����ۂ�^���A�{���̗��@��|���āA���̂悤�Ȗ��i���ߖ��j�ɂ܂œ��Y�������K�p����邨���ꂪ���邱�ƁA��2�ɁA�����̌_��ɂ����āA��̓I�ɂǂ̂悤�Ȍ��������n���ꂽ�̂��Ⴕ���͗��ۂ��ꂽ�̂����s���m�ƂȂ�A�����Ɏx��𗈂������ꂪ���邱�ƁA���������Ǝv����B
�@�܂��A���ۂ����肳��錠�����27���y�ё�28���ɋK�肷�錠���Ɍ��肵���̂́A���쌠���x�R�c��\���O���ɒu���Ă����u�������ւ̓��e�v�̂悤�ȏ��n�_��ɂ��ẮA��1�ɁA���쌠�̏��n�́A���앨������̂܂܂̌`�Ԃŗ��p���錠���̏��n����e�Ƃ͂��Ă��Ă��A����ɕt�����ėႦ�Ώ������f�扻������|���肷��Ƃ������A�I���앨���쐬�����藘�p�����肷�邱�Ƃɂ��Ă̌����܂ł��ړ]���邱�Ƃ́A��ʂɗ\�肵�Ă��Ȃ��Ƃ������f�ƁA��2�ɁA��̓I�ȓI���앨�̍쐬�E���p���\�肳��Ă��Ȃ��ɂ�������炸�A�I���앨���쐬�E���p���錠��������҂���ړ]���邱�Ƃ́A����ҕی�Ɍ�����Ƃ������f�����������̂Ǝv����B
�@��61���2���̋K��ɂ��ẮA����13�N�̑������ψ���A����14�N�̌_��E���ʏ��ψ���A����15�N�̖@����菬�ψ���ɂ����āA�u���쌠�@�̒P�����v�Ƃ����ϓ_�ŁA���̑����̐��������ꂽ���A�^�ۗ��_������A�@�����ɂȂ��錋�_�ɂ͎���Ȃ������B
![]() �������e
�������e
�@�E�K�p�͈͂̑Ó���
�A�D��ƊԂ̏��n
�@���쌠���x�R�c��̓��\�̑O��ɂ��������ӎ����炷��A��ƊԂōs����A�ɂ�炸���ɂ��_����쐬���钘�쌠���n�ɂ��āA�{���K�p�̕K�v���͒Ⴂ�Ǝv����B
�C�D�v���O�����̒��앨�̒��쌠�̏��n
�@�v���O�����̒��앨�́A���쌠���x�R�c��̌��������ɂ͈ӎ�����Ă��Ȃ��������앨�ł���A���A���\���O���ɒu���Ă������쌠���n�_��̏ꍇ�ƈقȂ�A����l�����ς�|�Ă��ė��p���邱�Ƃ���ʓI�ł���B�܂��A�l����҂���Ƃɒ��쌠�����n���邱�Ƃ��z�肵�������B�]���āA�v���O�������앨�̒��쌠�̏��n�ɂ��āA�{���K�p�̕K�v���͒Ⴂ�Ǝv����i![]() 96�j�B
96�j�B
�E�D���ۂ����肳��錠���͈̔�
�@���쌠���x�R�c��\�ɏ]���Ȃ�A���n�l�ɗ��ۂ���錠�����27���y�ё�28���ɋK�肷�錠���Ɍ��肷�闝�R�͖R�����悤�Ɏv����B
�Ȃ��A��27���y�ё�28���ɋK�肷�錠���𗯕ۂ��邱�Ƃɂ��ẮA�u�n�슈�������シ��Ƃ����Ӗ��ł�����Ȃ�̍�������F�߂邱�Ƃ��ł���B�v�Ƃ��錩���i![]() 97������B
97������B
�i
�i
�@�E�K��Ƃ��Ă̗L����
�@�̍쐬�҂́A���n����錠���ɑ�27���y�ё�28���ɋK�肷�錠�����܂܂�Ă��邱�Ƃ���L����A�{�K��̐���̓K�p��Ƃ�邱�Ƃ��ł���B�����āA���L���邱�Ƃ͖쐬�҂��{����m���Ă���A���������Ƃł͂Ȃ��B���̏ꍇ�A�{���́A���n����錠���ɑ�27���y�ё�28���ɋK�肷�錠�����܂܂�Ă��邱�Ƃ��A���쌠�@�ɐ��ʂ��Ă��Ȃ����n�l�Ɏ��o������ȏ�̌��ʂ͂Ȃ��B
�@�E���n�l���o�ϓI��҂Ɖ��肷�邱�Ƃ̑Ó���
�@���쌠���n�_��ɂ����āA��ɁA���n�l������l�ɑ��āu��ҁv�ł���Ƃ��邱�Ƃ͍���ł���B�]���āA���n�_���ʂɂ��āA���n�l���u��ҁv�Ƃ��ĕی삷�邱�Ƃ͓K���ł͂Ȃ��B
�@�������Ȃ���A���쌠���x�R�c����\�ɓ�����O���ɒu���Ă����A�u�������ւ̓��e�v�̗ތ^�ɂ��āA�l�����n�l�ŏo�ŎГ�������l�ł�����n�_��ł����āA�o�ŎГ����쐬�������K�p�����悤�ȏꍇ�ɂ́A�o�ŎГ��ƌl�Ƃ̊Ԃŏ��̎��y�їʁA�����Č��͂̊i�������݂���l�Ɗ�Ƃ̖_��ł���A�l���u��ҁv�Ƃ��ĕی삷�ׂ��ł���Ƃ���Ƃ̍l�������Ƃ�Ȃ�A���@�ɂ�鉽�炩�̎蓖�����������K�v�ł���B
�@�����钘�쌠�̏��n�_��ɂ��Ė{����K�肪�K�p�����̂́A�K�p�͈͂��L���Ȃ�߂��邽�ߓK���ł͂Ȃ����A����ŁA���쌠���x�R�c��O���ɒu���Ă�����������ւ̓��e��̂悤�ɁA�l����o�ŎГ��ɑ��A�o�ŎГ����쐬�����ɂ���Ē��쌠�����n�����悤�ȏꍇ�ɂ��ẮA�����������炩�̗��@�ɂ��蓖���K�v�Ǝv����B
�@�������Ȃ���A���炩���ߖ쐬�҂���27���y�ё�28���ɋK�肷�錠����ɂ����ē��f���Ă���ΈӖ����Ȃ��A���쌠�҂ɏ��n���钘�쌠�͈̔͂ɂ��ĔF����������x�̌��ʂ����Ȃ��B�܂��A���쌠�҂����쌠�@�̖{����K���m��Ȃ���~�ςɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ̎w�E������B
�@�܂��A��27���y�ё�28���ɋK�肷�錠���̂݁A��������ʂȐ���K��ɂ����炵�߂�K�R���͖R�����B
�@�ȏ�̂��Ƃ���A��61���2���͔p�~�̕����Ō������ׂ��ł��邪�A�{�K��͂����܂Ő���K��ł��邱�ƁA�y�єp�~����ꍇ�ɂ͒��쌠���x�R�c��O���ɒu���Ă����o�ŎГ��ɂ�錜������W�̂悤�Ȗɂ�钘�쌠���n�Ƃ��������̏��n�_��ɂ��ĉ��炩�̎蓖���s���K�v������ƍl������Ƃ��납��A����ɂ����ẮA�{�K��݂̂��ɔp�~���邽�߂̖@�������s�����Ƃ͓K���ł͂Ȃ��B
�E�����R�c��쌠���ȉ���i����16�N1���j
|
�y�O���̗��@��z
�E�t�����X�i
��131��3���@����҂̌����̈ړ]�́A���n�����e���������n�؏��ɂ����Čʂ̋L�ڂ̑ΏۂƂȂ�A���A���n����錠���̗��p���삪���͈̔́A�p�r�A�ꏊ�y�ъ��ԂɊւ��Č��肳���Ƃ��������ɏ]
| 2 | �� |
| 3 | �@�����o�|�Č���ΏۂƂ�����n�́A������앨�̖{���̏o�łɊւ���_��Ƃ͕ʌ̕����ɂ��_�̑ΏۂƂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ�� |
| 4 | �� |
�E�h�C�c�i
��31���@���p���̋��^
| 1�`4�� | |
| 5 | �@���p�������^����ɍۂ��āA���p���@�����m�ɂЂƂЂƂ\������Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�������҂���b�Ƃ����_��ړI�ɂ��������A���p���������Ȃ闘�p���@�ɋy�Ԃ������肳���B���p�������^���ꂽ���ۂ��A�ʏ험�p�����r���I���p�����A���p���y�ы֎~���͂����Ȃ�͈͂ɋy�Ԃ��A���тɗ��p���͂����Ȃ鐧���ɕ����邩�ɂ��Ă��A���l�Ƃ���B |
�E�C�^���A�i
��3�߁@�o�Ō_��
��119��
| 1 | �@�_��́A�_�Ɍ��͂����@���ɂ���ċK�肳���_��͈̔͂���ъ��Ԃɂ��āA����҂��o�łɊւ��Ē���҂ɑ����闘�p���̑S���܂��͈ꕔ����e�Ƃ��邱�Ƃ��ł���B |
| 2 | �@���̖�肪�Ȃ�������A�ړ]���ꂽ�����͔r���I�����ł���Ɛ��肳���B |
| 3 | �@�����̖@���ɂ���ė^�����錠������т��L���͈͂܂��͂�蒷�����Ԃ̒��쌠�ی���K�肷�鏫���̌����́A�ړ]�ɂ͊܂܂�Ȃ����̂Ƃ���B |
| 4 | �@�����̖�肪�Ȃ�������A�ړ]�́A�f��ɖ|�Ă��A�������A����ы@�B�I�@��ɘ^�����邱�Ƃ��܂ށA��ɒ��앨�ɂȂ����ύX����ς̗��p���ɂ͋y�Ȃ����̂Ƃ���B |
| 5 | �@���̖�肪�Ȃ�������A���p����1�܂���2�ȏ�̌����̈ړ]�́A��1�҂̋K��ɂ��ƂÂ��A���̌����������ނ̔r���I�����Ɋ܂܂��ꍇ�ł����Ă��A�ړ]���ꂽ�����ɂ͕K�������]�����Ȃ����̌����̈ړ]���܂ނ��̂ł͂Ȃ��B |
�i
�i
�i
�i6�j���m�̗��p���@�ɌW��_��ɂ���
�@���쌠�҂����앨���O�҂ɗ��p��������@�Ƃ��ẮA�_��ɂ�钘�쌠�̏��n�Ɨ��p�����i�ȉ�6�D�ɂ����āu���p�_��v�Ƃ���j������B�������A���p�_��̉��߂Ɋւ���K��Ƃ��ẮA��61���2���Ƒ�63���4����u���݂̂ł���B
�@�����҂����p�_��̒������ɗ\�������Ȃ��������앨�̗��p���@�i�ȉ��u���m�̗��p���@�v�Ƃ����j���A���p�_��̑ΏۂɊ܂܂�Ă��邩�ۂ��ɂ��āA�����ҊԂŖ��ƂȂ�ꍇ������B
�@�E���쌠�ҕی�̕K�v���̖��ɂ���
�@�܂����ƂȂ�̂́A���앨�̗��p�_��̉��߂ɂ����āA��ʂɁu���쌠�҂͎�҂ł���v�Ƃ������R����ی삳���ׂ��ł���ƍl���A���p�_��ɂ��^�����闘�p���͈̔͂�����I�ɉ��߂���Ƃ̌������̂�ׂ����ǂ����Ƃ����_�ł���B
�@���O���̗���Q�l�ɂ���ƁA���앨��n�삵������҂́A���앨��������o���ꂽ������o�Ϗ�̗��v�Ɋ֗^��������ׂ��ł���A����҂ɏ\���ɕ邱�ƂȂ����앨�̗��p���痘�v���l�����邱�Ƃ͐��`�ɔ�����Ƃ������n����A���p�_��ɂ����ČʓI�ɕ\�����ꂽ���p�ړI�ȊO�͊܂܂ꂸ�A���m�̗��p���@��ړI�Ƃ��闘�p�_��͖����ł���Ƃ̋K���݂��邱�Ƃ�A���p�_��̉��߂ɓ������ẮA�u�^�킵���͒���҂ɗL���ɉ��߂���v�Ƃ����������̗p���ׂ��ł���Ƃ̍l���������肤��B
�@�������A�ꗥ�Ɂu���쌠�҂͎�҂ł���v�Ƃ̑O����̂邱�Ƃ́A�K�������K�ł͂Ȃ��ƍl������B����ŁA���������̎Ⴂ�l�̒���҂����p�_��̈�������҂ł���ꍇ�ɂ́A�_������ɂ����Čo�ϗ͂܂��͏��͂̊i������\���Ȍ��͂�L�����A���Ƃ����ȂɂƂ��ĕs���ȓ��e�̗��p�_��ł����Ă����ۂɂ͌_�������]�V�Ȃ������Ƃ������Ԃ͏\���ɂ��蓾��Ƃ���ł��邪�A�����ŁA���Ƃ����쌠�҂Ƃ��ė��p�_��̈�������҂ł���ꍇ�����Ȃ��Ȃ��A���p�_��̎��Ԃ͐獷���ʂł���B��������ƁA�S�Ă̗��p�_��ɂ��āA�u���쌠�҂͍\���I�Ȏ�҂ł���v�Ƃ̑O��Ŗ@������ʂȈ��������邱�Ƃ́A����ɂ����v���Ȃ��ł��낤�B
�@���������āA���̓_�́A�䂪���ɂ����闘�p�_��̎��Ԃ������܂��������ŁA�ʋ�̓I�ȃP�[�X���ƂɌ�������̂��K�ł���ƍl������B
�@�E���p�_��̉��߂̖��ɂ���
�@�ȏォ�炷��ƁA�����҂����p�_��̒������ɗ\�������Ȃ��������m�̗��p���@�����p�_��̑ΏۂɊ܂܂�Ă��邩�ۂ��́A�ʂ̗��p�_��̉��ߖ��ɋA������ƍl������B�@�����ł̖��̎����́A�V���ȋZ�p���W���ɂ���Ď����������앨�̐V���ȗ��p���琶����o�ϓI�Ȏ��v���A���p�҂݂̂��l������Ɖ����Ă悢���A����Ƃ��A���쌠�҂ɂ������͈̔͂Ŏ��v�̕��z��F�߂�ׂ��ł��邩�ۂ��ɂ���B
�@�����̗��p�_�������������_�ɂ����ẮA�_���҂��A���ƂȂ��Ă���V���ȗ��p���@�ɂ��Ắu�\�������Ȃ������v�̂ł��邩��A�����҂̈ӎv���K���������ߎ�ɂ͂Ȃ�Ƃ͌����Ȃ��B��������ʘ_�Ƃ��ẮA���n�l���擾���ׂ������̕s�m��Ȏ��v�ɑ��錠�����_��ɂ���ĕ�I�ɏ��n���邱�Ƃ��\�ł��邩��A���쌠�҂����Y���p���@�̌o�ϓI���l��F��������ŗ��p�_���������Ă��Ȃ�����Ƃ����āA��ʂɗ\�������Ȃ��������p���@�����p�_��̑ΏۂɊ܂܂�Ȃ��Ƃ����킯�ł��Ȃ��B
�@��������ƁA���m�̗��p���@�����p�_��̑ΏۂɊ܂܂�Ă���Ɖ����ׂ����ǂ����̔��f�ɂ������ẮA���쌠�҂����p�_��Ɋ�Â����앨�̗��p�ɂ��āA�\���ȑΉ��Ă���ƕ]������邩�ۂ����d�v�ƂȂ낤�B
�@���̓_�ł́A���p�̑Ή��̌�����@�Ƃ��āA���p�҂��擾������v�ɔ�Ⴕ�����@���̂��Ă���ꍇ�ɂ́A�V���ȕ��@�𗘗p�_��Ɋ܂߂ĉ����Ă�����قǖ��͐����Ȃ��Ǝv����B���ƂȂ�̂́A�ꊇ����z�̑Ή��ɂ���āA��I�ɗ��p�����t�^���ꂽ�ꍇ�ł��邪�A���̏ꍇ�ɂ��ẮA�����̕s�m��ȗ��p���@���瓾������v�̉\�����A�����҂��\���ɕ]��������ŁA�Ή������肵���Ƃ݂邱�Ƃ��ł��邩�ǂ������d�v�ȍl���v�f�ƂȂ�ł��낤�B
�@�E���ߕ��@�E���ߏ����̗��@���̕K�v��
�@�ȏ�̂悤�ȍl�����ɗ��Ƃ��ɁA���m�̗��p���@�Ɋւ��A���p�_��̉��ߕ��@�Ȃ������ߏ����쌠�@�ɐ݂���ׂ����ۂ������ƂȂ�B���p�_��̉��߂��������̓I�ȏ�ʂƂ��ẮA���̓����ʂ��邱�Ƃ��ł��悤�B
�A�D���p�_��Ɂu�ʂ̗��p�ړI���f�L����Ă����ꍇ�v
�@���p�_��ɂ����āu�ʂ̗��p�ړI���f�L����Ă����ꍇ�v�ɂ́A���m�̗��p���@������Ɋ܂܂�邩�ǂ����Ƃ����`�Ŗ�肪�����B�T�^��Ƃ��ẮA�]���̓A�i���O�`���ŗ��p���Ă������앨���f�W�^�������ė��p����ꍇ�ɁA���ꂪ�����̗��p�_��̑ΏۂɊ܂܂�邩�ۂ������ƂȂ�ꍇ�Ȃǂ�����B
�@���̏ꍇ�ɁA�Ⴆ�A�u�����̗��p�_��Ɍf�L���ꂽ���p�ړI�܂��͗��p���@�ƌo�ϓI�ɓ�����������̂́A���i�̎���Ȃ�����A�����̗��p�_��̓��e�Ɋ܂܂��v�Ƃ��������ߋK���݂��邱�Ƃ��l������B�������A��L�̍l�����ɗ��ĂA�u�o�ϓI�ɓ��������邩�v�̔��f�́A��̓I�ȃP�[�X�ɑ���������������I�ɍl�������ׂ��ł��邩��A���̂悤�ȉ��ߏ�����݂��邱�Ƃɂ���قǂ̗L�p���͔F�߂��Ȃ��Ƃ�����B
�C�D���p�_��Ɂu��I�ȕ������g���Ă���ꍇ�v
�@���p�_��̕�����́A�T�^��Ƃ��ẮA�u���ׂĂ̕����������n����v�̂悤�ɁA��I�Ȍ`�ŗ��p�_��̑Ώۂ�������Ă���ꍇ������B���̏ꍇ�ɂ́A���p�_��̕������`���I�ɂƂ炦��A���m�̗��p���@�ɂ��Ă��_����e�Ɋ܂܂��Ɖ��߂��ׂ����ƂɂȂ邪�A��L�̍l�������炷��A���p�_��͈̔͂����肵�ĉ��߂��邱�Ƃ��\���ɉ\�ł���B
�@���̏ꍇ�ɍٔ������p���邱�Ƃ��ł���@�I��@�Ƃ��ẮA���p�_��������I�Ȃ�������I���߂ɂ��ق��A�����Ǒ��i���@��90���j�ɂ�藘�p�_��̌��͂��ꕔ�ے肷�邱�ƂȂǂ��l������i�������n�l�ɐ����ׂ����v�̕�I�ȏ����̗L�����ɂ��ẮA�������̈ꊇ���n�Ɋւ��锻��i��3��������11�N1��29�����W53��1��151�Łj���Q�l�ɂȂ�j�B
�@�ȏォ�炷��A���m�̗��p���@�Ɋւ��闘�p�_��̉��ߖ��ɂ��ẮA�ʋ�̓I�Ȏ��Ăɑ����āA���@�̈�ʌ�����p���čٔ����������I�ȉ��߂��s�����ƂɈςˁA����̏W�ς�ʂ��Ė@�`�����Ȃ����̂��K�ł���A���Ȃ��Ƃ������_�ɂ����ẮA���쌠�@�ɓ��ʂȋK���݂���K�v�͂Ȃ��ƍl����B
�@�Ȃ��A��L�̂悤�ȍٔ����ɂ�闘�p�_��̉��ߓ��ɂ��Ή��ɂ͌��E�����邱�Ƃ����������ꍇ�ɂ́A���O���̖@���ō̗p����Ă���@�I��@���Q�l�ɂ��Ȃ���A�䂪���ɂ����闘�p�_��̎��ԓ��̔c���܂��A�K�ȗ��@�Ή��̉\���ɂ��Č������s�����ƂƂȂ낤�B
�y�O���̗��@��z
�E��i![]() 101�j
��203���@����҂̌����t�^�ɂ��ړ]����юg�p�����̏I��
101�j
��203���@����҂̌����t�^�ɂ��ړ]����юg�p�����̏I��
�ia�j�I���̏���
�@�E�����앨�ȊO�̒��앨�̏ꍇ�A1978�N1��1���Ȍ�ɒ���҂��⌾�ȊO�̕��@�ɂ���čs�����A���쌠�܂��͂���Ɋ�Â������̈ړ]�܂��͓Ɛ�I�������͔�Ɛ�I�Ȏg�p�����̕t�^�́A�ȉ��̏����ɂ����ďI������B
| �@ | �i1�j | �E�i2�j�� |
| �i3�j | �@�����t�^�̏I���́A�����t�^�̎��{�̓�����35�N��Ɏn�܂�5�N�Ԃɂ��ł��s�����Ƃ��ł���B�܂��A�����t�^�����앨�s���錠���ɂ�����ꍇ�A��L���Ԃ́A�����t�^�Ɋ�Â����앨�̔��s�̓�����35�N��܂��͋��̎��{�̓�����40�N��̂����A�����ꂩ�����I��������Ԃ̍ŏI������N�Z����B | |
| �i4�j | �� | |
| �i5�j | �@�����t�^�̏I���́A�����Ȃ锽�̍��Ӂi�⌾���쐬���܂��͏����̌����t�^���s�����ӂ��܂ށj�ɂ�����炸�s�����Ƃ��ł���B |
�E�t�����X>�i![]() 102�j
102�j
��122��7���@�㉉�E���t���y�ѕ������́A�������͗L���ŏ��n���邱�Ƃ��ł���
| 2 | �㉉�E���t���̏��n�́A�������̏��n��Ȃ�� |
| 3 | �������̏��n�́A�㉉�E���t���̏��n��Ȃ�� |
| 4 | �_�A���̏��ɂ�����̌����̈���̑S�����n���ꍇ�ɂ́A���̗L���͈͂́A�_��ɒ�߂闘�p���@�Ɍ��肳��� |
�i
�i
��131��2���@���̏͂ɒ�߂�㉉�E���t�_��A�o�Ō_��y�ю����o����_��́A�����ō쐬���Ȃ���Ȃ�Ȃ�����t�̖��������ɂ��Ă��A���l�Ƃ���
| 2 | ���̑��̂�����̏ꍇ�ɂ��A���@�T��1341�������1348���܂ł̋K�肪�A�K�p����� |
��131��3���@����҂̌����̈ړ]�́A���n�����e���������n�؏��ɂ����Čʂ̋L�ڂ̑ΏۂƂȂ�A���A���n����錠���̗��p���삪���͈̔́A�p�r�A�ꏊ�y�ъ��ԂɊւ��Č��肳���Ƃ��������ɏ]���
| 2 | �@�� |
| 3 | �@�����o�|�Č���ΏۂƂ�����n�́A������앨�̖{���̏o�łɊւ���_��Ƃ͕ʌ̕����ɂ��_�̑ΏۂƂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ�� |
| 4 | �@����l�́A���̌_��ɂ���āA���n���ꂽ�����𗘗p����悤�ɐE�Ə�̊��s�ɏ]���ēw�͂��邱�Ƃ���A�y�і|�Ă̏ꍇ�ɂ́A����������ɔ�Ⴗ���V��҂Ɏx�������Ƃ���� |
��131��4���@����҂ɂ�邻�̒��앨�ɂ��Ă̌����̏��n�́A�S�����͈ꕔ�Ƃ��邱�Ƃ��ł��顏��n�́A�̔����͗��p���琶��������̔��z����҂̂��߂ɔ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��
| 2 | �������A���̊e���Ɍf����ꍇ�ɂ́A����҂̕�V�́A�ꊇ�������Ƃ��ĎZ�肷�邱�Ƃ��ł��� | |
| �i1) | �@���z���̎Z���b�����肷�邱�Ƃ����ۏ�ł��Ȃ��ꍇ | |
| �i2) | �@���̔z���̓K�p���Ǘ������i�������ꍇ | |
| �i3) | �@���̎Z��y�ъǗ��̎��{�̂��߂̌o��A���B���ׂ����ʂƒލ������Ƃ�Ȃ��ꍇ | |
| �i4) | �@����҂̊�^�����앨�̒m�I�n��̕s���̗v�f�̈���\�����Ȃ����߁A���͒��앨�̎g�p�����p�����ړI���Ɣ�r���ĕt���I�Ȃ��̂ɂ����Ȃ����߂ɁA���p�̐������͏������A����V�̋K���̓K�p��s�\�Ƃ���ꍇ | |
| �i5) | �@�\�t�g�E�F�A��ΏۂƂ��錠���̏��n�̏ꍇ | |
| �i6�j | �@���̑����̖@�T�ɋK�肷��ꍇ | |
| 3 | �L���Ȍ_�琶����g�p�����A����҂̋��߂ɉ����āA�������ҊԂɂ����āA�������ҊԂŒ�߂���Ԃɂ��Ĉꊇ�N�������ɕύX���邱�Ƃ��A���l�ɓK�@�Ƃ��� | |
��131��5���@���p���̏��n�̏ꍇ�ɂ����āA����҂��ߏ葹�Q���͕s�\���ȗ\���Ɋ�Â��Ē��앨���琶������v��12����7�ȏ�̑��Q�����Ƃ��́A����҂́A�_��̉��i�����̏C����v�����邱�Ƃ��ł���
| 2 | ���̗v���́A���앨���ꊇ�����̕�V�ƈ��������ɏ��n���ꂽ�ꍇ�Ɍ���A�s�����Ƃ��ł��� |
| 3 | �ߏ葹�Q�́A���̂悤�Ȍ_��ɂ�鑹�Q�����Ǝ咣���钘��҂̒��앨�̏���l�ɂ�闘�p�̑S�̂��l�����āA�]������� |
��131��6���@�_��̓��ɗ\�z���邱�Ƃ��ł��Ȃ������A���͗\�z����Ȃ������`���Œ��앨�𗘗p���錠����t�^���邽�߂̏��n�����́A�����K��Ƃ��A���A���p���琶���闘�v�̑��֓I�Ȕz�����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��
��131��8���@���̖@�T��112��2���ɒ�߂钘�앨�̏��n�A���p���͎g�p�ɍۂ��Ē���ҁA��ȉƋy�ь|�p�Ƃɑ��čŌ��3�N�ԂɎx������ׂ��g�p���y�ѕ�V�̎x�����Ɋւ��āA�����̒���ҁA��ȉƋy�ь|�p�Ƃ́A���@�T��2101���4���y�ё�2104���ɋK�肷����T�����L����
�E�h�C�c�i![]() 103�j
103�j
��31���@���p���̋��^
| 1�`3�� | |
| 4 | �@���m�̗��p���@�ɑ��闘�p���̋��^�y�т���ɑ���`���Â��́A�����Ƃ���B |
| 5 | �@���p�������^����ɍۂ��āA���p���@�����m�ɂЂƂЂƂ\������Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�������҂���b�Ƃ����_��ړI�ɂ��������A���p���������Ȃ闘�p���@�ɋy�Ԃ������肳���B���p�������^���ꂽ���ۂ��A�ʏ험�p�����r���I���p�����A���p���y�ы֎~���͂����Ȃ�͈͂ɋy�Ԃ��A���тɗ��p���͂����Ȃ鐧���ɕ����邩�ɂ��Ă��A���l�Ƃ���B |
�i
��32���@�����ȕ�V
| 1 | �@����҂́A���p���̋��^�y�ђ��앨���p�̋����ƈ��������ɁA��肳�ꂽ��V�����߂鐿�������擾����B��V�̊z�̒�߂��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����ȕ�V����肳�ꂽ���̂Ƃ݂Ȃ��B��肳�ꂽ��V�������Ȃ��̂ł͂Ȃ��ꍇ�ɂ́A����҂́A�_��̑�����ɑ��āA����҂ɑ����ȕ�V��F�߂�_��̉���ɓ��ӂ���悤���߂邱�Ƃ��ł���B |
| 2 | �� |
| 3 | �@�_��̑�����́A��1���y�ё�2���ɔ����A����҂̕s���ɂȂ�������p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B��1���Ɍf����K��́A�ʂ̕��@�ɂ���������ꍇ�ɂ��K�p�����B�A���A����҂́A���l�ɑ��Ă��A�����ɂāA�ʏ험�p�������^���邱�Ƃ��ł���B |
| 4 | �� |
��32 a���@���쌠�̂���Ȃ闘�v�z��
| 1 | �@����҂��A������ɑ��āA���p�������^�������A���̏������A��肳�ꂽ�����t������҂̑�����ɑ���S�W�Ɋӂ݂Ē��앨���p���琶������v�y�ї��v�ɑ��Ė��炩�ɕs�ύt�������炷���̂ł������ꍇ�ɂ́A���̑�����́A����҂̋��߂ɉ����āA�_��̉���ɓ��ӂ���`�����B���̌_��̉���ɂ��A����҂ɂ́A����ŁA����ɑ����ȗ��v���z���F�߂���B�_���҂��A����ꂽ���v���͗��v�̊z��\�����Ă������ۂ��A���͗\�����邱�Ƃ��ł������ۂ��́A�d�v�ł͂Ȃ��B |
| 2 | �@��������A���p�������n�����͂���ɗ��p�������^�����ꍇ�ł����āA��O�҂̎��v���͗��v���疾�炩�ȕs�ύt�������Ă���Ƃ��́A���̑�O�҂́A���C�Z���X�̘A���ɂ�����_��W���ڗ����āA��1���ɂ��������A����҂ɑ��āA���ځA�ӔC���B������́A�ӔC��Ȃ��B |
| 3 | �@��1���y�ё�2���Ɋ�Â��������́A���炩���ߕ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���̐������ɑ�����Ҍ��́A�������s���Ȃ��B���̊��Ҍ��̏����͖����Ƃ���B |
| 4 | �� |
| �O�̃y�[�W�� | ���̃y�[�W�� |
| �y�[�W�̐擪�� | �����Ȋw�ȃz�[���y�[�W�̃g�b�v�� |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology