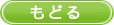
| 資料 4 |
積極否認の特則の導入について
1.現行制度における侵害行為の主張に対する否認の方法
著作権等の侵害行為の差止請求又は損害賠償請求訴訟を提起する場合には、権利者は、まず、侵害行為を具体的に主張しなければならない。一方、相手方は、権利者の主張について否認する場合は、その理由を明らかにする(積極否認)こととされている(同第79条第3項)。
| 民事訴訟法規則79条3項 「準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。」 |
2.積極否認の特則(具体的態様の明示義務)の著作権法への導入について
(1)特許法等の規定
特許法等においては、特許権侵害訴訟の審理促進等の観点から、民事訴訟規則が準備書面一般の記載事項として否認の理由を求める旨規定しているのに対し、権利者が主張する侵害行為の具体的態様を否認するときは、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない旨の規定(積極否認の特則)を平成11年の改正により設けている。
| 特許法第104条の2 「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。」 |
|
|||||||||
(2)積極否認の特則を著作権法に設ける意義
○著作権等侵害訴訟の効率化・迅速化
プログラムの著作物の複製など侵害行為の態様を特定することが困難な場合に、相手方に侵害行為の特定に積極的に関与させることにより、訴訟の効率化、迅速化を図ることができる。
(3)これまでの検討
特許法等において設けられた積極否認の特則の導入について、平成11年に著作権審議会第1小委員会において、検討を行った。
検討の結果、以下の通り、導入に消極的な意見、積極的な意見の双方があり、その必要性については、今後の侵害行為の態様の変化等の状況を踏まえながら引き続き検討する必要があるとして、法的措置を行うべきとの結論には至らなかった。
|
||||||||||||||||||
(4)今回検討すべき事項(案)
| ・ | 著作権等の侵害においても、侵害行為の特定が困難な場合があるか。 |
| ・ | 民事訴訟規則の規定では、不十分な場合があるか。 |
| ・ | 「相当な理由」に基づく適用除外を認めるべきか。 「相当な理由」を相手方の主張内容に営業秘密が含まれている場合と解釈するならば多くのケースにおいて相手方は、営業秘密を理由に開示を拒否することにならないか。 |
| ・ | 公表権との関係を考慮すべきか。 |