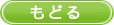
| 資料 3 |
新たな損害額算定ルールの導入について
1.現行制度における損害額算定ルール
著作権等の侵害行為があった場合、権利者は、民法第709条に基づき、侵害行為がなければ得られたであろう利益(逸失利益)の賠償を請求することができる。
| 民法第709条 「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ズ」 |
ただし、権利者は、この規定に基づき、逸失利益を請求する際に、以下の5つの要件について、立証しなければならない。
|
|
|||
このうち、特に![]()
![]() については、市場には、侵害品の他にも代替品が存在するなど、立証が困難な場合が多い。
については、市場には、侵害品の他にも代替品が存在するなど、立証が困難な場合が多い。
したがって、著作権法では、114条1項を設け、「侵害行為によって得た利益の額」をもって権利者の受けた損害額と推定する旨を規定している。
| 著作権法第114条第1項 「著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。」 |
この規定により、権利者の立証負担の軽減がされているが、侵害品の売上高から控除すべき額の算定が困難であるなど、侵害者が「侵害行為によって得た利益の額」を確定することは容易ではなく、結果としてこの規定が適用されない場合が多いといった指摘がある。また、侵害者の利益の額が立証し得ない場合に、割合的認定をしないというオール・オア・ナッシング的な運用がされている。
実際にも著作権侵害による損害賠償請求事件において、損害賠償額の最低限の保障として規定されている、使用料相当額の損害賠償請求に関する114条2項に基づく認定件数が多くなっている。
| 契約に基づくもの | 民法709 条に基づくもの | 著作権法114条1項に基づくもの | 著作権法114条2項に基づくもの | 人格権に基づくもの | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7件 | 6件 | 20件 | 47件 | 9件 | 89件 |
2.新たな損害額算定ルールの著作権法への導入について
(1)特許法等の規定
特許法等においては、逸失利益の立証の容易化の観点から、「侵害者の譲渡数量」に「権利者の製品の単位数量当たりの利益額を乗じた額」を、実施能力に応じた額の限度において、損害額とする旨の規定を、平成10年の改正により設けている。
| 特許法第102条第1項 「特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。」 |
|
|||||||||||
(2)特許法に準じた新たな損害額算定ルールを著作権法に設ける意義
| 権利者の立証負担の軽減 侵害行為によって、実際に権利者の著作物の売り上げ等がどれだけ減少し、どれだけ損害を被ったかを証明する必要がなく、権利者は比較的立証が容易な「侵害者の譲渡数量」と「権利者の著作物の単位数量当たりの利益額」を証明すればよいこととなる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侵害と損害額との相当因果関係の割合的認定 「侵害者の譲渡数量=権利者の喪失した販売数量」とはできない事情が存在する場合は、侵害者に立証責任を負わせることにより、損害額の割合的認定が可能となる。 <現行114条1項>
<新たな損害額算定ルール>
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
新しい損害額算定方法
a)民法709条に基づいて、1000円×3000個=300万円の請求が可能 b)著作権法114 条1項に基づいて、400円×1万個=400万円の請求が可能 c)新たな算定ルールに基づいて、1000円×1万個=1000万円の請求が可能 (但し、b)c)の算定方法によっても侵害者が権利者の実損害a)を抗弁として提出しこれを立証した場合には、a)の範囲の認容となる。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)これまでの検討
権利者の立証負担軽減のため、特許法等において設けられた新たな損害額算定ルールに準じたルールの導入について、平成11年に著作権審議会第1小委員会において、検討を行った。
検討の結果、著作権法への導入について積極的に検討すべきとの意見が多かったが、以下の通り、![]() 規定の適用範囲の問題や、
規定の適用範囲の問題や、![]() 侵害者側に抗弁の機会を与える場合の具体的な内容の確定が困難であったことなどを踏まえ、引き続き積極的に検討すべきであるとして、法的措置を行うべきとの結論には至らなかった。
侵害者側に抗弁の機会を与える場合の具体的な内容の確定が困難であったことなどを踏まえ、引き続き積極的に検討すべきであるとして、法的措置を行うべきとの結論には至らなかった。
|
||||||||||||||||
(4)今回検討すべき事項(案)
| ○ | 著作権法に導入すべき必要性 | ||||
| ○ | 対象とする侵害行為の態様
|
||||
| ○ | 損害額を減額する事情
|