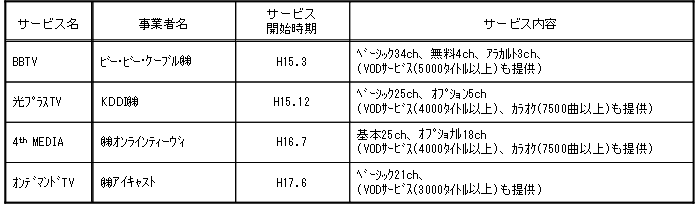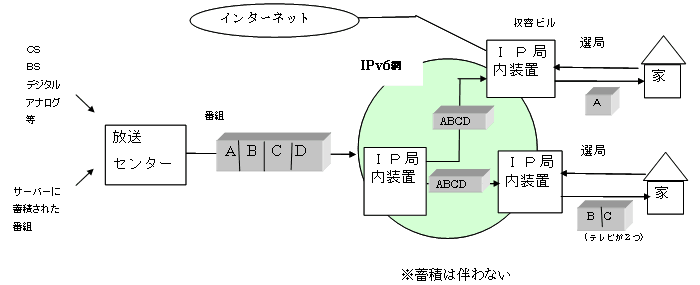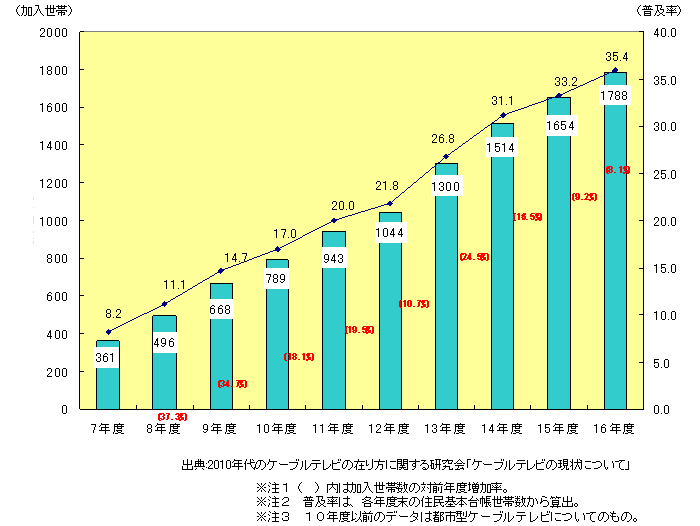.IPマルチキャスト放送の著作権法上の取扱い等について .IPマルチキャスト放送の著作権法上の取扱い等について
2.IPマルチキャスト放送と有線放送の現状
 |
IPマルチキャスト放送とは |
マルチキャストとは、コンピュータ・ネットワークにおいて、決められた複数のネットワーク端末に対して、同時にコンテンツ(IPパケット)を送信することをいう。IPマルチキャストは、複数の宛先を指定して1回データを送信すれば、通信経路上のルータがそのデータを受信して、次の複数のルータに自動的にコンテンツを送信する仕組みであり、IPマルチキャスト放送は、この技術を用いることにより、回線を圧迫することなく効率よくコンテンツを配信することができる。
IPマルチキャスト放送の主な特徴としては、以下の点がある。
| |
○ |
閉鎖的ネットワークを用いてコンテンツの配信を行う。 |
| ○ |
放送センターからは、IP局内装置に対して全番組が常に配信される。 |
| ○ |
最寄りのIP局内装置からは、ユーザーが選局した番組のみが配信される(リクエストに基づく送信)。 |
 |
IPマルチキャスト放送に関する放送関連法制 |
平成13年、通信と放送の伝送路の融合に対応し、電気通信設備を利用した放送を制度的に可能とするため、電気通信役務利用放送法が制定された。電気通信役務利用放送とは、「公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信であって、その全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行うものをいう」(電気通信役務利用放送法第2条第1項)と定義され、IPマルチキャスト放送もこの放送の一形態である。
IPマルチキャスト放送を行う事業者は、事業の開始に当たり、同法に基づく総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、以下の場合については、登録を拒否される。
| (ア) |
関係法違反行為や、登録の取消し等があった場合(同法第5条第1項第1〜3号) |
| (イ) |
経理的基礎・技術的能力がない場合(同項第4号) |
| (ウ) |
技術的基準に適合する電気通信役務利用放送設備の利用ができない場合(同項第5号) |
| (エ) |
できるだけ多くの者によって行われるようにするために総務省令で定める基準に合致しない者(同項第6号) |
また、事業者には、主に以下のような義務が課されている。
| (ア) |
放送事業者の放送を再送信する場合には、当該放送事業者の同意が必要である(同法第12条) |
| (イ) |
正当な理由なく業務区域内での役務提供を拒むことができない(同法第14条) |
| (ウ) |
番組準則、放送番組審議機関等放送法の関連規定を遵守しなければならない(同法第15条) |
 |
IPマルチキャスト放送の実態 |
以下の4事業者が電気通信役務利用放送法の登録を受けてIPマルチキャスト放送を実施している(平成18年2月現在)。
これらの事業者は、CSの再送信等を中心にサービスを行っており、現在のところ、地上放送やBSの再送信は実施していない。なお、この他、自社及び他事業者のインターネット接続やIP電話、VOD方式による番組配信等のサービスと併せて提供されている。
 |
有線放送について |
有線放送は、一般に、「公衆によって直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信」(有線テレビジョン放送法第2条第1項)のことをいい、具体的には、有線音楽放送やケーブルテレビが該当する。
ケーブルテレビとIPマルチキャスト放送を比較した場合、チャネルを選択することにより求める番組が視聴できる点では同じであるものの、有線放送については、受信者の受信装置まで有線放送される全チャネルの電波が届いているのに対し、IPマルチキャスト放送については、先述したとおり、受信者の選択したチャネルの番組のみ最寄りのIP局内装置から配信される点で異なる。
 |
有線放送に関する放送関連法制 |
ケーブルテレビ事業を規制する法律として、昭和47年に有線テレビジョン放送法が制定されている。有線テレビジョン放送法では、一定規模を超える有線テレビジョン放送施設を設置して有線放送を行おうとする者は、施設の設置について総務大臣の許可を受けなければならないとされており(同法第3条)、以下のような許可基準が設けられている。また、業務を実施しようとする場合には、これとは別に、総務大臣への届出が必要である(同法第12条)。
| (ア) |
施設計画の合理性・実施確実性があること(同法第4条第1項第1号) |
| (イ) |
技術基準への適合性があること(同項第2号) |
| (ウ) |
経理的基礎・技術的能力があること(同項第3号) |
| (エ) |
自然的社会的文化的諸事情に照らした必要性・適切性があること(同項第4号) |
| (オ) |
関係法違反行為等の欠格事由に該当しないこと(同法第5条) |
また、事業者には、主に以下のような義務が課せられている。
| (ア) |
テレビジョン放送の受信障害が相当範囲にわたる地域で有線テレビジョン放送を行う場合には、当該放送の再送信を行わなければならない(同法第13条第1項) |
| (イ) |
放送事業者の放送を再送信する場合には、当該放送事業者の同意が必要であり、同意の協議が整わない場合には、大臣裁定を申請できる(同条第2項・第3項) |
| (ウ) |
正当な理由なく業務区域内での役務提供を拒むことができない(同法第16条) |
| (エ) |
番組準則、放送番組審議機関等放送法の関連規定を遵守しなければならない(同法第17条) |
これらの事業者に課せられた義務については、有線テレビジョン放送法も電気通信役務利用放送法もおおむね同様であるが、有線テレビジョン放送法に定められている義務再送信及び大臣裁定に相当する規定は、電気通信役務利用放送法には置かれていない。
なお、有線テレビジョン放送法に基づく規制については、政府の規制緩和政策を背景に、地元事業者要件の廃止及びサービス区域制限の緩和(平成5年)、外資規制の撤廃(平成11年)など様々な規制緩和が行われており、事業の拡大等を行う環境が整いつつある。
ところで、設備の全部又は一部として電気通信事業者の有する電気通信設備を用いて有線放送を行うことも可能であるが、このような場合には、有線テレビジョン放送法ではなく、前述した電気通信役務利用放送法が適用されることになる。
 |
有線放送(ケーブルテレビ)の実態(総務省「2010年代のケーブルテレビの在り方に関する研究会」資料より) |
有線テレビジョン放送法上の許可を受けた施設数及び事業者数はそれぞれ、718施設、547事業者である(平成17年3月末現在)。ケーブルテレビ加入世帯数は年々増加しており、平成17年3月末には1,788万世帯、普及率にして35.9パーセントまで拡大している(自主放送を行う許可施設)。
また、共同受信(共聴)施設(都市受信障害対策、辺地難視聴対策及び集合住宅共同受信)についても、平成16年末で66,234施設、8,337,436世帯が受信している。
ケーブルテレビ事業者の経営状況については、インターネット接続サービスの提供(平成17年9月末時点で380社が提供、312.2万人が加入)やIP電話サービスの提供(平成17年12月末時点で91社が提供)、CSの再送信に加え、最近では、VOD方式の番組配信サービスも行われるなど、ケーブルテレビ事業の拡大・充実により、堅調に推移している様子がうかがえる(平成16年度は310社(注2)中251社(80.9パーセント)が単年度黒字)。
| (注2) |
自主放送を行う許可施設事業者(547社)のうち、ケーブルテレビを主たる事業とする営利法人310社 |
なお、電気通信役務利用放送法に基づき、有線放送の方式により事業を行う事業者は次の12社である。
【ケーブルテレビ方式を用いた電気通信役務利用放送事業者の登録状況】
| 会社名 |
登録日 |
業務区域 |
| 東京ベイネットワーク株式会社 |
平成14年9月20日 |
東京都江東区等 |
| 株式会社テレビ津山 |
平成15年9月1日 |
岡山県津山市等 |
| 株式会社メディアリンク |
平成15年10月29日 |
山口県周南市等 |
| 株式会社ケイ・キャット |
平成15年11月18日 |
近畿地方一帯 |
| 株式会社愛媛シーエーティヴィ |
平成15年12月26日 |
愛媛県松山市等 |
| 株式会社オプティキャスト |
平成16年2月25日 |
東京23区、大阪府大阪市等 |
| 株式会社ケーブルテレビジョン東京 |
平成16年3月24日 |
東京都港区等 |
| 株式会社タウンテレビ南横浜 |
平成16年8月25日 |
神奈川県横浜市金沢区等 |
| 株式会社ベイ・コミュニケーションズ |
平成17年5月31日 |
大阪府大阪市、兵庫県尼崎市等 |
| 東京ケーブルネットワーク株式会社 |
平成17年6月15日 |
東京都文京区等 |
| 株式会社STNet |
平成17年8月5日 |
徳島県徳島市 |
| 近鉄ケーブルネットワーク株式会社 |
平成17年9月26日 |
奈良県奈良市、京都府宇治市等 |
|
|