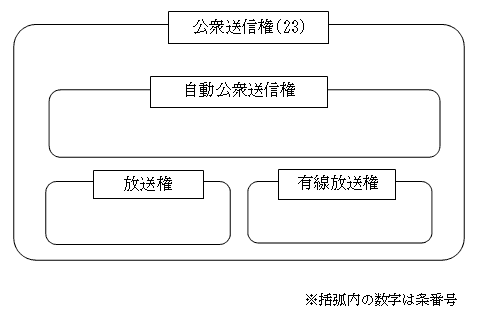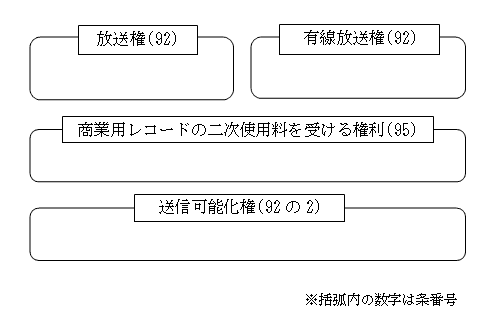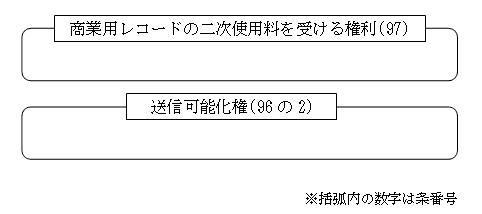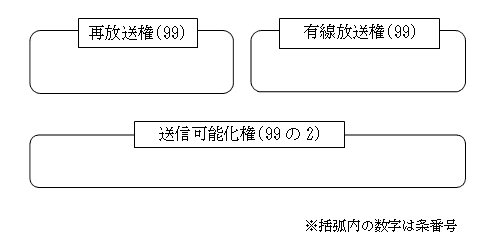3.現行著作権法におけるIPマルチキャスト放送の取扱い
 |
現行著作権法制定時(昭和45年) |
昭和45年に現行著作権法が制定された際、公衆送信に関する権利としては、放送又は有線放送に係る権利のみ規定されていた。
 |
昭和61年改正 |
キャプテン・システム、データベースのオンライン・サービスなど、双方向性のある情報伝達手段の発達・普及により、このような形態の送信についても、著作権が働くことを明確にする必要が生じたことから、昭和61年改正により、公衆に対する有線による送信を「有線送信」とし、「有線送信」のうち、CATVのような一斉送信型のものを「有線放送」と整理した。
 |
平成9年改正 |
インターネット等の急速な発達に対応するため、平成9年改正により、無線・有線を問わず、公衆によって直接受信されることを目的として行う送信を「公衆送信」とし、また、無線・有線を問わず、公衆からの求めに応じ自動的に行う送信を「自動公衆送信」とするなど、公衆送信に係る概念について再整理が行われた。
その結果、著作物の公衆送信については以下のとおり整理され、著作権者には、公衆送信権(自動公衆送信にあっては、送信可能化を含む。)が与えられた(第23条)。
公衆送信
(第2条第1項第7号の2) |
公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(同一構内における有線電気通信の送信を除く。) |
放送
(同項第8号) |
公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信 |
有線放送
(同項第9号の2) |
公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信(例:ケーブルテレビ) |
自動公衆送信
(同項第9号の4) |
公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)
(注)自動公衆送信には、「入力型」(公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるもの。例:ストリーミング型インターネット放送)と「蓄積型」(公衆送信用記録媒体に情報を記録すること等によるもの。例:ビデオ・オン・デマンド)がある。 |
送信可能化
(同項第9号の5) |
「蓄積」又は「入力」された情報が利用者の求めがあり次第送信され得る状態におくこと。 |
また、実演及びレコードに係る権利関係についても、次のように整理された。
| 商業用レコードの二次使用を受ける権利(第95条、第97条) |
市販用の音楽CD等を放送又は有線放送に利用している場合、当該CD等に係る実演家(歌手、ミュージシャン等)やレコード製作者が報酬を求めることのできる権利 |
 |
平成14年改正 |
放送事業者に係る権利関係が次のように整理された(有線放送事業者についても同様)。
| (2) |
IPマルチキャスト放送の著作権法上の位置付け |
| |
有線電気通信設備を用いた送信が著作権法上の有線放送と解されるには、 |
 |
有線電気通信設備により受信者に対し一斉に送信が行われること、 |
 |
送信された番組を受信者が実際に視聴しているかどうかに関わらず、受信者の受信装置まで常時当該番組が届いていること |
| が必要であると考えられる。 |
この点、IPマルチキャスト放送は、IP局内装置までは「同一内容の送信」が行われているが、局内装置から各家庭までの送信は、各家庭からの「求めに応じ自動的に行う」ものであることから、「自動公衆送信」であると考えられる(情報を入力し続けることによる送信形態であることから、入力型の自動公衆送信(注2)である)。
| (注2) |
入力型の自動公衆送信の概念については11頁参照。 |
| (3) |
現行法における「有線放送」と「自動公衆送信(送信可能化を含む)」の規定の比較 |
(2)のとおり、IPマルチキャスト放送は、著作権法上「有線放送」ではなく、「自動公衆送信」と扱われるため、放送番組の送信にあたっては、CATV等の「有線放送」とは、関係する権利の働き方が異なる場合がある。
 自主放送 自主放送 |
|
(○:許諾権、▲:二次使用料請求権、×:無権利)
(※括弧内の数字は条番号) |
| 送信の対象となるもの |
有線放送 |
自動公衆送信 |
| 著作物 |
  23) 23) |
  23) 23) |
| 実演 |
生実演 |
  92 92 ) ) |
  92の2 92の2 ) ) |
| 固定物 |
録音 |
許諾あり |
  92 92  イ) イ) |
  92の2 92の2 ) ) |
| 許諾あり 商業用レコード |
  95) 95) |
| 許諾なし |
  92 92 ) ) |
  92の2 92の2 ) ) |
| 録画 |
許諾あり |
  92 92  イ) イ) |
  92の2 92の2  ) ) |
| 許諾なし |
  92 92 ) ) |
  92の2 92の2 ) ) |
| レコード |
商業用レコード |
  97) 97) |
  96の2) 96の2) |
| その他のレコード |
  権利なし) 権利なし) |
  96の2) 96の2) |
|
自主放送番組を有線放送する場合には、原則として、著作権者の許諾(第23条第1項)、実演家の許諾(第92条第1項)が必要である。レコード製作者は有線放送権を有していないため、許諾を得る必要がない。なお、商業用レコードを用いて有線放送する場合には、当該レコードに係る実演家及びレコード製作者に対し二次使用料を支払わなければならない。
一方、自主放送番組を自動公衆送信する場合には、レコード製作者も含めて、許諾を得る必要がある(第23条第1項、第92条の2第1項、第96条の2)。
また、有線放送については、特別に以下の規定が置かれている。
| (ア) |
許諾を得て録音又は録画されている実演の有線放送(第92条第2項第2号イ) |
許諾を得て録音又は録画されている実演を有線放送する場合には、実演家の権利は働かない。
これは、実演家は、その最初の実演の固定を許諾する際に、契約上、以後の利用について利益を確保する機会を有していること、また、その後の利用については、有線放送事業者の権利による管理も及ぶことから、権利関係を簡明にするためにも、実演家に許諾権を認める必要はないと考えられたためである。
| (イ) |
一時的固定制度の適用(第44条第2項、第102条第1項) |
有線放送事業者は、有線放送することができる著作物等を、自己の有線放送のために、自己の手段によって、一時的に録音・録画することができる。
本規定は、有線放送事業者による自主制作番組の制作が増えてきて、放送と同様に一時的な録音物・録画物を作成することが不可欠となったことから、昭和61年改正によって定められた。
著作物を利用して有線放送を行う場合には、一定の要件の下で著作権者の権利が制限されている。
| |
(例) |
・ |
学校教育番組の放送等(第34条) |
| ・ |
時事問題に関する論説の転載等(第39条) |
| ・ |
政治上の演説等の利用(第40条) |
 放送の同時再送信 放送の同時再送信 |
|
(○:許諾権、▲:二次使用料請求権、×:無権利)
(※括弧内の数字は条番号) |
| (注) |
非営利無料の場合は、第38条第2項の規定により、( )の部分についても権利が制限( )の部分についても権利が制限( 無権利)されている。 無権利)されている。 |
| 送信の対象となるもの |
有線放送 |
自動公衆送信 |
| 著作物 |

  23) 23) |
  23) 23) |
| 実演 |
生実演 |
  92 92  ) ) |
  92の2 92の2 ) ) |
| 固定物 |
録音 |
許諾あり |
  92 92  ) ) |
  92の2 92の2 ) ) |
| 許諾あり 商業用レコード |
  95) 95) |
| 許諾なし |
  92 92  ) ) |
  92の2 92の2 ) ) |
| 録画 |
許諾あり |
  92 92  ) ) |
  92の2 92の2  ) ) |
| 許諾なし |
  92 92  ) ) |
  92の2 92の2 ) ) |
| レコード |
商業用レコード |
  95) 95) |
  96の2) 96の2) |
| その他のレコード |
  権利なし) 権利なし) |
  96の2) 96の2) |
|
営利又は有料で同時再送信を行う場合は、著作権については、有線放送及び自動公衆送信ともに、原則として、著作権者の許諾が必要であり(第23条第1項)(前述 (ウ)の権利制限に該当する場合は、有線放送は権利者の許諾不要。)、また、放送事業者の許諾も得る必要がある(第99条第1項)(法令の規定により、有線放送による放送の同時再送信を行わなければならない場合には、放送事業者の許諾は不要である(同条第2項))。 (ウ)の権利制限に該当する場合は、有線放送は権利者の許諾不要。)、また、放送事業者の許諾も得る必要がある(第99条第1項)(法令の規定により、有線放送による放送の同時再送信を行わなければならない場合には、放送事業者の許諾は不要である(同条第2項))。
一方、実演及びレコードの送信に関しては、有線放送と自動公衆送信で権利の働き方が異なる。
( ) ) |
実演の送信(第92条第2項第1号、第92条の2第1項・第2項第1号、第95条) |
| |
自動公衆送信による再送信を行う場合は、原則どおり実演家の許諾が必要(許諾を得て録画されている実演を除く。)である(第92条の2第1項・第2項第1号)が、有線放送による再送信の場合には、実演家の権利が及ばないこととされている(第92条第2項第1号)。これは、放送事業者の権利を通じて実演家の権利を実質的にカバーしてもらうことを予定していたためである。また、商業用レコードの二次使用についても、同時再送信による利用の場合は当該使用料を支払う必要はない。 |
( ) ) |
レコードの送信(第95条、第96条の2) |
| |
自動公衆送信による再送信を行う場合は、原則どおりレコード製作者の許諾が必要である(第96条の2)が、レコード製作者は有線放送権を有していないため、有線放送による再送信の場合に許諾を得る必要はない。また、商業用レコードの二次使用についても、同時再送信による利用の場合は当該使用料を支払う必要はない。 |
放送を受信して有線放送する場合は、非営利・無料であれば、著作権者、著作隣接権者(実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者)の許諾なく行うことができる(第38条第2項、第102条第1項)。
現行法制定当時(昭和45年)は、非営利・無料の有線放送としては小規模なものしかなかったため、権利者の許諾なく有線放送することができるとされていた。その後、有線放送の大規模化に伴い、昭和61年改正の際にも、権利の制限に関してもできるだけ放送と同様の扱いとするのが適当とされたが、共同受信組合等が行う難視聴対策のための再送信等にまで権利を及ぼすことは社会的影響から問題があると考えられ、放送の再送信に当たる場合だけ権利制限することとなった。
一方、放送を受信して自動公衆送信する場合は、原則どおり、各権利者の許諾が必要である。
 |
著作隣接権 |
有線放送事業者については、昭和61年改正によって、著作隣接権が付与されている。現行法制定当時は、有線放送は難視聴地域の解消を目的とするものがほとんどであり、その法的保護を図らなければならない実態になかったため、著作隣接権は付与されなかったが、その後の有線放送の発展により、放送事業者に著作隣接権を認めたときと同様の事情(放送の番組の制作・編成に著作物の創作性に準ずる創作性が認められること、また、そのために多くの時間と努力と経費を要しており、その第三者による利用について権利を認めないことは不公平であること。)が認められるようになったため、有線放送事業者にも著作隣接権が付与された。
一方、自動公衆送信を業として行う者については、著作隣接権を付与していない。平成7年に当該送信事業者にも著作隣接権を付与することが、著作権審議会マルチメディア小委員会において検討されたが、放送の場合の番組編成のような準創作的行為が存在するのかなどの指摘があり、見送られた。
|