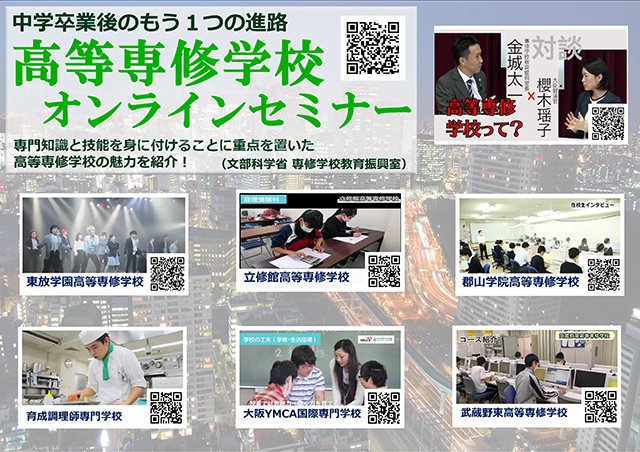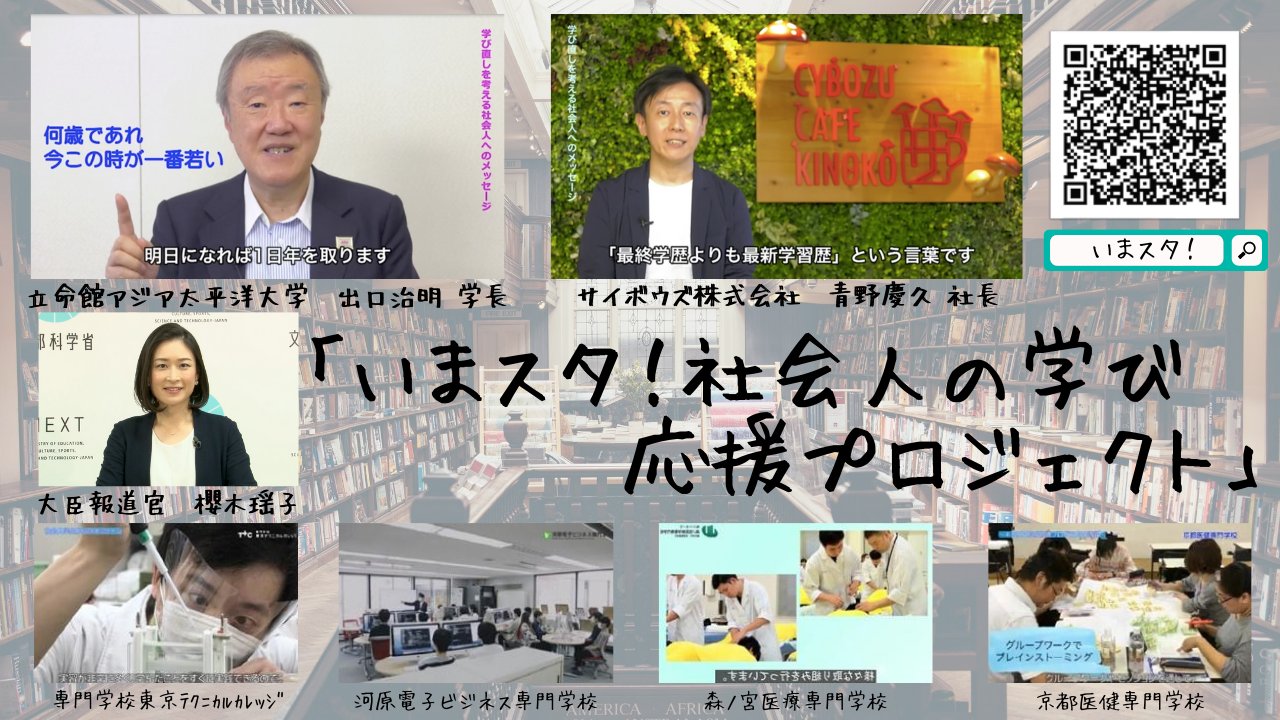教育再生実行会議デジタル化タスクフォース第2回開催
11月12日(木曜日)
教育
11月12日、第2回の教育再生実行会議デジタル化タスクフォースを開催し、藤村委員(初中WG委員/鳴門教育大学大学院 遠隔教育プログラム推進室長)、喜連川委員(高等教育WG委員/情報・システム研究機構 国立情報学研究所長、東京大学生産技術研究所教授)、堀田委員(初中WG委員/東北大学大学院 情報科学研究科教授)からご発表いただきました。
藤村委員からは、①教科等の指導におけるICT活用(スタディログ・ライフログ・アシストログの活用による個別最適な学び・生徒指導、LMSの整備等)、②校務の情報化(統合型校務支援システムの100%整備等(現在64.3%))、③情報教育・人材育成と、そのために必要な共通基盤についてお話しいただきました。
喜連川委員からは、医療がデータを基に薬の処方や手術等をしているように、デジタルを活用し、教育でもエビデンスに基づく教育、「データ駆動型教育」を目指す時代となることなどをお話いただきました。
堀田委員からは、就学時に個々の児童生徒ごとにマイページを作成し、スタディログ・ライフログ・アシストログ等個々の情報を蓄積していくシステムの活用や、自治体ごとにばらつきが出ないように国がモデルの検討を行うとともに、それら教育ビッグデータを分析する国の体制づくりが必要とのご意見を頂きました。
自由討議では、データを蓄積していくクラウドについて、セキュリティ等の重要性、必要に応じた法整備と併せて、ガバナンスもしっかり考える必要性があるなど様々なご意見をいただきました。
萩生田大臣は、最善を尽くしてICTの教育環境を創っていきたいと述べるとともに、一人一台端末が整備されて新学期が始まる来年4月までにガイドラインなどで各自治体共通で必ずやっておかなくてはいけない短期的視点と、データを積み上げながら将来もっといい教育ができるようにするための長期的視点、それぞれの視点でのアドバイスをいただき、適時にご提案をお願いしたいと伝えました。