- 現在位置
- トップ > 教育 > 幼児教育 > 調査研究事業 > 幼児教育支援センター事業 > 幼児教育支援センター事業
幼児教育支援センター事業
宮崎県延岡市
1 研究テーマ及び研究の観点
(1) 幼児教育の振興のための取組を支援するためのサポートチームの在り方
(2) 特別な配慮を要する幼児に対応する教員や子育て不安を抱える保護者への効果的な援助の在り方
(3) 幼小連携の推進やカリキュラム編成の効果的支援の在り方
2 地域の概要
| 人口 | 幼稚園 | 小学校 | 保育所 | |||||
| 幼稚園数 | 幼児数 | 学校数 | 児童数 | 保育所数 | 幼児数 | |||
| 延岡市 | 132千人 | 国立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公立 | 4 | 224 | 33 | 8,158 | 9 | 441 | ||
| 私立 | 13 | 1,426 | 1 | 22 | 27 | 2,431 | ||
| 合計 | 132千人 | 17 | 1,650 | 34 | 8,180 | 36 | 2,872 | |
これまでは公立幼稚園にて園庭開放事業等の取組みを行ってきたが、公立幼稚園の減少によって幼児教育の中心的役割が私立幼稚園へと移行してきた。このため、平成18年度より幼児教育支援センター事業に取組み、私立幼稚園を中心とした独自の支援組織づくりを行ったが、1年目は全体的に幼児教育に関する意識が低く事業への参加協力も消極的であったため、思うように成果をあげられなかった。
3 研究協力機関
私立幼稚園4園、小学校2校
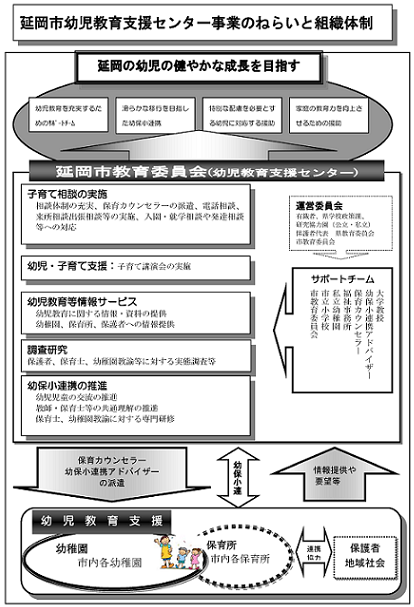
4 研究の内容及び方法
(1) 運営委員会等の実施
本年度は2回の運営委員会を開催し、サポートチームの支援や、幼小連携を中心として各関係機関との連携と支援の在り方を検討した。
(2) 幼児・子育て支援
保育カウンセラーによる巡回訪問相談を18年度より実施してきたが、1年目はカウンセラーのことを知らない保護者が多く、相談件数が少なかった。このため、事業紹介パンフレットにカウンセラーとアドバイザーの顔写真を載せて保護者へ紹介した。この結果、2年目は巡回訪問も順調に進み、相談件数も増加した。相談内容によっては、個別にサポートチームにつなぎ、専門的な検討を行った。
(3) 幼保小連携の推進
小学校の校長会が主体となり、保育所・幼稚園・小学校・中学校の各長がウルスラ幼稚園にて幼稚園における教育の実際を参観し、幼稚園経営と幼児教育や保育の現状について共通理解してもらった。その後中学校区のグループに分かれて、教育の連携の在り方やそれぞれの段階における役割と責任について協議を行った。
(4) 研修会の実施
- 幼小連携研修会
幼稚園と小学校、それぞれの現場での情報交換や教師間交流のため研修会を実施した。
幼稚園の教諭14名と小学校低学年を担当する教諭14名の計28名が参加して、「子育て支援」、「幼小連携」というテーマで保育カウンセラーと連携アドバイザーから講義を受けた後、協議を行ってもらった。日頃なじみのない顔合せでの協議であったが、お互いが現場担当者のため、活発な意見交換が行われた。 - 障害児教育研修会
障害児教育に対する教諭の資質向上を図るため、研修会を実施した。
講師に九州保健福祉大学言語聴覚療法学科の山田教授を招いて「ADHD及びLDの対応について」というテーマで講義を行っていただいた。
予定数を大きく越える85名の参加があり、幼稚園や保育所の障害児教育に対する意識の高さが感じられた。 - 子育て講演会
地域・家庭の教育力の育成を図るため、保護者や教諭を対象に講演会を実施した。
講師:奥村 高明(文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官)
演題:子どもの感性と表現
参加者:300名
講演は、美術教育を切り口にした子育て支援に対する話で、参加者はいつもとは違う角度からの子育てに新たな発見をしたようであった。
(5) その他
- 調査研究
協力校2校において幼小連携の公開授業を行い、市内の幼稚園や小学校の教諭に連携の実際を見学してもらった。協議の席において、幼稚園・保育所が広域化しており、すべての小学校と連絡協議会を持っているわけではないため、教師間の交流が難しい事や、カリキュラムの違いから時間調整が難しいといった取組みにおける苦労点の発表やこれから連携を行う学校へのアドバイスを行い、次年度からの連携活動推進を図った。 - 幼児教育等の情報提供
・ 幼児教育支援センター事業パンフレット
事業内容を紹介したパンフレットで、事業の円滑な進行を図るため幼稚園と小学校へ配布した。
・ 小学校紹介パンフレット
幼稚園・保育所から小学校への滑らかな接続・連携のため、小学校の様子を分かりやすく紹介したパンフレットを作成し、少しでも家庭での不安を軽減するため幼稚園・保育所に配布した。保護者からは小学校の様子がよく分かり不安が軽減したと好評であった、また県内各教育委員会からも問い合わせがあるなど十分な成果を得た。 - 図書の活用
・ 各幼稚園において絵本の読み聞かせ活動が充実するように、希望の絵本を配布した。
・ 各幼稚園において障がいのある子どもたちに少しでも早く気付き、対応がとれるように障害児教育研修から学んだ知識の専門書を幼稚園に配布した。 - 先進地視察
千葉市教育センターと柏市教育研究所を視察し、整備された連携基盤のもとに行われている活動内容や発行物を参考にさせていただいた。
5 研究成果及び今後の課題
(1) 研究成果
- 支援センターとしては年間計画等を早く提示して、参加しやすい環境作りを行う必要がある。
- サポートチームが活動を行うには、公立幼稚園を拠点・核とした専門の部署を持ち、常駐できるスタッフが運営する組織づくりが必要である。
- 幼小連携はどうしても幼稚園・保育所側に小学校の邪魔をしてはいけないという思いがあり積極的に動けないため、小学校主体で行われなければ上手くいかないが、お互いが指導案を持ち寄るなど対等の立場で気軽に行うことが継続につながる。
- 園児や担任の交流だけでなく、園と学校の全体交流こそが真の交流となる。
(2) 今後の課題
- 連携活動を行ううえで、広範囲から園児が集まっている幼稚園の対応や保育所及び待機児童までをどのように含めていくか。
- 小学校の情報は幼稚園や保護者へ発信し易いが、幼稚園の卒園生は別々の小学校へ進んでおり、地域小学校へ情報を伝えても卒業園ではないため感心が少ないことや、小学校によっては幼稚園の情報を必要としていない感じがあり、幼稚園の情報は小学校へ伝えにくい。
- 幼小連携に消極的な園をどのように参加させていくか。
参考:研究テーマのキーワード
幼小連携、幼稚園と小学校の教員の相互理解
お問合せ先
初等中等教育局幼児教育課
-- 登録:平成21年以前 --