- 現在位置
- トップ > 教育 > 小学校、中学校、高等学校 > 全国的な学力調査(全国学力・学習状況調査等) > 全国学力・学習状況調査等を活用した学校改善の推進に係る実践研究 > 全国学力・学習状況調査等を活用した学校改善の推進に係る実践研究成果報告書 > 長野県教育委員会 小中連携による「確かな学力」の向上の取組
長野県教育委員会 小中連携による「確かな学力」の向上の取組
はじめに
長野県教育委員会では,地域の実情や課題に即して,児童生徒の「確かな学力」を育成することをねらいとして,本年度より2年間「小中連携による学力向上地域推進事業」を行っている。県下4地区の小・中学校の連携推進拠点校において,児童生徒の発達段階や小・中学校間の接続に留意し,一貫性・系統性のある学習指導や教育課程の編成について,主に算数・数学を対象として実践的に研究を行っている。
1.長野県教育委員会における取組
1.事業内容について
(1)事業概要
全国学力・学習状況調査等により明らかになった,「学力」や「学習状況」に関する課題の改善に向けて,「地域推進校」(調査活用協力校)を指定し,授業改善に向けた取組について調査研究を行い,その成果の普及を図る。
(2)実施体制
- 中学校区を単位として,「小中連携」を推進する4地区に推進拠点校を指定する。(数字は特別支援学級を含む学級数)
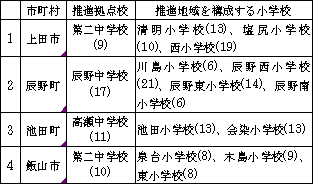
(東信,南信,中信,北信から各1地区を指定)
【イメージ図】
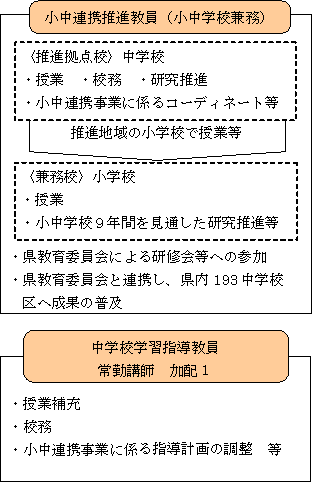
- 地域推進校においては,校区内の小学校と連携を図りながら授業改善を図る。
- 推進委員会を開催し,地域推進校の取組を支援するとともに,成果を全県に普及する。
- 全国学力・学習状況調査の結果を分析し,本県の課題を明らかにするとともに,改善の方向を示す。
(3)研究成果
A 次のような意識の変化がアンケート調査等から明らかになってきた。
1.児童・生徒の意識の変化
- 算数の授業が楽しみになった,好きになったという児童が増えている。
- 中学校生活へのイメージがもてた,中学校へ入学するのが楽しみになったという児童が増えている。
2.教師の意識の変化
- 小学校では,推進教員のもつ教科の専門性に刺激された,指導内容の縦のつながりに意識が向いてきたという感想が聞かれている。
- 中学校では,小・中学校を貫く教材研究の大切さがわかった,児童理解,対応の細やかさを知ったという感想が聞かれている。
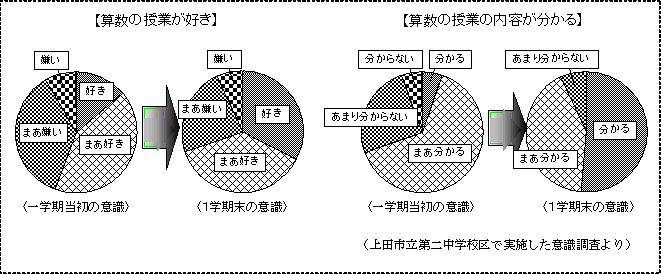
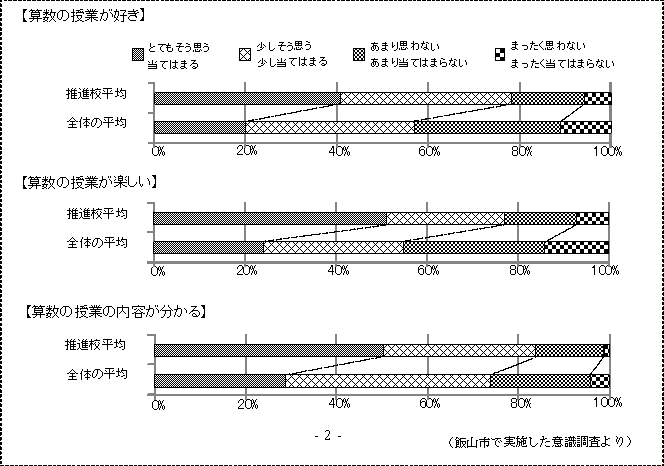
B 実践を通して小・中学校の系統を大切にした算数・数学指導のポイントが見えてきた
1.小学校の学習内容・経験を生かして,中学校の学習をつなげる例
小・中学校で同じような内容を学習するということが,算数・数学の特性の一つである。この点に着目し,小学校で学んだことと関連付けて中学校で指導することが有効な指導内容が見いだされた。
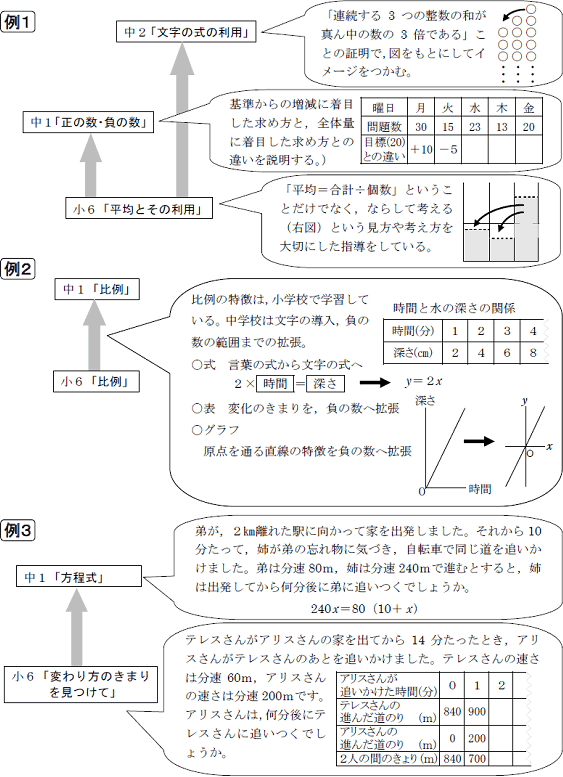
2.中学校の学習内容を見通して,小学校の学習内容を決める例
中学校での学習を見通して,小学校で扱っておいた方がよいと思われる内容が見いだされた。
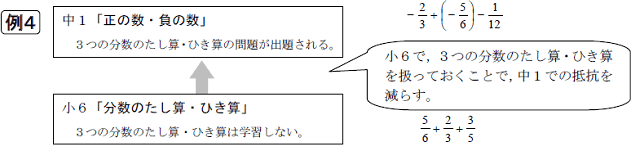
3.小・中学校を貫く考えに着目して,学習活動を充実する例
小・中学校の算数・数学の授業で,「式を読む」,「関数的な考え方」,「単位量のいくつ分」など一貫して大切に育てていきたい数学的な見方や考え方が見いだされた。
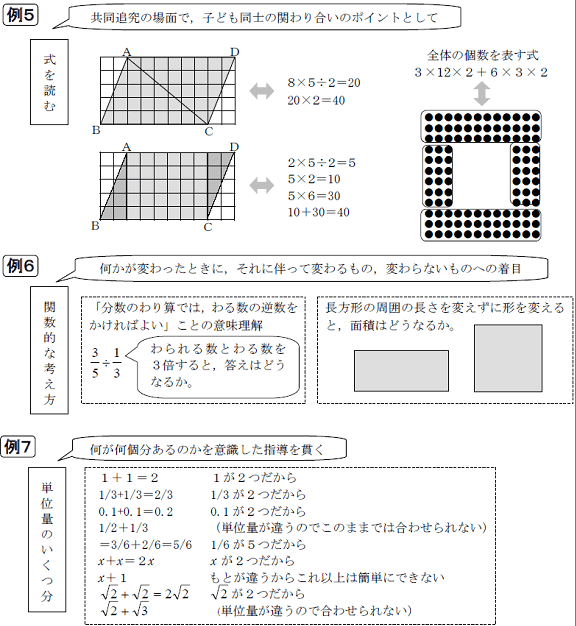
2.普及啓発と今後の取組について
(1)成果の普及啓発に関する取組
1.地域推進校の取組
- 周辺校に授業を公開し,成果を発表した。
- 推進委員会へ成果を報告した。
2.県教育委員会の取組
- 全国学力・学習状況調査報告書を作成し,全県小中学校並びに市町村教育委員会に配布するとともに,授業改善を促した。
- 地域推進校の成果と課題を県教育委員会発行の雑誌に掲載し,全県に発信した。
- 第2回推進委員会を開催し,成果と課題を県下の小中学校に広く普及した。
(2)来年度以降の取組
- 今年度関わった6年生が中学校へ入学する。推進教員が6年生と共に学んできたことを学習内容,学習方法の両面で数学の指導に活かしていきたい。また,生徒指導の面でも活かしていきたい。
- 中学校修了段階における到達目標の設定及び各学年終了段階での到達目標を考えながら,指導時数や単元展開を具体的に考えていきたい。
- 中学校区小中合同学力向上委員会を,より充実した実りある会にしたい。そのためには,必要に応じて研究主任等にも参加していただき,全体に波及できる小中の体制づくりが必要であると考える。
- 保護者,地域に向けてのPR活動も必要である。小中合同研修や推進教員の授業等は,積極的に保護者や町民の皆様に公開していきたい。
2.調査活用協力校における取組事例
取組事例1.上田市立第二中学校区の取組
(1)推進教員の動き
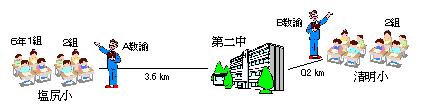
A 教諭
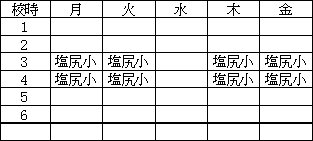
B 教諭
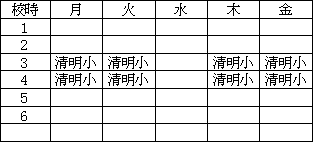
(2)成果
- 児童が算数の授業を楽しみにするようになっている。
- 授業が「考えさせる授業」になってきている。
- 児童にとってわかりやすい言葉で授業が進むようになっている。
- 小中共通して使える教材づくりが行われている。
- 児童が,中学へ行くとこんな先生がいるというイメージをもてるようになっている。
- 小学校で算数を好きにして,責任をもって中学校へ送り出せるようになる。
(3)課題
- 小学校の空き時間が少ないので,打合せ時間が十分とれない。
- 中学校で,推進教員の代わりに講師が担当する授業が,進めづらいことがある。
- 6年間を見通した算数の系統を明らかにしたい。
- いつでも小中の教師でTTを組むのではなく,空いた6年担任が別の学年の指導にあたるなど,組合せを工夫したい。
取組事例2.辰野町立辰野中学校区の取組
(1)推進教員の動き
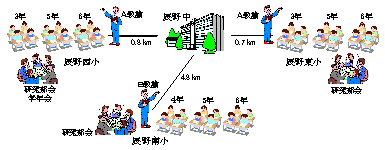
A 教諭
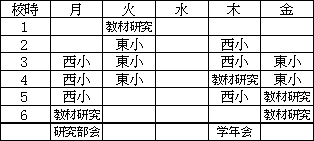
B 教諭
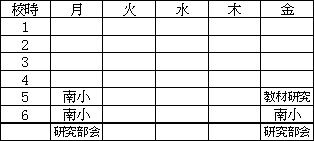
(2)成果
- 楽しい算数の授業で,児童が生き生きして取り組んでいる。
- 児童が,中学校の授業のスタイルに慣れてきている。
- 推進教員が運んでくる中学校の風を受けて,6年担任の,算数に対する授業観が変わり,意欲的に授業づくりに取り組む姿が見られるようになった。
- 小学校教師が,縦のつながりを見通したカリキュラムづくりに目が向くようになってきている。
- 小学校のうちに,このことだけは身に付けさせたいという指導内容がはっきりしてきている。
- 推進教員が小学校の様子を話すことで,中学校教科会の刺激になっている。
(3)課題
- 関係教師が全員集まって打合せをする時間をとりにくい。
- 行事等により,予定通り授業を進めることが難しい。
取組事例3.飯山市立第二中学校区の取組
(1)推進教員の動き
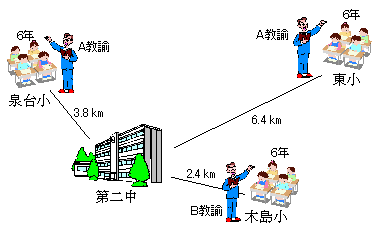
A 教諭
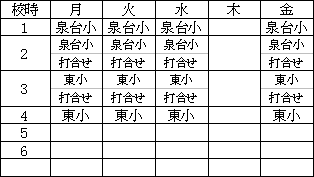
B 教諭
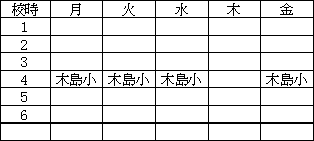
(2)成果
- 算数が好きになった児童が増えてきている。
- 学び方や授業の進め方,学ぶ構えや雰囲気等について,児童にとっても教師にとってもよい効果が上がっている。
- 児童をひきつける授業が行われ,「あの導入すごい」という声が小学校教師から上がっている。
- 推進教員は,小中両方の内容を教材研究しながら授業づくりができる。負担をメリットととらえたい。
- 6年担任以外の教師に授業参観してもらうことで,授業改善のきっかけをつくることができている。
- 異校種間の交流が教職員の資質・能力の向上につながる。
(3)課題
- 推進教員の移動,準備等の負担が大きい。
- 時間割の制約があり,見通しをもって打合せ時間を確保することが難しい。
- 一人が3校受け持つと,負担も大きいが,打合せ時間を確保できる利点もある。
お問合せ先
初等中等教育局参事官付学力調査室
-- 登録:平成22年03月 --