- 現在位置
- トップ > 教育 > 小学校、中学校、高等学校 > 進路指導・キャリア教育について > 「キャリア・スタート・ウィーク・キャンペーン」について > キャリア・スタート・ウィーク地区別協議会 > 佐賀県白石町教育委員会(平成18年度キャリア・スタート・ウィーク推進地域) > キャリア教育実践プロジェクト 平成18年度実績報告書
キャリア教育実践プロジェクト 平成18年度実績報告書
別紙様式2
(キャリア・スタート・ウィーク推進地域用)
キャリア・スタート・ウィーク推進地域名 佐賀県 白石町
1.研究テーマと設定理由について
生徒一人一人の職業観・勤労観を育成するために,職場体験学習等を通して職業に関する知識や技能を身につけさせるなど,組織的なキャリア教育の推進を図り,将来,社会人として自立するための資質や能力を育てる。
(設定理由)
近年,フリーターやニート等の増加による若者の職業に対する意識が社会問題となっているが,このことは本町にとっても将来のまちづくりを考える際の重要課題の1つである。本町内の中学校では6,7年前より職場体験学習を実施している。生徒たちからは「よい体験ができた」,「自分の進路決定の参考になった」というような感想が毎年寄せられとても好評である。しかしながら,取組方法については各中学校独自であったため,生徒受け入れ先の確保や町全体としての協力体制等に不十分な点が多かった。よって本推進地域の指定を受けることで,キャリア教育に対する住民の理解を深め,町ぐるみで子どもたちを育てるという体制作りをめざす。
2.事業の活動内容及び成果と課題について
(1)市区町村キャリア・スタート・ウィーク実行委員会の位置付けと果たした役割及び成果と課題
(位置付け)
職場体験学習を実施するにあたり,生徒を送り出す学校側と生徒を受け入れる事業所側とをつなぐパイプ役として位置付け,町全体の体制作りができるよう委員の人選を行った。
(役割)
学校側と事業所側との職場体験学習に対するそれぞれの考え方や捉え方を実行委員会の場で出し合うことにより,両者が共通理解の下で取り組めるようにすること。
(成果)
- 学校関係以外の委員においては,中学校が行う職場体験学習の現状と課題についてまた中学生全般についての理解が深まった。
- 学校関係者にとっては,生徒受け入れに際しての事業所等の考えを聞くことができ生徒への指導上参考になった。
- 事業所関係委員が,職務上の会合で職場体験学習について広報活動をしたので,地域における職場体験学習への認知度が高まった。
- 高校教員をアドバイザーとして迎えたので,高校でのキャリア教育を見通した指導が意識され始めた。
(課題)
- 保護者や青少年健全育成団体の方の委員も必要である。そのことで地域住民への啓発も進むと思われる。
1.実行委員会の名称
[白石町CSW(キャリア・スタート・ウィーク)実行委員会]
2.実行委員会の構成メンバーについて(平成19年3月現在)
| 氏名 | 所属・職名 |
|---|---|
| 山中 楠王 | 佐賀県立佐賀農業高校・教諭(進路指導主事) キャリアアドバイザー |
| 中村 清二 | 白石町商工会・会長(白石地域) |
| 草場 祥則 | 白石町商工会・副会長(福富地域) |
| 門田 憲治 | 白石町商工会・副会長(有明地域) |
| 筒井 一典 | 白石町商工会・事務局長 |
| 鶴田 治 | JA白石・総務部企画管理課長 |
| 家永 健一郎 | 白石町商工観光課・課長 |
| 堤 正久 | 白石町福祉課・課長 |
| 御厨 秀樹 | 白石町立白石中学校・校長 |
| 山口 宏子 | 白石町立白石中学校・教諭 |
| 北島 清澄 | 白石町立福富中学校・校長 |
| 蓮田 健 | 白石町立福富中学校・教諭 |
| 濱野 孝幸 | 白石町立有明中学校・校長 |
| 辻 豊昭 | 白石町立有明中学校・教諭 |
| 鶴崎 進 | 白石町教育委員会学校教育課・課長 |
| 永石 一弘 | 白石町教育委員会学校教育課・指導主事 |
| 木須 比呂美 | 白石町教育委員会学校教育課・主査 |
| 坂本 和人 | 杵西教育事務所・指導主事 |
| 青木 久生 | 佐賀県教育庁学校教育課・指導主事 |
| 藤田 裕之 | 佐賀県教育庁学校教育課・指導主事 |
| 井手 和憲 | 佐賀県教育庁学校教育課・生徒指導担当係長 |
【組織関係図】
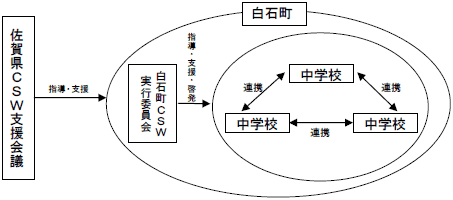
3.実行委員会における会議開催日毎の主な活動の内容(議論の内容)について
(ア)第1回 7月18日(火曜日)
(内容)実行委員委嘱状交付,事業説明,推進校のこれまでの取組状況説明,意見交換,アドバイザーの指導助言
- 生徒受入事業所の開拓について,事務局が中心になって,中学校,商工会等の協力を得ながら200箇所を目標に探す。
- 小中高の見通しをもった計画的なキャリア教育が必要である。特に高校が行っているインターンシップとの関連にも留意すべきである。
- 生徒たちには期間中,難しいことを要求する必要はない。大切なのは職業に対する心の面である。
- 白石町のよさを生徒たちが再認識するような配慮も必要である。そのため基幹産業である農業を体験させることも忘れてはならない。
- 仕事の大変さもわかってもらうために,ちょっときつい体験も必ずどこかに入れるべきである。
(イ)第2回 10月6日(金曜日)
(内容)職場体験学習現地視察,意見交換,アドバイザーの指導助言
- 腕章をしていないとわからないぐらい本物の従業員と同じ扱いを受けていたところが多く,受入事業所の意識の高さが伺えた。
- 生徒たちは普段見ることがない職場の裏を体験して,仕事の奥深さを感じたであろう。
- 自分が希望した職種で体験しているせいか,生徒は目を輝かせて一生懸命仕事をしていたように感じた。
- 産婦人科で体験した生徒が,新生児を抱きながら「助産師になります」とはっきり応えた姿が印象的だった。
- 学校との学習の違いを痛感した生徒も多かったのではないかと思う。
- 職場での服装がまちまちであったが,職場の制服の貸与を受けることで体験に対する意識も違ってくるのではないかと思うので,今後検討する必要がある。
- 生徒にはお世話になる事業所に関する事前学習をもっときちんとさせて臨ませるべきである。
- 4日目の視察であったが,生徒に疲れが見えるところもあり,5日間は長すぎるのではないかと感じた。
- 1つの事業所で5日間ではなく,2箇所ぐらい体験させてみても良いと思う。
- 幾分,事業所によって生徒に任せる仕事内容に差が合ったような気がするので,事務局で調整する必要があると思う。
(ウ)第3回 11月16日(木曜日)
(内容)「職場体験発表の集い」への参加,体験発表,職業に関する講演会
意見交換等の時間なし
4.実行委員会における活動の成果と課題について
(成果)
- 実行委員会委員のはたらきかけにより,町商工会加盟事業所,JA白石,町役場の全面的な協力を得ることができ,202箇所の生徒受入事業所を確保できた。
- 今年度実施の職場体験学習を実際に視察していただいて意見をもらうことができたので,今後改善していくべき課題が明確になった。
(課題)
- 各業種の組合への働きかけにばらつきがあり,受入事業所に業種の偏りがややうまれたので,委員会を通じてもれなく協力依頼をすべきであった。
- 来年度の実行委員会を行うための予算確保ができなかった。
5.実行委員会の活動の課題に対する取組方針について
- 来年度は,1つ1つの事業所にそれぞれ協力依頼をするのではなく,各業種の組合に協力依頼をしたい。そのことで,事業所間の温度差や体験内容の程度の差が小さくなるであろう。
- 委員会設立・運営のための予算がつかなかったが,来年度も教委が事務局として本町キャリア・スタート・ウィークを盛り上げていきたいと考えている。
(2)推進地域における活動の具体的内容及び成果と課題
1.推進地域における総学校数【数は、本事業における職場体験を実施する学校数】
| 市町村名 | 総中学校数 | 職場体験を受け入れた総事業所数 |
|---|---|---|
| 白石町 | 3校(3校) | 受入登録事業所202箇所のうち 今年度受け入れた事業所123箇所 |
2.推進地域における活動の具体的内容について
- 生徒受入事業所を開拓し,町全体の体制を整備すること
効果的な職場体験学習を実施するためには,まずは生徒の希望するところで体験させることが第一と考え,十分な数の事業所を確保することとした。そこで,これまで学校に任せていた受入事業所の開拓を事務局である町教委が中心となって行った。チラシを配付したり,町内放送等で広く宣伝活動を行ったりした。またいくつかの業種組合の会合に参加して受入協力をお願いした。さらに役場職員の仲介により受入事業所確保の足がかりとした。その他,学校においてはPTAや保護者の仲介で受入先を開拓した。その結果202事業所が,生徒の希望があれば受け入れてくださることとなり,町全体の基礎的な体制ができた。
- キャリア・スタート・ウィークによるキャリア教育の重要性を町住民へ啓発すること
町独自に作成したポスターを協力事業所に掲示した。また,期間中生徒全員は「職場体験」と書かれた腕章をつけ,職場体験学習が行われていることがはっきりとわかるようにした。さらに受入事業所には「職場体験協力店」ののぼり旗を立てた。このことで町民の方の認知度は高まり,期間中,中学生が注目された5日間となった。 - アンケート調査によって成果と課題を考察すること
職場体験学習実施後に,生徒,事業所,指導教員を対象にアンケート調査を実施した。その結果を分析することによって,来年度以降に向けての改善点を明確にした。
3.推進地域における活動の成果と課題について
- 「地域の子どもは地域で育てる」ということを前面に押し出して体制作りや広報活動を行ったので,期間中の反響も大きく,地域教育力向上の気運が高まった。
- 多くの受入事業所を確保できたので,全生徒の70パーセントが第1希望のところで,88パーセントが第3希望までの事業所で体験することができた。このことは生徒たちの体験意欲にも十分につながった。
- 受入事業所によって,職場体験学習に対して温度差が見られたり,体験内容に差が生じたりした。事業所側からも生徒にどこまで体験をさせていいのかわからないというような意見が出された。
- さらにできるだけ多くの生徒が第1希望のところで体験できるように,受入事業所を拡大しなければならない。
4.推進地域の活動の課題に対する取組方針について
- 受入事業所用にマニュアルを作成したいと考えている。他の事業所が中学生にどのような体験をさせているのかわかるような資料が提示できれば,事業所にとっても対応がしやすくなると思われる。また事業所間の差も小さくなるであろう。
- 上でも述べたが,業種に偏りがあるので,もっと幅広い業種について協力事業所を開拓していこうと考えている。
(3)職場体験実施校(本事業による)における活動の内容及び成果と課題について
1.実施校における活動の内容について(事前指導、体験中指導、事後指導の留意点等について)
本町では,町内すべての3校(中学2年生290名)が,一斉に職場体験学習を123事業所で実施した。事前に職業適性検査を実施することで自分の適性を考える機会にしたり,職業人を講師とした職業講話を実施したりして職業観の育成も図った。その他礼儀マナーなどについてのスキル講座も行った。また生徒たちは賠償責任保険へ加入して職場体験学習に臨んだ。
2.職場体験の主な受入先について(概要)
- 生徒受入登録事業所(生徒希望があれば受入可の事業所)202事業所
寺院・病院・老人福祉施設・飲食店・理容店・美容院・農漁業・畜産業・農産物流通業者・ガソリンスタンド・自動車整備工場・建築工務店・建設業・コンビニ・スーパー・生花店・鮮魚店・酒店・和洋菓子製造業・給食センター・運送業・消防署・郵便局・小学校・保育園・幼稚園・旅館・物産直売所・縫製業・衣料品店・公民館・図書館・板金業・弁当仕出し店・町商工観光課・町国土調査課・町管理課・ゴルフ場 など
3.職場体験の受入先の開拓方法について
上でも述べたように,今年度からは町教委が中心になって受入事業所を開拓したので,各実施校はその補助を行った。生徒を通じてチラシを保護者に配付したり,PTAや保護者の仲介を受けたりして受入先を開拓した。
4.実施校における活動の成果と課題について
- 職場体験学習の前に職業適性検査や職業講話,マナーなどのスキル講座等を行ったので系統的なキャリア教育を行うことができた。
- 後で述べるアンケート結果の内容からもわかるように,この職場体験学習をとおして学校ではできない数多くの体験を生徒にさせることができた。
(5)実施校における活動の課題(概要)
- 職場体験学習を実施した学年のみが,5日間集中的に総合的な学習として授業時数を消化するので,他の学年との授業時間の調整が難しい。
- 町内3校が一斉に同じ期間実施するので,1つの事業所へ2つの学校から生徒が体験に訪れる場合,各学校での指導内容に不揃いがあったので,対応する事業所が困惑されるということがあった。
5.実施校における活動課題に対する取組方針について
- 職場体験学習実施期間に,他学年も総合的な学習の時間のまとめ取りをするように,年間指導計画の見直しを行う。
- 町内3校が実行委員会以外にも打ち合わせる機会をもっと取り,細部にわたる申し合わせを行い,学校によって指導内容に違いが生まれないようにする。
6.実施校における児童生徒の勤労観、職業観に対する意識の変容等について
- 事後アンケートにおいて,次の問いに「そう思う(4点)」,「少し思う(3点)」,「あまり思わない(2点)」,「ぜんぜん思わない(1点)」としたときの全生徒(290名)の平均点は次のとおりである。
- 「働く」ということについて考えることができた。(3.59)
- 仕事の喜びや楽しさを感じることができた。(3.62)
- 仕事の厳しさを感じることができた。(3.69)
- 職場体験学習を通して,学校での学習の大切さがわかった。(3.09)
- 職場体験学習を通して,自分の将来について考えた。(3.24)
- 職場体験学習は,充実して,とても自分のためになったと思う。(3.74)
この結果から見ても,生徒の勤労観や職業観は十分に育成されていると考えられる。
7.実施校の状況
| 学校名 | 教員数 | 生徒数 | 所在地(電話・FAX番号・Eメールアドレス等) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 白石町立白石中学校 | 24 | 409 | 佐賀県杵島郡白石町大字遠江143番地1 電話 0952-84-2411 FAX 0952-84-2412 URL http://www3.saga-ed.jp/school/edq14051 (※白石中学校ホームページへリンク) |
|
| 白石町立福富中学校 | 14 | 197 | 佐賀県杵島郡白石町大字福富3497番地 電話 0952-87-3531 FAX 0952-87-2963 URL http://www3.saga-ed.jp/school/edq14151 (※福富中学校ホームページへリンク) |
|
| 白石町立有明中学校 | 20 | 309 | 佐賀県杵島郡白石町大字坂田290番地 電話 0954-65-2127 FAX 0954-65-2128 URL http://www3.saga-ed.jp/school/ariakejh (※有明中学校ホームページへリンク) |
8.実施校における職場体験の実施状況について
| 学校名 | 職場体験の実施形態(連続5日間の実施等) | 職場体験の教育課程上の位置付けについて | 来年度の取組予定について |
|---|---|---|---|
| 白石町立白石中学校 | 連続5日間実施 | 総合的な学習 | 10月に連続3日間実施予定 |
| 白石町立福富中学校 | 連続5日間実施 | 総合的な学習 | 10月に連続3日間実施予定 |
| 白石町立有明中学校 | 連続5日間実施 | 総合的な学習 | 10月に連続3日間実施予定 |
(4)全体的な研究の総括と展望
このキャリア・スタート・ウィーク推進地域の指定を受け,1年間,町全体の体制作りに主眼をおいて取組んできた。その結果,ある一定の成果はあげることができたと考えている。この取組が町民の中学生理解につながり,「地域の子どもは地域が育てる」という町民の意識を高め,地域教育力向上の足がかりになることを願った。来年度は3日間に縮小の予定だが,この取組を永年継続し,キャリア教育を地域が一体となって行えるよう工夫を重ねていきたい。
3.その他
○当課キャリア教育推進地域指定事業関係機関・他府省事業等の連携について
このことについては,該当ありません。
4.その他特記事項
特にありません
5.キャリア教育実践プロジェクトの市町村教育委員会担当者
| 氏名 | 勤務先・職名 | 連絡先(電話・FAX番号、Eメールアドレス等) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 永石 一弘 | 白石町教育委員会 学校教育課 指導主事 |
電話 0952-87-2111 FAX 0952-87-2744 MAIL nagaishi-kazuhiro@town.shiroishi.lg.jp |
-- 登録:平成21年以前 --