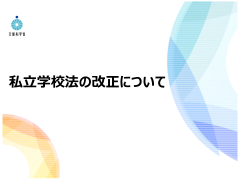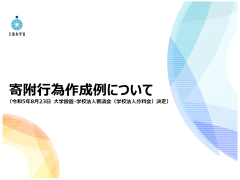- 現在位置
- トップ > 教育 > 大学・大学院、専門教育 > 私立学校・学校法人の振興 > 私立学校法の改正について(令和5年改正)
私立学校法の改正について(令和5年改正)
令和5年通常国会に提出をしておりました「私立学校法の一部を改正する法律案」が令和5年4月26日に参議院本会議にて可決され、5月8日に公布されました(私立学校法の一部を改正する法律(※公布された法律を掲載しているページにリンク)。今般の法改正の内容について理解を深めていただくため、説明動画及び資料を掲載いたします。
なお、改正内容に係るQ&Aにつきましては、「私立学校法の改正に関する説明資料(令和7年3月25日更新)(PDF:3.8MB)」の80ページ以降に掲載しております。
また、本改正に関するお問合せ窓口を設置しましたので、説明動画・説明資料をご確認いただいた上で、本改正に関してご質問がございましたら、私立学校法の改正に関するお問合せフォーム(※Microsoft Formsへリンク)からお願いします(回答にはお時間を頂戴しております。また、内容によっては回答できかねることがありますので、ご了承ください。)。
施行通知はこちらをご覧ください(私立学校法の一部を改正する法律等の施行について(通知)(※通知を掲載しているページへリンク))。
説明動画
※説明動画は令和5年4月末に収録したものであり、その後説明資料は更新しているため、動画内と説明資料のページ数が一部異なる場合があります。
説明資料
※説明資料は公開時点での法改正の解釈に基づき記載しており、今後変更の可能性があることをご了承ください。
寄附行為作成例
今般の私立学校法の改正に対応した寄附行為作成例について、文部科学大臣所轄学校法人向け、都道府県知事所轄学校法人向けをそれぞれ作成しています(令和5年11月に内容を一部修正、令和6年3月5日に形式的な修正)。
また、本寄附行為作成例についての説明動画を公表しました。以下のYouTubeのリンクから視聴ください。
各学校法人におかれては、令和7年4月の施行に向け、本寄附行為作成例を参考に寄附行為変更の検討を進めていただくようお願いします。
なお、都道府県知事所轄法人向けの寄附行為作成例の備考欄を充実させた【解説版】と、必要的記載事項(寄附行為に必ず記載しなければならない事項)一覧を掲載しますので、検討の際の参考にしてください。
- 寄附行為作成例(文部科学大臣所轄学校法人向け)(令和6年3月5日大学設置・学校法人審議会(学校法人分科会)決定) (PDF:435KB)

- 寄附行為作成例(都道府県知事所轄学校法人向け)(令和6年3月5日版) (PDF:425KB)

- 寄附行為作成例(都道府県知事所轄学校法人向け)【解説版】(令和6年3月5日版) (PDF:501KB)

- 寄附行為に必ず記載しなければならない事項(必要的記載事項)一覧 (PDF:102KB)

説明動画【寄附行為作成例について】
学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税の承認の適用を受けようとする場合の学校法人の標準的な寄附行為(都道府県知事所轄学校法人向け)について
譲渡所得等の非課税の特例(一般特例)の対象となるためには、寄附行為に一定の事項を定める必要があります(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号など)。
「学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税の承認の適用を受けようとする場合の学校法人の標準的な寄附行為(都道府県知事所轄学校法人向け)」に則って、寄附行為を定めていただくことで、一般特例の対象となるための一定の事項が全て定められることになるところ、今般の私立学校法の改正にあわせ、「標準的な寄附行為(都道府県知事所轄学校法人向け)」を改正しましたので、ご確認いただき、寄附行為変更の検討を進めていただきますようお願いいたします。
なお、大臣所轄学校法人等において、学校法人の理事等及びその親族から寄附を受け入れるなど、一般特例の制度を適用する場合については、「標準的な寄附行為」によらず、寄附行為作成例(文部科学大臣所轄学校法人向け)を参考に、上記の一定の事項を反映した寄附行為を定めていただく必要があることにご留意ください。
※ 譲渡所得等の非課税の特例(一般特例)の対象となるために寄附行為に定めるべき事項については、次のページから確認することができます。
このページのほか、譲渡所得等の非課税の特例(租税特別措置法第40条)と寄附行為の関係等の詳しい内容は最寄りの国税局までお問い合せください。
寄附行為についての確認事項(※PDF 国税庁のページにリンク)
- 譲渡所得等の非課税特例の対象となるための「標準的な寄附行為」について(概要) (PDF:399KB)

- 学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税の承認の適用を受けようとする場合の学校法人の標準的な寄附行為(都道府県知事所轄学校法人向け) (PDF:437KB)

内部統制システムの整備について
今般の私立学校法改正により、大臣所轄学校法人等においては内部統制システムの整備が必要となり、その基本方針を理事会で決定しなければならないことになります。 また、大臣所轄学校法人等以外の学校法人においても、各学校法人の実情に応じ、内部統制システムを整備することが望まれます。
改正私立学校法施行に向けた準備・手続(todoリスト)
私立学校法改正対応について何から着手したら良いか分からないという学校法人にも参考にしていただけるよう、施行までに必要な基本的・一般的な準備・手続の概要をまとめました。
政省令の整備について
「私立学校法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和6年政令第209号)」及び「私立学校法施行規則の一部を改正する省令(令和6年文部科学省令第21号)」が令和6年6月14日に公布されました。
- 私立学校法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (PDF:161KB)

- 私立学校法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 新旧対照表 (PDF:334KB)

- 私立学校法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 概要 (PDF:83KB)

- 私立学校法施行規則の一部を改正する省令 (PDF:611KB)

- 私立学校法施行規則の一部を改正する省令 概要 (PDF:1.6MB)

学校法人会計基準の改正について
改正私立学校法において、ガバナンス強化の観点から、現在の学校法人会計基準を、私立学校振興助成法に基づく基準から、私立学校法に基づく基準に位置づけ直すこととなりました。
学校法人会計基準の改正については、次のリンク先のページにて改正の方向性についての報告書や、改正内容に関する説明動画等を掲載しています。
改正法施行後の理事会の議事録の作成例について
改正法施行後の理事会の議事録の作成例をお示し致します。
- 理事会の議事録(例) (PDF:220KB)

- 理事会の議事録(例)(理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したことにより、当該事項を理事会への報告することを要しないこととされた場合) (PDF:172KB)

本改正に関する専用のお問合せ窓口
本ページに掲載している資料をご確認いただき、組織内でご相談のうえ、本改正に関してご質問がございましたら、私立学校法の改正に関するお問合せフォームからお願いします(回答にはお時間を頂戴しております。また、内容によっては回答できかねることがありますので、ご了承ください。)。