- 現在位置
- トップ > 教育 > 大学・大学院、専門教育 > 国公私立大学を通じた大学教育改革の支援 > 新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム(学生支援GP) > 平成19年度「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム」実施委員会(第2回)議事次第・配付資料 > 参考資料4 平成19年度「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム」審査要項
参考資料4 平成19年度「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム」審査要項
1.本プログラムの目的
学生の人間力を高め人間性豊かな社会人を育成するため、各大学・短期大学・高等専門学校における、入学から卒業までを通じた組織的かつ総合的な学生支援のプログラムのうち、学生の視点に立った独自の工夫や努力により特段の効果が期待される取組を含む優れたプログラムを選定し、広く社会に情報提供するとともに、財政支援を行うことで、各大学等における学生支援機能の充実を図ることを目的とする。
本プログラムの審査は、この審査要項により行うものとする。
2.審査体制・方法
- 本プログラムの審査は、以下の体制により行う。(次ページ参照)
- 実施委員会
- 実施小委員会
- 総合評価部会(大学・短期大学別)
- 審査会(大学・短期大学・高等専門学校別)
- ペーパーレフェリー
- 各「審査会」及び「ペーパーレフェリー」の分担は、申請件数に比して、おおよそ均等の件数となるよう、中立公平性に配慮した上で割り振る。
- 具体的審査に入る前に、各「総合評価部会」又は「高等専門学校を担当する審査会」は、申請書類の形式的要件や対象となるプログラムであることなどの基本的要件の審査を行う。
- 各「審査会」は、書面審査を行い、合議によりヒアリング対象とするプログラムを選定する。
なお、合議の際は、審査の客観性・公正性を担保するために「ペーパーレフェリー」の意見も参考とする。 - 各「総合評価部会」は、各「審査会」(「高等専門学校を担当する審査会」を除く。)により選定されたヒアリング対象とするプログラムを決定する。
- 各「審査会」は、ヒアリングを実施し、合議により選定候補のプログラムを選定する。
- 各「総合評価部会」は、各「審査会」(「高等専門学校を担当する審査会」を除く。)により選定された選定候補のプログラムを総合的に評価し、調整を図る。
- 「実施小委員会」は、各「総合評価部会」及び「高等専門学校を担当する審査会」の結果について審議し、全体的調整を図る。
- 「実施委員会」は、「実施小委員会」の調整結果について審議し、選定プログラムを決定する。
新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム審査体制
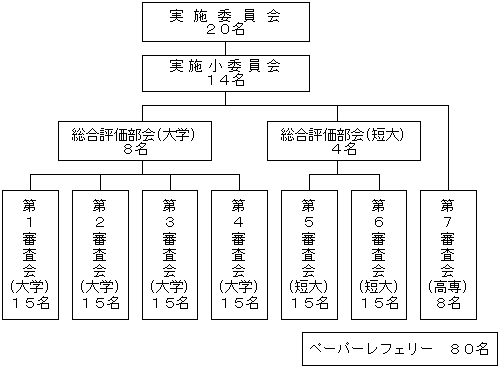
- 実施小委員会は、実施委員会委員7名及び各審査会の主査7名の計14名により組織する。
- 総合評価部会は、大学及び短期大学について設けることとし、各審査会(高等専門学校を担当する第7審査会を除く。)の各主査・主査代理(大学8名・短大4名)により組織する。
- 審査会委員に関する事項は以下のとおりとする。
- 審査会委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
- 委員の数は、一審査会あたり15名(高等専門学校を担当する第7審査会は8名)(計98名)を目安とする。
- 委員が自ら所属する大学・短期大学・高等専門学校が申請したプログラムの審査に加わることができない。
- 同一の大学・短期大学・高等専門学校に所属する委員は、原則として3名以内とする。
- 同一の大学・短期大学・高等専門学校に所属する委員は、同一の審査会に所属しないものとする。
- 申請1件につき、2名の委員が書面審査を担当する。
- ペーパーレフェリーに関する事項は以下のとおりとする。
- ペーパーレフェリーの任期は1年とし、再任を妨げない。
- ペーパーレフェリーの数は、80名を目安とする。
- ペーパーレフェリーが自ら所属する大学・短期大学・高等専門学校が申請したプログラムの審査を担当することができない。
- 同一の大学・短期大学・高等専門学校に所属するペーパーレフェリーは、原則として3名以内とする。
- 申請1件につき、2名のペーパーレフェリーが書面審査を担当する。
3.審査手順(選定までの流れ)
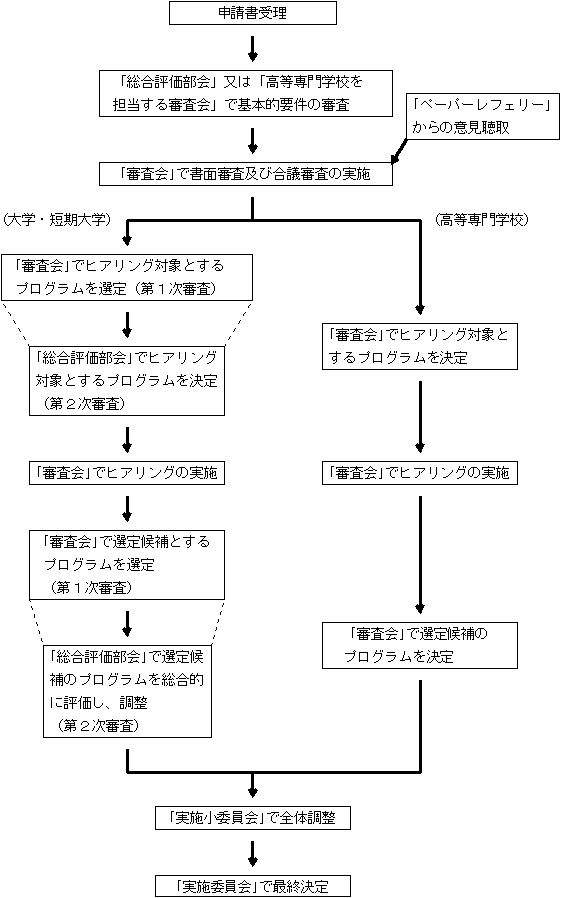
4.審査方針
本プログラムにおける選定にあたっては、次のような諸点に留意する。
学生支援に対する現在の基本的考え方等について
1 学生支援に対する理念や目標
- 学生支援に対する理念や目標は明確になっているか。
- 学生支援と教育活動や研究活動とが関連付けられているか。
- 学生支援によって十分な効果が得られているか。
2 学生支援に対する現在の取組の組織性
- 取組を実施するための体制(学内の意思決定手順や実施体制等)が整っているか。
- 取組の実施にあたって学内外の連携体制が十分かつ適切か。
3 社会的ニーズや学生のニーズへの対応の現状
- それぞれのニーズの把握の方法や内容は適切か。
- (把握した結果を十分に活用するなど)それぞれのニーズに応じた適切な取組が実施されているか。
4 現在の学生支援を行う教職員の資質向上(ファカルティ・ディベロップメント(FD)、スタッフ・ディベロップメント(SD)など)
- 学内で学生支援の重要性について教職員の共通認識を得るための努力が行われているか。
- 教職員の専門的な知識や能力の向上のための取組が適切に行われているか。
5 現在の取組の実施後の評価及び取組内容の改善
- 学内の評価体制・方法は適切か。
- 評価項目の設定は十分か。
- これまでの評価結果の活用が十分行われているか。
6 学生支援に対する現在の基本的な取組の状況
- 現在の取組が入学から卒業までを通じた総合的なものとなっているか。
- 現在の基本的な取組が、ひとつひとつの単独の取組としてだけでなく、相互に連携した体系的な取組としても機能しているか。
- 真摯な努力を継続的に積み重ねる等、学生支援の充実に地道に取り組んでいるか。
社会的ニーズ等に対応し、特段の工夫などが行われ、著しい効果が期待できる新たな取組について
7 新たな取組の趣旨・目的
- 新たな取組を実施するに至った動機や背景は明確になっているか。
- 新たな取組は、大学等において、意義(意味)のあるものとなっているか。
8 新たな取組の独自性(工夫されている内容)
- 新しい発想や独自の創意工夫(他にはない特色)が見られるか。
- 他大学等の参考となるか。
9 新たな取組の有効性(効果)
- 学生や大学等にとって、この取組を実施することにより、現在の取組と比して、効果の拡大が十分に見込まれるか。
- 現在の学生支援の取組全体との間で相乗効果が見込まれるか。
- 新たな取組は社会的ニーズや学生のニーズに十分応えているか。
- 教育活動や研究活動との関係において有効な取組となっているか。
10 新たな取組の改善・評価
- この取組の効果に関する評価体制・方法は適切か。
- 評価項目の設定は十分か。
- 評価結果の活用方法について、十分考慮されているか。
11 新たな取組の実施計画・将来性
- 実施計画やスケジュール、実施体制等は適切か。
- 実施するにあたり十分な取組の組織性が確保されているか。
- 既に実施されている他の取組との関係から過大な計画となっていないか。
- 補助期間が終了した後も、引き続き取組が進展し、さらなる効果が見込める計画になっているか。
5.その他
1 開示・非開示
(1)「実施委員会」の審議内容等の取扱いについて
- 「実施委員会」の会議及び会議資料は、原則、公開する。
ただし、次に掲げる場合であって「実施委員会」が非公開とすることを決定したときは、この限りではない。- 審査・評価(人選を含む。)に関する調査審議の場合
- その他委員長が公開することが適当でないと判断した場合
- 「実施委員会」の議事要旨は、原則、公開する。ただし、審査・評価に関する調査審議の場合は、非公開とする。
- 選定された取組は、文部科学省及び独立行政法人日本学生支援機構のホームページへの掲載等により、広く社会へ情報提供する。
(2)委員等氏名の公表について
- 「実施委員会」の委員の氏名は予め公表する。
- 「実施小委員会」、「総合評価部会」、「審査会」委員及び「ペーパーレフェリー」の氏名は選定後に公表する。
2 利害関係者の排除
申請に直接関係する委員等は、審査を行わないものとする。
書面審査の場合は、当該委員等を除く委員で審査を行うこととし、合議審査(ヒアリングを含む。)の場合は、当該申請の審査には参加しないものとする。
利害関係者とみなされる場合の例
- 委員等が現在所属し、又は、過去3年以内に所属していた大学・短期大学・高等専門学校に関する申請
- その他委員等が中立・公正に審査を行うことが困難であると「実施委員会」において判断される申請
お問合せ先
高等教育局学生支援課
-- 登録:平成21年以前 --