- 現在位置
- トップ > 基本・共通 > 国際関係 > 第9回OECD/Japanセミナーについて > 第9回OECDジャパンセミナー プログラム > 第9回OECDジャパンセミナープログラム
第9回OECDジャパンセミナープログラム
印刷用(PDF:52KB)
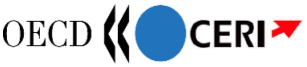 |
 |
大学の将来像:
大学の担う役割、変化の原動力、未来予測図、及び政策的挑戦
主催
文部科学省
OECD/CERI(教育研究革新センター)
協力
東京大学
平成15年12月11日(木曜日)~12日(金曜日) 2日間
三田共用会議所
9時10分-9時30分 登録
9時30分-9時45分 開会
中等後教育への高まる需要、教育・研究におけるICT活用の増加、国際化や開発途上国における高等教育の需要の高まり、新たな中等後教育組織の台頭といった社会の動きは、中等後教育システムにおいて従来の大学が担ってきた役割を変えようとしている。OECD/CERI(教育研究革新センター)で進められている「大学の将来像」プロジェクトは、社会が研究、指導・学習、サービスの必要性といった条件を満たすために選択するさまざまな方策や、果たして大学はこうした役割を今後も続けていくことになるのか、それとも今後は新たな役割を担うのかといったことを分析するものである。この目的は、今後10~20年間における大学の将来を明確に描いた予測図をいくつか入念に作成することで成し遂げられる。大学の将来像を映し出すこうした予測図を作成することは、政策立案者や教育関係者がOECD諸国の大学にとってもっとも望ましい方針を模索するための一助となるだろう。このOECDジャパンセミナーは、高等教育に関わるOECD諸国の政策決定者や関係者がこうした課題について議論を行う今までにない機会である。
| ・ | 河村建夫(文部科学大臣) |
| ・ | バリー・マクゴー(OECD教育局長) |
| セッション1: | 高等教育改革の現在の方向性と将来的政策課題について |
議長:宮田 清藏(東京農工大学長)
| OECDに加盟する全ての国では高等教育における急速な変化に直面しており、大学やその他の高等教育機関をどのように位置づけていくかということが当面の課題となっている。変化が早く、競争もますます激化する現代社会において、労働者に関連技術を身に付けさせる、革新を促進する、生産性をサポートする、生活水準を向上させるといった高等教育が担う役割が、非常に重要なものとなってきている。こうしたことから、変化の原動力や、高等教育システムにとって望ましい将来の方向性についてすでに論議を重ねている政府もある。 このセッションは現在の高等教育について各国の情報を共有し、高等教育及び大学が持つ将来の課題について検討することを目的にしている。 |
9時45分-11時15分 基調講演
| ・ | 佐々木 毅(東京大学学長) 「日本の高等教育における現状と課題」について |
| ・ | マーガレット・ヴェステガー(デンマーク国会議員、元教育相) 「政策決定者の視点から見た大学の将来像」について |
10時45分-11時15分 質疑応答
11時15分-11時30分 コーヒー・ブレイク
| セッション2: | 大学の将来の役割と変化の原動力 |
議長:木村 孟 (大学評価・学位授与機構長)
大学は現在、少なくとも4つの役割を担っている:
ここで論点となるのは、大学は将来もこうした役割を果たしていくのか、それとも新たな役割を担うことになるのか、ということである。高等教育の内部で起きている変化は社会そのもので起きている変化と直結していると言える。例えば、教育や学習の需要の大衆化、若年層人口の減少、人口の高齢化、民族の多様性などの人口統計、急激に変化する国際労働市場、生産、消費、学習の新たな技術、個人による知識生産の増加と知識管理の新たな形態、知的所有権に関する制度変更、公営、統治、公民権の形態の変革、能力評価、資格、市場シグナルの新しい形、社会の分節化または団結、価値体系の変化などといったさまざまな変化の原動力に、現在の高等教育は直面している。これら全ての変化が大学の3つの主要な役割である指導、研究、サービスに影響を及ぼしている。 こうした変化は高等教育に付随する価値観を予期せぬ方向に変えてしまう可能性もある。高等教育の将来を考えるには、高等教育に付随する本質的価値を発展させることについて考えてみる必要がある。そうした本質的価値は先に述べたような変化を踏まえてどのように発展するだろうか。またそうした価値観は、将来起こる変化によってどのような影響(あるいは恩恵)を受けるのだろうか。 このセッションは、大学が担う将来の役割と大学に影響を及ぼす社会経済的変化についての共通の理解を形成し、中等後教育にかかわる政策決定者や利害関係者がこうした変化に対して適切な対応を行う一助となることを目的としている。 |
11時30分-12時30分 講演
| ・ | 梶山 千里(九州大学学長)「九州大学の役割と変化の原動力」について |
| ・ | ダン・アトキンス(ミシガン大学教授) 「大学研究における将来の変化」について |
12時30分-14時 昼食
| セッション2: | 大学の将来の役割と変化の原動力(続き) |
議長:小宮山 宏 (東京大学副学長)
14時-15時 講演
| ・ |
|
||
| ・ | 林 未央(東京大学大学院教育学研究科総合教育学専攻博士課程3年) 「現在大学が果たしている役割の再評価を」 |
||
| ・ | マルシャン・ザビエ(東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修士課程1年) | ||
| ・ | 「日本における留学生:その期待と可能性」 |
15時-15時30分 質疑応答
15時30分-15時50分 コーヒー・ブレイク
15時50分-17時30分 ワークショップ(4つ並行)
各国の参加者は既存の報告書や事実を基に、大学の将来の役割と自国の高等教育システムにおける主要な変化の原動力についてメモを用意することが望ましい。各国の参加者が共通した構成とテーマのリストを得られるように、OECD事務局から参加国あてにカントリーノートを作成する際のガイドとして所定の用紙を送付済みである。
このワークショップでは、まず国別の観点から見た高等教育の将来の役割、原動力、価値観についての簡単な講演を二つ行う。ここではカントリーノートが議論のベースとなる。そして、高等教育の将来の役割や変化の原動力における共通点や違いを明らかにして分析を行う。
また、OECDの教育や研究についてのデータベース及びその他のデータを使って、高等教育を取り巻く最近の包括的な傾向を明らかにする。これには人口統計、生徒数、高等教育機関の種類、高等教育及び研究に対する財政的支援の程度及び財源などが含まれる。
テーマ:
| - | 大学の現在の役割は他の教育機関などに代替され、そして/または大学は新たな役割を担うことになるのだろうか。 |
| - | 今後10~20年の高等教育の需要と提供の変化の主な原動力は何か。 |
| - | 今後10~20年の大学の知識の生産、普及、活用と研究の主な変化は何か。 |
| - | これらの変化によって、高等教育機関が持つ社会的・学問的価値は変わるのか。 |
ワークショップ1
| 議長: | リチャード・イエランド(OECD) |
| 発表者: | ヘレナ・セブコヴァ(高等教育研究センター、チェコ) イウ・クワン・ファン(香港バプティスト大学、香港) |
ワークショップ2
| 議長: | クリストス・ニコラオウ(クレタ大学、ギリシャ) |
| 発表者: | リリア・オランテス・ガルベス(教育省、メキシコ) ビュンシック・リー(韓国教育開発院、韓国) |
ワークショップ3
| 議長: | ピョートル・ウェグレンスキー(ワルシャワ大学、ポーランド) |
| 発表者: | <予定> 黄 福涛(広島大学高等教育研究開発センター) |
ワークショップ4
| 議長: | 高石 道明(信州大学)日英同時通訳有 |
| 発表者: | レネイ・ブッゲ・バートラムセン(科学技術革新省高等教育官、デンマーク) ダララット・アナンタナスオン(国立開発行政大学院、タイ) |
18時- 文部科学省主催レセプション(※招待者のみ)
第2日目:平成15年12月12日(金曜日)
| セッション3: | 大学の未来のシナリオの開発 |
議長:金子元久 東京大学教授
| OECD事務局が大学の未来に向けたシナリオ案をいくつか紹介する。このシナリオ案は、2003年6月24日及び25日に行われたOECD/CERI専門家会合での論議を基に作成されたものである。 このセッションは大学の将来像に向けた有望かつ可能なシナリオについて論議し分析することを目的としている。 |
9時30分-10時 プレゼンテーション
| ・ | リエル・ミラー(OECD) |
| 10時-12時 | 大学の未来のシナリオを開発するワークショップ(4つ並行) |
このセッションはOECD事務局により用意された大学の将来像についての2種類のシナリオについて議論することを目的としている。学習社会における高等教育の将来像についてのシナリオを議論するワークショップが二つ、そして残りの二つのワークショップでは大学の将来像についてのシナリオを議論する。
二つのシナリオの主な相違点は、第一のシナリオは学習社会(社会的視点)を背景にした高等教育の将来像についての議論を目的とする一方で、第二のシナリオにおいては大学機関(機関的視点)の将来の展開がより具体的に議論されるという点である。
この日のワークショップは、初日に行われた大学にとっての主要な変化の原動力についての話し合いを基に構築され、大学の将来像についてのシナリオ案について議論される。参加者は用意されたシナリオについて意見を述べ、自国の状況にもっとも近いシナリオを特定し、将来にとってもっとも望ましいシナリオを見出すよう促される。
従ってこのワークショップでは、それぞれ有望なシナリオ、可能性のあるシナリオ、望ましいシナリオを見分けながら、大学の将来像についてのシナリオを特定・議論することが目的である。OECD事務局が用意する学習社会と大学についてのシナリオを記載した資料は、セミナーの前までに参加者に提供される。
テーマ:
| - | どのシナリオが自国に最も近い状況を描いているか。 |
| - | 自国の大学セクターはどのシナリオを目指しているだろうか。 |
| - | 学習と大学のそれぞれについて、最も望ましいシナリオはどれか。 |
| ワークショップ1 | 「社会における学習の未来に向けてのシナリオ」 |
| 議長: | 山本 眞一(筑波大学) |
| モデレーター: | リエル・ミラー(OECD) |
| ワークショップ2 | 「社会における学習の未来に向けてのシナリオ」 |
| 議長: | ハーウィンド・ハリボウォ(国家教育省、インドネシア) |
| モデレーター: | カート・ラーセン(OECD) |
| ワークショップ3 | 「大学の未来に向けてのシナリオ」 |
| 議長: | ジョン・A・スピンクス(香港大学) |
| モデレーター: | スティーブン・ヴィンセント=ランクリン(OECD) |
| ワークショップ4 | 「大学の未来に向けてのシナリオ」(日英同時通訳有) |
| 議長: | ヒョンチョン・リー(韓国大学教育審議会韓国大学総長協会) |
| モデレーター: | 籾井 圭子(OECD) |
12時-13時30分 昼食
13時30分-14時30分 ワークショップでの議論を全体会議で報告
| セッション4: | 政策的挑戦と選好:高等教育の将来像と政府の役割 |
議長:バリー・マクゴー(OECD教育局長)
| このセクションではそれぞれ学生、雇用主、高等教育機関、政策決定者の視点から見て望ましい手法でシナリオをどのように構成しうるかについて議論する。ここでは特に中等後教育システムの運営にあたり政府が将来果たすべき役割に焦点を当てる。政府は大学の将来の役割や変化の原動力を考慮に入れた上で、政策的に望ましい方法で中等後教育システムをどのように運営していくべきだろうか。 |
14時30分-16時 パネル・ディスカッション
| ・ | 羽矢 惇(新日本製鐵株式会社常務取締役) |
| ・ | オズモ・ランピネン(フィンランド教育省) |
| ・ | 田中 俊郎(慶応義塾大学常任理事) |
| ・ | 原 圭史郎(東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学専攻博士課程3年) |
| ・ | リチャード・イエランド(OECD高等教育機関の管理運営に関するプログラム担当課長) |
| 15時30分-16時 | 質疑応答 |
| 16時‐ | クロージング・リマークス 高塩 至(文部科学省 大臣官房審議官(高等教育局担当)) |
当セミナーについての詳細は、下記のウェブサイトを参照ください。
http://www.simul-conf.com/oecd_japan/index_en.html
-- 登録:平成21年以前 --