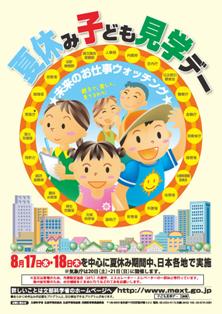- 現在位置
- トップ > 教育 > 社会教育 > こども霞が関見学デー > 平成23年度子ども見学デー(8月5日報道発表)
平成23年度子ども見学デー(8月5日報道発表)
平成23年8月5日
8月17日(水曜日)、18日(木曜日)を中心に実施する「子ども見学デー」における文部科学省のプログラム概要が、まとまりましたのでお知らせします(プログラムの内容については、「別紙1 文部科学省内プログラム一覧表を参照)。今年度は、東日本大震災を踏まえ、親子で防災や防災教育、環境、エネルギー等について考える契機となるような取組も行います。
「子ども見学デー」は、子供たちが親の職場を見学することなどを通して、親子のふれあいを深め、広く社会を知る機会とするために、文部科学省を始め24府省庁が実施します。詳しくは、「7月15日付報道発表資料又は各府省庁のホームページ を御覧ください。
|
お仕事見学してみよう! |
1.参加・申込み方法
文部科学省のプログラムには、当日参加できるプログラムと、あらかじめ申込みが必要なプログラムとがあります。
※当日参加できるプログラムについては、会場に直接お越しください。
※あらかじめ申込みが必要なプログラムについては、申込み方法に沿って、お申込みください。
1.自由に参加できるプログラム
(1)『放課後子ども教室体験コーナー』
- 日時 8月17日(水曜日)10時~16時、8月18日(木曜日)10時~16時
※日程や時間指定のあるプログラムに御注意ください。 - 場所 文部科学省3階 第1講堂
- 内容 防災や防災教育、環境、エネルギーに関する体験や学習(エッキーの実験教室(液状化現象の実験)放射線について学ぼう)及び様々な体験プログラム(ちぎり絵体験、子ども手品教室、子ども将棋教室)等を用意しています。
(2)『情報ひろば~子ども見学デー特別イベント~』
- 日時 8月17日(水曜日)10時~16時、8月18日(木曜日)10時~16時
- 場所 旧文部省3階展示室 情報ひろば
- 内容 文部科学省の仕事の今と昔を探検しよう。GTF浮世絵展2011(浮世絵の展示と参加者による試しづり体験)等のイベントもあります。
(3) 「霞が関をクールダウン!~みんなで打ち水」
- 日時 8月18日(木曜日)12時~(予定)
- 場所 文部科学省庁舎前 中央ひろば
- 内容 子供たちが、文部科学省職員や霞が関近辺の方々と一緒に水をまきます(打ち水を行います)。
(4) 共催企画「コミュニケーション教育・フェスタ」
- 日時 8月17日(水曜日) 13時~16時30分
- 場所 旧文部省庁舎6階 第2講堂
- 内容 〔児童生徒のコミュニケーション能力の育成に資する芸術表現体験〕の実施に当たっての成果・課題を共有するフォーラムを開催します。
2.あらかじめ申込みが必要なプログラム
(1)「吉田秀彦さんと一緒に柔道を知ろう!~VIVA JUDO~」(事前申込み終了)
- 日時 8月17日(水曜日)(1)14時~15時、(2)15時~16時
- 場所 文部科学省庁舎前 中央ひろば
- 内容 オリンピックメダリストと一緒に畳や柔道着の雰囲気を楽しみ、スポーツの楽しさについて直接貴重なお話を聞くことができます。
- 人数 各50名程度
- 申込み方法 メール(hiroba@mext.go.jp)若しくは往復はがきに郵便番号、住所、本人(子供)氏名(フリガナ)、年齢、引率者氏名、電話番号、メールアドレス、希望プログラム(第一(14時~15時)又は第二(15時~16時)又はどちらでも可)、を記載して文部科学省広報室にお申込みください。
(2)「大臣室をのぞいてみよう」(事前申込み終了)
- 日時 8月17日(水曜日)の午前中1時間程度
- 場所 文部科学省庁舎内
- 内容 大臣室を探検したり、記念撮影を行います。
- 人数 60名程度
(3)「ロボットコンテスト」 (事前申込み終了)
- 日時 第1部 8月17日(水曜日)10時~12時、第2部 8月18日(木曜日)10時~12時、13時30分~15時30分
- 場所 文部科学省3階 第1講堂
- 内容 【第1部】省エネ・運搬ロボット 【第2部】高度ICT人材育成プロジェクト「プログラミングロボコン」
- 人数 第1部 25名程度、第2部 各15名程度
2.取材について
取材を希望する方は、取材日前日の16時までに、「別紙2 報道関係者登録票」によりお知らせください。
3.備考
(1)プログラムについては、現段階のものであり、今後変更する可能性があります。
(2)取材については、下記問合わせ先までお問合わせください。
4.資料
お問合せ先
生涯学習政策局生涯学習推進課
課長 藤野 公之(内線3456) 民間教育事業振興室長 根本 幸枝(内線3282) 民間教育事業第二係長 船木 茂人(内線2642)
電話番号:03-5253-4111(代表) 03-6734-2092(直通)
-- 登録:平成23年08月 --