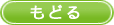議事録
- 日時 平成11年7月16日(金)10:00〜12:00
- 場所 科学技術庁第7会議室(通商産業省別館9階)
- 出席者
-
石塚主査、秋吉委員、飯田委員、礒山委員、伊藤委員、上野委員、
宇津野委員、戎崎委員、小柳委員、金久委員、後藤(敏)委員、
後藤(滋)委員、諏訪委員、田中委員、土居委員、西村委員、林委員、
樋口委員、畚野委員、松田委員、米澤委員
丸山計画・評価課長、土屋科学技術情報課長、
(事務局)(科学技術庁) 池田研究開発局長、中澤官房審議官(研究開発局担当)、
米倉情報科学技術推進室長
(文 部 省) 太田学術情報課長、山田学術情報基盤整備推進室長
- 議題
(1)重点領域の設定について
(2)中長期的な検討事項について
(3)その他
- 配付資料
資料3−1 科学技術会議政策委員会情報科学技術委員会(第2回)議事録(案)
資料3−2 重点領域に対する一般意見募集結果
資料3−3 情報科学技術先導プログラムの重点領域の設定について(案)
資料3−4 産業競争力の強化を踏まえた重点領域に関する追加的検討について
資料3−5 中長期的な観点から当委員会で扱うべき事項に係る論点の整理
参考資料 科学技術会議政策委員会情報科学技術委員会構成員
- 議事概要
(1) 主査による開会の挨拶後、委員及び事務局の紹介があった。 (2) 重点領域案に関する一般意見の募集結果、及び、これらの意見への対処方針が検討され、重点領域案に所要の修正を図った上で、情報科学技術委員会としてこれを決定し、政策委員会に報告することとした。 (3) 産業競争力強化の観点からの重点領域に関する追加的の検討結果が、重点領域検討WGから報告され、情報科学技術委員会としてこれを了承し、政策委員会に報告することとした。 (4) 委員会の当面の進め方について意見交換が行われた。次回の委員会は、8〜9月に開催することとされた。 (5) 主査から閉会の挨拶があった。
- 議事内容
(冒頭、主査より開会の挨拶)
(事務局より出席委員の紹介、配付資料の確認)
【重点領域の設定について】
○主査 本日の議題に入りたい。皆様ご承知のとおり、科学技術会議第25号答申を受け、本委員会における第一段の取組みという位置づけで、この答申にもあった先導プログラムを実施するに当たって、重点的に取り組むべき研究領域、すなわち重点領域の設定作業を現在進めているところである。
第2回の委員会において、本委員会として重点領域の案を外部に意見聴取するため決定し、その後、インターネット等で一般の意見聴取を行ったところである。寄せられた意見のうち重点領域に反映することが適当と認められるものは反映した上で、本日の委員会において重点領域を決定したい。
寄せられた意見とその概要、それらの意見に対する対処方針が本日資料3−2という形で取りまとめられているので、まず事務局の方から説明いただきたい。
(事務局より資料3−2に基づき説明)
○主査 ただいま、一般の方から意見を聴取した結果の概要と、それをどのように重点領域に反映させるかという案について、事務局から説明があった。資料3−3の重点領域の設定について、、第2回の委員会で皆様方からいろいろいただいた意見をもとに、私とWG主査との間で調整、修文したものを一般の方に意見を聴取する前の段階としてインターネットで公表したわけである。従って、本日の資料3−3は、それにさらに一般に公募した意見を取り入れたものになっている。一般意見の公募から大変貴重な意見もいろいろ頂いたが、そういったものをこういう形で取り入れるということでよろしいかどうか。それから、本日は重点領域を決定いただくということをお願いいたしたいと思う。全体として、最終案としてこれでよいかどうか、何かご意見があれば伺いたい。
ところで、今、事務局からご紹介があったとおり、きょうご欠席の委員から重点領域についてのご意見が来ている。人材養成が重要でありもっと具体的な案が欲しい、重要性に対する重みづけが欲しい、有効な実施手段を考えるべきであるという3点についての追加のご意見である。このあたりもご覧いただきながら、さらにご意見をいただきたい。
○WG主査 一般意見に関する対処方針まで含め、WGの方で慎重に検討させていただいた。ところで8番目の対処方針のところであるが、時間切れということで多少修正すべき点が残っているので、この場で検討し、修文させていただきたい。「災害時の被害状況をリアルタイムで統合し最適な救助戦略立案を助けるエージェント機能を有する危機管理情報システム」とあるが、何もエージェント機能に限る必要はないということで、「エージェント機能を有する」という部分は削除したい。
○主査 では、そのように修正することとする。また、先ほどご紹介した委員のご意見のうち、人材養成が重要ということについては、まさに中長期的にこの情報科学技術委員会においてもいろいろと議論を深めるべき重要な論点の一つであり、次回以降の検討項目の一つということになろうかと思う。ここでは現在とりまとめ中の先導プログラムの重点領域をまとめるということで、人材育成のことは留意事項に書かれている程度でよろしいのではないか。
次に、重要性に対する重みづけについて、第2回でもプライオリティーをつけるのかというご質問があり、そのときにもいろいろと議論していただいたが、この重点領域というのをこれからどういうふうに実施していくか。いろいろな制度に乗せて実施していくことになるが、制度によってはやはり公募をして、その時点できちんと評価して決めていくという性格のものがかなり含まれており、そういう段階で重要性というものが決められていく、あるいはそれにのっとって選択していくということで、あらかじめここで重要性の重みづけというのは少し難しいのではないか。前回もこういった議論をしていただいたと思う。
また、有効な実施手段を考えるべきであるというご指摘であるが、これから重点領域を決定して、具体的にどういうふうに進めるかというのはこの一つ後の段階の議論である。これも皆様方からこれからいろいろと検討いただく必要があろうかと思われるが、今のこの重点領域の決定の段階でそれを書き込むというのには時間が足りないのではないかという感じがする。
こういったことについても何かご意見があればお伺いしたい。
○委員 場違いな意見であるかもしれないので、早目に申し上げようと思う。
この報告書に盛り込んでいただきたいとか、そういうことでもないが、私は本当にずぶの素人であり、その立場から参加するようにというお申し出をいただき、いかに私自身がわからないかということを確認するために出させていただいたようなものである。ただ、本当に私のような人間の周辺を見ても、こうした情報化というものはひしひしと迫ってきており、私はこういう情報化から逃げ切った一生を送りたいと思っていたが、とうとうこの60代にして捕まってしまった。この間OECDの福祉の問題の会議に出たおり、7カ国からエキスパートが来ていたが、Eメールを持っていないのは私だけであった。ファクスはあるが。それで、もう嫌な顔をされてしまう。「おまえのところはEメールはないのか」と言われ、「別に、ファクスがよく機能しているからよろしい」と言ったのだが、考えてみれば、ほかの6人は一遍で済むのに今度また私にファクスを送り直すということがあるわけで、向こうとしては二度手間になる。ついに私の研究室にインターネットを入れて、この間WHOと厚生省を開いてみて、「あった」と。もう一つ、私がやっている地方分権推進委員会というのを呼び出してみたら、「ホームページは開いておりません」という答えが出てきて、非常におもしろかった。そう言えばもう数年前に木村尚三郎先生が、文系の方だけれど、「これからはテクノじじいにならなければならない」とおっしゃっていて、では私もと思い、今ここにいるわけである。
ところでここで議論したことは誰に出すのか。総理大臣か。
○主査 この情報科学技術委員会の親委員会に科学技術会議政策委員会というのがあるので、政策委員会に報告し、また政策委員会でいろいろと議論することになる。
○委員 私も、片仮名に弱いというか、英語がそんなにできる人ではないが、この片仮名の言葉はわからない。でもそれはそういう出し方であれば、これでよろしいのかなと思っている。
ただ、一つ申し上げたいことがある。やはり一般の私レベルの要するに情報技術音痴の人が見ると、「人にやさしい」などという言葉でうれしくなると思う。しかし、その言葉というのはかなり難物で、ここで拝見する限り、「人にやさしい」というのはどうやら2つの角度から考えていらっしゃるようである。一つ目は、こういう情報音痴にとっても、あらゆる人々にとって使いやすい技術を開発しなければいけないということと、二つ目は機械に人を合わせるのではなくて、人間に合わせていく。人間のいろいろな段階、いろいろな年齢、障害を含めたいろいろな人々、その人間をもっと研究していくという2点というふうに了解したけれど、本来「人にやさしい」ということにはもっと多様な意味があると思うので、どういうご議論があったのか、WG主査に承りたい。
それから、この文章の中には入れにくいのかなと思いながら、私はどこの会議へ行きましても男女平等・男女共同参画を唱えて、少しずつ実現している。この委員会も私一人、きょうは事務方に一人お出でいただいているが、一般のご意見の方も結果として男の方である。例えば小中学校の中でこうした技術教育、あるいはそういうハードをどう取り入れて教育するかなどということに関しても、やはり女教師と男教師ではかなりギャップがあるようで、そんな研究も現場レベルで少しはあるようである。私が東京都の行政とか、あるいは男女共同参画行政に少し携わって見ている限りにおいては、アクセスするという意味では、コンピュータ技術に関するジェンダーギャップがどこまであるのか、それは私はよくわからない。障害者や高齢者についてはお話があったが、やはり現状では圧倒的にジェンダーギャップがあると言える。オペレータ部分では女の人がものすごく働いているけれど、そういう情報アクセス、使いこなし方に関するジェンダーギャップについて、あらゆる人々と言うときに、男女両性とか、あるいは何かそういったことを不自然でなく入れていただけたらとてもありがたいし、その面へのご配慮をいただきたい。その点は何かご意見か、議論がでたのだろうか。私はWGに入れていただけるということだったのに、ちょうど授業の日と重なってしまい、そんなことはWGで申し上げるべきだったと思うが、ぜひ承りたい。
○WG主査 難しいご質問をちょうだいした。まず最初の「人にやさしい」という方である。委員のご理解どおり、まず2つあるが、いずれにしても、コンピュータそのものは、あるところ以上はとてもとても使いやすいとは言えないというところがあるので、そういうことを含め、モーダルというか、人間の五感をできるだけ使い、まず一般の人たちがある意味において意識しないで使えるというようなシステムを目指していく。今、例えばトースターだとか、電気釜だとか、洗濯機、車等にコンピュータが入っているが、とにかく使いにくいという意識を消してしまうというようなことが一方の極にあるが、それへ向けていこうということ。それから、システムをつくる、あるいは計算したい、絵をかきたいということでも、今のままだと、ある程度以上のことを知らないとできないということもあるので、そういう場合にも「人にやさしい」ということをそれなりに考えなければいけない。その他、「人にやさしい」というのは何かという議論も確かにフェース・トゥー・フェースのときにあったけれども、とにかくその2つは現時点でスタートしなければいけないということで取り上げたものである。
それから、2番目のジェンダーというか、そういうことを含めて考えてのことである。これは、文言としては具体的に出てきていないが、7ページ目の「ネットワーク社会の経済的・社会的影響に関する総合的研究」というところで、要するにそれなりにいろいろな問題が社会的な影響等を含めて出てくるであろうと。ここに書いてあるのは単に例であるので、そのようなことを含めて、倫理、経済等までも含めていろいろな問題が俯瞰的にここで検討されればよろしいのではないかということで考えていた。それと、先ほどの人材養成が重要ということもあるし、前回は教育というのもあったが、ここはその点を除くと、基本的には技術項目ということで取り上げてあるもので、そこに参加・参画されることに関しては、男女の差別ということは一切起きないということで進めているし、バリアフリー等も、年齢だけではなく、障害者の方々も含めて全部ということで、皆特段の区別なく差別なくということで、文言としては書いたつもりである。であるから、特に取り上げていないところでは区別していないとご理解いただきたい。
○委員 区別がないとか、差別をしていないというのは、それはそのとおりであるが、現状で既にこうした科学技術的な分野へのアクセスにジェンダーギャップ、バリアが存在するといえる。文部省と一緒になる前に文部省の悪口を言ってはと思うが、今の30歳ぐらい以上の方は、例えば中学校において女子は家庭科、男子は技術科という教育を受けている。女は機械に弱いというのは、もしかしたらDNAの問題なのかもしれないが、それ以上に育てられ方とか教育が圧倒的な問題。だから、これからは全然アクセスは平等だと思って、逆にそういうジェンダーギャップをこういうコンピュータの世界でなくしていくことはむしろ可能だと私は思っている。けれど、現にあるジェンダーのバリアも今まで歴史的、文化的に形成されてきたんだということへのご配慮を何かのときに考えていただけないか、そういう意味である。
○委員 今の「人にやさしい」とかバリアフリーという言葉と、DNAとおっしゃいたけれども、私は生命科学のゲノムの方で情報の技術を使っている者である。生命科学のゲノムプロジェクトというのはお聞きになっている方は多いと思うが、ゲノムプロジェクトは何もDNAの文字列を決めるというだけではなく、人間が情報システムであるという観点から、究極的には人間のシステムを理解するというプロジェクトだと位置づけている。例えば医学の分野においては、既にゲノムの情報を使って、この人にはこういう薬がいいとか、それぞれ個人に適応した治療法という可能性が開けてきているわけである。この情報の方についても同じだと思うが、今、出発点は常にある意味では上から来ている。技術開発があって、それを皆さんお使いくださいと。実はそれは逆の方からも来ることができ、この人はこういう人間のシステムを持っているのだから、そのシステムに合うような情報システムというのはどうなるべきだという、つまりそこにゲノムの情報を使ってその人に適したものを開発するという可能性も開けてくる。であるから、留意事項に「データベースを整備していくことが極めて重要である」と書いてあるが、今後そういう個人一人一人が持っている情報を蓄積することによって、そこから一般的なルールを探して、例えば女性と男性の違いというのは実はDNAの違いがあるのかもしれないので、そういうものを取り入れた情報システムの開発という位置づけができるのではないかと思う。
○主査 本質的な領域まで踏み込んだ今のお話であるけれども、樋口委員のご主張はよく理解できた。どこかでそういう配慮ができれば、考えさせていただきたいと思う。
○委員 人材の問題というのは、これは少なくとも戦後半世紀、日本の国がR&Dに対しての投資が少なかったということの積分値なので、急にはいかないと思うし、これは情報通信だけの問題ではない。であるから、別のところで検討していただくのがいいと思う。それと同じような意味であるけれども、この国家戦略目標というのは、やはりここの場でもある程度きちんとしておかなければならない。今回のものについては、これはもうこれでいいと思う。ただ、こういうところが納得できない。「プロジェクトを構成していく段階において、戦略的な要素を加味していく」、こんなことでいつもお茶を濁していてはだめだと思う。確かに、日本の場合はアメリカと違って、そういう戦略を打ち出してやっていくのが本当に得かどうかというのは難しい。国の力の問題とか、いろいろあり、例えばアメリカというのは、そういうきれいごとのビジョンを打ち出すだけではなく、スーパー 301にしろ、情報通信の暗号の問題にしろ、最近の情報収集衛星の問題でも、とにかく主張を通すようなことをやっている。それが通る中で、日本がそういうことをむき出しに打ち出してやっていくのが本当に得かどうかというためらいは確かにある。ただ、そういうのがないところが一つ日本の今までの欠点だったと思う。やはりそういうビジョンをある程度打ち出して、責任を持っていくということは必要である。ただ、それをどのような打ち出し方をして、どう実行していくかというのは、これは工夫は要ると思うが、今までのような形でそういうことを出さないで何とか実質的にやっていくというのではもう済まない時代になっていくだろう。我々はそれを今度できる総合科学技術会議などにも期待しているところであるけれども、そこを認識して、こういう場でそういうことがきちんとディスカッションできるような機会をつくっていく必要があるのではないか。
○主査 ただいま科学技術会議の方で、現在の科学技術基本計画は5カ年計画ということで策定されているが、次の段階の科学技術基本計画はどうあるべきかという検討を既に政策委員会の中で始めている。その中にはまさに一番大きな項目の一つとして、この国の戦略としての目標をどのように定めていくのか、その分野を明らかにして、さらに分野ごとの重点を決めていくという作業がこれから本格化していくと思うし、情報についてはまた場合によってはこの委員会でご検討いただくということもあろうかと思うが、今後の一つの重要な課題であると私どもは認識している。
○委員 バリアフリーのお話であるが、明確化のためにご質問したい。今ここに書かれているのは、障害者とか、高年齢者とか、若い人たち、そういうのが特に出されていると思う。そうでなくてもコンピュータシステム間でもともとシームレスでないという基本的な技術、複数のコンピュータがお互い自由に情報を伝達し合って動くという基本技術すら今はなかなかない事情であるけれども、そういうところよりも障害者とか高年齢というふうなところが非常に強調されているように見える。ここのバリアフリーというのは、そういう一般的な意味でのバリアフリーが含まれているのだろうかということが気になった点である。というのは、情報システムが入ってきたら、例えば貧富の差の問題で、情報システムを買うことのできる人は非常に多くの情報にアクセスできる。しかし、買うことのできない人は全然取り残されていって、そういう意味でのすごい情報ギャップが人々の中に生じるという可能性がある。だから、情報化というのがそういうものを拡大するのでは困るということがあろうかと思うし、バリアフリーという言葉をどの程度広くとらえるかということでその考え方が大分違うんじゃないかと気になったが、いかがか。
○主査 バリアフリーという言葉のとらえ方であるが、今は確かに高齢者とか、そういったむしろ情報弱者というか、そういう人たちに対するバリアをなくすという範囲でとらえられていると思うが、今、委員がおっしゃったように、もっとほかの例えば技術分野との間のバリアをどうするかという、それもバリアフリーのうちの重要な一要素ではないかというご指摘である。それはそのとおりであるが、いかがか。
○WG主査 極めて重要なものだとは思うが、今日は重点項目についてのみに絞らせていただくのがよろしいのではないかと考える。ただし、技術的につながるかどうかということは、おのずとこの中のどこかに吸収されると考えられる。
○委員 実は、私も情報を流す立場でいろいろ苦労しているが、いわゆるそれを流すラインというか、線の太さの問題がある。大体このプログラムは、全体に流す線はあるという前提でつくられているように感じる。例えば、きょうの新聞などを見ると、明らかにアメリカと日本の間の情報を流す線のコストの違いというのが明確に出ている。そういうことを考えると、本当に線の太さとか、例えば今後ライフラインなどを考えていくというときでも、ただいまの発言にもあったように、持てる者と持てない者の差、例えば1万円のラインがないと情報が利用できないというような環境条件で幾らライフラインを守るプログラムをつくっても、これは意味がない。そういうことから考えると、これは先生方皆さんどういうお考えがあってなのか、私もぜひお聞きしたい。例えば5年、10年ぐらいの間で考えて、日本の家庭内で利用できる線の太さというのが一体どのくらいのコストで可能なものか、そういうことが前提として考えられているかということをお伺いしたいと思う。
○WG主査 家庭内でのコストということに関しては極めて難しい面があるが、今おっしゃられたようなことで、例えばフラットレートというか、定額料金、固定料金でというのが1万円では高いとか 5,000円にしろとかいろいろもめている。そのもとになった郵政の次世代ネットワークの報告書の取りまとめに携わったので、その点を踏まえてお話しする。要するに幹線であるが、その幹線の速度は2005年で大体 100倍、2010年で 1,000倍というところでいくだろう。もう前倒しになるだろうと思うが。というのは、ギガビットネットワークというのが郵政で今始まっているし、アメリカでも100倍、1000倍のものがNGI 、ネクストジェネレーションインターネットというので始まっているので、その成果が出てくると、もう少し前倒しになってくると思う。
問題は、家庭との間のアクセスラインである。アメリカでラストワンマイルプロブレムと呼ばれているが、日本で抱える問題とは性格が違う。極端な話、アメリカの場合は1マイル四方に1本、光ファイバーを落とすという。したがってラストワンマイルというのはそういうものを含めてのことである。日本の場合は、各家庭まで持っていってしまおうというのが基本的にはある。例えば、私も現在住んでいるのは集合住宅、いわゆるマンションであるけれども、入り口から先が入らないということがあるし、各家庭の中でも、家庭内をよほど投資されて引かれないと、それが入らない。各家庭では何をそれにお使いになるかということもいろいろあり、いわゆるオンデマンドのテレビを見たいということになると、MPEG2という圧縮がかかっているものがあるが、それで大体6メガぐらいあればいいだろう。4人家族だとすると、4人が同時に全然違うものを見るということはないということだとか、いろいろなことがあり、オーダーが違うようなことが人により業界によって出てくる。要するに、家庭内で20〜30メガ使えればいいとか、いや 150〜 160メガは欲しいんだとか。ところが、そのアクセスラインをどうするかということが一番の問題である。
そこで、各家庭で幾ら出すかということは、その辺に各家庭の今の住環境に応じて各家庭がどの程度投資しなければいけないかということと、家庭内の配線をどのようにされるかということ、及びそこでの機器をどのようなもので楽しまれるか、あるいは使われるかということで、例えばインターネット冷蔵庫などというのが出てきているが、あれが在庫管理までしてくれるようになったときにどのようなことが起こるだろうか等の累積をすると、その辺にかかってくるコストがかなりの額になるだろうと思われる。ですから、それを今度はフラットレートで利用できるようにしないと、ますます負荷がかかるではないかという前哨戦が今行われるのではないかと私は思っている。コストの絶対額が幾らかということになると、これは経済学者にいろいろシミュレートしてはじいていただいたが、これは仮定でものすごく振れるので、確たる数字を申し上げるようなことは今現在は不可能であるけれども、おおよそ問題としてはそういうことである。したがって、フラットレートといいますか、固定料金制をどこの辺に落とすかというのが今申し上げたようなことで、差し当たってのプレッシャーをNTTが受けていらっしゃるという感じだと思っている。
○委員 ここでは「古典芸術をディジタル保存し利用する社会システム」となっているが、実は私どものようなところの場合は、ディジタル情報を古典だけでなくて、納本というか、固定化されたディジタル情報そのものを保存し利用するわけであるけれども、いわゆる保存というのが、広い意味で言えば、非常にすぐに変わっていくものであるから、それをリフレッシュするには非常にコストがかかるわけで、そういう意味でアメリカ等でも、電子情報のアーカイブというか、保存ということについてかなり大きな課題として進められているわけである。そのあたりについて、ここでは「ディジタル保存し利用する」ということになっているので、そういうことも幅広く含まれている意味でのディジタル保存なのか。ディジタル情報の保存というのがブックフォームの保存とは異なるから、そのあたりについてここで非常に短い期間に入ってきて、この10年で変わって使えないようになる。そういうところについてはどういうふうにここのところで理解すればいいのか。
○主査 これはかなり広い概念で整理されていると思うけれども、いかがか。
○WG主査 ある意味において、前回のこの委員会のときに委員が、このもとになった部会での報告を取りまとめるときに分科会ということでまとめたのでというお話もあったので、今回3ページの「留意すべき事項」で、1番目は、ソフトウェア開発は極めて重要であるということだが、2番目に「重要技術項目としてとりあげてはいないものの、各種技術が真に社会に役立つものとなっていくためには、コンテンツやデータベースを整備していくことが極めて重要であること」ということで、実は内容的には今ご指摘があったようなところ及び幾つかのところに散らばっている。しかし、コンテンツそのものをつくるということは、ある意味において技術項目とはまた別の大きな問題であろうと思う。要するに、我が国のいろいろな分野で、データベースというか、コンテンツに関しては、諸外国、特に欧米に負っているということがかなりあるので、そういうことを含めて、基本的に根底から考えなければいけない問題だと思っている。もっともこの技術項目のところにはあまりなじまないと言ってはおかしいが、難しいという点があるので、技術項目として取り上げられるのが散らばって入れてあるとご理解いただければと思う。
○主査 本日はこの後また重要な議題も控えているので、本件についてはそろそろ締めくくりたいと思うが、ほかに、ご意見はあるか。もしお許しいただけるのであれば、きょういただいたご意見を踏まえてさらに修文をさせていただき、これを当委員会の決定という形で処理し、政策委員会の方に私から報告をさせていただきたいと考える。なお、修正については、またWG主査とも相談しながら、私の方にご一任いただければ大変幸いである。
以上のような処理でよろしいか。
それでは、本件はそういうことにさせていただきたいと思う。
【産業競争力強化の観点からの追加検討について】
○主査 それでは、次の議題に入る。産業競争力強化の観点からの追加の検討結果についてである。
前回の本委員会において、経団連が産業競争力強化の観点から検討したという産学官共同プロジェクトの構想、ディジタル・ニューディール構想、これらについて経団連の方からご説明をいただいた。政府においても、産業競争力会議等の場で産業競争力強化のためのいろいろな議論がまさに行われている最中である。前回の委員会でも申し上げたが、私ども科学技術会議としても、今日の社会における重要な課題である産業競争力強化のための方策について、科学技術政策の観点から検討を加え、我が国としての方向性を指し示すということが重要であると考えている。こうした考えに基づいて、前回の委員会において産業競争力強化を踏まえた重点領域についての追加的な検討を重点領域検討WGの方に再度お願いしたところである。本日は、その検討結果が取りまとめられているので、WG主査からその内容についてご説明を承りたい。
(WG主査から資料3−4に基づき説明)
○主査 WG主査を初め、WGの各委員におかれましては、大変短時間の間に大変集中的な作業をしていただき、改めて御礼を申し上げたい。
この報告の中では、産業競争力の強化という観点から重点的に進めていくべき技術、これが3つの基本的な考え方のもとに整理されているということで、まさにこういう考え方あるいは技術の方向性を示すことが、この科学技術会議としての重要な役割ではないかと思う次第である。
また、この3つの考え方の一つ一つについても、単に産業界の短期的な要請にこたえるにとどまらず、情報科学技術政策の観点から産業競争力の強化を図るための視点がそれぞれ適切に盛り込まれているのではないかと考える次第であるが、WGでおつくりいただいたこの報告の内容について、ご議論をいただきたいと思う。
○委員 市場に対する非常に大きなバリアの一つが、通信コストが高いということである。津々浦々に安いインフラをきちんと整えることができる環境をそろえるということがこういったことに対するベースになるかと思うが、それを何らかの形でプッシュするというか、そういうものがやはり必要ではないか、何かそういうことも反映できないだろうかという気がする。
○主査 実は、経団連からの提案があった情報のディジタル・ニューディール計画というのは3本柱からできており、1本目の柱がこの研究開発に関連の深い分野のご指摘、あと2番目、3番目というのは、電子政府であるとか、かなり情報インフラの整備ということに主な焦点が当てられており、今、委員がおっしゃったのは、そちらの2つの柱でかなり政府としても取り組んでいかなくてはいけないという状況にあるように思う。
それで、ここで整理したのは、どちらかというと研究開発を進めなくてはいけない部分について、産業競争力会議の方でご議論いただいている構想と私どもの重点領域とを重ね合わせたもので、そういう意味でWG主査に伺いたいのは、私どもがまさに先ほど決めていただいた重点領域の何割ぐらいがこれでカバーされており、逆に競争力会議の方のニューディール計画の何割ぐらいのものがこれによってカバーされることになるのか、その重なりの部分の割合は、大ざっぱに言ってどんな程度なのか。
○WG主査 まず、この先導プログラムの重点領域と産業競争力会議のものとの割合とすると、およそ2割、3割。ラフな数字で恐縮だが、それぐらいのところだろうと思う。
○主査 経団連提案の第1の柱のみについてはどうか。
○WG主査 それに関しては、基本的にこの中に入ってくると思う。
○委員 私は経団連のものにもかかわったものだから、その関係から今回の話についてさせていただく。私もこのWGに今回入っている。
それで、私は、この3つに分けて類別するのは非常に重要なことだと思い、日本の今まで自分たちのレベルがどういう技術かわからない、そういうことを位置づけを世界のレベルできちんと分けて、だから自分たちはどうしていかなくてはいけないという意味で、今後あるパターンに分けて、多少グレーなところがあるけれども、やはりこういう認識は非常に大事なのではないか。
ただ、まだこれからきちんと議論していかなくてはいけないことは、この1、2、3というパターンがあるけれども、これらに対して産官学がどういう形の協力をするかということは、一通りではないということだろうと思う。これはこれから議論をきちんとしなくてはいけないが、例えば、1のパターンなどは、大学だとか国研とかというところがかなり中心となってやらなくてはいけないようなものと思うし、2というのは、恐らく企業の方がかなり中心となって、国のある種のサポートなりを受けて、何か発展できるようなものという感じもする。3については、これは一番難しいところで、既にある程度日本が強い。事業もやっている。こういうところに対して国がどういうところにまで関与した方がいいのか。アメリカでは、こういうところには関与しない方がいいといった意見もある。そういうところは産業自身にどんどんやらせた方がいいと。そのあたりをどういうやり方で行うかということをここで議論していくことが、これから大事な施策になるのではないかと思う。
○主査 おっしゃるとおりである。これはこの産業競争力の分野に限らず、先導プログラムでも同様に、どういう体制で進めるか、どのあたりに目標を定めてスタートするのか、そういったことは中間評価といった形で随時フォローしなくてはいけない問題でもあるけれども、そのあたりはやはり、どういうテーマなのか、そのテーマによって国の役割、企業の役割、大学の役割をそれぞれ明確にして進めなくてはならないし、それではどういう体制でやるかというのは、それぞれのテーマによって、それぞれ個性があって違ってくるだろうと思う。これからどの制度に乗せていくにせよ、具体的には、今、産業競争力会議の方で手当てしようとしている国の施策としての何らかの枠組みといったものが出てくると思うし、既存の制度としては、各省庁がそれぞれ進めているプロジェクトもあるだろうし、各省横断的あるいは産官学共同というようなことで進めているものについては、科学技術振興調整費というものがある。それからまた、やや個人的なレベルで進めているものには戦略基礎研究制度もあるわけで、そういったいろいろな制度を活用して進めていくことになるが、それぞれの段階できちんとした体制、目標といったものが決められていくということになろうかと思う。そういったものはやはりこの委員会できちんとフォローして評価をしていかなくてはいけないと考えいる。その体制の問題、より具体的な目標の定め方といったものは、この後の段階ということで作業が出てくると理解している。
○委員 R&Dというのは、広い意味でのナショナル・セキュリティーのためにやるんだと割り切って考えた方がいい。そういう意味でいうと、産業競争力の強化などというのは確かに非常に重要なことで、むしろある意味ではR&Dをやることの主要目標の一つだとも言えないことはない。ただ、実はこの前のものは総論だったからきれいごとである。私も手前勝手でないような具体的な提案をしたらどうかと言ったけれども、何でかというと、そういうきれいごとの下で一体産業が何を考えているのかというのは、非常によくわからないというか、問題なところがいっぱいあるわけである。恐らく、情報通信の分野はそういう部分は非常に少ないが、例えば宇宙とか航空の分野などは、国におんぶに抱っこでいこうという基本的な体質がある。であるから、そういうことを言われたのでは困るということがある。先ほどアメリカの話が出たけれども、アメリカの場合は全然メカニズムが違って、例えば、建前としては国は関与しないと言っているけれども、実はDODみたいなところは、R&Dと巨大なマーケットが直結しているところがいっぱいある。それで、実際にそこで力をつけた者が外へ打って出て戦うわけで、とにかく、それでは日本の産業が戦えないというのは、確かにそういう状況があるわけである。けれども、今、日本の中でどういうふうにやっていくか、このR&Dのコミュニティーの中でどういうふうにそういうことを認識してやっていくかという意味で、こういうふうに大きく3つに分けられてR&D側の考え方をきちんと出すというのは非常に重要だと僕は思う。そういうものをベースにして、産業側と対等にと言ったらおかしいけれど、お互いに納得できる形で我々も実際に具体的なものをどういうふうに打ち出していくかを考えていかないといけない。この3つの中身については、僕自身一つ一つ、これが妥当だとか言えるほどの見識はないけれども、この中身についてはこれからいろいろ検討していかないといけないけれども、こちらからこういう考え方を打ち出していくというのが非常に大事である。ただし、総論として産業化が大事だからというので、そのままうやむやになってどんどんそういう方向に引きずられていくのは、余り賛成できない。
○委員 産業競争力などというと、これから新しい企業が起こってくるというか、ベンチャー企業というか、業を起こすというようなことが非常に大切だと思う。どこかには当然あるんだと思うけれども、この報告書の3ページの中にはどこにもそのベンチャー企業とか業を起こすというワードがない。別にプロジェクトがそういうものではなくてもいいと思うけれども、何かこれをやるといろいろスピンオフができるというような技術をもちろん目指していると思うので、そういうことがどこかにあるといいなと思う。
○主査 あるいは、その点は留意事項として指摘するという方法もあろう。
○委員 私の立場が必ずしもベンチャーを代表しての意見ではないけれども、個人的な意見でそこにかかわっている立場で、今、委員が言われたこととかかわりながら、お話しさせていただきたい。
ここにまとめられている3つの大きな枠、あるいは先導プログラムの重点領域等については、基本的に先行ききちんと議論していき、それぞれを設定していくということではいいかもしれないが、基本的に私の理解で、単純な理解だけれども、科学というのは一つの仮説を立てて実証して一般化していくという、そのプロセスをもし経るのだとすれば、ここに掲げられている重点領域だとか、あるいは3つの領域についても、仮説であると思える。あるいは、逆に言うと、仮説でありながらもう既に社会的に認知されているものをピックアップしているとか、方向性が定まっているものを入れているという意味では、必ずしも仮説でないものも入っているのではないかと思う。いずれにしても、この委員会がどこへ方向性を持っていくかということはすごく大事だと思うけれども、ただ仮説なり方向性を立てるだけなのか、実証してそれを一般化まできちんとフォローしていくのか。ということは、ここの中で例えば総合シミュレーション技術開発と書いてあるが、技術のシミュレーションも大切だけれども、こうした計画そのものを長期にわたって実際に本当にその成果はどういうふうになっているのかというシミュレーションをするということを日本は余りしていない。ここに書かれていることは、多くのものはきっと実現されるだろう。ただ、実現されたのは、この提言によっているのか、あるいはもう社会的な要請が既に存在しているから自動的になっているのかということの見きわめというのは、非常に難しいのではないか。今まで委員会で、あるいはこのほかにもいろいろ公募を通じての基盤的な技術の募集というのは、何もこの委員会に限らず、いろいろな省庁でなされている。それでも、本当に産業を大きくし、GNPに対してはっきりと何かインパクトを与えるようなものが出てきたという話は聞いたことがない。科学の立場からすると、実証と一般化ということについての整理をずっと進めていくということが概念的に少し欠けているのではないかという意見である。
それと、そのためにはR&Dに対して明快な判断できるパラメータを設定すべきではないか。例えば、パテント関係などという形から見ると、一般に基本的な科学技術のR&Dでは新規性を必ず求められているが、かなり多くの場合は学術的な新規性に偏り過ぎているという意見がベンチャーの方からはある。やはり、産業的要素から見たノベルティーというか、新規性を整理する方法論が一つと、それからもう一つは、通常ステップ・オブ・インベンションと呼ばれるが、発明とか産業化の過程が明快に他の手法と異なっているということが明示できるということと、それからもう一つは、今、議論されているところのインダストリアル・アプリカビリティーという、産業競争力に直接作用するだけの具体的な内容を持っているか、そういうパラメータを明快に持ちながら何か専門の委員会なり、投資がなされるのであれば、それをずっとフォローしていくようなシステムをぜひつくっていただき、その中でいろいろな人が応用できるような手法を考えていただくと、委員会の目的だったり、ここの技術委員会が求めている、これまでにない方向性を明快に定めていくことができるのではないかと理解している。
○主査 先導プログラムにせよ、産業競争力強化のための枠組みにせよ、これからそういったものが立ち上がっていくわけで、この情報科学技術についてこの前の部会でいろいろご検討いただいた答申の中では、先導プログラムというのは、ニーズをまずくみ上げて、それで重点領域を定め、さらにそれを進めるための体制を構築した上で、最後に成果をどのように活用していくのか、そちらまで踏み込んだ戦略的なプログラムである。先導プログラムというのは一つのそういう仕組みだと理解しているわけであるが、産業競争力強化の枠組みの中でも当然今のような条件というのは非常に重要な視点であって、当委員会でも将来の検討項目の重要な一つのイシューになってくる。
それから、先ほど委員からベンチャー企業といったものへの配慮がどこかにあった方がいいのではないかというご指摘があったが、恐らくそれもどういう制度に乗って進められるテーマであるのかによるわけである。例えば戦略基礎研究制度の中で取り上げるようなテーマについてはかなりそういうニュアンスが出てくるのではないかと思う。
ほかにご意見はないか。
それでは、本日はいろいろとご意見も賜ることができた。これからもいろいろと重要な点についてはフォローしていかなくてはいけないことになるかと思うが、先程の検討事項については主査預かりとさせていただきたい。本日はこのWGからのご報告を当委員会として了承していただいたということで、さきの先導的プログラムの重点領域とあわせて私の方から政策委員会に報告し、政策委員会でまたご審議をしていただくということにしたいと思う。
【中長期的な検討事項について】
○主査 それでは、次の議題に移りたいと思う。中長期的な検討事項についてである。
本委員会における最初の検討事項として、本日までにこの重点領域の設定に関する議論を行ってきたけれども、当委員会の守備範囲はそれにとどまるものではないと思われる。もっといろいろな広範な議論をしていただく必要があろう。科学技術会議の情報科学技術に関する第25号答申を踏まえ、情報科学技術の基礎・基盤の強化に関する幅広いご議論、この基礎基盤の強化というのはこの答申の中で取り上げた一つの戦略として打ち出されている領域であるが、そういった分野についての幅広いご議論をいただくべき場として、今後進めていかなくてはいけないと考えている。次回以降の本委員会において何を議論すべきか。どういう中長期的な検討事項を取り上げていくか。もちろん本日お決めいただきた重点領域に沿った先導プログラムのフォローということもあるけれども、それ以外にもいろいろな論点について今後議論していかなくてはならないということで、次回以降どういうことを議論すべきかということについて、ここで皆様方から自由にご意見を拝聴させていただきたい。
前回までの委員会、あるいはWG等において、委員の皆様から既に多くののご提案があった。人材問題、あるいは特許の問題、いろいろな問題があると思うが、そうしたご提案をとりあえず簡単に整理していただいた資料がある。事務局の方で整理してあるので、事務局の方から最初にご説明願いたい。
(事務局より資料3−5に基づき説明)
○主査 ただいまご紹介いただいた論点のたたき台、あるいはこれから調査をしようという調査項目、調査の視点といったものについても、何かご意見があれば、お伺いしたい。後で説明のあった調査のスケジュールについて、いつごろこの委員会で調査結果の紹介をしていただけるか伺いたい。
○事務局 まだ具体的な委託契約とかという段階に入ってないので、近々スタートさせていただきたいという予定である。成果は、今の段階でいつごろかというのは明確に申し上げられないが、まとまらなくても、途中の段階での状況等も必要であれば、適宜ご報告したいと思っている。 ○主査 本日の段階では、これからしようとする調査に対し、さらにこういう点をつけ加えてはいかがかという観点からのご意見があれば伺いたい。その調査の結果をこの委員会の方にまたご報告いただければ、私どもの議論の基礎資料になると考えている。本年度の調査ということであれば、恐らく来年の2月とか3月ごろには大体まとまってくるだろうと思うが。
○委員 既に何人かの委員の方からご意見も出ていたようなのだが、あえて繰り返して、この委員会でこの後扱っていただきたい項目を一つお話ししたい。
この事務局の案ではどちらかというと政策の推進という部分にかかわることだと思うが、今回のこの重点領域の提案、決定、それを実際に実行していくということについて、きちんとフォローをする、実施状況をモニターする、あるいは評価をして、その結果をさらに重点領域の見直しにフィードバックをかける。委員の意見にもあるが、せっかくの答申がどこか棚の上に並んでいるのではなく、やはりきちんと実施に移されて、それが結果としてどうであったかというきちんとした評価の仕組みができるかということをぜひこの委員会で検討していただきたい。
○主査 この委員会が常設委員会として設置された趣旨に既にそれが入っており、先導プログラムを進めていく一つの仕組みとして、事前の評価、中間評価、事後の評価、それをどうまたフィードバックしていくのか、あるいは成果の活用という道を切り開いていくのか、そういったこともきちんとフォローするためにこの委員会が常設委員会ということでつくられたわけであるので、今ご指摘の点についてはきちんとフォローしていかなくてはいけない事項であると考えている。
○委員 今、委員がおっしゃったこととほぼ同じことであるが、やはり評価というのは非常に重要で、特に最近科学技術会議でも評価の重要性ということは言われている。実際いろいろな評価に立ち会ってみると、いろいろな点でなかなか難しいという意味で、評価というものをどういうふうにしたらいいかということを含めて、今後この委員会なり、適当な機会で考えていくことは大変重要じゃないかということを私も申し上げたい。
○委員 今のフォローアップのお二方のご意見に賛成であるが、一番最初に私は申し上げたが、この計画は非常にいいものができたのであるけれども、これをこの後各省庁と例えばすり合わせてという話もあり、その際にどこかに埋没してしまうということでは大変困る。国がどういう方向へいくんだというところについては、やっぱり総理大臣のリーダーシップというようなものでずっと引っ張っていってもらいたい。政策として入ってくるときに、技術という分野と、それが結果的に社会あるいは国民にとってどういうふうに変わっていくのかというところの絵が割合うまく書かれていると、政策にも乗りやすいのではないか。技術は技術だけというだけではなかなか、他の優先事項があるなどと言われてしまうので、できればそこの絵をもう一回わかりやすく書くということが必要なのではないかという感じがする。それが一つ。
それからもう一つは、非常に重要なのは産官学の連携のあり方、さっき委員が幾つかパターン分けして言われたけれども、これをきちんと分けていく必要かあると思う。また、先ほど委員が言われたベンチャーなるものについて、ベンチャーが何で出てくるのかといったときに、国がどこをサポートしているかというところがアメリカと日本とは違うのではないか。日本の場合には、確かに国立大学もあるし、そこに金を出していると言えば出しているのかもしれないが、もっと学校というか、教育、人材育成というか、そこにきちんとしたものを出すべき。今の場合には企業に入った人は企業の中でもう一回再教育しているのが実態なものだから、必ずしも企業の教育の力より、前の段階の大学あるいは大学院のところについて、もっと優先的な予算の立て方などをサポートして、むしろ新進気鋭の若い研究者が自分でスピンアウトして何か新しいことを起こそうという気風を醸成できるような仕組みをやる必要があるのではないか。以上2点を申し上げたい。
○主査 今、後からおっしゃった件は、恐らくこの後の委員会でご審議をいただく重要な論点の一つになってくるであろうと思う。
それから、最初にご指摘いただいた、これをどういうふうに効果的に実施というものに反映させられるのかということであるが、科学技術会議としては、政策委員会でご報告を受けとめ、あるいは政策委員会なりの決定とか、そういう形にすれば、その段階で政策委員会決定という形で一般に公表されることになる。それは各省庁に対して非常に大きなインパクトになるし、財政当局も含めて大きなインパクトを与えることができると期待しているが、それを受けて、後は行政当局の方でそれをどういうふうにしっかりと受けとめていただけるかという段階があろうかと思う。
○事務局 各省に協力を求めなければいけないけれども、こういう領域設定をしてプログラムをつくるという過程では、科学技術会議でこういう意思表示をしていただくわけであるから、これは政策委員会の場でそのようにエンドースしていただき、各省に呼びかける。それについては、既存のプログラムでどんなものがあるのか、それから新しく取り上げるものにどんなものがあるのか、これは各省でそれぞれレビューをしていただく必要もあると思うし、そうした上で今年度からどういう形で実施方取り組むかといったことになるわけである。その辺は、この委員会の場でも次回以降どういう格好で見えるようにさせていただくかといったことは私どもの宿題だと思っている。その過程で、この委員会もそういう意味では対外的にいろいろアピールさせていただく場だと思っているし、こういう作業自身が外から見えるようにすることが大事だと思っている。今おっしゃったような実施、取組みも、そういう過程を通じて外からも施策が見えるようになる。それから、その成果も我々自身が評価に供するような材料を用意させていただき、それで進捗状況についてもまた適宜ご判断いただくようなことをさせていただきたいと思う。今おっしゃったように、政策委員会という場も十分活用させていただきたいし、科学技術会議でこの指導、推進をやっていただくということが我々にとっても大事だと思っている。
○委員 調査報告をこれから頼まれるということで、こんなことも入れていただければと思っている。実はこういう報告書は、今まで私も幾つか関わり、ほかの省でもやっているけれども、今のこの調査だと、この日本の中を調べようとしている。それで、日本でこんな問題があるということになる。なかなかそういう問題は、問題があるということばかりが出て、では本当にどうしたらいいのかというところにつなげていくときに、いつもなかなか問題が解決しないという問題がある。
○主査 例えば、海外の技術水準の基礎調査というものは、この調査とは別個進められているというふうに理解してよいか。
○事務局 基本的には本年度実施する予定であるので、予算等といった問題もあるけれども、その中で行っていきたい。
○委員 あるいは欧米との比較ということについても、私は細かくは知らないが、アメリカのサイエンティストは、コンピュータサイエンスとか情報分野のサイエンスについては、年齢別のカリキュラムというものがかなり明快になっており、先生方が集まって、初等教育から中等、そして上に上がっていくまでにどんなものをどういうふうに研究するか、あるいは各項目ごとに非常にディテールにわたるまでカリキュラムの中身のディスカッションがされて、方向性が示されたというように伺っている。そういうことを調査の中に入れていただけないか。というのは、今の基礎研究を大学研究でされているのは、多くの場合、各先生方のモラルであるとか研究の中身に応じて学生が育てられているという形が多く、必ずしも共通パラメータではない。コンピュータサイエンス上のカリキュラムというのは最近ずっと出てきているわけだから、なかなかまとまりが明快ではないということで、逆に文部省では既にそういうことが整理されているのかということを実は私自身もお伺いしたい。
いずれにしても、ぜひとも欧米におけるコンピュータサイエンスのカリキュラムについて、年齢別に調査をしていただきたいと思っている。
○委員 今までの日本流の行政のあり方などではかなり無理があることを承知の上であえて述べるけれども、現在特に情報科学技術の分野のいろいろな施策を国として、あるいは産学官連携でやっていく上で障害になっているのは、やはり縦割りの問題である。それぞれの縦に割られたところのローカルオプティマイゼーションのコンペティションで済んだ時代から、そうではない時代になっているということはもうわかっていて、かつ今度は縦割りの中で少しグローバルに考えようとなると、それぞれがみんな金太郎あめになってしまう。同じようなことをやっていくことになる。例えば、ここで今これから調査などをいろいろやろうという話も、実は既にあちこちでやっているという状況の中で、それを繰り返していくことで本当に済むのかという問題が根本的なところにあると思う。
大きな流れとしては、行革の中で総合科学技術会議というような観点で、横をきちんと連携しながらそういうものを考えていこうということになると、まず一つ、この情報科学技術委員会というものの位置づけに、単に今の科学技術会議の中の組織だけにとどめない、何か新しい発想を持ち込めないか。つまり、非常に平たく言うと、ここに科学技術庁と文部省の方がお見えになっている。そちらの方の政策展開をする上で非常に重要という認識でご参加いただいていると思うが、例えばほかの省庁にも声をかけて、情報科学技術委員会というものを今までのコンセプトの中での科学技術会議の一つの委員会という位置づけというよりは、むしろ次に展開を図るための一つのパイロットモデルとして横断的に議論をする場というような働きかけをしながら、そういう制度の問題であるとか、予算の問題、人を育てる話などを考えられないか。例えば、ある省庁で、大学の教育というのはものすごく大事であるということで、アクレディテーションというものを文部省以外の省庁が働きかけるというような動きがあるとする。そのよしあしはいろいろ議論があると思うけれども、人を育て、技術をつくり、そしてそれを世の中に送り出してという大きな流れをとらえようという動きがだんだん出てきていると思う。そういう試みを何かこの場でできないだろうか。もちろん、現状が難しいことは百も承知ながら、これはあえて申し上げておかなければいけないと思ったことの一つである。
それからもう一つは、この委員会でそういうものを進める体制はどうかということで、これも前回申し上げたが、例えばWGに何回か参加させていただいた経験から、瞬間風速的には対応できるけれども、それをずっと続けていくことはなかなか難しいというのが実感である。事務局の方も非常によくやっておられる。しかし、お伺いするところによると3名ということで、いろいろと今、委員の方々からご指摘があった検討しなければならない課題というのはものすごくあるわけで、どれ一つたりともないがしろにできない中で、そこの作戦をどうするかというあたりをひとつぜひ考えてみなければいけないのではないかと申し上げたい。
○主査 まことに重要なご指摘で、おっしゃるとおりである。最初の縦割りをうまく配慮して、実質的にもっとオールジャパン的な議論ができるような場にしなくてはいけないというご指摘は、まことにそのとおりである。ただ、もともと事務局は文部省・科学技術庁ということになっているが、科学技術会議そのものは横断的に取り組むということで一貫している。この事務局も再来年2001年の1月からは内閣府に移るので、内閣府の内部部局が事務局ということになるから、事務局体制も本来の各省横断的な形になっていくだろう。
もう一つの方の作業の進め方、今回は重点領域のWGには短時間でハードスケジュールなことをお願いして、大変申しわけなく、本当に感謝の気持ちでいっぱいであるが、ああいう形でのWGのやり方というのはそうそう続くものではないというのは、ご指摘のとおりである。ただ、テーマによっては、やはりWGで突っ込んだ議論をしていただく方がより効率的、効果的に議論が進むということもあろうかと思う。今回の重点領域については、今回をもって一応作業は終了し、WGは解散ということにさせていただくが、今後、議題によっては、そういった分科会あるいはWGをまた適宜設置して取り組んでいただくということも考えていきたい。
ほかにご意見、ご質問等はあるか。
それでは、そろそろ時間であるので、いろいろとまたご意見もあろうかと思うが、今後、本委員会において取り上げた方がよろしいという中長期的な検討事項については、もし追加のご提案があれば、私のところでも結構だし、事務局の方でも結構なので、また後日お届けいただきたいと思う。
本日のご意見を踏まえ、私の方で次回以降の議題を整理し、次回の委員会の準備をさせていただきたい。
それから調査計画について、これも先ほどご指摘があった点を踏まえて、調査の中で可能な限り取り上げていただけるように措置をしていただきたい。
最後に、今後のスケジュールについて、事務局からご説明をお願いする。
○事務局 まず、きょうもご提起いただいた中長期的な検討事項について、きょうのご意見も踏まえてまた少し整理させていただき、その後にまたご議論いただきたい。
それから、これから概算要求があるので、そういった各省庁の要求内容についても整理して、この場でご報告させていただければと思う。
具体的な時期については、来月または9月といった時期を想定し、先生方のスケジュールを見て調整させていただきたいと思っている。
○主査 重点領域を決めていただいたし、また産業競争力の分野での取組みというものも議論されているので、予算要求の段階でそれがどういうふうに反映されたのかという点については、次の委員会でまたご報告し、ご意見をいただく機会を持ちたいと思う。
それでは、本日はこれで閉会とさせていただきたい。活発なご議論に感謝する。次回の具体的なことは、また事務局の方からご案内を差し上げたい。ほかになければ閉会とさせていただく。