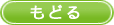議事録
- 日時 平成11年7月5日(月)10:00〜11:40
- 場所 通商産業省別館第939号会議室(通商産業省別館9階)
- 出席者
石塚主査、秋吉委員、礒山委員、伊藤委員、猪瀬委員、上野委員、宇津野委員、
(政策委員会) 廣田委員
戎崎委員、小柳委員、上林委員、後藤(敏)委員、清水委員、諏訪委員、
田中委員、土居委員、西村委員、林委員、樋口委員、畚野委員、古濱委員、
松田委員、米澤委員
(説明員) 永松経団連産業本部長
(事務局)(科学技術庁) 池田研究開発局長、中澤官房審議官(研究開発局担当)、
岩瀬情報科学技術推進室長
(文 部 省) 太田学術情報課長
- 議題
(1)重点領域の設定について
(2)その他
- 配付資料
資料2−1 科学技術会議政策委員会情報科学技術委員会(第1回)議事録
資料2−2 重点領域検討WG報告書
資料2−3 情報科学技術先導プログラムの重点領域の設定について(案)
資料2−4 「産学官共同プロジェクト」構想
資料2−5 今後のスケジュール(案)
- 議事概要
(1) 主査による開会の挨拶後、委員及び事務局の紹介があった。 (2) 重点領域検討WGにおける審議結果が報告され、所要の修正を図った上で公開し、一般の意見を募集することとした。 (3) 経団連から産学官共同プロジェクト構想について説明がなされた。これを受け、本委員会としても、こうした産業競争力強化の観点から、先導プログラムの実施のための追加的な検討を行うこととされ、重点領域検討WGに作業が指示された。 (4) 委員会の当面の進め方について意見交換が行われた。次回の委員会の日程は、7月16日を軸に調整することとされた。 (5) 主査から閉会の挨拶があった。
- 議事内容
(冒頭、主査より開会の挨拶)
(事務局より出席委員の紹介、配付資料の確認)
○主査 それでは、議事に入らせていただく。重点領域の設定についてであるが、これは前回の本委員会でお諮りしたとおり、科学技術会議第25号答申を受けた本委員会における第一段の取組みという位置づけであり、答申にある先導プログラムを実施するに当たって、重点的に取組むべき研究領域、すなわち重点領域を設定しようという作業である。
第1回の委員会で、本委員会のもとに重点領域検討ワーキンググループ(以下、「WG」という。)を設置することを決定させて頂いたが、その後、私の方から土居委員をWGの主査に、それから小柳委員、後藤敏委員、諏訪委員、中村委員、西村委員、林委員、古濱委員、松田委員、米澤委員の各先生方をWGの構成員に指名し、この1カ月の間に極めて精力的に集中したご審議を頂いた。
WGにおける審議の成果は、配付資料で後ほど紹介するように、本日の資料の中に資料2−2という形で取りまとめていただいている。本日はこの報告書についてWG主査からご説明をいただき、本委員会として検討してまいりたい。
なお、今後のスケジュールについては、後ほど改めてご相談申し上げるが、検討の結果、重点領域の案についてご了解を頂いた際には、本委員会として広く一般の国民の意見を募集し、適切な反映を図った上で正式に決定する運びとしたいと考えている。
(WG主査から報告書を説明)
○主査 短期間で大変立派な報告書を作成して頂き、WG主査をはじめ、WGにご参加いただいた委員の皆様に改めて御礼申し上げる。
この報告書を今説明頂き、とりあえず私なりの感想を申し上げると、まずこの3つの重点領域ないし目標は、情報科学技術についての今後の方向性を大変的確にとらえたものではないかと思う。
また、その領域の中でも技術項目を網羅的に並べるというのではなく、先端的で、かつ波及性の大きい技術項目にうまく重点化されているのではないかと思った次第である。冒頭にも申し上げたが、この報告書については、各委員のご意見、ご知見により必要な修正があれば修正を行い、本委員会として本日ご了解いただき、その案に対して、一般の意見を募集した上で、それを反映させたものを次回の委員会において正式にご決定いただくというスケジュールを考えている。
したがって、ここではこの報告書を本委員会として世に問うに当たって特段の問題がないかという観点からご検討を頂きたい。
ところで、先ほど、WG主査から一部修文のご説明があったが。
○委員 6頁の(4)についてであるが、そこに社会的インフラにかかわる文言を加えさせていただきたい。報告書の仕上げの段階で欠落してしまい、大変失礼した。
○委員 この3つの大きく分けられた枠組み、1番が通信に対応して、2番が情報に対応する。それから3番というのは、一番必要だけれども、現状とターゲットの間の距離が一番離れていて、非常に難しい。
それから、現在の検討のスケジュールの上というか、デッドラインの中でやるなら、これが非常に適切だと思うけれども、ただこれから将来、先にこういうのを検討していくとした場合に、やはり先ほど主査が言われたように、一般のニーズ、動きを的確に把握するということを努力していかないといけない。この報告はいわゆる開発側から、従来我々がやってきた手法に沿ってつくられたもので、そういう意味では、非常に適切だと思う。
この前も申し上げたが、昔は、我々が、いわゆる研究者、技術者の側から将来のトレンドを見て研究を行い、それが完成すれば社会のインフラとして受け入れられた時代であった。今は、世の中は非常に大きく変わっている。特に情報通信の世界は。とにかく的確な将来方向を予測するのが非常に難しい状況になっており、そういう意味で、裏側、反対側の視点は非常に重要。むしろ、そちらの方がこれから重要になっていくと思う。
ご承知のように、そういう意味で言うと、インフラの部分は決してそうではないけれども、実際に社会を動かすようなニーズの末端の部分では、いい技術が生き残るとは限らないような状況になってきている。みんな家電感覚で何でも使うようになり、電波であれば昔は免許を持っている者しか使えなかったのが、今はみんなその辺で電話でも何でも使っているし、計算機にしたってシステム全体が非常に変わってきたわけで、昔はエキスパートしか使わなかったのが、最近は誰でも必死になってやっている。これは今回の2番目の大きな枠組みの中にもかかわることだと思うけれども、そういうことを十分に理解して、努力していく必要がある。
情報通信は、来世紀は、社会・経済のシステムを揺るがすような大きなものになると言われるけれども、そこがちゃんと適用しないとそうはならない。我々は、かかる認識を強く持ってこれから検討していかないといけない。
○委員 今の先生のお話とかかわるのかもしれないが、この委員会の目的は、21世紀を拓く戦略的な政策が情報産業あるいは情報科学にかかわるという観点にあり、私が自分の立場から言わせていただくと、技術的な関係についてはとてもよくまとめられておると思うけれども、やはり21世紀に向けて切り拓いていくときの受益者は一体だれなのか、ということをもう少し明快に書くべきではないかと思う。戦略的なもの、必要性があるということは、必ずしもアメリカと全て比べていいかという問題はあるけれども、アメリカの情報産業における裾野が非常に広いということは、やはり受益者なり、開発当事者が非常に裾野が広いということにかかわっていると思う。ただ、ここに書かれている技術の基本的な多くのものは、受益者というのは大きな企業であったり、あるいは大きな研究機関であるというような形の比較的社会的インフラにかかわるところが非常に多く見受けられるように思われる。やはり次世代の情報産業とか情報科学技術におけるメインプレイヤーはどこになるのかという観点を少し広げて入れておく必要性があるのではないかと思っている。国際的にも、こうして国がかかわって資金を投じることに対して、かなり批判があるのも事実。やはり国際的な貢献とか、受益者であるいろいろな一般のユーザであるとか、いろいろな方々が参加できるような開発の部分を残していただきたい。
○主査 答申の中では、社会のニーズを明確に指向した情報科学技術の基礎・基盤を強化するのが戦略として重要という指摘があり、今回のこのWGの作業もまさに社会のニーズを把握した上で重点領域を決めていくという作業をしていただいたわけである。
ユーザ側のニーズをどういうふうに把握していったかという記述については、やや影に隠れて見えにくいということも事実であろうかと思うが、もともと答申がそういう精神だったわけである。総論の方にも少しその点は書いてあるけれども、49人の方々からのヒアリングの結果、ヒアリングの内容は、いろいろな方のニーズが現れていたと思うけれども、そういった調査の分析資料をもとに今回のこの重点領域といったものが絞り込まれてきたものと思う。ニーズと重点領域の関係について、何か補足説明はあるか。
○委員 今、主査の方からご説明いただいたとおりである。ニーズということになると、資料2−2の表紙にもあるように、分析の結果、多数の技術項目が出てくる。その多数の技術項目を個々に挙げていくということになるとばらばらになってしまい、同時に、戦略性という方向が国民に対してもわかりにくいということにもなるので、それを括ったというわけである。こういう3つの大きいものになったわけであるが、特段WGでやっているときには、大企業思考というようなことは一切なく、大・中・小、どこの規模によっても取りかかっていただけるような面を持っているものと理解している。
○主査 波及効果が大きいものという観点もあったわけであろうから、利用できる人はだれか、ニーズは何かといった場合には、必ずしも1つのニーズ、1つのある固定のユーザだけが利益を得るということでは必ずしもないのではないかと思う。
○委員 こういうときに、やはり動機になった米国のピータック(PITAC)と少し比較してみると、米国はやはり非常に具体的である。研究者を何名にしろ、予算はいくらでやれ、とはっきりしていて、それが、各テーマに対してどれがどれだけ大事かという重みづけにもなっているわけである。それから、今言われたユーザのことで、具体的な目標を、ラーニング、コマース、ワーク、ヘルスケア、エンバイラメントであるとか、そういういわゆるアプリケーションエリアをまず設定し、そこから問題点を出すという時間的な余裕がある。
もう1つは、政府が何をすべきかということが書いてある。産学官がということであるが、やはり政府が分担すべきものが書いてある。それから、基盤ソフトウェアが非常に重要であるというのが米国では一項目になっているのが、こちらでは全部に入って、各分野でソフトウェアを頑張れという書き方になっているという、その辺のちがいがあると思う。
やはりアメリカと日本の違いで、この前も話題になったけれども、アメリカはやはり需要があるところに人が集まるということで、大学などでも、例えばコンピュータが大事になれば、コンピュータに人が集まるわけである。日本はそれができない。であるから、大学教育が非常に固定化しているために人材養成ができない。ここに「人材養成」と書いてあるけれども、これは企業以上の問題で、大学でGNPに比例しただけの、例えば比例した形で各学科で人材養成をしているかというと、全くしていない。それは本質的な問題だと思う。
もう1つは、数年前アメリカでもコンピュータサイエンスの人の大きな就職難があった。それがなぜ解消したかというと、実は2000年問題であった。向こうで2000年問題が解決したらどうなるんだという話があるけれども、結局そこにいるソフトウェアの人間とか、そういう人間を次のところへ活用できる基盤が今そろっている。2000年問題で騒いで、すごいお金をとって、それで人材養成して基盤をつくった。結果論的には非常にうまいことやったという気がする。そこでまた差ができてしまっている。であるから、インターネット以外にソフトウェア技術者の基本的な差ができていて、何か提案しても社会システムが違う以上、実現の形が違うわけである。そのあたりを変えてほしい。変えてほしいと言っても変えられないだろうけれども、具体的にいつも何かやろうとしても、日本のシステムが最後は悪いということで終わってしまう。その辺で何かもう少し欲しいなという感じがする。
あと、先ほど著作権と言われたが、もう1つ、遠隔医療などの点で、法的な問題がいつも遅れて出てくる。それはもう少し早くやってほしいという気がする。アメリカとの比較ということで、意見を述べさせていただいた。
○主査 今は重点項目をつくろうという作業の段階。この段階を終わった後で、人材問題、あるいは知的所有権の問題等については、今後逐次取り上げていかなくてはいけないだろうと思っている。また、留意点がここに5つほどあったけれども、こういった形で、人材問題等、各重点技術事項に共通したような問題点が上がっているけれども、場合によっては、この留意事項を追加しなくてはいけないことがあるかと思う。
○委員 重要領域のまとめとしてはとてもすばらしいものだと思うけれども、アメリカに勝つというか、世界で生きていくという戦略としてこういうものをどう考えるのか。つまり、全部あらゆることをやっていけば、2番手をキープするのか、ある領域は1番手になって、そこのところだけは絶対勝つというふうな形で生きていくのか、それこそ戦略なのかもしれないが、そこに対する視点とか検討が見えない。それは明示的に見せるかどうかは別としても、まずは検討の段階ということでも何かあればいいのではという気がする。
○主査 幾つかここに重点領域、重要技術項目が並んでおり、それぞれに課題が今回明らかにされているけれども、それぞれいろいろな段階のものがあって、追いつくのを目指すものもあろうし、日本が得意とする分野についてさらにやることによって世界をリードできるような分野も中には含まれていると思う。そこを峻別していく必要があるのか、可能なのかということかと思う。
○委員 WGでもかなりの時間、今委員がおっしゃったようなことを、時間を割いて検討したが、結局強いところをより強くする、あるいは弱いところを育てる、あるいは両方やらなければいけない、また技術項目によれば当然そういうことで両方やらねばいけないような面も出てくる。あるいは、黙っていても企業の方でやっていただけるもの、そうではなくて、やはり国としてやらねばならないものというような、ケース・バイ・ケースに考えなねばならないことが多々あるのではないかということが出た。これをどうするということになったわけだが、だれがやる、あるいはどの水準に力点を置くかということは、差し当たっては、この中では誘導することなく、重要な点を取り上げた。それで、これはまず第一段階として出てきたものであって、そのうち、企業でやっていただけるものは企業でやる、国としてやらなければいけないものは国としてやるということ。ただ、全体として、何か欠けている面があって、ここはどうしても我が国がやっておかなきゃいけない、あるいはこちらの方はもっとより強くやらなければいけないというような作戦、あるいは戦略的な面は、この委員会の方でまたフォローしていただくのがよかろうということで、そういう面は特段出さずに取りまとめたという経過がある。
○委員 この3つのポイントは大変すばらしくでき上がっていると思ったが、どのぐらいの規模になるのかがわからない。例えば、金額で言うとどのぐらいの金額で、何人ぐらいの学者が何年ぐらいかけて取り組むと大体これが実現できるのか、その辺のところがわからないので、少し伺いたい。
○主査 一斉に全部やるのか、このうち幾つか重要なものについて絞ってやるのか、今のところは白紙の状態。どれくらいの財源がどういう形でどこに準備されるかということも、今のところは固まっていない。具体的にどれを取り上げてやるかということについても、この後実際問題としては、これをどういう形で実施に移すか、あるいは公募してその中から評価して選んでいくという、いかなる制度、財源を使うとしても、そういう段階があるのではないか。
委員もご承知のとおり、現在、別途官民共同プロジェクトというものも走ろうとしている。そうしたものについても相当な財源が準備されるということを期待するわけであるが、いろいろなシステムが走れば、そういったものを整合性を持って国の戦略として一定の方向に向けていかなければいけない。そういった過程で、どの程度の規模のもので何人ぐらいの研究者がそれに参加できて、どういう形で進むかということは固まってくると思う。
○委員 この中で、優先順位はやはりつけざるを得ないということになるのか。
○主査 実際上は、この重点領域を踏まえての公募の過程や、事前の評価を経て、重要なものが選び出されていく。そして、研究の規模もそういう段階で、適正なものにまとめていく、そういうことは次の作業として出てくることと思う。
○委員 まず、すばらしくまとめていただいてお1と思う。最初の印象は、まず先程秋吉委員が言われたことと全く同じこと。先ほど主査がご説明になったので、その方向でぜひお願いしたい。
各論で(1)から順に、個別の技術を書いてあるけれども、何々が重要であるというふうに言っていくと、ニーズがやはり見えてこない。こういう分野でこういうものが必要であると書いてもらって、それでこういう技術という説明をすれば、比較的ニーズとの関係がそれぞれの項目でわかりやすいのではないかと思う。
それから、細かいことで恐縮であるが、5ページの(1)のフレキシブル・ネットワーク技術を読むと、高速ネットワークを指向する技術という感じを受けるが、同じ通信速度の中でもできるだけ圧縮して、たくさんの情報を送る技術という点も重要でないか。特に、これから画像伝送が重要かと思うが、画像伝送で低速でも十分保証できる品質のものを送る技術開発が日本は非常に遅れているのではないかと感じている。であるから、この中の一定の通信速度や云々というところに入れられているのかもしれないが、その点が明確になるといいという印象をもつ。
それから、6ページの(5)であるが、先導的ネットワークアプリケーションということで、遠隔医療システムというのが出てくるが、教育の観点だと、例ばオンデマンドのような形で主体的な学習ができる遠隔学習システムというものがこれから非常に重要になってくると考えている。キーワードとして「遠隔医療」が入るのであれば、「遠隔学習システム」という言葉も欲しいと思う。
それから、7ページの(6)に、こういう形の総合的研究を入れていただいたことは、非常に感謝している。倫理問題ということで書いてあるが、やはり情報モラルという点は今後非常に大きな課題であり、情報モラル、倫理面での教育のあり方、そういったことも含めてこの中に記述があるとうれしいと感じている。
○主査 ただいまのご意見は適宜補充するということでよろしいかと思う。
○委員 この報告書は、情報科学技術分野の中でプッシュしていくのであれば、こことここは重要であろうという意味の整理だろうと思うが、情報科学技術というものは、ほかのいろいろな分野、医学、薬学、農学等にしましても、いろいろなところが関係あるかと思う。そういうところに対する関係がほかのものと違って共通的な基盤となるというか、関係が非常にあるというのは少し変わったところでないかと思う。そういう意味でのほかの分野に対する関係というか、ほかの技術を振興していく上で情報技術というのは基本的に重要である、たとえば数学みたいなものだ、というたぐいの話をどこかに入れておけば、ほかの分野の方々が見るときに、これの位置づけが少し加味していただけるという気がする。
○主査 他の技術分野への波及という、特に3本目の柱はそういう意味が大きいと思うけれども、そういったことを記述しておいた方がよいというご趣旨と思う。
それでは、特に今この時点でこれ以上のご意見がないようであるので、本日いただいたご意見については、必要な修正を加えるという前提で、本委員会としてこの重点領域案をとりあえず決定し、この後広く一般の意見を求めることにいたしたいと思うが、具体的な修文は私の方でWG主査と相談をして処理させていただくこととしたいと思うが、よろしいか。
○委員 1つだけ質問させて頂きたい。「一般に広く意見を求める」とおっしゃるが、その「一般」というのはどのような内容か。
○主査 その点については後ほど事務局から説明があると思うが、インターネットを通じて広く意見を聴取するという趣旨である。
それでは、この修文については、よろしいか。
ただいまご質問があったけれども、具体的な一般意見の公募の方法について、事務局から説明願いたい。
(事務局より資料2−3を説明)
○主査 ただいまの事務局説明に対して、何か質問、意見はあるか。
○委員 インターネットで公開という意味であるが、科学技術庁のホームページに載せるという意味か。
○主査 科学技術会議のホームページということである。
では、以上のように、この取りまとめの作業をさせていただきたいと思う。
○主査 次に、情報科学技術の推進という、この委員会での当面の取り組みについてお諮りいたしたいと思う。
先ほどのWG主査からのご説明の中でもご指摘があったように、先導プログラムの重点領域の設定については、こういうことで作業が進んでいるけれども、それをもとにして、具体的に先導プログラムを実施に移していくということが次の課題になってくる。その際、情報科学技術は社会の様々な問題と密接にかかわっており、先ほどもそういうお話があったが、本委員会としては、関連のある重要な動き、そういったものを十分に踏まえて検討を進めていく必要があろうかと思う。この委員会が発足した際にも、内外の諸情勢の変化、あるいは動き、そういったものに適切にすばやく対応していく、そのための常設委員会ということで設けられたわけである。
そこで、そのような観点から留意すべきこととして、政府が経済界と協議しつつ取り組んでいる産業競争力強化の問題がある。去る6月11日に政府の産業構造転換・雇用対策本部が決定した「緊急雇用対策及び産業競争力対策について」というのがあるが、その中に、技術開発の活性化の一環として、情報の分野を含め国家産業技術戦略というものを策定することが第1点、また、第2点として、官民共同プロジェクトを早急に推進することが決まっている。この点については、科学技術会議の政策委員会としても検討を行うことになっているが、差し当たり、この官民共同プロジェクトのうち、情報科学技術に関するものについては、本委員会において早急に検討をして、それについての考え方を政策委員会に伝えるということにしてはいかがかと考えている。
この点について、産業界の立場から補足していただくことが何かあればお願いしたい。
○委員 実は、今日は経団連の永松産業本部長にお越しいただいているが、今朝8時から産業競争力会議があって、そこで経団連側から1つの意見というか、構想をお話しており、その柱の中に情報関係が1つの柱として入っているので、できれば今日ご披露させていただいて、参考にしていただければと思う。産業界のニーズという形で、本案にどこまで織り込んでいただけるかわからないけれども、そういう検討の1つの材料にしていただければということで、若干お時間を頂戴したい。
○主査 本日は、経団連から永松産業本部長に説明員としてお越しいただいており、経団連から提案のあった構想について、ご説明を承りたいと思う。
(説明員より資料2−4を説明)
○主査 本件について質問、意見等はあるか。
○委員 私自身も、先ほど言ったように、例えば電電公社の枠組みがだんだん消えていっていることについて危機感を持っている。日本の政府が何かの形で補っていけるのかということについては、いろいろ考えていかないといかんと思う。日本とアメリカの違い、アメリカでいろいろな仕組みがある。例えば、アメリカの、国はもちろん、州であろうと、大きな企業であろうと、人が出張するときには飛行機はバイアメリカンというのはむき出しで言っている。そういうことを、日本が貿易の問題で言えないというのは、結局基本的には大きな貿易のインバランスがあるということ。だから、理屈のないスーパー301みたいなものがまかり通っているわけで、そういう環境の中でどうするかをこれから具体的に考える。その場合、やはり政府だけではなしに、企業の側からそういうこともちゃんと目配りした手前勝手でないようないい案を提案されるのが必要だと思う。
○委員 少し質問をさせていただきたいけれども、特に我々のところと関係のあるデジタル・ニューディール構想という部分であるが、名前がニューディールという意味で、非常に政策的な感じがする。それが反映されているのかもしれないが、3つ○があるけれども、最初の○の部分は多少違うと思うが、残りの2つの○は、基本的には技術的に難しいことではないわけで、実際には、それが資金的、制度的にやっていけるかどうかというところが基本的な問題という気がするけれども、そういう理解でよろしいか。
○説明員 2ページ以降に、その3分野について若干細かく書いてある。お配りしていないが、、この3つを説明したレポートでもう少し詳しく説明してあるが、今ご指摘のとおり、1番についてはかなり技術指向のいろいろなプロジェクトが書いてあるが、まさに2番目、3番目については、金さえつけばという分野もかなりある。
○主査 主として1番は、技術開発に非常に密接に関係がある分野、あと2番目、3番目は、どちらかというと基盤整備というか、インフラ整備ということで、予算が準備されればある程度は実現できる、しかしその中にも、あるいは若干技術開発を必要とし、より効率的にやっていくという部分があるかもしれないという、そういうことかと思う。
○委員 先ほどの説明の中で、今後の研究開発の主流は産業界が担っていくつもりだというお話があり、実際に、これまでも我が国全体の技術開発投資の中で、政府の負担は20%ぐらいで、産業界が80%を持ってくださったということで今日まできているわけで、これは世界中どの先進国に比べても大変に低い。したがって、我が国の産業界のご努力は高く評価するわけであるが、ただ先ほどのお話を伺い、今後とも市場原理に従ってやるというお話だが、この市場原理というのはなかなかくせ者ではないかと思う。というのは、バブルの最盛期でも、私にしばしば本当に有名な経済評論家の方とか、あるいは企業のトップの方から、研究開発なんかにお金を使っても確実にリターンがあるかどうかわからないが、不動産を買えばマネーマーケットで勝負するわけだから短期間に十分お金は入ってくるのであり、あなた方みたいな研究開発やっている人はもう時代遅れだ、と何度も何度も言われた。しかも、こういうふうにバブルがつぶれてなおさら、そういうご意見は消えてなくなるどころか強い。これからの世の中のマーケット、世界の市場原理というのは、いわゆるボーダーレスの時代の中において、為替とかありとあらゆる道具を使って、金融商品を開発し、それで儲けることであるということは相変わらず強くて、それがもし市場原理であるとすると、それに従っていくと、今までの80%を維持することは大変難しいだろうと考える。
そこには何か、悪く言えば投機志向の市場原理に、歯止めをかけるようなものがなければならないのではないか。もちろん、経団連の中にもいろいろの部会や委員会がおありになるから、産業技術を開発する分野の先生方は、皆さんやはりその分野で思い切って研究開発をしなければいけないとお思いになっているのかもしれませんが、我が国全体の経済人の、あるいはこれは日本の経済人のメンタル・ステイツというよりも、アメリカの見方の影響も大きいのかもしれないけれども、その辺を見ると、やはり単に経済原理に従ってやるから大丈夫だとおっしゃられると、少し心配になってくる。その経済原理の中に、今の中期、短期的なプロフィット追求ではない何かがあり得るのかどうか、その辺についてもしご意見が、議論がされておるとすれば伺わせていただければ大変安心できると思う。
○説明員 ここで「市場原理に従い」と書いてあるのは、まさにバブル期の反省に立ち、日本はやはり基本的には物づくりという世界でこれからも国際競争を行って、それに打ち勝っていくことしかないんではないかという基本的な認識から出てきている言葉である。そういうまさに製造業がこれから頑張らなければ日本はだめだと、そんな意味合いも込めて、私どもも産業競争力会議の設置を提唱した次第である。
したがって、ここに書いてある市場原理は、あくまで競争を通じたそういった研究開発競争という意味以上のものではない。
それから、先ほど少し説明を落としてしまったが、基本的には、今申し上げましたように民間企業が研究開発を主導していくということであるけれども、ご案内のとおり、非常に技術開発のスピードが早まっている。あるいは研究開発のコストも非常に大きくなっている。リスクもたくさんあるし、民間だけではできない分野も多々ある。そういう意味で、一番下の枠であるけれども、産業技術政策の推進ということで、科学技術データ等知的基盤整備と、そういったことについてはぜひ国、大学が中心になって進めていただきたい。こういった共通の基盤については、まさに国なりそういった公的分野が大いに頑張っていただかなければ、民間企業だけではなかなか取り組めないと、そういうことも併せ書いてあり、そういう意味でも、すべて産学官共同でやるということではないけれども、ある分野では官、ある分野では民、ある分野では学と、それぞれがそういった分野について共同で、それぞれの役割分担を明確にしながらやっていきたいと、こういう趣旨である。
○主査 今のような考え方は、まさに答申の中にもそのようにうたわれているのであり、産業界が非常に大きな役割を果たすであろうけれども、市場原理メカニズムにのっとった産業界だけの努力ではやはり足りない部分があるかもしれないという意識で、産業界と国との役割分担ということが答申の中にうたってあるわけである。今の話を伺って、そのあたりはかなりはっきりしたと思う。
○委員 この構想と、我々の、重点領域WGでの報告を比べてみると、ほぼ問題意識は同じで方向性は、表現は違うけれども、同じ方向に向かっているということがわかって大変心強く思うけれども、1つだけかなり違う点がある。それは教育のことである。
この重点領域の方には教育のことが散りばめてはあるけれども、重点項目としてはどこにも挙がっていない形になっていて、やはりもう少し教育ということはもう少し踏み込んでもよいのではないかという印象をもった。
○主査 どこかに教育については触れられていたような気もするが。
○委員 総論のまず留意すべき事項、3ページであるが、その3番目で研究プロジェクトの中で優れた人材を適切に育成することということ、及び、中でも人を育てることは重要であるというふうなことは、散りばめては書いてある。特段、何か項目立てでやってあるわけではないが。
○主査 今のご指摘は、そういう人材育成の問題なのであるか、あるいは教育に関連する情報システムの研究開発、技術開発的なことをおっしゃったのか、どちらであるか。
○委員 このような書き方だと、こういう技術を推進していくための技術者育成のように読めてしまう。そうではなくて、小学校、中学校で、我々の子供を教えている現場におけるアプリケーションをもう少し考えるべきではないかという趣旨である。
○委員 以前の部会のころから教育に関しては重要と常々申し上げてきた者といたしましても、極めて重要なことだと思うが、それをこの重点領域として、どこかで具体的に我々としても何か言及しておく必要があろうか。
○主査 ニーズとしてはかなり大きなニーズの分野ではあるけれども、ニーズを志向した重点領域という整理をするのではあれば、どこかでそういったものについては読み取れるような部分があった方がいいのかもしれない。
○委員 では、検討させていただいて、主査とご相談させていただくことでいかがか。極めて重要なこととは思う。
○主査 そのようにしたい。
○委員 先ほど何も申し上げなかったが、もし余地があるのであれば、経団連の方もおっしゃいました最初のページの一番下の科学技術データ等知的基盤整備、これも基盤をただデータを集めて整理するためでなく、そこに相当の研究開発の努力をして、いわゆるコンテンツというものを充実していくことは非常に重要だと思う。
実は、この委員会ができる前の情報科学技術部会でも、分科会を担当させていただき、そこでは専らこのコンテンツとその流通の問題を扱ってきたわけである。この報告書の中にほとんどその項目がないというのは、これは少し寂しいという気もする。
それから、コンテンツ、アプリケーション、ネットワークと言っている中で、ネットワークとアプリケーションだけが扱われているのもどうかと思う。今後、これをさらに進めていかれる上でつけ加えていただいても結構であるが、この報告書は、そういう意味で若干不十分かという感じもする。
教育の問題は別として、この問題は十分議論したことであるので、もしチャンスがあれば、入れていただければ大変ありがたい。
○委員 ただいまのご指摘は、書き方が多少弱くというか、量的にも少ないので、そういう意味では失礼した。例えば先端的計算の中では、いわゆるハイエンドコンピューティング&コンピュテーションであって、コンピュテーショナルサイエンスだけではなくて、そういう多量なデータに基づくようなことも含んでいるつもりであり、13ページの(4)のアーキテクチャなどのところで、結局データ入出力技術だとか管理技術だとかというようなところは入れておいたつもりであるが、少し説明不足というか、量的にも抜けているところがあろうかとも思う。
あるいは6ページのネットワークのところで、先導的ネットワークアプリケーションなども、一番最後のところ、例示としてのデジタル保存利用する社会システム等のということでこういうものを挙げているけれども、これは種々雑多のコンテンツをというようなことの1つの例だというようなつもりで取り上げている。また、7ページのところでもデジタルコンテンツの問題、著作権等の問題も含めてということで散らばって、少しずつ取り上げているというようなことで、ある意味においてはまだ書き足りないというようなことがあろうかと思う。その点も多少、まだ考えさせていただければと思う。よろしいか。
○委員 決してご無理にお願いしているわけではない。今、教育の話が出てきまして、やらなきゃいけないことはほかにもたくさんある。その中の1つに、特にこの委員会ができる前の情報科学技術部会で審議をかなり時間をかけ、大勢の方にご迷惑をかけてできたわけであるので、それは反映していただきたい。
○主査 今のご趣旨をなるべく反映できるよう、またWG主査と相談し、できるだけの努力をしてみたいと思う。
経団連のご説明について、ほかに何か質問があるか。
○委員 経団連の産業技術委員会が6月に提言、戦略的な産業技術政策の確立に向けてフォローアップ報告書というのを出されていて、拝見いたしたが、それと本日ご説明いただいたものとの関係は何かあるか。
○説明員 十数業界から今年ヒアリングを行い、今ご紹介いただきましたようにフォローアップ報告という形でまとめてあるが、それをいろいろ勉強しながら、ある意味ではこれを選択していったという形になっている。ただ、厳密に議論に議論を重ねて絞り込んだということでもない。
○委員 ボーダーレス社会において、幾つかの経団連なり、そこでかかわっている企業グループのところというのは、既に市場原理の中という意味で言うと、他の外国の企業と既に組み合わせをたくさん複雑にされている。情報産業においては、当然ながらマーケットは日本よりもアメリカとか世界の方が広いわけで、そうした研究が片やあって、それは市場原理に基づいているから、資本も人もいっぱい入っていると思うけれども、それとは別個にこうした、どちらかというとオールジャパンみたいな形のものの区分けをどうしていくのか。そこのところは、逆に国際的な研究みたいなものがこちらに反映されていくことがあり得るのではないか。それとも、プロジェクトは別に立ててやっていき、市場原理の中でおいしいプログラムは、個々の企業は外でやって、日本の中で産業競争力に転換できるという部分については、なかなか実際のマーケットオリエンティッドだったり、市場原理にそのまま反映できるようなものがなかなか反映されないのではという疑問はあると思う。そのあたりはどうなのか。
○説明員 私ども昨年産業問題委員会というのを設置して、そこが中心になり、いわゆる競争力の問題を議論しているが、実はそこでの問題意識は、とりわけ85年以降の円高局面の中で大変な海外投資が行われたわけであるが、そういった海外投資の中には、単に市場原理といえば市場原理の結果ではあろうとは思うけれども、今日考えれば、無理して海外に行かなくても済んだ産業もあるのではないかということ。為替レートの問題を含め、何とか魅力ある日本をつくりたい、その1つがやはり産業の競争力であり、あるいは高コスト構造の是正だと、そういう問題意識の中で、繰り返しになるが、魅力ある国づくりをしたいというのが基本である。そういう中で、市場原理の中でいろいろなアライアンスを組んでいくというものは仕方ないということであるが、同時に魅力ある国づくりということによって、外資も日本にどんどん迎え入れるということも視野に入れている。
○主査 経団連の提言についてのご説明を伺ってまいったが、今後、先導プログラムを進めていく上で、ただいま経団連の方からご説明のあった官民共同プログラムに対するご提案、これをこの先導プログラムにどのように反映させていくのか、特に科学技術会議の主導のもとに産学官連携を進めるといったもの、そういった面に対する留意点というか、そういったことについて、先ほど申し上げましたとおりこの委員会から政策委員会に考え方をご報告したいと考えている。産業界が提案された共同プロジェクト、特にデジタル・ニューディール構想というのは技術開発に非常に関係が深いわけであるが、一方私どもが本日議論した先導プログラムも、いろいろな重点領域を示す作業を進めており、私どもの考え方をどのように反映させていったらいいのかという点についてのご意見があれば承りたい。
この時点で特にないようであれば、ただいまのいろいろな皆様方のご発言を踏まえて、次回の委員会において、本委員会としてこの官民共同プロジェクトについての考え方をある程度まとめたい。そのための作業の進め方であるが、やはりWGで重点領域について大変精力的にご審議をいただいた際のいろいろなノウハウの蓄積がたくさんあるのではないかと思う。そういったこととの関連を十分踏まえながら1つの考え方を出していく作業が必要ではないかと考える。
そこで、できれば、大変ご多忙な日程を消化していただいたわけであり、大変心苦しいのであるけれども、再度WG主査に中心になっていただき、WGの先生方のご意見をまず整理していただき、そしてその考え方について1つの案を次回の本委員会までにまとめて頂けないか。WG主査、いかがか。
○委員 引き受けさせていただく。
○主査 よろしくお願い申し上げる。
本委員会においては、この先導プログラムを速やかに実施に移すための重点領域の設定、先導プログラムにおいて産業競争力強化への取組みがどのようになされるべきかといったようなことについて、さらに検討していく必要があるわけであるが、こういった論点については、次回の委員会で一応一区切りがつくのではないかと考える。
そこで、次々回以降の委員会では、情報科学技術の推進のため、むしろ中長期的な課題についてもいろいろとご検討をいただくことができると考えている。今後、どういうような点について本委員会が取り組むべきか、もし本日ご意見を承ることができれば、それを伺った上で今後の審議の進め方について、次回の委員会でご相談をしたいと思う。当面のスケジュールについて案を用意してあるので、事務局からご説明願う。
(事務局より資料2−5に基づき説明)
○主査 情報科学技術委員会が総合科学技術会議になった場合にどういう組織になるのか、それは総合科学技術会議の方でご議論があると思うけれども、私の希望としては、やはり常設委員会というものが引き続き設置される必要があるのではないかと考えている。
それまでの間、スタッフ機能をどうするか、今も各省庁からのいろいろな資料の提供とか、基礎資料についての分析等については、直接の事務局である文部省、科技庁に限らず、各省からいろいろなインプットを得て進めるような体制にはなっているけれども、総合科学技術会議に至るまでの間、その橋渡し的な時期、あと1年半位あるが、その間においても何かさらに具体的にできることがあれば検討をしていく必要があると考えている。そういったことについてもまたご議論をいただきたいと思う。
○委員 今、言われたことに大変共感するが、先ほどの経団連の話の中でも、最後の方に科学技術政策の立案・推進体制の強化ということが5つの○の中の最初に書かれて、資料2−4の1ページであるけれども、こういうことは日本の中で、特に我々であると情報科学技術という分野の中でもう少し体制的に確立すると、これからの発展が希望の持てるものになるのではないかという気がする。
○主査 それでは、次の委員会は一月後ではなくて、かなり近い機会にもう一度開くことになろうかと思う。本日は大変活発なご意見を賜り感謝する。本日の議論をもとにして、この重点領域の案を一般に公開し、そして次回の委員会で重点領域の決定をさせていただきたい。
WGには、またお願いをして大変心苦しいが、そういった資料も踏まえて次回を開催させていただきたい。
次回の日程については、現時点では、7月16日金曜日の午前が最有力と考えている。
それでは、これをもって、本日第2回の委員会を閉会する。以 上