- 現在位置
- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 科学技術・学術審議会 > 資源調査分科会 > 光資源を活用し、創造する科学技術の振興-持続可能な「光の世紀」に向けて- > 第3章 健康なくらしに寄与する光 1 照明光に対するヒトの適応能―生理人類学からのアプローチ―
第3章 健康なくらしに寄与する光 1 照明光に対するヒトの適応能―生理人類学からのアプローチ―
九州大学大学院芸術工学研究院長 安河内 朗
1-1 生理人類学的背景
生理人類学は、主として現代の科学技術文明によって創り出された生活環境に住む人間を対象に、その環境への適応能を研究する分野である。中でも特に注目するのは、人類の進化史において適応の対象となる環境の違いである。現代のような文明化のきっかけをつくった農業の発明は今から約一万年前と考えられる。人類史を500万年とするとその内99.8パーセント以上は狩猟採集時代の生活環境が占めることになる。生物は一般に長い年月をかけて環境にうまく適応できたものだけが生き残ってきた。私たち人類も種々の環境要因に適応してきたはずである。そしてその適応の対象となった環境は、まさに狩猟採集時代の環境といえる。すなわち、私たちは生物学的には氷河時代のネアンデルタール人とほとんど同じ身体と機能をもって現代に至ったといえる。一方で、残り0.2パーセントのうちに生活環境をアッという間に激変させ、文化的適応に強く依存しながらこれが当然のように生きている現代人の姿がある。人類に備わった高い知性は便利なモノを次々に生み出し、その結果私たちの身体が馴染んできた環境とは全く異なる環境を自ら造り出すことになった。このように、本来狩猟採集の生活環境に馴染んだはずの私たちの身体は、全く異なる人工環境下でときにからだが悲鳴をあげていることにも気づかずに余分な緊張を抱えたまま生活している可能性がある。私たちが、「脳の欲求に身体が無理なくついてゆけるか」を評価するために、意識にのぼらない”余分な緊張”に注目する理由がここにある(図1)。
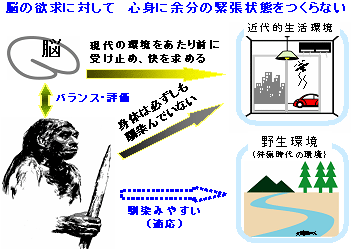
図1 脳と身体反応のバランス
以上のような背景を踏まえて、ここでは科学技術が創り出した照明光を取り上げ、後述のように人工光に対するヒトの適応能という観点から照明の生体への非視覚的影響をみることにする。
1-2 余分な緊張の評価法
“余分な緊張“という考え方自体がこれまでなかったものだから、その生理的評価方法として確立されたものはない。しかしながら、これまでの一般的に知られている生理反応からいくつかのアプローチを試みることができる。以下に3つの方法を紹介する。
(1)中枢神経系からのアプローチ
大脳新皮質の全体的な覚醒水準と作業効率との間には理論的に逆U字の関係にあることが知られている。覚醒水準が低い状態から上昇するにつれて作業効率は増大する。しかしある水準を超えると作業効率は下降してくる(図2)。この作業効率が下降する相は、脳の覚醒が強く、イライラしたり怒っているときなど興奮した状態に相当する。この相の初期の部分は、意識下の余分な緊張が生じている状態と見なすことができる。
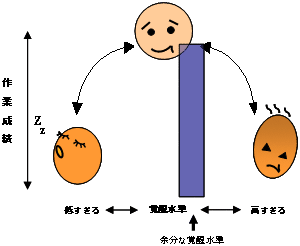
図2 脳の覚醒水準と作業成績の逆U字関係
脳波の事象関連電位の一つである随伴性陰性変動(CNV:Contingent Negative Variations)は、この逆U字関係をみる良い手法のひとつである。CNVの短期成分は脳の覚醒水準を反映し、CNVを測定する中で反応時間も同時に得られる。例えば、蛍光灯の電球色と昼光色のそれぞれの光に曝露しているときのCNVを測定した実験(岩切ら、1997)では、昼光色条件のCNV短期成分は電球色条件より統計的に有意に大きく覚醒水準が高くなっていると考えられた。このとき同時に測定された反応時間は覚醒水準の高い昼光色条件の方が有意に遅くなり、覚醒水準における余分の緊張が存在すると考えられた(図3)。
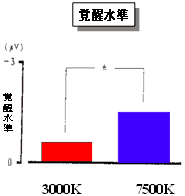
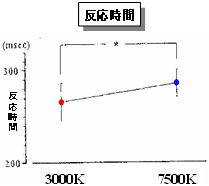
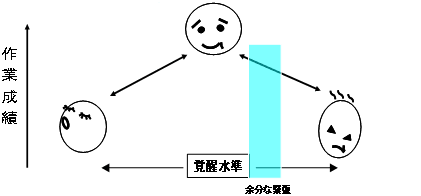
図3 脳の覚醒水準にみられる余分な緊張の存在
(2)自律神経系からのアプローチ
自律神経系は臓器の諸機能を交感神経及び副交感神経の二つの拮抗する活動によって制御している。心拍数を例にとると、副交感神経活動が交感神経活動に対して優位に働けば心拍数は減少し、逆に交感神経活動が優位なときは増大する。通常安静時の心拍数は副交換神経活動の増減によって制御されているが、精神的もしくは身体的ストレスが生じた場合には交感神経活動が優位となり心拍数は増大する。心拍数を制御する副交感神経と交感神経の両活動のバランスにおいて、精神的もしくは身体的ストレスを感じない状態下で交感神経活動が優位になる初期の段階は自律神経活動における余分な緊張とみなすことができる(図4)。
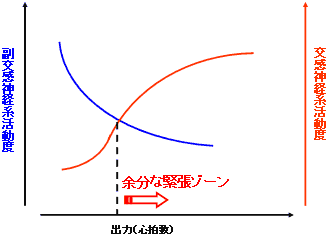
図4 自律神経系活動度からみた評価
夜のリビングを想定した蛍光灯照明光の実験(Tsutsumi et al.,2002)では、昼光色曝露条件では、昼白色、電球色条件よりも心拍変動から求められた交感神経活動指標は有意に高くなることが認められ、夜の照明光としての昼光色は余分な緊張をもたらすことが示唆されている。
(3)生体リズム(biological rhythms)からのアプローチ
体温をはじめとする自律神経機能、ホルモン分泌、免疫反応など多くの生理反応には約24時間周期のいわゆる概日リズム(circadian rhythms)が存在する。光の明暗は概日リズムの主たる同調因子になるため、照明光の生体への影響をみるにあたって、概日リズムは適した評価法になる。この概日リズムはその周期と振幅によって特徴づけられる。したがって、照明の条件によって振幅やリズムの位相(あるいは周期のピーク時間)が通常の値からどの程度影響を受けるかが評価されることになる(図5)。
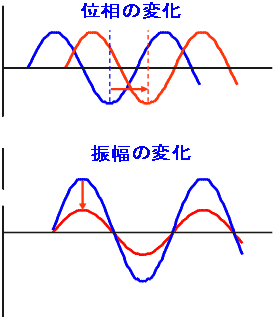
図5 生体リズムの位相と振幅からみた評価
夜の寝室の蛍光灯照明を評価した実験(Tsutsumi et al.,2002)では、就寝の前まで曝露されていた光が昼白色もしくは昼光色のとき、睡眠中の直腸温(深部体温)の低下勾配が抑制され、直腸温の概日リズムの振幅が小さくなる(図6)という点から昼光色は余分の緊張を生じさせることが示唆された。
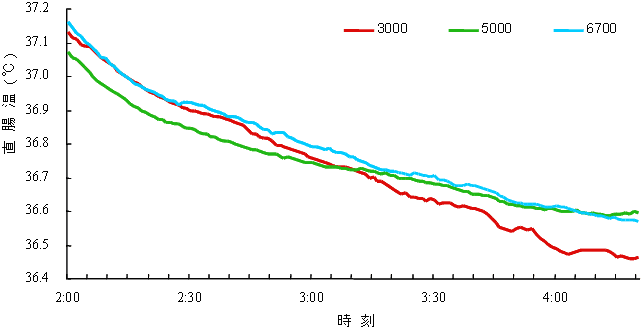
図6 消灯前の色温度が睡眠前半期の直腸温(深部体温)に及ぼす影響
1-3 生体に影響する光の物理的条件
どのような光が生体に影響するかその光の条件を知る必要がある。
光は波長が380~780nmの範囲の電磁波で構成され、自然光(太陽光)の強さや波長の構成は一日の時間帯や季節によって変化する。したがって、光の照度や分光分布が生体の機能に影響する主たる光の要素になると考えられる。その他、光曝露の時刻、曝露時間、あるいは曝露の時刻と時間を組み合わせたパターンなども重要な光刺激の要素となる。
人工照明について考えると、自然光に比べてはるかに照度は低く、一般的な蛍光灯や白熱灯の分光分布も全く異なる構成となっている。さらに照明光への曝露開始時刻やその時間やパターンも不定期であることから、人工照明光の生体への影響には注目する必要がある。特に蛍光灯の分光分布については赤、緑、青の各波長帯で強いエネルギーをもつ三波長形になっており、赤と青のエネルギーの相対比によって青っぽい光を放つ昼光色、白っぽい昼白色、赤っぽい電球色など、種々の相関色温度をもつ光源が一般に市販されていることから、色温度の生体への影響にも注目しなければならない。
1-4 光の非視覚的影響の予測
外界からの光刺激は網膜の光受容器を介して信号化され脳内に入ったのち、大きく二つの経路を通る;ひとつは外側膝状体を通って視覚野へいき視覚的イメージ化をはかる経路と、ひとつは網膜視床下部経路を経由して松果体に達する非視覚的経路である。図7は、網膜から松果体に至るまでの光情報の伝達経路を示す。網膜に到達した光は、網膜視床下部経路を経由して視交差上核(SCN)、室傍核(PVN)を通り、そこから内側前脳束(MFB)、脳幹網様体(RF)を抜けていったん脳の外に出た後に上頸部交感神経節(SCG)を経て再び脳内に入り松果体へ達する(Klein et.al.,1983)。この一連の経路の中で、視交差上核は生体リズムに、室傍核は心拍数や血圧などの循環系を制御する自律神経系、及びコルチゾール等を分泌する視床下部-下垂体―副腎皮質系に、内側前脳束は快や不快に関連する情動に、脳幹網様体は大脳新皮質の全体的な覚醒水準にそれぞれ関連することが知られている。また覚醒水準の変化は下行性の脳幹網様体賦活系、脊髄の運動神経を介して筋の緊張度にも影響する。松果体では、数種類のホルモンが分泌されているが、このうち光に対してはメラトニンに関する研究が最も多い。
このようなことから、照明光の明るさや分光分布に対する生体の生理的反応としては、中枢神経系、自律神経系、ホルモン分泌系、運動系の広い範囲にわたる反応系の関連が予測され、これらは光に対する非視覚的生理反応もしくは生物学的反応と呼ぶことができる。これらの反応は、明視性や色に対する嗜好性といった視覚による反応とは独立するものと考えている。これまで、照明光に対する非視覚的反応の研究は非常に少なかったが、1990年頃から当時の九州芸術工科大学(現九州大学芸術工学研究院)の生理人類学教室を中心として数多くの成果が報告されてきており(Yasukouchi,2005)、以下にいくつか紹介する。
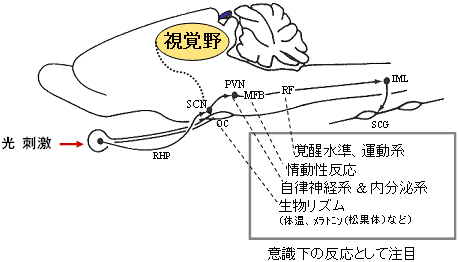
図7 ラットの脳における光の伝達経路(Klein et al.1983)
1-5 余分な緊張としての照明光の非視覚的影響の検証
(1)中枢神経系からのアプローチ
照明光の明るさは大脳新皮質の覚醒水準に影響するが、同じ照度でも分光分布が変われば覚醒水準も変化することが示されている。われわれの実験では、RA88の市販蛍光灯において、電球色や昼白色より昼光色の光が覚醒水準を高めるという結果を得ている。先の岩切ら(1997)の研究で示したように、通常の覚醒時においては、昼光色条件によって脳の覚醒がさらに高まっても作業効率は必ずしも向上しない、もしくは低下することさえあったことから(岩切ら、1997)、昼光色光は余分な緊張を引き起こす可能性があると考えている。この大脳新皮質の覚醒水準からみた余分な緊張は、事象関連電位のうち随伴性陰性変動(Deguchi and Sato,1992)、また音刺激によるオドボール課題(Inoue and Yasukouchi,1993)を用いた研究においても認められている。また覚醒水準の変化は脳幹網様体の下降性経路を経て筋の緊張度にも影響を与え、Yasukouchi and Ejima(1998)の実験では、覚醒水準と姿勢の体幹傾斜角度との間に有意な相関関係を示し、高色温度では低色温度条件より回帰直線の傾きが大きくなることを示している。
(2)自律神経系からのアプローチ
昼光色光は、心拍変動から解析される自律神経系の指標においても余分な緊張を与えると考えられている(Mukae and Sato,1992)。また昼光色光は、Tsutsumi et.al.,(2002)の例でも紹介したように、夜間においても交感神経系の活動を高める方向に作用する。
自律神経支配のうち、体温調節に対する光の影響はやや複雑である。被験者を15℃の部屋に軽装にて90分暴露する寒冷実験では、蛍光灯色温度によって直腸温(深部体温)の低下度に違いがでることがわかっている(Yasukouchi et.al.2000)。電球色蛍光灯の光では寒冷による直腸温の低下が抑制され、身体表面からの放熱量の抑制がみられた。これは末梢血管の収縮活動の亢進によると考えられたが、50℃の高温環境暴露後の常温下での直腸温復帰の経過をみる別の実験(Iseki and Yasukouchi,2000)においてもやはり電球色光は放熱量を抑制した。このことから、電球色光は寒さに対しては血管の収縮性にさらに緊張を与え、暑さに対しては血管収縮性の緩和に緊張を与えて拡張性を妨げたものと考えられた。つまり、寒さに対しても暑さに対しても放熱を抑制する方向に作用すると考えられる。ただし夜間の照明においては、結果が異なることが予想される。われわれの夜間実験では、電球色光は昼間とは逆に末梢からの放熱量を促進させ、消灯後の睡眠時の直腸温低下を妨げない方向に作用した。これは、夜間のメラトニン分泌に対する光の抑制度が電球色光において昼光色より弱く、その分メラトニンの体温低下への作用が強くでたものと考えている。この推測は、夜間の5,000luxと30luxの照度条件下で観察された別の実験において、高照度によってメラトニン分泌が大きく抑制された個人ほど放熱量は抑制され直腸温の低下は妨げられたことから検証されている(有倉ら、未発表)。
(3)生体リズムからのアプローチ
有倉ら(未発表)の実験では、夜の9時30分から就寝直前の午前2時までの4時間30分の間に照度30luxと5,000luxのそれぞれに曝露すると睡眠中の直腸温の低下度は前述のように高照度条件で小さくなったが、直腸温が最低値を示す時間も低照度条件に比べ平均で約1時間遅くなった。夜間の就寝前に浴びる光が強いと体温のリズム位相が後退することを意味する。
Tsutsumiら(2002)の実験では、1,000luxの同一照度条件においても色温度が異なると睡眠中の直腸温の低下度が異なった(前述)。すなわち、就寝前の光が昼白色もしくは昼光色の条件では電球色に比べて体温のリズムの振幅が小さくなった。
生体リズムを形成する視交差上核の生物時計としての機能は、受胎後32週齢前後から働き出すといわれている(Mirmiran and Kok,1991)。平均27週齢で誕生した早産の乳児60名を対象にBrandon(2002)は明暗のリズムを与える時期と体重増加率との関係を調べた。彼の研究では乳児を3つの群に分けて保育器で育てたが、A群では明暗のリズムを32週齢から、B群では誕生直後(32週齢以前)から、C群では36週齢からそれぞれ与えた。その結果、32週齢より4週間遅れて明暗のリズムを開始したC群においてのみ体重の増加率が他の2群より小さかった。通常母親のお腹にいるときの胎児のリズムは母親のリズムに同期している(Reppert and Schwartz,1984)ことを考えると、母親の1日の行動はもちろんだが、夜間の照明条件にも注意を払うことが重要であるといえる。
1-6 最後に
生理人類学では環境への適応能の個人差、集団差の研究に注目している。光と健康を考えるにあたっても光への反応の個人差、性差、年齢差等を配慮した光計画が重要である。特に光とメラトニンの関係は、睡眠の質や位相の問題、季節性障害や不規則な生体リズムに対する光療法、癌との関係等で非常に重要な研究テーマになっている。年齢差でみると、高齢者の水晶体は白濁化が進み、短波長の光の透過性が若年者に比べると小さくなる。そのため夜間の昼光色光によるメラトニン分泌の抑制度は若年者より小さくなる(橋富ら、2005)が、一方で一日のリズムのメリハリ(振幅)も小さくなる。またわれわれの研究(Hashitomi and Yasukouchi,2006)では、女性は性周期によっても夜間の光によるメラトニン分泌の抑制度が異なり、卵胞期よりも黄体期においてメラトニンの分泌は抑制を受けにくいという結果を得ている。夜間の光によるメラトニン分泌の抑制度については、同じ個人でも夏季より冬季でより大きくなり(Higuchi et al.,2007)、また日中屋外で光りを多く浴びれば抑制度は小さくなる(鳥越ら、未発表)というように季節や個人の行動によっても異なる。個人差でみると、われわれの研究では30luxという低い照度でもメラトニン分泌の抑制を示すものが存在する。600lux程度の照度では瞳孔反応の小さい(瞳孔径が大きい)ものはメラトニン分泌の抑制度は大きくなるが、30luxにおいて生じる抑制は光に対する感受性そのものの違いに帰因する可能性が示されている(Yasukouchi et al.,2007)。
照明光に対する種々の非視覚的生理反応にみられる個人差、性差、年齢差、また場合によっては民族差までも含めて、今後の照明光の標準化や使用計画を検討するにあたって重要な検討課題になると考えられ、照明光への人間の適応能という観点からの今後のさらなる研究が待たれる。
参考文献
(注1)Brandon DH, Holditch-Davis D and Belyea M(2002)Preterm infants born at less than 31 week's gestation have improved growth in cycled light compared with continuous near darkness. J Pediatr 2002;140:192-199Deguchi T and Sato M(1992)The effect of color temperature of lighting sources on mental activity level. Ann Physiol Anthropol 11:37-43.
(注2)Hashitomi K and Yasukouchi A(2006)The Pupil Responses to Light Exposure during Menstrual Cycle. Proc 8th Int Congress Physiol Anthropol, p38
(注3)橋冨加奈、野口朱里、小崎智照、安河内朗、2005:高齢者の日常生活において光がメラトニン分泌に与える影響について.日本生理人類学会第53回大会要旨集 p.110-111
(注4)Higuchi S, Motohashi Y, Ishibashi K and Maeda T(2007)Less exposure to daily ambient light in winter increases sensitivity of melatonin to light suppression. Chronobiol Int 24:31-43,2007
(注5)Inoue S and Yasukouchi A(1993)Effects of color temperature and ambient temperature on brain event related potentials. Ann Physiol Anthropol 12:110.
(注6)Iseki T and Yasukouchi A(2000)Effect of color temperature of fluorescent lamps on rectal temperature during and after heat exposure. Proc of 44th Meeting on Physiol Anthropol:72-73.
(注7)岩切一幸、綿貫茂喜、安河内朗、栃原裕(1997)光源色がその曝露中と曝露後にCNVの早期成分に及ぼす影響.日本生理人類学会誌2:31-37
Klein DC, Smoot R, Weller JL, Higa S, Markey SP, Creed GJ and Jacobowitz DM(1983)Lesions of the paraventricular nucleus area of the hypothalamus disrupt the suprachiasmatic→Spinal cord circuit in the melatonin rhythm generating system. Brain Research Bulletin 10:647-652.
(注8)Mirmiran M and Kok JH(1991)Circadian rhythms in early human development. Early Hum Dev 26:121-128
(注9)Mukae H and Sato M(1992)The effect of color temperature of lighting sources on the autonomic nervous functions. Ann Physiol Anthropol 11:533-538.
(注10)Reppert SM and Schwartz WJ(1984)Functional activity of the suprachiasmatic nuclei in the fetal primate. Neurosci Lett. 46:145-149.
(注11)Tsutsumi Y, Kitamura S, Kozaki T, Ueda S, Higashihara Y, Horinouchi K, Noguchi H, Ishibashi, K and Yasukouchi A(2002)Effects of color temperature of lighting in the living room and bedroom at night on autonomic nerve activity.6th Int Congress of Physiol Anthropol, p.36
(注12)Yasukouchi A, Hazama T and T Kozaki(2007)Variations in the light-induced suppression of nocturnal melatonin with special reference to variations in the papillary light reflex in humans. J Physiol Anthropol 26:113-121
(注13)Yasukouchi,(2005)A physio-anthropological approach in evaluation of human adaptability to living environment: In the case of artificial light environment. J Physiol Anthropol Appl Human Sci 24:307-312.
(注14)Yasukouchi A, Yasukouchi Y and Ishibashi K(2000)Effects of color temperature of fluorescent lamps on body temperature regulation in a moderately cold environment. J Physiol Anthropol Appl Human Sci 19:125-134.
(注15)Yasukouchi A and Ejima H(1998)The effects of color temperature of light sources on the arousal level and postural change with different mental tasks. Proc of Second Int Conference on Human-Environment System :247-250.
お問合せ先
科学技術・学術政策局政策課資源室