- 現在位置
- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 科学技術・学術審議会 > 資源調査分科会 > 資源調査分科会(第19回) 配付資料 > 参考資料4 平成19年度自然資源の統合的管理に関する調査 > 3.各論 第8章 わが国の自然資源の統合的管理のあり方と必要な技術開発
3.各論 第8章 わが国の自然資源の統合的管理のあり方と必要な技術開発
8‐1 わが国の自然資源の統合的管理のあり方
8‐1‐1 自然資源の統合的管理のあり方
自然を構成する基本的要素としての土地、水、空気の管理は、それらが自然界に元来存在することを認識し、自然といかに共生するかが、管理の基本である。わが国土地形構成及び利用構成は表8‐1‐1、表8‐1‐2の通りである。その特徴は、日本は山岳島、森林国であり、かつ海に囲まれた火山と地震の国である。
表8‐1‐1 国土の地形構成
(%)
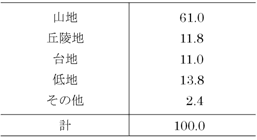
(注)
- 丘陵とは、低地からの高さ300m以下
- 台地は主として洪積台地
- 低地は主として洪積世に形成された地形で扇状地、三角州など
- その他は、北方領土や内水域(湖沼や河川など)
- 表8-1-1~8-1-2は日本国勢図絵 2007/08、原資料は日本統計年鑑(総理府統計局)2006、土地白書(国交省)
表8‐1‐2 国土利用構成(2004)
(%)

第2次世界大戦後、国土の復興から高度成長期にかけて、土地と水はもっぱら生産性向上の場、そして資源利用として、具体的には農業開発、やがて工業化、都市化の波に乗って、臨海工業地帯開発、そして宅地化の対象として、経済効率向上を目標とし、さらに産業の基盤としてのエネルギー生産向上のために優先的に利用されてきた。その場合、土地や水が自然構成のかけがえのない要素であることへの認識に欠けていた。日本は山岳島であるために、開発事業においてトンネルや橋を多数建設しなければならず、火山と地震の国は風光明媚な利点の一方、耐震構造に技術と費用を多く費やさなければならなかった。
8‐1‐2 戦後60年余の国土の統合的管理の教訓
戦後から高度成長までの約30年間、活発な開発が、それぞれの分野ごとに実施され、日本の経済発展、庶民の生活水準向上に成功した。さまざまな開発事業によって、土地利用は都市化、工業化の進行によって激変した。
しかし、全国各地の土地利用の急激な変化は、都市水害はもとより、流域開発による洪水流出の変化により水害の質的変化をもたらした。一方、土地利用の変化と水利用の拡大は、大気汚染、水質汚濁、地盤沈下などの国土の質を落とし、いわゆる公害を、都市を中心に全国的に発生させた。一方、土地と水利用の変化は、自然の水循環を狂わせた。自然の水循環に適合していた水田経営は、都市化によって著しく変化してしまった。地下水の過剰汲上げが地盤沈下を各地に発生させた。このように水循環の変化は新型水害を助長し、地下水位低下などさまざまな悪影響を日本の国土にもたらした。元来、水利用は、地表水、地下水、各種の水利用を統一的管理のもと、水と土地という自然との共生の理念のもと行うのが理想である。高度成長期までは各個別の水利用開発は、それぞれの部分に関する限り効率的であった。
しかし、無秩序な開発による水循環の不健全化、生態系の破壊が、1980年代から顕在するようになり、それを護るためにも水、土地という自然の管理を統合する必然性が高まって来た。各地に発生した開発事業反対運動、あるいは自然再生運動の高まりは、自然界のリズムが各地域ごとに乱れていることの顕れの一端であり、自然管理の統合化を求める叫びでもあった。法的対応も90年代から2000年代にかけ徐々に整い始めている。1997年の河川法改正に端を発した自然環境の整備と保全は、他の法体系にも及び、2002年の自然再生推進法、1995年に制定された生物多様性国家戦略、同じく2002年の新・生物多様性国家戦略などとともに、自然破壊を恢復するための自然再生事業が漸く軌道に乗りかけている。しかし、そのための法体系、行政組織を改革するのは一般に容易ではない。
自然再生事業は釧路湿原を皮切りに全国では19地域で始められているが、その対象地域は、森林、草原、里山、河川、湖沼、湿原、干潟、サンゴ礁などさまざまであり、多様な生態系を有し、事業遂行は容易でない。そのための科学的方法も技術的手段も模索段階とさえいえる。これら事業は環境省、農林水産省、国土交通省がそれぞれ関わり、その統一的手法による省際的提携が強く求められている。それらは、自然の秩序が乱れ、その復元のための自然再生事業であり、その重要性はもとよりではあるが、同時に重要なことは、現在または近未来における開発及び保全事業、およそ土地利用と水利用を著しく変更する恐れのある事業が、生態系に悪影響を及ぼさないために、さらに新たな危険な状況を生み出さないよう留意すべきである。
今後のわが国の統合的管理で憂慮されるのは、いずれ来るであろう大災害(大地震、火山爆発、大水害など)、及び着実に進行する恐れのある生態系の破壊とそれによってもたらされる悪影響である。その場合、教訓としなければならないのは、1995年1月突然発生した阪神・淡路大震災である。わが国の過去の災害史を顧みれば、1世紀に1~2度は大震災、火山大噴火、そしてさらに頻度の高い大水害を経験している。阪神・淡路大震災は、高度経済成長からバブル景気と続く、安逸な日本社会への痛烈な警鐘と受け止めるべきであった。日本のすぐれた科学技術によるビル群・交通設備が破壊されたのみならず、昔であったら使用できた都市河川は涸れていたため、消防活動には利用できず、各地に発生した火事への消防車の移動は思うに任せず、大都市のハード、ソフト両面にわたり弱点を露呈した。それは単に防災条件の不備に止まらず、都市計画を含む統合的計画及び管理ができていなかったことを意味する。総合的自然管理の必要性は敗戦直後から指摘されてはいたが、このような大災害の際にもっとも明確にその弱点が明示される。阪神・淡路大震災の教訓は、ビルや各種インフラの耐震計画はもとより、いかに都市及び防災計画に統合的管理体制をとれるか否かにかかっている。しかも21世紀が進むにつれ、気候変動と少子高齢化による自然及び社会条件の急変に対し、土地、水などの自然管理の在り方が問われている。
8‐1‐3 自然資源の統合的管理の今後の課題
21世紀は前世紀と決定的に異なる条件は、気候変動、少子高齢化であり、それによって派生するさまざまな異常事態に備える必要がある。気候変動による治水、水資源、海面上昇についての国土の自然への影響と、その基本的対策については8.3において述べる。
重要なことは、わが国においては気候変動が人口減少、首都圏南部への人口集中と、地方特に農山漁村と、河川上流部の人口の極端な過疎化、空洞化を伴って発生する点である。第1次産業人口のさらなる減少は、農林漁業の産業としての危機のみならず、わが国土の統合的管理の仕組み、方法における発想の転換、旧来の管理の改革を迫っている。農林漁業の人口減、極端な高齢化は、わが国土の3分の2を占める森林経営、及び水田経営にとって重大である。森林、水田は決して木材や米の工場ではなく、国土防衛の意義が重要だからである。第1次産業の衰退は、国土保全の危機であるとの思想に基づいて統合的自然管理の体制を整えるべきである。休耕田が増大しつつあるのは、単に米作の問題であるのみならず、日本の水循環、日本人の食生活、食料自給率に関わる多面的課題である。森林の荒廃は、単に木材の輸入問題であるのみならず、森林・治山治水の在り方と深く関係しており、それぞれの局面を統合的管理する方向に、今にして行政、学問、産業を向けなければ、事態はいよいよ難しくなるであろう。それを可能にする強力な省際的機関、学問と研究部門も学際的協力を必然とするために、従来の枠を破る組織替えが欠かせない。
より重要なことは、わが国の国土経営、自然管理は、戦後60年余、目まぐるしく変化してきたそれぞれの局面打開に追われ通しであり、いわば対症療法的対応に終始し、確たる自然観に基づいた国土保全、国土経営思想が欠如していたのである。今こそ、強力な統合的管理を目ざす国土思想を構築し、来るべき国土の危機に備えるべきである。
8‐2 今後の国土に関する統合的管理
今後の国土に関わる統合的管理を考える場合、最も重要な変化要因は、気候変動と人口動向である。それへの適切な対応なくして、統合的管理の実を挙げることはできない。
8‐2‐1 気候変動と治水対策の転換
気候変動に関する展望は第2章において、土地資源への影響を含め、農林漁業生態系への影響などについて述べられている通りである。
ここでは気候変動による水資源、及び新たな災害発生について略述する。地球シミュレーターでは、“降水量”と“豪雨の頻度”について予測している。降水量に関しては、2071~2100年の平均と、1971~2000年の平均を比較して“バランス型社会A1Bシナリオ”では地球規模で6.4%増、日本の夏では19%増となっている。日本の夏に降水量が増えるのは、熱帯域の太平洋の温度上昇に伴う、日本列島の南側が高気圧偏差となって、湿暖な空気が日本列島に大量にもたらされるからと予測されている。さらには、日本の北側も高気圧偏差となり、梅雨前線の北上を妨げるためと考えられている。日本の夏の豪雨頻度も平均的に上昇すると予測され、降水量の増加のみならず、大気中の水蒸気量の増加のためと推定されている。これによって、日本においては洪水などによる豪雨災害の危険度が高まる。
現在の日本の治水計画では、特に重要な河川は200年確率洪水に耐えることを目標に事業が進められている。続いて河川重要度に応じて、150年、100年、80年確率洪水に対する安全を求めて計画が推進されている。しかし、近年の豪雨増加傾向は、従来の確率値では対応できないことを示している。例えば従来の100年洪水が約30年洪水となり、それに応じて治水事業計画を拡大することは、財政的にも、治水戦略としても現実的でない。従って、21世紀の進行とともに気候変動が進むと予想される状況に鑑み、治水戦略を転換せざるを得ない。具体的には、かつてのようにハードな技術手段にのみ依存するのではなく、守るべき地域の特性、河相に即して、ハードとソフト手段を混合して対処すべきである。
人口密集地域は、従来のハード方式に頼りつつも、地域内での情報伝達、警報システムの完備に基づく、避難対策の整備が切望される。河川上流域の特に峡谷部、山間部などの人口過疎化の進行地域では、一般に高齢化が進んでいるので、従来の河川整備よりはむしろ、住民の避難対策に重点を移すべきである。河川中下流部では地域の事情は多様であるが、沿川に低湿地、沼沢地などが存在すれば、それらを長期的には洪水調節地的に土地利用を変換したい。さらには休耕田、耕作放置地なども、土地を選んで洪水氾濫を積極的に許容できるよう、治水もしくは環境の観点からの土地利用を計画すべきである。そのための制度改革が必要であり、省際協力は必須である。それは歴史的経緯に照らしてきわめて困難であるが、それなくして治水政策の抜本的改革はできない。
8‐2‐2 気候変動と水資源
気候変動による水資源への影響もまた重大である。その顕著な例として、日本においては降雪量の減少による被害を強調しなければならない。地球規模では北極と南極の山岳氷河と積雪での著しい減少は、IPCCの第4次評価報告書でも自信を以って強調している。日本列島でも既に降雪の減少は明瞭に進行している。北陸、東北、北海道の降雪量減少は数年前から発生している。もっとも、気候変動はいずれの局面においても、規則的に増加と減少の傾向を辿るとは限らない。一般に不規則に増減を繰返す。降雪量の場合も、今後数年に1回は豪雪の年もあろうし、長期傾向として減少して行くであろう。
降雪の現象は、融雪水の河川への影響に関して、憂慮すべき事態の発生が予想される。日本の雪国における水田も発電水力ダムも豊富な積雪とそれから流出する融雪出水に多くを頼りとしている。只見川水系や北陸の黒部ダムなどはその典型例であり、集水域の積雪量が減少すれば、融雪流量は減少し、気温上昇とも相まって、融雪の大部分は春先に集中する。そのため夏期には渇水が頻発する。従来の流出パターンで運営してきた水位操作は狂い、発電効率も落ちる。
“大雪の年に不作なし”とは古くから北陸、東北などの雪国において伝えられてきた。大雪は一挙に河川や水路に流出せず、徐々に融けて地下水を涵養する。田植以後の水田にとって、この豊富な地下水は有難い。雪は、冬季の戸外労働を不可能にし、雪崩をはじめ、雪害に悩まされてきた。しかし、雪は水循環における貴重な存在であり、それが雪国の人々の水との付き合いにおいて貴重な役割をになってきているのである。
元来、雪国文化は藩政時代から雪や氷の水循環、その季節変化に溶け込んだ生活習慣に根ざして形成されてきた。積雪の減少は、単に雪を頼りにしている生活や産業、あるいはエネルギーへの影響に止まらず、生活や文化の在り方を左右する可能性のある課題である。
8‐2‐3 海面上昇と沿海部の災害増大
表8‐2‐1に示すように27,800kmもの長い海岸線を有するわが国にとって海面上昇は由々しき問題である。IPCC第4次報告書に基づき、同報告の執筆者でもある三村信男茨城大学教授によれば、今世紀末に海面は18~59cm上昇すると予測している。30cmの上昇で、日本の砂浜面積は56.6%失われるという。
特に心配されるのは、東京、大阪、名古屋の三大都市圏の災害ポテンシャルの増大である。このいずれの大都市圏も、広大な海抜ゼロメートル地帯を有している。名古屋圏は約405km2と最も広く、東京117km2、大阪59km2である。もし21世紀末の最大予測値の59cm海面上昇し、満潮時に高潮が発生すれば、それぞれの湾の中等潮位以下のゼロメートル地帯は、名古屋で878km2、東京322km2、大阪384km2に達する。現在東京ゼロメートル地帯の人口は約232万人であり、前述の満潮高潮時には約415万人に達する。
表8‐2‐1 各国の海岸線延長比較表
| 国名 | 面積(A) 千km2 |
人口(B)
万人 |
人口密度
人 / km2 |
海岸線延長 ( C )
km |
1,000 km2 当たり C/A
km / km2 |
平均幅 A/C
km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デンマーク | 48 | 480 | 111 | 6,450 | 150 | 7 |
| 日本 | 370 | 10,372 | 280 | 27,800 | 75 | 15 |
| イギリス ( 本国 ) | 244 | 5,507 | 226 | 8,850 | 26 | 29 |
| オランダ | 41 | 1,300 | 375 | 1,450 | 35 | 28 |
| イタリア | 901 | 5,233 | 174 | 5,050 | 17 | 60 |
| スウェーデン | 450 | 781 | 17 | 6,790 | 15 | 66 |
| フランス | 547 | 4,989 | 91 | 7,820 | 14 | 70 |
| 西ドイツ | 248 | 5,749 | 232 | 2,820 | 11 | 88 |
| 米国 | 9,368 | 19,912 | 21 | 56,700 | 6 | 165 |
| スペイン | 505 | 3,187 | 63 | 3,000 | 6 | 168 |
| ブラジル | 8,468 | 8,512 | 10 | 5,780 | 1 | 1,470 |
(注)
1)沖縄県を含んだ日本の海岸線延長は29,400kmとなる
2)出典;『海岸便覧』、社団法人全国海岸協会発行、1971年11月
これら予想される大災害への減災措置は、きわめて困難である。堤防を主体とする従来のハードな防災手段に過度に依存するのは危険である。海面上昇により発生する恐れのある大災害は、想像を絶する悲劇となる可能性が高い。これら三大都市圏海岸部の海岸堤防、多数の水門及び多数の内部河川の堤防が、巨大災害時に発生する恐れのある流砂現象を含めて、すべて破損、沈下しないことがあり得ようか、海面より低いゼロメートル地帯では数箇所が破堤すれば、広大な地域が地震水害によって水没する恐れがあり、一旦広範囲に浸水すれば排水もまた容易ではない。重要な対策は、停電を早急に回復し、住民に被災実況の映像を配布できるシステムの構築、避難路を含む情報を被災者に周知される体制の整備である。
大都市以外の沿岸域は、三大都市圏とは異なる対応を用意したい。人口密度の低い地域は時間をかけて、より安全な地域への移転がきわめて望ましい。河川上流部の地域のなかにも、同様に下流部への移転計画を考える時期である。わが国は有史以来初めて人口減少時代を迎えている。それを今後の土地利用計画にどのように適合させるかは、国土計画の重大課題である。しかし、これを防災面に実現させるためには省際的協力は不可欠であり、防災行政が開発及び土地利用計画と一体になった強力な防災と開発行政の一元化が強く望まれる。しかし早期に手を打たないと、来るべき大災害は国家をゆるがすことになるであろう。気候変動によって一躍危険度を増した災害への事前の対策は、きわめて困難ではあるが、従来の発想を覆えす発想によってのみ実施できるであろう。
ある程度の人口を抱える中都市の沿岸域は部分的に海岸堤防で守るにしても、一様に施工するのではなく、海面上昇に伴う海岸線の後退に対しては、重点的に養浜など、地域の特性に応じた海岸防御を、海岸生態系、干潟の保全と一体化した海岸線防御が必要である。この場合も、海岸線に近い住居施設は基本的には移動、移設すべきである。
8‐2‐4 第1次産業は自然との共生を基礎に
大中都市以外の小都市及び農山漁村は、今後貧困と公共サービスの劣化が重なり、かつ防災力も弱まる。沿岸域、河川上流部に限らず、これら災害に脆弱な地域への対策は容易ではないが、新しい着想に基づく土地の統合管理が求められている。
本来、これら地域の産業基盤は農林漁業であった。しかし、これら第1次産業は高度成長期の都市化、工業化の波に煽りを受けて衰退の一途を辿っている。農林漁業、特に農林業は、生産効率の面で工業とは到底競争できない。EC諸国で近年考えられているように、第1次産業は国土基盤形成産業として位置づけ、土地資源を守る業として扱うべきである。
例えば、水田農業は古来水循環のにない手として重要な役割を果たしてきている。水稲生育期の湛水栽培は、地下水を涵養し補給している。出水時における水田は、一時的ながら、出水調整、洪水貯留の機能を持っている。湛水栽培の役割は、単に稲の成長のためのみならず、栄養分を苗の根本に確実に届け、雑草駆除労力の節減はじめ、きわめて多機能であるが、特に重視したいのは、生態系保全に対する貢献である。兵庫県豊岡におけるコウノトリの放鳥成功の影には、県の但馬県民局豊岡土地改良事務所などの貴重な努力がある。コウノトリの餌として、かつては水田の蛙やドジョウの存在があった。この土地改良事務所では農薬禁止はもとよりのこと、水田へ魚を持ち上げる魚道を設け、放鳥成功の一役をになっている。
水田は水稲栽培のためにのみ営まれているのではない、上述のような地域の水循環につとめ、生態系保全への貢献も大きい。戦後の食料増産の掛け声に支えられ、高度成長期にはひたすら米の増産と収益化につとめたが、1970年以降は過剰生産が祟って減反政策に追い込まれた。すべて水田を米の生産工場と間違えたからであり、農政は依然としてその反動に苦しんでいる。経済効率向上の世相に流されて、水田をあたかも米の大量生産する場としてしか考えなかったからである。水田が水循環に適合しているのは、減反の対象となった水田の周辺で、地下水位の下がっている例が多いことでも明らかである。水田は日本列島の自然界の水循環に良く適合した土地利用を維持し、生態系保持にも役立ってきたことを評価すべきである。
水田の宅地化が、高度成長期以降、日本の大都市周辺を中心に鋭意進められてきた。それが氾濫水害を助長したのも、水田が洪水の遊水池的役割を果たしてきたことを裏書きしている。さらに農村の農業用水路は、農業用水を運ぶ単目的施設と考えた途端に、その本来の役割が忘れられてしまった。かつて農村の人々は、用水路の水を飲料や家事用水、防火用水に利用していた。従って、用水路の水質や水路維持に留意し、その管理も行き届いていた。そこで、農村を流れる水路の醸し出す風景は、一幅の絵画たり得たのである。
農業用水路は現代的表現を借りれば、多目的水路であった。しかし、かつての農民にとっては水路が多目的であるとの感覚は無かったに違いない。行政から見れば多目的といえば費用振分けを考えた途端に、この話は立ち消えになる。個々の目的を明瞭に分けられず、ましてやそれぞれを数量化できないし、それは無意味である。つまり、藩政時代以来の農業用水路は、人間と自然との付き合いの場であり、数量化して効率向上を目ざす、という自然科学的思考論理以前の、人間と自然との関係である。
近年のコトバでいえば、“自然との共生”であり、それは生態系の一角を占めている自然との触れ合いの在り方が問われるテーマである。農業用水路をめぐる“自然との共生”の状況は、農村に水道が普及し、近代的消防施設が整い、農村の日常生活が都市化されるにつれ、一変した。農村は生活の効率化、合理化という都市化と引きかえに、自然との協調、融合を犠牲にしてしまったのである。こうして、全国の多くの農村で農業用水路は見る影もなく荒れ果てている。都市生活化に伴って、多くの用水路は下水路と化し、水質は汚れ水路の維持管理も滞る例が多く、かつての水路を要とする田園風景は見られなくなった。農業用水路の近代化はコンクリートの三面張り水路となり一刻も早く用水を運ぶための施設となり、流速を高めた流水は、一旦子供が落ちると危険であるので柵をめぐらしている。農業用水路は、用水を効率良く運ぶことに特化したのである。米の生産機能と経済効率を高めるためには、それが水路の近代化であった。近代化は“自然との共生”という数量化しにくい抽象的概念を捨て去ったのである。たとえ“多目的水路”を認識したとしても、それは水路が農民と自然との付き合いの路として育ててきた“地域”の水路であることが忘れ去られた証拠である。そもそも農民の意識が都市化し、農業は自然との共生の場であるより以前に、再び新たな価値観で、水田を米生産の場としてしか認識させない農政が続いている。
第1次産業は、自然、土地資源を基盤とする産業であり、水田が米の生産現場であり、森林が木材の生産工場という認識では将来は暗い。まず生産以前に“自然との共生”概念が先行しない限り、その発展は覚束無い。農林地は国家財産として、土地資源としての地位を与えるべきである。水田はわが国が所有する広大な湿地である。個々の水田の、生態的健全性、社会的健全性、経済的健全性から評価するシステムを考えたい。
8‐2‐5 水の統合的管理の必要性
水資源とその利用をめぐる情勢は、第2次大戦以後、目まぐるしく変転してきた。戦争直後の大水害頻発時代(1945~59)は治水投資に重点が置かれ、それに続く水資源不足時代(1960~72)は、水資源開発、具体的にはダム建設謳歌時代であった。これに対応する活発な河川事業は、その所期の目的は達したが、河川にとっては深刻な重荷となり、それは河川環境の復元を目ざす河川事業への要求となり、河川法にも“河川環境の整備と保全(1997)”が明記された(1973~97)。
農業用水、工業用水、都市用水とも建設から維持管理の時代に入り、水質に関しては次々と発見される新化学物質の対応に追われている。かつて、水資源の開発、そしてその利用はそれぞれの所管官庁によって、ともかくそれぞれが能力を発揮し、共存共栄(?)してきたといえる。しかし、近年は省際的課題が続出し、それに応ずる水行政システムができていない。水を全水利体系からみると不能率、あるいは不備が出現している。
わが国の第2次大戦後の水制度は昭和20年代から30年代にかけて確立した。例えば、河川総合開発や水力発電開発関連法案は、昭和20年代に続々と公布された。昭和32年(1957)には、水道行政を次のように決定した。すなわち、下水道は建設省、終末処理場は厚生省、上水道は厚生省、工業用水は通産省が所管。同年、水道法公布、特定多目的ダム法公布、昭和33年(1958)。同33年には改正下水道法公布によって、合流式下水道を前提として、“都市環境”の改善、都市の健全な発達と公衆衛生の向上を目的と定めた。昭和30年代が進むにつれ、河川の汚濁が広がり、昭和45年の下水道法改正において、“公共用水域の水質保全に資する”が、その目的に加えられた。なお平成8年(1996)には情報社会の情勢変化に応じて下水道管内部に光ファイバーなどの敷設を可能にするなど下水道法が改正された。平成17年(2005)には広域的雨水排除の推進などを内容とした法改正が行われている。
一方、治水・水資源に関する分野では、昭和30年代から40年代にかけ、ダムブームの時代が続いた。昭和20年代から30年代にかけては、電力不足を補うための電力専用ダム、建設省による多目的ダムの場合も、治水と発電水力、食糧増産の要請を受けた農業用水開発の組合せが多かった。やがて都市化、工業化の勢いは激しく、都市上水、工業用水需要の急増に対して、多目的ダムの目的に都市や工業用水が、農業用水に取替る傾向が強まった。昭和30年代後半から40年代には、全国的に都市上水や工業用水の不足が深刻であった。その頂点は昭和39年(1964)夏の東京の極度の水不足であった。折りしもアジアで初めての東京オリンピックを控え、東京の水不足は世界のマス・コミの関心もしくは冷笑の的となった。東京は果たしてオリンピックを開く資格があるのか、という批判さえあった。結果は、東京オリンピックの見事な成功は周知の通りである。東京都水道局が水道専用に計画し、昭和32年(1957)に完成していた小河内ダムの水位は極度に下がり、貯水量も底を衝いた。幸にして、その年8月20日以後、順調に雨が降り、オリンピック開会式の10月10日には水不足は解消していた。
東京の水不足は象徴的事件であり、当時全国的に急激な都市化で人口急増都市や新工業地帯育成に際しては水の確保が急務であった。昭和37年(1962)、水資源開発促進法が成立したのも、全国的水不足への法的対応であり、同時に水資源開発公団が誕生し、ダム、河口堰など水資源開発を進めることになった。前述の東京水不足の際はもちろん、当時のマス・コミは、ダムをなぜ速やかに建設して置かなかったかと、東京都水道局をはじめ水資源開発側を厳しく攻撃していた。
前述の法的措置や水資源開発の努力によって、昭和50年(1975)ころには、福岡など一部を除いて、大都市や工業地帯の水需給はほぼ安定した。しかし、昭和48年(1973)のオイルショックは日本経済に激震を与え、水需給情勢にも転期をもたらした。これ以後、工業用水需要は頭打ちとなり、東京・大阪などの大都市の水需要もまた横這いとなった。すなわち、それまでの右肩上がりの水需要増加は終息し、水需給計画は新たな段階に入っていた。
図8‐2‐1は1975年以降の全国の水使用量の推移を生活用水、工業用水、農業用水ごとに示し、その合計を概観している。図8‐2‐2は都市用水(水道用水+工業用水)需要の1965年以降の推移であり、1980年以降おおむね横這気味であることを示している。図8‐2‐3は生活用水を示し、図8‐2‐4は工業用水について淡水補給量と再利用(回収水、回収率)を示している。
しかし、水計画の担当者たちは、それまで辿って来た生長路線、そして東京水不足のように、一時それが頓挫した際の非難の嵐を想い出し、いつまでも増加する水需要予測を捨てることができず、1990年代に至るまでオイルショック以前に樹立した右肩上がりの水需給計画をそのまま続け、その後の多くのダムや長良川河口堰計画などにて、その欠陥を指摘されることとなった。水計画に限らず、転期に立った際でも、その直前までの計画を延長し、従来の計画を続行するのが、その時点においては無難で実行しやすい方法である。しかし、近未来を見透す視野で転期を認め、それに則る計画変更ができれば、その後の不要な軋轢を回避し、それぞれの時代の特性に則った計画が実行できる。転期に立った時、それを認め行動に移すのは困難な場合が多いが、それこそが最も意義深く、眞の長期計画である。
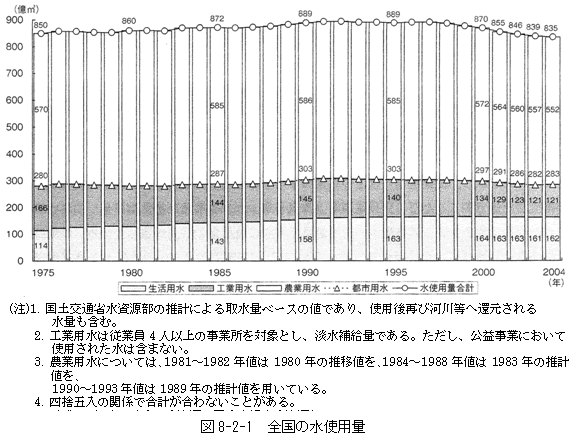
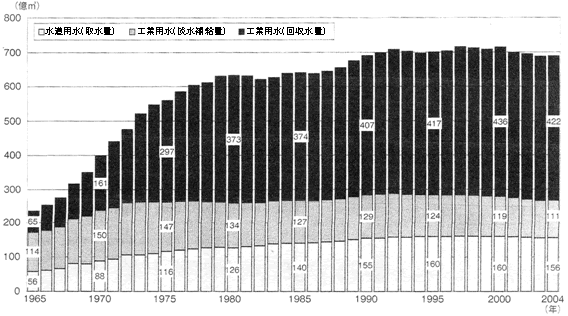
(注)
- 厚生労働省「水道統計」及び経済産業省「工業統計表」による。
- 工業用水は従業者30人以上の事業所についての淡水量
- 水道用水は上水道事業と水道用水供給事業についての取水量であり、簡易水道及び専用水道についての取水量は含まない。
- 水道用水のうち事業所での使用量は工業用水に含めている。
- 平成19年度 日本の水資源 国土交通省水資源部
図8‐2‐2 都市用水使用量の推移
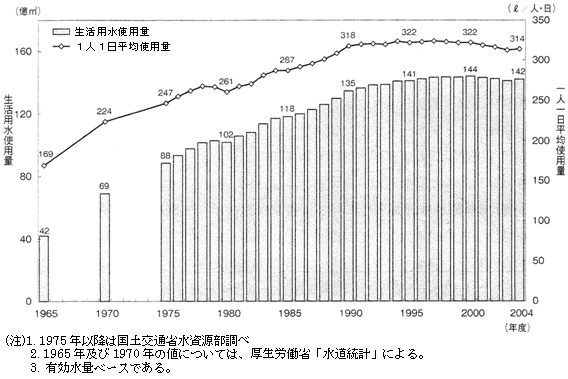
図8‐3‐3 生活用水使用量の推移
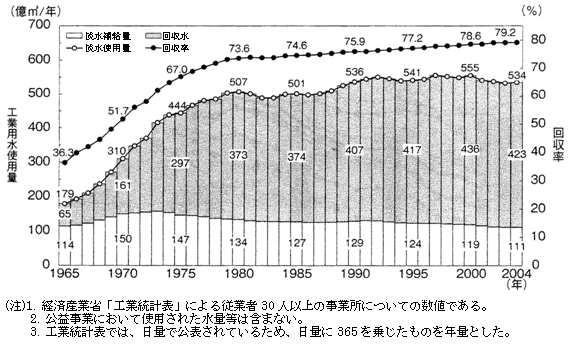
図8‐2‐4 工業用水使用量等の推移
昭和50年代後半から1980年代にかけて環境問題がどの分野でも重大となり、治水、利水、水環境の三本柱の新時代に突入した。それ以前まで、水環境といえば、もっぱら水質汚濁であったが、このころから、河川生態系の危機が叫ばれ、河川景観への重視も、単に風景論に止まらず、人間と水及び河川という自然との共生の在り方との関連での河川景観が問われるようになっていた。
8‐2‐6 健全な水環境と治水、上下水道
上下水道に関しては、水の需給バランスのテーマは漸くほぼ解決し、水道水質に発生する新たな化学物質の処理、下水処理水の再利用の普及に伴う上水道計画との関係などから、上下水とも健全な水環境のなかでどう捉えるかが重要課題となってきた。さらには徐々に伸びつつある雨水利用、沖縄及び福岡などで始まった海水淡水化など水利用の多角化が進みつつある。
健全な水環境が行政面で注目されるようになったのは、1990年代後半、治水技術の革新に関わる数々の提案が当時の建設省、国土庁、環境庁において発表されたことによっている。河川技術の革新は、行政面では1990年の建設省による“多自然型川づくり”に始まる。それは河川技術が河川との共生を認識する契機となった。一般住民サイドの河川事業改革の声を代表したのが、1994年完成の長良川河口堰反対運動であった。反対のおもな理由は、堰建設による河川環境破壊、水資源のさらなる開発の不要などであったが、この反対は当時のマス・コミの支援下、想像以上の盛り上りを見せ、社会問題と化した。
90年代は、上述のように、上下水道、治水、利水、水環境ごとに新たな課題が続出し、しかもそれらが重なり合って、その解決への道は、古くから主張されていた水の統合的管理の再来であった。しかもより強力に次代の動きを洞察した上で水の統合的管理である。水の各分野ごとに、従来の制度、行政の枠を越える新しいさまざまな課題が、1990年代から芽生え、21世紀となってそれが次々顕在化してきたのである。そのいくつかの例を、以下に紹介する。
河川と下水道の関係は、前世紀の高度成長期からしばしば指摘されていた。特に人口密集都市の豪雨排水は両行政が担当している。本来は都市計画の在り方に関わる課題であるが、ここでは河川と下水道との関係についてのみ触れる。気候変動によって近年時間雨量100mmを越える豪雨が必ずしも特異現象ではなくなってきた。かつて多くの都市では時間雨量50mmが10年確率豪雨で、それに耐える排水が目標であった。時間雨量100mmに対して安全な排水もしくは治水整備を、従来の考え方では、到底不可能である。河川事業と下水道事業との権限争い以前の問題である。かつて洪水処理をめぐって、河川と下水道が裁判の場で争ったことがあり、以後両者の話し合いは或程度進んだが、現在問われている気候変動に関わる難問は、発想の転換によらなければ解決できない。都市河川の氾濫、地下室での(東京や福岡での)水死事故の発生は、偶発的、局所的ではなく、基本的には都市計画の問題であるとともに、都市河川、下水道行政の在り方を問うている。
2007年から2008年にかけて発生した“飲用水に医薬品残留”、“高レベル有機フッ素の水道への混入”などの新たな課題に対して、それが直ちには健康影響なしとして、厚労省はさらに調査を続けている。しかし、より注視すべき点は、この種の有毒物質を含む排水を下水道や公共用水域に排出しても、現行の下水道法、浄化槽法、水質汚濁法では必ずしも違法とはいえない場合が多い。また、この種の物質が水道水に混入しても、現行水道法では必ずしも水道管理者が責を負うとは限らない。要するに、現行水法の成立時には、十分に想定できなかった問題が近年続出し、法的にも新たな措置が必要となっている。
8‐2‐7 水利用の多面化と国家戦略の方向
水利用に関しては、水需要が停滞横這いを続けているので、かつてのように開発のおくれによる水不足現象はほぼ消滅している。ただし、気候変動による降水量の時間的不規則が顕著になると、豪雨とともに渇水の心配も重なる。その場合の対応として、多くのダムの水位操作を従来の方式を越えて近隣複数流域を含めて対象とすることも一案として考えられるが、そのための法的及び行政対応が求められている。
水利用における農業用水、工業用水、都市上水(生活用水及び都市活動用水)の特に渇水時における調整に関しては依然として解決すべき課題を残している。従来のようにダム開発を主軸とした河川開発には今後大きな期待をかけられないが、下水処理水の再利用、雨水などとの共存の在り方については、まさに統合的管理の対象である。
まず主として上水道と下水道の統合的管理の必要性が無視できなくなってきた。下水処理水の再利用が進行しつつあり、本来の水道水源との役割分担、さらには徐々に普及しつつある雨水利用、その管理も水資源政策としては位置づけられていない。
一方、上下水道民営化が国際的に重要話題となっている。水源水質の新たな課題、水源の多様化に対する国家としての水戦略が問われている。これらの課題に対する、基本的姿勢のみを以下略述する。
政府及び地方自治体は、上下水道事業の民営化の場合、公共性を確保できる制度と組織を設けるなど、企業利益に振り回されない強力な措置を講ずるべきである。
水の統合的管理は、可能な限り流域圏単位で行われるのが望ましい。特に上水道と下水道事業の統合推進を優先的に検討したい。政府及び地方自治体は、治水、上下水道、水源からの取水と排水を通じて流域及び関連隣接流域における健全な水循環の持続可能性を保障する。そのために基礎的調査を関連機関が実質的に協議できる仕組みを早急に設立すべきである。上述水関連の各部局が実質的に統合的管理できる新たな組織を創り、各部局の代表が、協議できるようにする。
これら管理を実施するためには、水関連のすべての法をしばる水基本法、もしくはそれに準ずる法制定によって、気候変動と水問題の国際化という新たな状況に対処することを検討すべきである。
戦後復興から高度成長期に多数のダムが果たした功績は大きかった。しかし1970年代後半以降、ダムの環境に与える悪影響が顕在化し、かつ水資源や水力発電への新たな需要が減り、ダムへの批判が高まった。一部にはダム廃止論まであるが、これからは新たな発想によって、ダムを有効に利用することを考えたい。
例えば、近隣のダムを連結し、より広範囲に運営するとか、目的を時代の要請に合わせて変更しやすくするなどが考えられる。一方において、ダム湖の堆砂除去など、ダムの若返りが必要なことはいうまでもない。
8‐3 水とエネルギーと食料は一元的視野で管理
水、エネルギー、食料はそれぞれの部門で独自に対処しているが、この3要素は密接不可分の関係にあり、その相互関係を把握し、3者を一元的視野で統合的管理をめざす。
すなわち、わが国の食料自給率はカロリーベースで39%にまで落ち込んだ。先進国間では特に桁外れに低く、それ自体回復すべき重大課題であるが、水の仮想水(virtual
water)問題と深く関連している。わが国が仮想水としての年間輸入量は、沖大幹教授の試算によれば、その量は約744億m3であり、わが国の2004年の年間水使用量(農業用水552億m3、生活用水162億m3、工業用水121億m3、合計835億m3)の約90%にも相当する莫大な量である(平成19年版
日本の水資源、国交省水資源部より)。すなわち、わが国は国内における総使用水量にほぼ匹敵する水量を、仮想水の形で外国(特に米国、カナダ、オーストラリア)から輸入している。これら輸入国からの牛肉の輸入が仮想水量を増加させている。牛肉が食卓に上がるまでには、特に膨大な飼料を必要とし、その飼料育成に大量の水を要するからである。
水を伴う食糧の大量輸入は、その輸送に大量のCO2を消費する。地球規模で水不足が進行する状況では、将来水のコストは、仮想水を含め値上がる可能性があり、その取引が国際政治に利用される恐れもある。このように水と食料は密接に関連し、両分野が連携して水輸入の減少に努力すべきである。水輸入に関連して、ボトル水の外国からの輸入が増大しつつあるのは望ましくない。高価な水代さえ払えば、嗜好に応じてどこからでも、いくらでも輸入して良い時代は終りつつある。わが国は国際水戦略を確立して、この種の問題にも対処したい。
水が生産されるまでには、時には大量のエネルギーを使う。もちろんなるべくエネルギーを必要としない水の生産が望ましい。国際的に水資源開発の極め手と言われる海水淡水化に使われる大量のエネルギー消費の減少が課題である。サウジ・アラビアやクウェートなどアラビア半島で海水淡水化が普及しているのは、石油資源に恵まれ、水資源開発の他の手段が無いからである。サウジ・アラビアでは下水などの再利用と海水淡水化のコスト比較が、ひとつの選択基準である。つまり、海水淡水化の普及は、それぞれの国、それぞれの地域特性に支配される。わが国では沖縄及び福岡で淡水化プラントが運用されているが、いずれも財政援助が無いと成立しない。しかし、主として将来の技術開発とコスト減に備えての運用と評価したい。
海水淡水化に限らず、ダム開発、浄水、配水、処理過程を含め、水の開発、運搬、利用、排水すべての過程でのトータルエネルギーとコストを計量し、その相互比較から、将来の水生産、送水、排水の在り方を検討すべきである。CO2削減問題が脚光を浴びるなか、個々の部分でのCO2削減は議論され、いくたの提案があるが、より重要なことは、水システムのエネルギーの在り方をエネルギー・フローの観点から検討すべきであり、そのための水に関わる統合的管理手法が問われている。
水とエネルギーの関係で重視したいのは水力発電である。水力発電は一時、クリーン・エネルギーとして評価されたが、今後の各国の経済とエネルギー政策により左右される。これもまた、今後の水とエネルギーの国家戦略に深く関わる。
食料とエネルギーの関係は、最近話題となっている、エネルギー対策としてのバイオ燃料が食料価格を釣り上げている。食料生産とバイオ燃料の密接な関係は、いずれもそれぞれを生産する水のコスト、その輸出入価格に関わり、現段階では見通しは不透明である。
このように、水、エネルギー、食料は密接不可分の関係にあり、水の将来構想を練るに際してその一部面にのみ注目してはならない。つねに他の部分との現在及び将来の関係を念頭に置いて判断すべきである。個々のテーマごとに需給計画を作成するのではなく、3者が協議して共通理念のもとに、トータル・システムでの最適解を見出し、それに基づく管理体制を構築するのが望ましい。
8‐4 自然資源の統合的管理に必要な技術開発、ソフト資源開発並びに予測技術開発
持続型社会へ向けての科学技術の在り方に関しては、2002年に「持続型経済社会の実現に向けた科学技術」の今後の在り方について詳しく記述する。この中に述べられている「情報ヘッドクオータの創設」については、2001年11月22日に公表された経済財政諮問会議、循環型経済社会に関する専門調査会で下記のように政策提言されている。
≪情報ヘッドクォーターの創設≫
循環型経済社会の実現に向けては、極めて複雑で多様な側面があり、知識・情報の体系化・構造化が不可欠であり、「循環型経済社会推進のための情報ヘッドクォーター(仮称)の創設」が提言される。主たる目的は、下記2点に要約される。
- 知識の構造化・データの共有化システムを構築、各種取組の成果を蓄積
- わかりやすい情報提供、世界への情報発信
8‐4‐1 持続型社会への基本的な考え方
(1)自然科学と人文・社会科学を融合させた取組みに関して
1.物質的な側面の課題
多くの要素技術の中から、物質・エネルギーなどのマス・バランスを考慮した適切なプロセスの設計とその評価を行うため、資源や廃棄物のフローやストックを体系的・定量的に把握するマテリアルフロー分析や、システムにおける物質・エネルギー収支等の定量化手法の開発を進める。これらの定量化手法の開発に際しては、その精密性を追求するよりもむしろ基本的に間違っていないというレベルの合理性を有し、平易に管理・利用できるものである必要がある。これらの個々の手法を総合することで、持続型社会システムの成立を脅かす要因を特定することが重要である。
物の利用と循環については、プロダクト・ライフサイクル(開発→製造→加工→消費→廃棄等の一生)、循環系を構成する人工物の生産、再処理などの変換設備のライフサイクル・エンジニアリングの推進が必要である。個別技術としては、
- 設計工学、生産工学、人工物分解工学の統合、異なる生産形態の統一化。環境を考慮した製品設計支援と循環系全体からの評価。
- 機能劣化、材料劣化、品質回復等の検知、予測、原料変化に対する品質影響など循環物質の品質工学。
- プロダクト・ライフサイクルにおける環境影響評価の予測技術。
などが考えられる。
2.自然科学と人文・社会科学を融合させた取組み
都市規模及び地球規模における持続型経済社会システムを、地球環境の観測や変動予測に関する研究とも連携し、自然現象と人間活動を統合したモニタリングやシミュレーションを行うことにより、自然科学と人文・社会科学を融合した取組みによる総合的社会システム設計技術を開発する。こうしたシミュレーションにおいては、特定の規模・課題を切り口にしたケーススタディー(事例研究)を行い、社会システム全体を持続可能にするための方策や意志決定に関することを検討していくことが重要である。また、物質的な側面と人文・社会科学的な側面の両面からの検証を必要とする具体的なケーススタディー(事例研究)を行うことを通じて、自然科学と人文・社会科学の融合を図る先導的な例としていくことが必要である。
ケーススタディー(事例研究)としてのシミュレーションの切り口としては以下のような課題が挙げられる。
‐シミュレーションの切り口‐
(A)規模毎のシミュレーション
a)ミクロ(小規模)スケール
<例>
○ 家庭
○ 学校
○ 企業 等
b)メゾ(中規模)スケール
<例>
○ 都市
○ 地域
○ 流域圏 等
c)マクロ(大規模)スケール
<例>
○ 国
○ 東アジア圏域 等
(B)種別毎のシミュレーション
a)気象・地球環境
<例>
○ 大気循環
○ 水循環
○ 温暖化
○ オゾン層破壊 等
b)物質の流れ
<例>
○ 家庭一般ごみによるごみ発電
○ 生産・流通・消費・循環等
・食料
・エネルギー
・物質・元素
・化学物質
・水
・廃棄物 等
c)人間行動・社会問題
<例>
○ 廃棄物処分問題の社会的合意プロセス等
○ 産業活動における環境報告(自主的な責任ある対応)の実践の進展
・産業活動において環境に対する目標を設定し、それを公表することでどのような経済的価値を生み出していくかについてのシミュレーション
○ 人間の消費行動を含め、市民レベルでの人間の環境保全に対する意識や行動の変化
○ 環境に関する教育の成果
d)有害化学物質等に対する人体の応答
<例>
・内分泌かく乱物質等の有害化学物質、大気汚染やオゾン層破壊など環境問題による人体の健康への阻害要因が、人体にどのような影響を及ぼすのか、遺伝子レベル、細胞レベル、臓器レベル及び人体レベルそれぞれにおける人体の応答のシミュレーション。
(2)統合的な評価基盤の形成に関して
持続型経済社会の実現のためには、環境の保全と経済・社会の発展との両立をより近づけることを目指す必要がある。そのためには、持続型経済社会に向けた適切なシナリオやモデルを逐次検証することが必要であり、多くの要素技術を統合しシステム化した持続型社会システムの経済性・環境評価とともに、そのための手法を開発する。また、資源採取・循環・処分過程における環境負荷を評価するため、ライフサイクルアセスメント[LCA;Life
Cycle Assessment、製品及びサービスについて、製造→使用→廃棄または再利用されるまでのすべての段階における環境への影響の総合的な評価]等による評価基準を提示する。なお、これらの手法や基準は精密性を追求するよりむしろ合理性を有した適切なものとする必要がある。このことにより、総合的な評価基盤の形成に資することとなる。
統合的な評価基盤は、学界、産業界、行政はもとより、一般市民に対しても、持続型経済社会の課題を明らかにし、解決策の検討などに対応し得ることが必要であり、特に、市民の理解促進に資することが重要である。そのため、総合的な評価基盤の構築に際しては、市民、学界、産業界、行政の間を連携し、専門・学術的な研究内容やそれによってもたらされる成果を容易に理解可能とするような情報を基にしたコミュニケーション手法の開発・提供を推進する。
統合的な評価基盤の形成に資するため、持続型経済社会のモデルの検証やシミュレーションに必要となる広範かつ大規模なデータや研究成果・情報を収集・処理し、共有化を図る情報基盤の構築のための計算機システム、ネットワークや情報処理技術などの研究開発や基盤整備を推進する。
8‐4‐2 研究開発の推進方策
(1)自然科学と人文・社会科学との融合のための方策
自然科学と人文・社会科学との融合を図り、総合的科学技術として新たな研究領域を創生するとともに、その研究領域を学問分野として認知・定着させていくためには、空間的に異分野を1つにした研究開発の場を形成し、異分野の人材を動員して、融合を必要とする具体的な研究開発プロジェクトを推進することが重要である。また、異分野を1つにした場においては、研究・技術管理能力を有するコーディネータの役割が重要であり、その役割を明確にし、正当に評価することが新たな研究領域の定着・認知を図る上で必要である。
そのための具体的な研究プロジェクトの推進体制としては、コントロールタワー(司令塔)となるべき組織を各分野の全体を把握している人材で構成することである。そのコントロールタワーの下に、核となる既存の分野はしっかりと確保しつつ、各分野をバーチャル(仮想的)につないでいくことにより異分野を1つのものに融合した新たな研究開発を推進させるものである。
このような観点からの具体的な研究プロジェクトの推進方策としては、既存の学問的枠組みを前提とした分類にとらわれない研究資源配分や評価自然科学と人文・社会科学との融合によるプロジェクトを優先するなどの動機の付与
両分野の研究者や技術者の参画による目的を絞り込んだ政策追求型の研究プロジェクトの形成新たな研究領域における研究は、どのような成果が得られるのかどうか危険性を抱えているため、いくつかの研究提案を短期間試行させ、その成果の評価に基づいて大規模プロジェクトを行っていくという2段階方式による研究開発の推進等が考えられる。
(2)統合的な評価基盤の形成のための方策
持続型経済社会の実現のためには、学界、産業界及び市民の各層を通じた意思決定が重要であり、その意志決定に基づいた社会全体における合意形成が必要となる。そのため、社会におけるさまざまな層や分野の人間の意思決定に資するため、容易にアクセスかつ理解可能な統合的な評価基盤を形成することが不可欠である。また、この総合的な評価基盤を活用し、方向性の検討過程における情報、研究開発の状況や成果、持続型経済社会の実現に向けた各要素技術やプロセスの重要度や全体への影響度、社会への定着や政策への反映の観点からの経済性、法制度・社会制度的な側面からの影響評価、及び持続的経済社会を実現するに当っての課題等に関して、学界・産業界の研究者・技術者のみならず一般市民も含めた社会全体における情報の収集・処理・発信及びその共有化等が必要である。
このような観点からの具体的な総合的な評価基盤の形成のための方策としては、技術開発の進歩や国際的取り決め等、さまざまな状況変化に対応できる機能を持った「持続型経済社会を推進するための情報ヘッドクォーター(仮称)」の創設
、社会の各層及び各分野と総合的な評価基盤の間を有機的に結ぶコミュニケーション手法の開発等が考えられる。
(3)人材の育成・確保のための方策
持続型経済社会の実現に向けた科学技術においては、既存の学問分野や領域にとらわれない新たな研究パラダイム(方法論)の構築、つまり自然科学と人文・社会科学を融合させた新たな研究領域を創生し、それを学問分野として認知・定着させることが必要である。このため、大学・研究機関においては、広範な分野にわたる知的基盤の形成と、知的・人的資源の活用の推進など、人材の流動性を助長し、異分野の接触を促進する仕組みの形成が必要となる。
特に、異分野を融合し1つのものとしていくためには、研究・技術管理能力を有するコーディネータの役割が重要であり、その役割を明確にし、正当に評価することが、こうした新たな統合的科学技術における専門家の育成や人材の確保につながっていく。
また、産業界における実用化を視野に入れ、産官学の連携による実践的な環境保全課題に対応できる研究者・技術者の育成も必要である。持続型経済社会に関わる物質・元素、エネルギー、有害化学物質、水資源、生態系等の物質的な側面と、人間社会や経済などの人文・社会的側面の各要素が移動・流通・影響する範囲は地球規模に及んでいるため、学際的・国際的な協力に柔軟な対応能力を有する人材の育成も重要となる。
さらに、経済社会の大きな部分を占める消費者、つまり市民層の参加による調査などを進めることにより、市民や社会と連携した研究開発を進めることのできる人材を育成するとともに、次代を担う研究者・技術者の育成や人材の確保につながっていく。
このような観点からの具体的な人材の育成・確保のための方策としては、例えば、分野横断的で新たな境界領域の研究を受け容れる学術雑誌の創生などによる研究発表の場や仕組みの形成
境界領域への優先的な研究資源配分や境界領域の研究者・専門家としての正当な評価等が考えられる。
(4)国際的な取組みの推進方策
持続型経済社会に関わるさまざまな側面や要素は地球規模に及んでおり、持続型経済社会の実現に取り組むには、その視点は自ら世界規模にならざるを得ず、国際的な連携・協力は必須である。
とりわけ、わが国に環境面で直接的な影響を及ぼすとともに、土地利用条件や社会基盤で類似点が多く、また、近年、わが国の産業立地が移転・重点化し、経済圏を形成してきている東アジア諸国との連携・協力は、わが国の持続型経済社会の今後を検討する上で極めて重要である。これら地域との間で、わが国も含めた広域規模での持続型経済社会の実現のためには、研究開発における積極的な連携や技術移転などの協力を進めることが必要である。特にわが国は、経済の高度成長の過程で生じた公害問題を克服してきた経験を有するとともに、省エネルギーや低コストのための技術開発を積極的に進め、結果として環境負荷低減につながった多くの技術を有している。従って、目覚しい経済成長の過程にあるこれらの地域に対して、物質的な側面による自然科学技術に関する情報の発信源となるのみならず、広域規模での持続型経済社会の構築に向けた主体的な協力を推進する必要がある。
このような観点からの具体的な国際的な取組みの推進方策としては、例えば、科学技術振興調整費の活用も含め、国際協力を確実に実行に移すための国際会議の開催、国際共同研究の実施、専門家派遣等の機動的な推進
科学技術振興事業団や日本学術振興会の諸事業を通じた国際共同研究の一層の強化等が考えられる。
(5)研究を社会経済活動や市民生活に反映させるための方策
研究成果を社会・経済活動や市民生活に反映させるためには、社会(特に産業界)における持続型経済社会の実用化と市民生活への普及を視野に入れた研究開発を推進する必要がある。そのため、産学官連携、特に産業界からのコミットメントの獲得と市民参加の促進・強化が必要である。市民層に関しては、調査等に参加するなどコミュニティー意識を通じて、自らの生活や消費行動に関して自主的・主体的に環境に配慮した行動や管理を行い、持続型経済社会を構成する一員であることを認識するようにしていくことが重要である。同時に、さまざまな環境情報に裏打ちされた総合的な評価基盤と市民の間を有機的に結ぶコミュニケーション手法が知識を構造化した体系で開発され、個人の能力や興味の度合いに合った形でデータ等を理解できるようにすることが重要である。
また、持続型経済社会を実現する科学技術は、地域に根ざしてこそ成果が達成されるものである。例えば、地域の大学や研究機関が地域産業と連携するなどして環境に関する研究開発を行ったり、地域の政策立案・決定に資するため自治体・地域コミュニティーとも連携して研究開発を行うことが重要である。こうすることにより、地域全体の環境への取組みを促進することにもなり、市民層の関心と理解を深めることにも寄与するものである。
こうした観点からの具体的な研究推進方策としては、ビジネスモデル、環境モデル及び都市モデルに関して、都市・田園等の一定地域における政策立案・決定と科学技術が融合する社会実験的な取組みを進めること
等が考えられる。
8‐4‐3 「サスティナビリティ・サイエンス」の創生に向けて
(1)「サスティナビリティ・サイエンス」の概念
1984年に発足した「環境と開発に関する世界委員会(WCED;World Committee on
Environment and Development)」が8回にわたる会合の後にまとめた報告書では、環境保全と開発とは相反するものではなく、不可分なものであるとする「持続可能な開発」の考え方を提案した。さらに、1987年に、同委員会が公表したブルントラント報告は、「持続可能な開発/持続可能な社会」という概念を国際的に広める先駆けとなった。この報告では、「サスティナビリティ(持続的な発展)とは、将来の世代が自らの欲求を充足する能力を損なうことなく、今日の世代の欲求を満たすような開発をいう。」としている。
サスティナビリティ・サイエンス(Science for sustainability)の前提であるサスティナビリティ(持続的な発展)については、経済社会の持続的発展を目指しながら、資源・エネルギーの有効活用や、適切な水・食料の確保、自然生態系の保全及び有害化学物質等の管理など、環境への阻害要因がより緩和され、経済社会システムと市民の生活様式を、「物である資源」を大量生産・消費し、環境への負荷を容認してきたものから、省資源、リサイクル、汚染・有害物質の抑制など環境への負荷が最小化されたものに転換させることにより、将来にわたる生存基盤となる環境の保全を図ると同時に、経済・社会の成長・発展との両立をより近づけることである。
また、サスティナビリティ・サイエンス(Science for sustainability)の概念については、物質・元素収支、エネルギー収支、微量有害化学物質管理、水資源管理、食料収支、生態系保全等の物質的側面、及び貧困問題等も含めた経済や人間社会等の人文・社会科学的側面の両面にわたり、極めて多様な問題の解決と関係者の意思決定に基づいた共通認識と合意の形成に資するような総合的科学技術である。特に政策立案・決定と科学技術の融合が重要である。
(2)「サスティナビリティ・サイエンス」の方向性
持続型経済社会には物質・元素収支、エネルギー収支、微量有害化学物質管理、水資源管理、食料収支、生態系保全等の物質的側面、及び貧困問題等も含めた経済や人間社会等の人文・社会科学的側面の両面がある。従って、持続型経済社会の実現には、このような両面に関わる利害関係者を発生させることになり、コスト、エネルギー、環境負荷等の価値判断基準が多岐にわたっている。このため、極めて多様な問題の解決ととともに、その関係者の意思決定に基づいた共通認識と合意の形成が不可欠である。この受け皿として、知識の構造化や、要素技術やデータの共有化システムとしての総合的な評価基盤の構築と、社会のさまざまな層や分野の人間がこの総合的評価基盤に対して容易にアクセスでき、理解が可能なコミュニケーション手法が不可欠となる。
また、技術開発の進歩・国際的取り決め等さまざまな状況変化に対応できる機能を持った「持続型経済社会推進のための情報ヘッドクォーター(仮称)」の創設が望まれる。
これらを学術的な視点から支援するためには、持続型経済社会を総体的・俯瞰的にとらえる総合的な学問体系の構築と人材の育成・確保が不可欠となり、自ずから「サスティナビリティ(持続的発展)」をテーマに自然科学と人文・社会科学の融合した総合的科学技術に取り組む研究推進体制を構築することが求められてくる。さらに、このような総合的科学技術の研究領域の創生や定着は、将来の経済社会に対する潜在的なニーズを顕在化させ、新たな産業・市場の創出と産業構造の高度化に寄与するものともなる。また、市民社会全体においても、自ら持続型経済社会を実現するために主体として参加しているという役割・責任が共有のものとされることになる。持続型経済社会の実現のためには、政策と研究・技術開発の関わりを科学的に検討していくことが重要であり、このためには社会実験的な取組みを推進していくことが必要である。
8‐4‐4 統合的管理に必要な技術開発、ソフト資源開発
(1)指標の開発とデータの収集整理
総合国力概念やフットプリント概念による表現などによるさまざまな指標の開発とそれに関するデータの収集整理が必要なことは言をまたないが各システムが閉じた系(システム)で行われているところに大きな問題点があると考える。エネルギーにみられるように1次エネルギーを2次エネルギーとして利用するように、1次情報から2次情報(知識化)としてガバナンスに利用できるような知識の体系化・構造化が必要である。また、統合的な自然管理を考える上では資源の観点を中心としたシステムばかりでなくそれらを有効に活用するためのソフト資源もふくめた幅広い考え方が重要でありこれらがシステムとして十分に考慮されていない。
重層的な社会システムとしては下記のようなシステムが考えられる。
1.短期的(ミクロ)視点からのシステム
・総合国力概念をベースに各国毎の指標・データの整理を行うとともに
環境指標:環境情報;Footprint、OECDコアセット指標等
経済指標:経済統計;グリーンGDP等
社会指標:社会統計;HDI、Social Capital等
を考えるなど総合的視点からの指標の選定が必要である。
2.中期的(メゾ)視点からのシステム
・環境・社会指標を中心としてストックとフローの両側面から考える必要があるがストックを主として長期的視点からのシステムとして考えることにすると人間のライフサイクルスパン程度を考えることが出来る。
3.長期的(マクロ)視点からのシステム
・生態系に関する資源やエネルギーに関する資源は、長期的な視点からの社会システムにより対応可能であるが長い時間スパンに対応するデジタル情報システムは必ずしも十分な研究開発がなされているとはいえない。
望ましい研究開発の在り方として、これら時間の短期、中期、長期的視点と資源のストックの概念、資源のフローとしての概念について、従来からの管理的発想からではなくマネジメント(ガバナンス)の概念をシステムのダイナミズムの中に包含していることが重要である。そのためには、統合的管理の考え方の中に、市場原理ばかりでなく官の役割の見直しも含めたガバナンスの総合的な検討が必要である。さらに、関連する知識の統合的な体系化・構造化が必要である。エネルギー資源を考察すれば、1次エネルギーのように資源そのままを利用する場合もあるが、実際には2次エネルギーとして利用するように多様に形や利用形態を変えて利用される。また、原油価格の高騰により従来は価格競争力がなかったバイオエネルギーが急に政策の柱になりさまざまな穀物を転用する事態が発生している。これらの状況からみると資源としての統合的管理の視点からは、単なる市場原理にまかせるばかりでなく新たなガバナンスのシステムが重要である。
一方、グローバリゼーションの進行により国家を越えた経済活動やEUのような共同体が機能するようになり、国家を一単位とした取り扱いでは問題提起や問題解決にならない事象が多く現れている。そのため、ミクロ、メゾ、マクロスケールでの重層的な多階層モデルとしての社会システムの研究がなされる必要がある。社会システムやプロセスを抽象化を記述する方法も国連CEFACT標準化推進委員会などでビジネスモデルの抽象化手法として検討が進んでいる。
また、資源の多様な側面、利用方法の複雑化、経済的効率の側面、ミクロ、メゾ、マクロレベルでのマネジメントを考える上で単なる数値的なシミュレーションではなく、多階層で社会システムを記述可能な予測手法技術の開発が必要である。さらにそれを可能とするためのデータやシステムの記述にセマンテック(意味構造を持つ)なオントロジー(概念化)注)を内包した予測手法の開発とシステムの構築が待たれる。これが実現するとネットワーク上で分散化したデジタルコンテンツの統合的なデジタル処理が可能となる。
(注):オントロジー 文書等の内容を説明する意味情報(メタデータ)を各文書、データ等に付加し、メタデータを記述する用語を定義する構造(オントロジー)を意味する。
(2)定量的モデルと定性的モデルの融合の必要性と知識の体系化・構造化について
従来行われているフットプリントなどのさまざまなモデルは、ターゲットとする要因を定量的に表現しモデル化する手法が主であった。自然資源のようなストックとしての側面が重要だと考えられる資源については、定量化に結びつけるための定性的な研究を情報システムとして組み込むための研究・開発が重要である。
1つの事例として、河川における魚の生態モデルの例を紹介する。
この生態モデルでは、縦軸が魚類(198種)名、横軸が生息分布条件28項目及び生態的特性49項目に計78項目について(78×198種類=15444項)調査した。また、生息環境条件に関して水温、濁り、流況に関する26項目について(28×198種類=5148項)について調査している。これらが、河川における魚類の基礎的特性であるがエキスパートシステムで言う知識ベースに当たる。さらに、生態系に影響を及ぼす環境変化の知識ベースをインパクトマトリックスを作成し整理研究したものである。
(3)体系的・構造的な知識の整理について
知識の体系化・構造化が必要となるのは、専門外の人々へのアカウンタビリティばかりでなく「知識の細分化と対象の複雑化」の中で「全体像が見えない」ことを解決するためである。また、ネットワーク型統合知識基盤(視点に応じた像、シミュレーション機能、可視化機能、常に更新する機能、データベース、知識ベース、法・規制、国際情勢)が必要でありネットワーク上の分散協調型システムとしてWeb2.0の基盤技術としてのXML
Web Servicesを中核としてインターネット上のiDC(インターネット・データ・センター)のアーカイブ能力、コンピューティング能力、仮想化能力、セキュア能力等をフルに活用した ディレクトリサービスを担う情報ヘッドクォーター(途上国型→先進国型への戦略構築システムの進歩)のネットワーク利用の分散協調型システムの創設が望まれる。
これら知識を体系化構造化するためには、さまざまなデータや情報を統合化してマネジメントする仕組みが必要でそのためには、分散している情報やデータの所在情報(1次情報)ばかりでなく2次情報として知識化するためのネットワークを活用したシステム及び情報の信頼性を確保するためのメタデータ(情報だけでなく作成者、データの出所、過程等の情報が付加されている)としての位置づけが重要である。さらに2次システムにおいてもメタデータの活用により1次情報が追跡可能なシステムの考え方が重要である。また、デジタルでの長期的なデータの保存・活用の指針を示すことも重要である。
(4)予測技術開発の必要性
日本が開発した「地球シミュレータ」は各国に衝撃を与えた。それまで不可能と思われていた予測を可能にしたばかりでなく予測技術による信頼性のあるシミュレーションを可能にした。その技術が、衛星観測など進歩していた観測技術と結びつき予測技術のさらなる高度化を可能にしたからである。
1969年7月のアポロ11号の月面着陸成功など大規模な科学技術の開発は、90年代に入り、バイオ研究としてDNA、タンパク質、細胞の働きの分析、核融合プラズマ分野、地球温暖化問題の解析、気候変動予測、地球磁場(磁気流体方程式のシミュレーション、地磁場の再現の成功)研究、プレートテクトロニクスの基本的解明などがあり、地震研究では震源地の精密な特定、発生(解放)エネルギー(マグニチュード)を初期値とする地震波による被害予測と到達時間のかなり正確な予測が可能となっている。しかしながら地震発生のシミュレーション予測は巧妙なシミュレーション・アルゴリズムを考案することなしには不可能である。一方、経済並びに社会現象のシミュレーションについてみると、その基本構成の中心は人間であり、人間の行動には物理のような普遍性はない。
しかしながら、関係する人間の行動パターン、経済状況や社会的位置などの初期条件を与え、さらに境界条件(周辺条件)を与えることによりシミュレーションが可能な分野も存在し研究も行われている。もちろん、リーダーの選定や、一般市民のグループ化(行動パターンの特性)などさらなる研究が必要な分野もあろう。
現在での医療や社会分野の研究での大きな問題のひとつは、人間の特性や行動を研究する際に学問的要求に必要な量と質の個人情報が得ることが難しくなっている点にある。これら予測には、統計的に処理する場合でも個人に関する情報が不可欠でこれらの十分な情報がない場合には正確なシミュレーションは困難になる。これらの要素から、社会的シミュレーションの開発研究は、単なるシミュレーション技術の開発にとどまらず完結するまでエンドレスに続くものと思われる。このように、社会科学分野のシミュレーションでは単なる技術の開発ではなく社会制度や文化といった従来の研究では考慮されなかった多元的な視点での総合的な研究が不可欠である。
さらに、自然資源のシミュレーションを考えると社会科学的な問題ばかりでなく下記のような時間・場所のスケールの問題が存在する。
従来の科学的と言われるシミュレーションの多くは、短期的予測を可能にしたに過ぎない。初期値として現在もしくは一歩前のデータを用いて計算を始め現在の境界条件から計算をスタートせざるを得ない。自然資源のシミュレーションを考えると、短期的(ミクロ・スケール)、中期的(メゾ・スケール)、長期的(マクロ・スケール)にわけて考える必要がある。これらをシミュレートするためには、多階層での新しい考え方をしたシミュレーションモデルの研究が必要である。さらに社会的には、ローカルレベル、国家レベル、グローバルレベルといった、地域的特性も考えなくてはならず、時間の多階層だけではなく地域の多階層も考えなくてはいけない。さらに難しいのは、ミクロスケールの積み重ねがメゾスケール、さらにマクロスケールになるわけではなくそれらの関係が非線形性を持つばかりでなく階層毎に別の問題を解決しなくてはならないという難しさを伴う。しかし、研究方法としてコンポーネント化出来る部分から着手しコンポーネント間の関係性を記述しそれぞれの階層別に開発研究を進めて接点となるデータを初期条件・境界条件として受け継いでいくことは可能であると思われる。
コンポーネント指向多階層モデルと呼べる分散協調型モデルで時間の3階層と組み合わせて地域(場所)の3階層の研究を進めることは今後の国家戦略ばかりでなく21世紀の人類にとって豊かな社会構造を考える意味でも重要である。日本において研究開発の方向性を示し世界に先駆けて早期に着手する必要があると考える。
参考文献 8‐4節
(1) 経済財政諮問会議(2001)「循環型社会に関する専門調査会」中間報告書
(2) 文部科学省(2002)「持続型経済社会の実現に向けた科学技術に関する懇談会」中間報告
(3) 山田規世,大橋正和,日野幹雄,小松泰樹(1994)河川環境の変化を伴う水塊生態モデルの研究について,水工学論文集,土木学会
(4) K. Kashiyama , M. Ohashi and T. Suzuki(1992) A Knowledge‐based
Expert System for Natural Disaster Prediction Using Geomorphological and Geological
Information, Microcomputer in Civil Eng., 7., pp.283‐290.
お問合せ先
科学技術・学術政策局政策課資源室
-- 登録:平成21年以前 --