- 現在位置
- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 科学技術・学術審議会 > 資源調査分科会 > 資源調査分科会(第19回) 配付資料 > 参考資料4 平成19年度自然資源の統合的管理に関する調査 > 3.各論 第5章 自然資源の統合的管理を支える社会システム及び必要なソフト資源のあり方
3.各論 第5章 自然資源の統合的管理を支える社会システム及び必要なソフト資源のあり方
5‐1 自然資源の統合的管理を支える社会システム
5‐1‐1 自然資源の概念と利用の方向性
最初に自然資源の概念を若干整理しておく必要がある。というのは、自然資源を直近の価値観の延長線上で考えてしまう傾向があるからである。こうした傾向は自然資源に限らず一般に普通に見られる。しかし、世紀を跨るような機会には、自然資源について過去から未来を俯瞰してより長い時間スケールで捉えることが重要だと思う。21世紀に入って間もない現在、以上の観点から自然資源の概念、特に資源観について、少なくとも以下の4点に配慮する必要がある。
(1)非再生型から再生型への自然資源の転換の必要性1)
第1は、自然資源は必ずしも絶対的で普遍的なものではなく、時代によって資源としての利用価値の変化していることを認識し、それへの対応を考えることである。現在、資源価値の高いものが、将来にわたって、その評価が続く保証はないし、反対に、現在は資源価値のないものが、将来は高い資源価値を持つこともある。
例えば、19世紀、石油がにじみ出ていたカリフォルニアの土地は、誰も見向きしなかった。当時、石油は資源として認められておらず、ただの厄介者だった。資源は利用価値が出て始めて意味をもつ。石油の資源性が認められると状況は一変し、その結果、20世紀前半まで他に見るべき資源を持たなかった多くの産油国が20世紀後半から21世紀にかけて世界の経済を握っている。さて、それでは22世紀はどうだろうか?来るべき22世紀を人々が希望をもって迎えるために、私たちは21世紀にどのような資源観をもつべきなのだろうか?
石油は石炭や他の地下資源と共に20世紀の人類社会を飛躍的に発展させたことは記憶に新しい。しかし、地下資源は量が限られていて、その上、生産速度が遅いから使っていけば枯渇する(資源枯渇)。同時に、地下資源の利用は地下にあった物質を地上にまき散らすことになり、環境変化が避けられない(地球環境の汚染・変化)。従って、非再生型の地下資源に依存する20世紀型の資源観を継続していたのでは、資源枯渇と地球環境変化の2大問題の深刻化が避けられない。メタンハイドレートの利用技術開発などはまさに典型的な20世紀型の資源観で、緊急対応にすぎない。
そこで、人々が希望をもって22世紀を迎えるには20世紀とは別の資源観が必要になる。そのために、今、考えられているのが主力資源を従来の非再生型から新たに再生型へ切り替えることである(表5‐1‐1参照)。切り替えができるまでは20世紀型の資源を使っていくしかないが、現状の地球環境の状況を考えると切り替えはできるだけ急ぐ必要がある。
表5‐1‐1 これまでの資源(20世紀型)とこれからの資源の特徴
| これまでの資源(例:石油・石炭) | これからの資源(例:太陽光・風力・海洋深層水) | ||
|---|---|---|---|
| 濃い資源密度 | ○ | 薄い資源密度 | × |
| 少ない資源量 | × | 豊富な資源量 | ○ |
| 限られた資源価値 | × | 多くの資源価値 | ○または× |
| 枯 渇 | × | 再生循環 | ○ |
| 多くの環境問題 | × | 少ない環境問題 | △ |
再生型資源の多くは、薄い資源密度のために効率よい利用技術の開発が不可欠である。20世紀は私たちの知識が乏しく技術も未熟だったために低密度資源は効率よく利用できなかった。しかし、21世紀を迎えた現在、知識・技術がかなり進歩し、一部の低密度の再生型資源の事業利用が可能になってきた。太陽光、風力、海水、バイオマスなどである。太陽光と風力はエネルギー資源だけであるが、海水とバイオマスからはエネルギーを始めさまざまな物質資源が得られる。
植物は太陽光を吸収して高い効率で水から水素を取り出す能力をもっているし、微生物や植物は目的物質が超低濃度でも環境中から高い効率で吸収できる。人類はまだいずれの技術も利用可能なレベルまで開発しえていない。従って、光利用や物質吸収だけ取り上げても人類は無限に近い開発の目標をもっているといえる。
われわれの資源利用では未だに20世紀型の資源観が根強い。しかし、これからの資源利用では、21世紀型の新しい資源観への転換が喫緊の重要課題である。それが主力資源を20世紀の非再生型から21世紀の再生型へと切り替えていくことである。
参考文献 5‐1‐1(1)節
(1) 高橋正征.2008.希望をもって22世紀を迎えるために必要な「資源観」、資源テクノロジー,社団法人資源協会,309.
(2)経済性に公益性を加えた自然資源の資源観拡大の必要性
第2は、従来の狭い意味の経済価値の有無で自然資源をとらえるだけでなく、自然資源の持っている環境維持作用などの公益的価値の重要も加えて、私たちの資源観の幅を拡大する必要性である。
2000年の国際連合総会において当時のコフィ・アナン事務総長がおこなった「私たち人類:21世紀における国際連合の役割」という演説に応えるかたちで、国連環境計画(UNEP)を事務局として2001~2005年にミレニアム生態系評価が行われ、成果がWorld
Resources Institute(2005)として報告されている。その中で、自然資源は“生態系サービス”という考え方で捉えられていて、従来型の経済性だけでなく、新たに公益性が自然資源に加わっている。
経済性(供給サービス)としては、食料、淡水、木材、繊維、燃料、鉱物資源などのように、直接に人間生活に利用され、経済的価値を有しているもので、これらはこれまでの自然資源観と変わりない。一方、公益性(調整サービス、文化的サービス、基盤サービス)は、森林が人間活動によって放出した二酸化炭素を吸収したり、私たちが必要とする酸素を供給してくれたり、また海流による温暖な気候の維持(以上は調整サービス)、清々しい空気を呼吸したり、美しい景色を堪能したり、海・野・山でレクレーションを楽しんだり(以上は文化的サービス)、森林が土壌をつくる(基盤サービス)、といったような、経済的な直接価値は明確でないが社会にとって極めて重要なもので、従来は資源には入れられてこなかったものである。最近、公益性についても経済評価をする試みが始まってはいる(Hawkenら、1999)。かっこ内に示した“サービス”を、まとめて“生態系サービス”と呼び、自然資源を評価する際の国際的な認識になりつつある(図5‐1‐1参照)。
“生態系サービス”には、文字通り生態系を構成している生物と非生物環境が含まれていて、生態系とは直接関係していない石油・石炭・各種の地下鉱物資源は含まれていないが、自然資源を考える際にはそれらも含めて考えることをここでは提案しておく。
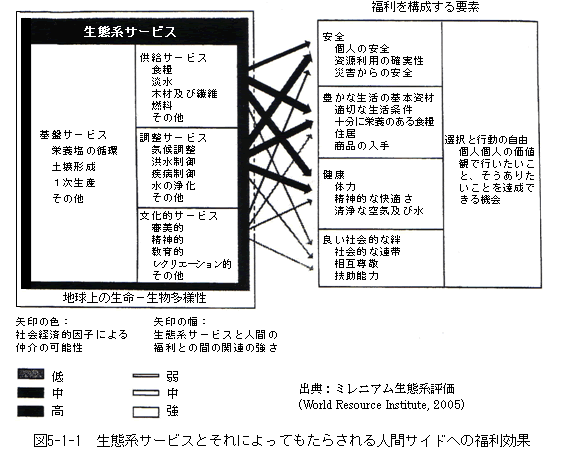
“生態系サービス”の考え方はConstanzaら(1997)によって提案された。彼らは、地球上の陸域と海の全面を生態系で区分して、それぞれの年間の生態系サービスを推定した。まとめた結果が表5‐1‐2である。生態系サービスとしては17項目を上げていて、その中で経済性のある供給サービスとしては食料生産、原材料、遺伝子資源があり、あとのほとんどが調整サービス、文化的サービス、基盤サービスといった公益性の高いものである。ただ、Constanzaら(1997)は、生態系サービスとしてひと括りにしていて、経済性と公益性の区分はしていない。また、Constanzaら(1997)は生態系サービスを1994年の面積あたりの米ドルで表示している。それぞれの生態系サービスをまとめて図示したのが、図5‐1‐2である。Constanzaら(1997)の生態系サービス概念は、最初の試みのために、サービス内容はごく一部しか取り上げられておらず、しかもその経済評価は必ずしも十分に検討されてはいないので、現状の図5‐1‐2の結果がひとり歩きするのはよろしくない。ただ、生態系サービスという考え方は斬新できわめて重要であるから、できるだけ早い段階で内容を詰めていく必要がある。
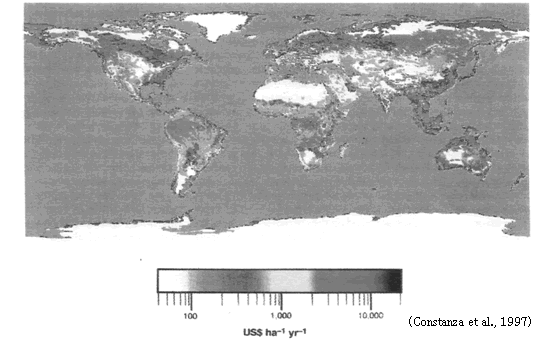
図5‐1‐2 世界各地の生態系で推定された生態系サービスの分布状況
その後、生態系サービスはミレニアム生態系評価によって着目項目が増え、細分化され、さらに包括的に整理されて、評価も説得力のある内容になってきた。しかしながら、生態系サービスはあまりにも規模が大きく内容が多様なために、その内容と評価はともにまだ完全ではない。今後の積極的な検討の継続が必要である。
以上のように生態系サービスは未完成ではあるが、従来の経済性だけに着目した自然資源の評価に公益性という画期的な価値を加えた点で高く評価される。生態系サービス的な資源観によって始めて自然資源の上手な利用に一歩近づくことができる。従来は、経済性だけが注目されたために、公益性の高い自然資源が安易に根こそぎ使われてしまったケースが多々ある。
例えば、沿岸の水産生物資源を増やすために、海底に山を築いて、潮汐などの流れを利用して、海底近くの栄養に富んだ海水を光のあたる表層付近に混合湧出させて生物生産を高めることが行われている5),6)。海底に山を造る材料として当初は産業廃棄物の石炭灰で作ったアッシュクリートが開発されて利用されたが、最近では天然の岩を切り出して利用している。アッシュクリートに比べて天然岩の方が安いというのが主な理由である。天然岩を切り出す石切場の生態系サービスが全く考慮されていないために、生態系サービスの消失による損失分が岩の価格に組み込まれていない。1基の海底の山を造るのに、数万m3の岩が使われるので、陸上にある小山が完全に消えてしまう。それと共に、岩を掘り出す小山の生態系サービスの公益性が消滅している7)。
長崎県佐世保市にあるハウステンボスをもう1つの例として紹介する。長崎県は工業団地の造成目的で大村湾の北端の浅瀬を埋め立てた。しかし、埋め立てが終了した時は既に高度経済成長を過ぎていて、しかも工業用水の確保が難しいこと、加えて地理的な弱点などがあって、工場の進出希望はまったくなく、埋立地は放置されていた。埋め立てに用いた資材に土壌が十分には含まれていなかったので、埋立地は草や木の生長もまばらで砂漠状態だった。こうした埋め立て荒れ地を、周辺と同じ草や木の生える環境(人々が生活する街)にして、観光客がたずねてくるリゾート地にすることを目指したのがハウステンボス計画である。そのために周辺と同じような生態系サービスを確保する目的で、埋め立て地に土壌を客土し、自然に生えているような樹木40万本を植えた。これに要した費用が約51億円、維持費が約20億円で、合計すると71億円になる(ハウステンボス環境研究会、2004)。埋め立て地のコンクリートの直立護岸も取り除いて、代わりに石積み護岸に替え、砂浜も造成した。これにも相当の費用負担があった。埋め立て地ではない周辺の土地にハウステンボスを造れば、現状復帰の71億円は必要なかった。もちろん、ハウステンボスの場合は、現状復帰して海に囲まれた魅力的な環境ができたので、意味はあったが、そのために必要な公益性の確保に大きな出費を必要とした。余談になるが、埋め立て地で周辺環境と同じような生態系サービスを得るためにハウステンボス株式会社は銀行から多額の借金をし、その返済が予定通りに進まなかったために会社更生法の適用を受けることとなり、いわゆる倒産した。生態系の公益サービスが社会的に認められ、それを担保に組み入れて計上できていればハウステンボス株式会社は倒産せずに済んだ可能性が高い。また、社会的に公益サービスの回復の意義が認められれば、人々が公益サービスの回復に強い関心を持つことにもなる。現状では自ら進んで公益サービスの回復をしようとする人や会社は出にくい。公益サービスの回復に対して果敢にチャレンジしたハウステンボス株式会社の倒産で、こうした試みをしようという人々の気持ちも大きく後退してしまった。
Constanzaら(1997)ならびにミレニアム生態系評価の生態系サービスでは地下資源は考慮されていないが、人間が使う自然資源のすべてを生態系サービスに入れておけば、1つでまとめて示すことができて便利である。地下資源は、生態系サービスとは直接には関係しないが、生態系の活動の営まれている空間の地下深くに埋蔵されているので、それぞれの該当場所の生態系サービスに含ませておくことができる。そのために表5‐1‐2の供給サービスの中に地下資源を加えた。
参考文献 5‐1‐1(2)節
(1) Costanza, R., R. d'Arge, R. de Groot, S. Farber, M. Grasso, B.
Hannon, K. Limburg, S. Naeem, R. V. O'Neill, J. Paruelo, R. G. Raskin,
P. Sutton and M. van den Belt. 1997. The value of the world's ecosystem
services and natural capital. Nature 387:253‐260.
(2) ハウステンボス環境研究会.2004.創造型環境会計の理論と実践;21世紀型環境会計.知新,10,123頁.
(3) Hawken, P., A. B. Lovins and L. H. Lovins. 1999. Natural capitalism‐
Crating the next industrial revolution. Spieler Agency. (佐和隆光(監訳)・小畑すぎ子(訳):ホーケン・ロビンス・ロビンス.自然資本の経済.日本経済新聞社、東京.2001.)
(4) World Resources Institute. 2005. Millennium ecosystem assessment.
Ecosystems and human well‐being: Synthesis, Island Press, Washington, D.
C.(横浜国立大学21世紀COE翻訳委員会(訳).2007.生態系サービスと人類の将来.オーム社,東京.241頁)
(5) 鈴木達雄.1999.石炭灰硬化体の開発と漁場施設への適用.水産工学、36:61‐69.
マリノフォーラム21社団法人.2001. 平成12年度マウンド漁場造成システム開発に関する報告書.99頁.
(6) 高橋正征.2008a.漁場環境を考える~海の水産生物資源を増やすには(前編).日本水産資源保護協会月報,508:3‐5.
(7) 高橋正征.2008b.漁場環境を考える~海の水産生物資源を増やすには(後編).日本水産資源保護協会月報、509:3‐8.
(3)ヒトと自然は対峙するものではなくヒトを含めた資源観の必要性
第3は、現行のわれわれの自然観では「ヒトを自然の外側においてしまう」、つまり自然とヒトを対峙させがちなことで生じてくる問題である。
一般に、われわれはヒトが手をつけていないものを「自然」と捉えがちである。そうなるとヒトは自然に自然の外側におかれてしまう。しかし、実際は、ヒトは自然の中で生活している。例えばヒトは植物が出した酸素を呼吸し、ヒトが出した二酸化炭素は植物が吸収して、ヒトと植物は切り離せない相互依存関係で繋がっている。また、ヒトが出した糞尿は汚水処理場で途中まで浄化され、自然界に出されると自然の水の循環によって浄化される。ヒトが食べる食物のほとんどすべてが、全部あるいは一部を自然の仕組みで作られている。つまり、ヒトは自然の一員で、切り離すことはできない。従って、ヒトは自然と対峙するのではなく、自然の中の構成員として扱わなくてはならない。
自然の中におけるヒトの生活現象を研究対象としているのが生態学であるが、既存の生態学ではヒトはせいぜい生物への影響要因としてしか見られておらず、ヒトの生活を対象とした生態学的研究はほとんどないといってよい。その点に着目して高橋(2001)は「「新しい」生態学」を提案した。「新しい」という形容詞は地球上でのヒトの生活を自然の生物と一緒に研究対象とすることを意味している。自然を人工の対極で捉えることを止めないと、ヒトを自然の一員として考えることは難しい。しかしながら、現実は「人工」と「自然」という捉え方が一般的なため、「人工」も「自然」の一部と考えることは簡単ではないが、以上に述べた理由から自然資源を考える際には努めてヒトも自然の一員と考える努力が必要である。
参考文献 5‐1‐1(3)節
(1)高橋正征.2001.「新しい」生態学~生きられる環境づくりの基礎.ビオシティ、東京、298頁.
(4)自然資源の徹底利用の必要性
20世紀型の資源が非再生型であったことに加えてもう1つの特徴は資源の単一目的利用で、これを第4の考慮点としたい。例えば、鉄鉱石からは主として鉄を取り出し、残りは捨ててしまうという利用の仕方である。だからごく微量の鉄に対して捨てる鉱滓の量は莫大である。そこで考えられているのは利用だけで、その他のことはせいぜい捨てることくらいである。従って、当初、鉱滓は精錬所のそばに野積みして放置されていたし、水で洗えるものは川に流されたり、地下浸透処分されていた。さすがに、20世紀の終りにはそうした野放図な資源利用は影を潜めたが、資源の単一利用目的は基本的にずっと続いている。
21世紀型の資源利用では、利用する部分だけでなく、廃棄物処理についても徹底管理する必要がある。そうなると廃棄物の多く出る資源利用は、廃棄物の処理で多額の経済負担を追うことになる。当然、資源価値をもった資源は変わってくる。つまり、廃棄物が出にくい、あるいは廃棄物が出ても処理が簡単で安くすむものが資源として価値が高くなる。太陽光、風、空気、淡水、海水、バイオマスなどが資源としての価値を高めることになる。これらの資源はどれも資源密度が低いので、資源を経済的に抽出する技術開発が大きな課題である。また、海水やバイオマスは、エネルギーや様々な物質資源を含んでいるので、限られた資源だけを利用しようとすると廃棄物が出るが、多次元的に完全利用すれば廃棄物は限りなくゼロになる。
以下に自然資源の多次元あるいは多段利用の例を3件紹介する。
第1の例は海洋深層水の資源利用である3)(図5‐1‐3参照)。図の例では、海洋深層水の冷熱を利用するために冷熱利用が周年期待できる亜熱帯から熱帯を想定し、水深600mから水温7℃の海洋深層水を日量100万トン揚水して利用例を考えている。まず、深層水の低温と温度の高い表層水の温度差を利用して2000kWの発電をし、9℃に昇温した海水95万トンで200万平メートルの床面積を空調し、5万トンは低温利用の農業・水産・食品工業などに回す。空調して14℃に昇温した海水で60万キロワットの火力発電機を冷却し、26℃に昇温した海水をハイテク産業・水産・農業・上水・温浴などに利用し、栄養塩類の残留している温海水は環境改善に使う。こうすることにより、排水される海洋深層水は清浄な表層水とほとんど同じ水質になっている。図5‐1‐3は海洋深層水の揚水量を始めとして、その後の深層水の利用内容や量は必要に応じていかようにも変えられる。この図は多段利用の1例に過ぎない。例えば、温度差発電と火力発電所の冷却を省けば、空調により多くの例熱エネルギーを回すことができ、空調面積は大きくなる。
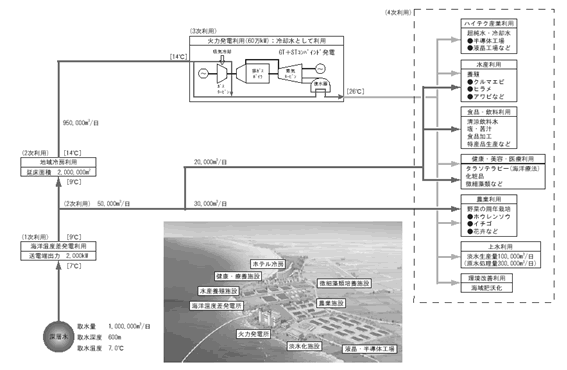
図5‐1‐3 亜熱帯・熱帯域における海洋深層水の多段利用による持続性を強化した資源利用の概念
海水からリチウム、ウラニウムを始めとしたさまざまな金属を取り出す場合には、金属吸着物質を塗布した粒子に海水を接触させて金属を吸着し、適宜塩酸などの酸で溶かして金属を取り出す。吸着は化学反応なので、水温は高いほど効率よく吸着は進む。この方法では廃棄物は全く出ないで済む。問題は吸着効率を高めることで、それが解決すれば21世紀は海水鉱山から必要とするほとんどの金属類を取り出すことが期待できる。
第2の例は、森林バイオマスである。1969年の推定だが、地球上の全バイオマスの92.3%が陸地の38.3%の面積を占めている森林にあり、生産力も森林が陸上生物生産の68.2%を占めている2)。従って、バイオマス利用では量が多く、生産性も高い森林のバイオマスをいかに利用していくかが鍵になる。その場合、20世紀の中頃までの建築・家具材や燃料とした単純なバイオマスの利用ではなく、21世紀型の新しいバイオマスの利用の工夫がポイントになる。
例えば、バイオマスを構成しているさまざまな単糖に分解して多次元的に利用する仕組みの確立である1)。図5‐1‐4に示したように、木材はセルロース、ヘミセルロース、リグニンを含んでいるが、それらを構成成分に分解すると用途が飛躍的に広がる。セルロースは単糖類のブドウ糖(グルコース)が繋がってできているので、セルロースを分解してブドウ糖にすると、バイオエタノールの原料として利用でき、最近問題となっているトウモロコシやサトウキビなどの食料や飼料と競合しなくなる。また、ブドウ糖は化学繊維やプラスチックの原料にもなる。現在、セルロースの分解は技術的に検討が進んでいるが、現状では費用的に直ちに事業化できるところにまでは達していない。技術開発の可能性は時間の問題と考えられている。ヘミセルロースは、グルコース・マンノース・キシロースといった3種類の単糖類で構成されているので、分離技術が確立すればそれぞれの単糖類を用いた高次利用が可能になる。同様に、カテコールなどの芳香族化合物で構成されているリグニンの分離ができれば高次利用の道が開ける。ヘミセルロースの分離技術は未だ道が遠い。リグニンにいたってはさらに困難と専門家は見ている。21世紀にどこまで技術が進むか興味深い。
木材は、最初は住宅や家具として利用し、その後、利用が済んで古材などになったら上述したような成分を分解して高次利用を図る。最後に残ったものがあれば燃やしてエネルギーを利用すればよい1)。また、図5‐1‐4の最後に入れた木炭は、火事さえ注意すれば生物影響を受けることなく、安定して永久保存ができるので、大気中の炭素固定剤としての利用が期待される。大気中の二酸化炭素の吸収固定としては極めて効果的だと思うがなぜか誰もチャレンジしていない。木炭を溜め込んでおけば、将来、炭素が必要になった際に資源として利用することもできる。ただ、木炭は火事の心配があるので、安全に貯蔵する工夫が必要であるが、それには例えば河川とか沿岸の水中に入れておけばよい。木炭の吸着効果を利用して水の浄化効果(四万十方式)も期待でき、単なる木炭の貯留効果だけでなく2次的効果も期待できる。
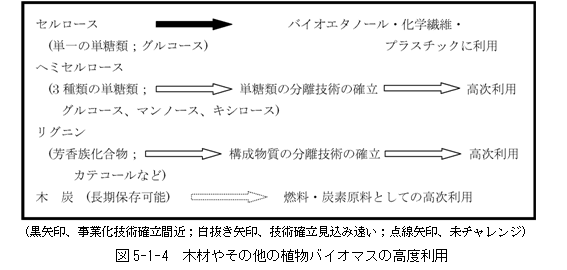
日本は、温帯多雨気候のために、西日本の平地は常緑広葉樹林、東日本と西日本の山地は落葉広葉樹林を極相とする森林が発達する環境である。森林面積も広く、森林のバイオマス資源の活発な利用は大いに期待がもたれるところである2)。
第3の例は、海産バイオマス資源のナンキョクオキアミの利用である。日本では以前に鯨の資源利用で肉はもちろんのこと皮や骨まで徹底利用した歴史をもっている。しかし、その後、水産生物資源利用では必要な部分だけ利用してあとは廃棄物として処理する方向がとられてきた。先にも述べたように、廃棄物は処理費用がかかるので、21世紀にはいわゆる「ゼロエミッション」型の生物資源利用が望まれる。吉富ら4)はナンキョクオキアミを対象として、食料、魚類養殖飼料、ファインケミカル素材抽出を組み合わせたゼロエミッションを目標にした多次元型の資源利用を提案している。上記3種類の資源利用ではまだゼロエミッションにはならないが、それを目指して資源利用を工夫する姿勢をもつことが重要である5)。
参考文献 5‐1‐1(4)節
(1)奥 彬.2005.バイオマス,誤解と希望.シリーズ地球と人間の環境を考える10.日本評論社,東京,215頁.
(2)高橋正征.2007a. 22世紀を目指した森林計画のあり方.森林計画学会誌 41:137‐142.
(3)高橋正征.2007b. 海水の資源で築く豊かな持続型社会.116‐123頁.黒潮圏科学の魅力(高橋正征・久保田賢・飯國芳明編著).ビオシティ,東京,165頁.
(4)吉富文司・大嶋俊一郎・高橋正征.2007.海産バイオマス(ナンキョクオキアミ,Euphausia
superba Dana)資源の多次元利用.黒潮圏科学 1:56‐71.
(5)高橋正征.2007c. 世界の漁業の運命,22世紀の水産業 第3.部 これからの水産資源利用の方向性~多次元利用,アクアネット,12月号,74‐73頁
5‐1‐2 自然資源の統合的管理の概念と取組の方向性
以上で述べたように、自然資源は、従来は狭い意味での経済性を中心として管理されてきた面があるが、今後は経済性と公益性の両面を視野に入れ、しかも当該自然資源だけでなく、関連するすべての自然資源を考慮して統合的に管理していくことが重要である。
(1)人間活動による自然資源への影響
増加した人口と豊かさの追求による個人の物欲の増大によって、人間活動によってもたらされる自然資源への影響は極めて大きくなっている。特に、食料、淡水、木材、繊維、燃料の需要が過去50年間急増し、それに対応するために人類は歴史上かってない速さで生態系を大規模に改変してきた。生態系に加えられた改変は、人間の経済発展には多くの利益をもたらしたが、反面で、多くの生態系サービスが劣化し、新たな変化を生み出す危険を増した。中でも、おびただしい数の種の絶滅を招いて、地球上の生命の多様性を不可逆的に大きく損ねたことは重大である。人間活動が原因となって起こっている種の絶滅は現在もとどまることなく続いている。地球上の種の絶滅の速度は、現状では化石年代に比べて1000倍以上速くなったといわれている。
また、地中海に面した8カ国で森林のもっている経済性と公益性を経済価値に置き換えて比較したところ、経済性(木材と燃料製品)は公益性(炭素固定、流域保全、非木材製品、レクレーションなど)の1/3にも満たないことが明らかになっている(World
Resource Institute, 2005)。公益性の経済評価は年々高まる傾向にあるので、経済性と公益性の差は将来もっと拡大することが予想される。
さらに、これらの経済性による自然資源の利用によって生じる問題を解決しておかないと、将来世代が得る利益が激減してしまう。特に、生態系サービスの劣化は今世紀前半にはさらに増大することが心配されていて、事態は緊急である。
1969年の集計(Whittaker and Likens, 1975)によれば、地球上の陸地の38.3%が森林で、その内訳は熱帯多雨林が11.4%、熱帯季節林が5.1%、温帯常緑樹林が3.4%、温帯落葉樹林が4.7%、北方針葉樹林が8.1%、疎林と低木林が5.7%を占めている(表5‐1‐2参照)。草地は16.1%で、その内訳はサバナが10.1%、温帯イネ科草原が6.0%である。砂漠・荒地の面積は33.6%で、これにはツンドラと高山荒原が5.4%、砂漠と半砂漠が12.1%、岩質及び砂質砂漠と氷原が16.1%含まれていて、都市は砂漠と半砂漠に分類されている。耕地は9.4%、沼沢・湿地と湖沼・河川がそれぞれ1.3%である。耕地のほとんどが元は森林、草地の一部も家畜の放牧のために本来は森林のところを人為的に草地にしていて、また、都市の多くは森林を伐採してつくられている。従って、これまでに人為的に伐採された森林を考えると、ヒトが手を加える前の陸地は半分以上の面積が森林で覆われていたことが容易に想像される。
表5‐1‐2 地球の陸域生態系のタイプとそれぞれの生態系の植物バイオマスの量と生産速度
| 生態系のタイプ | 面積 | 単あ位面積あたりの1次生産量 | 全1次生産量 | 単位面積あたりの生物量 | 全生物量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106km2 | % | g乾重・m-2・年-1 | 109t乾重・年-1 | kg乾重・m-2 | 109t乾重 | |
| 森林 | 57 | 38.3 | 1,250 | 79.9 | 29.9 | 1,703 |
| 草地 | 24 | 16.1 | 730 | 18.9 | 3.1 | 74 |
| 砂漠・荒地 | 50 | 33.6 | 56 | 2.8 | 0.4 | 17.9 |
| 耕地 | 14 | 9.4 | 650 | 9.1 | 1 | 14 |
| 沼沢・湿地 | 2 | 1.3 | 2,000 | 4 | 15 | 30 |
| 湖沼・河川 | 2 | 1.3 | 250 | 0.5 | 0.02 | 0.05 |
| 陸域合計 | 149 | 100 | 773 | 115 | 12.3 | 1,837 |
森林と農地・牧草地の占める割合は1969年にはそれぞれ38.3%と25.5%だったが、2000年には約30%と34%に逆転している。農地や牧草地が増えたのは、森林が伐採された結果で、食料などの生産は高まったが、森林は農地・牧草地に比べて平均して10倍以上のバイオマス資源量があり、さまざまな公益性をもっているから、森林を失ったことはこれらの公益性を失ったことになる。人口が増えると、食糧増産のためにより多くの農地や牧草地が必要となるので、さらに森林が伐採される。森林が持っている公益性の多くは定性的にしか理解されていないために、それらが失われることによって生態系、ひいては地球環境にもたらされる影響の評価は正確にはまだできないのが現状である。つまり、人口増加と個人の欲望の増大は、陸地の土地利用を自然状態から人間中心に一大変革してしまっていて、しかも、それがとどまるところなく現在も加速している。
土地利用の変化だけでなく、実際の利用でも人間活動は自然資源に対して大きな影響を与えている。例えば人口増加による食糧増産は、地球上での肥料と農薬の使用量の増大につながる。
肥料の内、窒素は空中窒素から人工的にアンモニアを合成して、それらを農地に撒くので窒素肥料汚染を加速する。世界で1年間に撒かれる窒素肥料は今や1億トンNを越えるようになり、地球上の自然の窒素固定量を超えてしまったと考えられている。ヒトは人工的に窒素固定して肥料を作るだけで、脱窒は自然任せである。自然の脱窒は自然に起こる窒素固定が対象で、人工的に合成された窒素化合物まで手が回っているとはとても考えられない。ということは、肥料は脱窒されないで世界中の農業地域を中心にして地表に溜まり続けていることになる。世界各地の窒素肥料汚染がそれを裏付けている。特に、農業地域を中心に、先進国も途上国も窒素肥料汚染が加速している。いわゆる硝酸態窒素(NO3)の濃度の上昇である。
肥料として農地に撒かれているリンの方は、リン鉱石などを掘りだして使用するので、リン鉱石資源の枯渇問題を生む。米国ではかなり前からリンの国外への輸出を禁じている。リン肥料の多くは鳥の糞の堆積でできたグアノを掘って供給されてきた。赤道直下のナウル共和国はリンの採掘権で得られる収益で国は大変豊かであったが、20世紀の終わりはリンを掘り尽くしてしまった。豊かだった時にリンがなくなった時の収益事業をうまく育てられなかったために国全体が貧困問題に直面している。
それ以上に、世界のリンの供給を見ると、肥料としてリンの利用できる時間の余裕はそんなに長くはなさそうである。そのために現行の、多肥料型農作物ではなく、少肥料型農作物を開発する努力を速やかに始めるべきだと思われるが、日本ではその気配すら感じられない。新しい品種の開発には長い時間がかかり、特に多肥料型から少肥料型のような、対象とする性質がこれまでとは全く異なる作物の開発には新たなアプローチの工夫が必要となる。
19世紀にドイツのリービッヒが提唱した化学肥料を利用する施肥型農業は、それまでの自然農法に比べて農業生産性を飛躍的に高め、同時に農作業労働を軽くし、食料が安定供給され社会の安定に大きく貢献した。しかし、皮肉なことにそれが人口増加の根本原因にもなった。特に、第2次世界大戦後に工夫された多くの多収穫品種の開発と途上国を含めた普及は、「緑の革命」として称えられノーベル賞の受賞にもつながる評価を受けた。しかし、多収穫品種は多量の肥料を要求し、同時に病虫害に弱いために多くの農薬を大量に撒く必要があった。新しい多収穫品種の開発後しばらくは病虫害の影響をあまり受けないので、次々と多収穫品種を改良して用いるというイタチごっこの病虫害対策がとられた。しかし、ここ20年間は新しい品種の開発はほとんどない。専門家の間では、品種開発はやりつくされて、更なる新たな品種開発の可能性はもはや困難で、今後は全く新しい作物を見出して始めからやり直すしかないとも言われているくらいである。
また、農地から流出した肥料が河川・地下水・湖沼・沿岸域に流れ込んで富栄養化、貧酸素、赤潮・青潮などの新たな問題を起こし、自然の生態系サービスの質を低下させている。農薬も、当然のことながら農薬汚染を加速・深刻化し、自然資源を劣化している。
最近、長年かかって集められたFAOの漁業統計などに基づいて今後の有用水産生物の資源供給能力が評価された。それによれば、現状の漁業活動を続けていくと、2050年までに有用水産生物の90%以上が漁業活動の対象にならないくらいに資源量が激減してしまうことが指摘されている(Worm
et al., 2006;高橋、2007)。論文では、直ちに漁業活動に抜本的な工夫をすれば予想される事態は回避できる可能性があると述べられているが、当面考えられていることは、大幅な漁業制限で、それは容易ではない。その背景には、過去の漁業を行いながらの漁獲調整は、そのほとんどが不成功に終わっていて、唯一、世界各地で成功しているのが海域や時間を決めて完全に漁業活動を中止することがあるからだ。
漁業に関して付け加えるならば、従来の漁業の工夫は新しい水産生物資源の開発・資源探査・資源集約・資源捕獲の技術で、資源を新たに増産する試みは世界中でほとんど行われてこなかったといっても過言ではない。
最近の地球温暖化の進行で、海でも海水の温度が上がって海の砂漠化が広がっていることが地球観測で明らかになってきた。1998~2000年の9年間で、赤道をはさんだ南北太平洋・大西洋で両海洋の20%が砂漠化したという。砂漠化は生物生産性を低下させるので水産生物資源の生産も低下し、漁業活動に加えて水産生物資源への影響が出る。
こうした中で日本では、1900年代後半から自然海域での水産生物資源の増産に向けた積極的な取組が行われている。基本概念は栄養塩類を多く含んでいる真光層以深の海水を真光層内へ混合湧昇させて生態系の1次生産を増産し、引き続く高次栄養段階の生産を増やしていこうというものである。200m以浅の大陸棚までの浅海域では人工的に海底に山を築いて、潮汐などの自然の力を利用して湧昇させることが事業として進んでいる(鈴木、1999)。200m以深の大水深では、200mより深い層から富栄養な海洋深層水を人工的に揚水し、表層水と混合して密度調節して真光層へ密度流放流する方式が試みられている(高橋、2008a,b)。
参考文献 5‐1‐2(1)節
(1) Whittaker, R. H. and G. E. Likens. 1975. The biosphere and man.
305‐328pp. In Primary Productivity of the Biosphere (eds. H. Lieth and
R. H. Whittaker), Springer, New York, 339pp.
(2) Worm, B., E. B. Barber, N. Beaumont, J. E. Duffy, C. Folke,
B. S. Halpern, J. B. C. Jackson, H. K. Lotze, F. Micheli, S. R. Palumbi,
E. Sala, K. A. Selkoe, J. J. Stachowicz and R. Watson. 2006. Impacts
of biodiversity loss on ocean ecosystem services. Science 314:787‐790.
(3) 高橋正征.2007.世界の漁業の運命,22世紀の水産業 第3.部 水産業の未来に向けて,アクアネット,1月号,82‐83頁
(2)自然資源の統合的管理の緊急性
従来は、経済性のある資源が注目されてきたので、自然資源の管理も必然的に利用対象となる資源について行われてきた。再生の速やかな自然資源は、資源が枯渇しないように再生速度をにらみながらの資源管理であり、再生速度の極端に遅い資源は無駄のない資源採掘利用が望まれた。しかし、先に述べたように、自然資源の経済性だけでなく、公益性も注目されるようになると、従来型の資源管理では不十分になった。
1994年にカナダのブリティッシュ・コロンビア大学の大学院生だったWackernagelはRee教授の指導の下で進めた博士論文研究でエコロジカル・フットプリント(Ecological
footprint)という新しい概念を提出した(Wackernagel, 1994;Wackernagel and Rees.
1996)。具体的には、人類が地球に与えるさまざまな「環境負荷」を「人が生きるために必要とする土地面積」で表したもので、食糧生産、資源の消費、廃棄物の発生などの人の生活で必要としている再生可能な自然資源の利用を必要とする土地面積(ha)で表している。もう少し詳しく解説すると、「特定の国を考えた場合、その国で人々が消費するすべての資源の生産ならびに、排出されるすべての廃棄物の処理を生物生産に換算して、そのために必要な自然の面積」を求め、それを「世界の平均生産力の土地面積」と比較したものである。世界の平均生産力は、農地・牧草地・森林・海に分けてそれぞれの平均的生産力を求め、地球上での面積を乗じてから、地球の全面積で除して求めている。例えば、10tのオレンジジュースでは、オレンジ果実が50t必要で、それを栽培するために2.8haの農地が必要という計算になる。物品や人々の輸送に使われる化石燃料では、排出した二酸化炭素の吸収に必要な森林面積を使う。この概念を利用すると、先に述べた自然資源の経済性と公益性の両者を取りこんだ自然資源の管理が可能になる。
ちなみに日本の現在のエコロジカル・フットプリントは146ヵ国中27位の4.4ha/人、1~3位は中東の産油国でアラブ首長国連邦は11.9ha/人、米国は9.5ha/人、中国は1.5ha/人で、124位のインドは0.8ha/人、144位のアフガニスタンは0.2ha/人である。土地面積で表した現在の地球の全生産力を、約60億人の世界人口で除すと2.13ha/人になる。これを基準とすると、世界中の人が日本人と同じ生活をした場合は地球が2.0個、米国人では4.5個必要になる。既に地球上の人々の要求は地球が日常的に支えられる限界を20%超えて、フットプリントは拡大する一方である。ということは、地球の持っている自然資源の資産部分を食いつぶしていることにもなり、人類の将来の安心・安全な生活のためには速やかに統合的管理を始めなければならない喫緊状態である。
エコロジカル・フットプリントは厳密性ではいろいろと問題をもっているが、地球全体を視野に入れた概念としては、極めてわかりやすいメッセージ性や個人レベルでも算定できる手軽さなどから、評価が高い。
図5‐1‐4は、エコロジカルフットプリントは人類による再生可能な自然資源の使用を測定したものである。1961年から1999年の間で80%増加しており、地球の生物学的限界を20%上回っている。エコロジカルフットプリントは地球何個分という形で表され、地球1個分とはどの年であれ生物学的生産能力の合計とイコールである。自然資源の消費は、自然の資産を食いつぶすことで地球の生産能力を超えることができるが、無限に持続できるわけではない。(WWFJapan,URL)
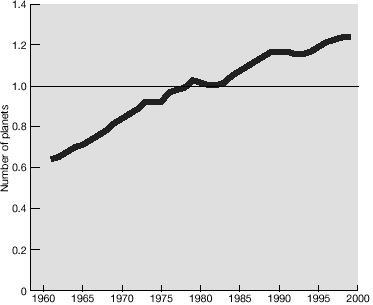
図5‐1‐4 エコロジカルフットプリントによる自然資源の使用試算
参考文献 5‐1‐2(2)節
(1) Wackernagel, M. 1994. Ecological footprint and appropriated carrying
capacity: A tool for planning toward sustainability. Ph.D. Thesis, School
of Community and Regional Planning. The University of British Columbia, Vancouver,
Canada.
(2) Wackernagel, M. and W. Rees. 1996. Our ecological footprint: Reducing
human impact on the earth. New Society Press.
(3)自然資源の統合的管理を支えるための社会システム
先に述べたエコロジカル・フットプリントによれば、人類による地球の再生可能な自然資源の利用は、地球が支えきれる限界を超え、しかも現在も着実に増え続けている。つまり、人類による自然資源の過剰利用によって、地球全体として自然資源の再生力を徐々に失いつつあり、それが加速していることになる。貯金で言えば元本を食い始め、日増しに元本の引き出しが増えていることになり、これではやがて破産してしまう。
この問題に対して、筆者(高橋正征)は次のように考えている。
こうした現状を認識して統合的自然資源管理を考えると、人類による自然資源の利用を早急に抑えていく必要がある。その場合、1.個人の物欲の抑制と、2.人口増加を止めて人口を適正規模に収斂させる、といった2つの努力の方向がある。両者をともに考えるのが理想であるが、実際はそんなに簡単ではない。個人の物欲の抑制は、現在の世界の多くの国々で人々が最も関心を持っている豊かさを追求することをやめることになり、それは人々が希望を失うことにつながる。従って個人の物欲を抑制するためには、豊かさに変わる人々の生きる希望・目標を見出して育てる必要がある。これは地球と人類の将来にとってはとても重要なことであるが、残念ながらまだ皆目見えてきていないのが現状で、そうした状況下での物欲の抑制は難しい。
そこで、ここではもう1つの人口対策の可能性を考えてみることにする。社会的には“人口減少”を避けたいという風潮がある。しかし、人口減少をくい止める努力だけでは人口問題の本質的な解決にはならない。ここでは“人口減少を止める”のではなく、この機会に“適正人口”を真剣に考え始めることを提案したい。そうすれば、人口の減少を止めようといった単純な考え方に気づき、人口問題をより本質的に解決しようという考え方が生まれてくると思う。適正人口を考えるにあたって何の制約も与えないと目的達成が難しいので、ここでは条件を2つ入れる。第1条件は“食糧の自給”である。というのは、この条件を入れないと、適正人口を考えることが極めて困難になり、また、入れることによって適正人口が論理的に求められる。また、それ以上に、地球環境の維持にとって重要な“物質循環”を正常に維持する上で決定的である。
物質循環の維持の重要性についてもう少し詳しく説明する。人口が多くなると当然のことだがより多くの食料が必要となるので、どうしても食料は遠隔地からも運び込まなければならない。食料の、野菜・果物や穀物は農地で栽培され、そこでは土壌中から窒素・リン・カリウム・カルシウム・マグネシウム・鉄・・・などの30種類近い元素を吸収して育ち、葉・実をつけ、それを人が食物として利用する。野菜・果物・穀物を利用するということは、農地から農作物に取りこまれたさまざまな物質を食料のかたちで人が消費地で利用することに他ならない。食料が生産地から遠くに運ばれてしまうと、農地からとられた物質は食べられた後で元の農地に戻ることができない。そのために農地からは物質が失われ、土地は痩せていく。農地の肥料不足の一部は施肥で補われるが、窒素・リン・カリウム以外は肥料として撒かれないので、それらの物質は農地から永久に失われてしまう。一方、消費地では、食べた結果、出された排泄物と共に物質は周辺の環境中に出されて富栄養化あるいは過栄養化といった問題を起こす。従って、食料を一定以上の距離を越えて移送すると、生産地では農地が疲弊し、消費地では環境中の栄養物質の過剰問題が起こり、生産地も消費地も共に物質循環が滞ることになる。
そこで、物質循環を正常に維持するには食料の長距離輸送をできるだけ避けることが肝要になる。万一、食料を長距離輸送した場合には排泄物を生産地に戻す覚悟が必要だ。正常な物質循環の維持にはどの程度の広さを考えたらいいのかその答えは難しいが、仏教で古くから言われている「身土不二」(身と土とは分けられない)が参考になる。これは明治30年代に当時の陸軍の薬剤監であった石塚左玄らが起こした「食養生運動」のスローガンとして「身の三里四方」または「身の四里四方」という日本語に翻訳された(山下、1998)。つまり3里もしくは4里、すなわち「12kmまたは16km四方から食物を得て、生活していれば(排泄物は当然に12kmまたは16km四方内に出す)自身は健康で、環境も正常に維持される」という内容である。中国で長い農業の歴史から悟った教訓である。以上を考えると、人口問題の解決のための自給率を考える場合は、国単位では広すぎる。身の三里または四里四方の考え方と各種の社会関連データの集計単位から、市町村を単位とするのが適当である。
市町村で食料を自給するとなると、食材の種類は著しく少なくなってしまう。それを我慢しようとすると、食料自給に対して人々の気持ちが批判的になってしまう恐れがある。従って、市町村での食料自給はあくまでも基本的な姿勢として考えることで、たまにはよそで取れた食材を楽しむゆとりが必要だ。また、食材の主産地に出かけていって、産地で、その土地の調理法で日頃食べられない食材を楽しむことも重要である。要は、現在の日本で一般的になっているあらゆる土地の食材を身の回りに取り寄せて食べるという習慣を根本から見直し変えることである。
先の考え方に基づいて、井上・高橋(2007)は市町村を単位とする“地域食料自給率”という新しい概念を提案した。こうすることによって、正常な物質循環の維持を心掛けると共に、食料供給が突然に支障をきたすような場合に被害を最小限にでき、周辺からの支援も容易になるといったメリットが生まれる。ただし、これはあくまでも考え方の基礎で、東京や大阪を始めとして、県庁所在地のような人口の集中している都市では、市内での完全な食料自給は不可能になるので、それへの対応が必要だ。その場合は、地域で食料の自給ができない程の人口集中の必要性を訴え、食料自給に余裕のある他の市町村からの支援を取り付ける。二酸化炭素の排出権取引と同じ考え方である。人口集中の必要性を皆が納得すれば、全国的に存在を支える動きを作り出すことができる。その場合、果たして数100万人とか1000万人といった巨大な人口集中が本当に必要かどうかも真剣に考えることが重要だ。ドイツのように100万人程度の都市を国内に散らばらせるという方法もある。
“地域食料自給率”の向上(つまり本当の意味の地産地消)で障害になっている問題のひとつが、マーケッティングのグローバリズムである。日本の魚介類の消費の筆頭はマグロ・サケ・エビで、これはスーパーマーケットが流通のやりやすさと人々の嗜好の両面からとった流通戦略である。そのために、魚介類の地産地消が著しく損なわれてしまっている。本来は食材の多様性を高めるはずだったグローバリズムが、食材の多様性を著しく低下させていることは皮肉である。また、同時にスーパーマーケットのような大型店では地元産の食材の扱いが一時期激減した。最近は地元産のコーナーなどが設けられて地域産の活路ができてきたことは喜ばしい。
食料自給の重要性を、地球環境の維持で決定的な物質循環の維持の視点で論じたが、無駄な自然資源の利用を避ける意味でも必要である。これには“フードマイレージ”と呼ばれる最近になって提唱されている概念が有効である。食材の重さに輸送距離を乗じて数値化(t・km)して表す。フードマイレージを表示すれば、消費者はより近場で生産された食品を選択することができる。いわゆる地産・地消である。にほんのフードマイレージは9000億t・kmと試算されていて、これは1690万tの二酸化炭素排出量に相当し、これは日本国内の年間の食品だけでなくすべての貨物の輸送量の何と約1.6倍にもなる。農業国フランスの9倍、イギリスの5倍である。
第2条件として、住民の意志を入れて地域の適正人口をはじき出す。市町村程度の広さにすると適正人口も考え易い。広い空間でゆったりと過ごしたいと考えるヒトが多ければ、人口は少なくなり、また多くの人々と暮らしたいヒトが多ければ人口は多くなる。人口が少ないと1人当たりの社会的な費用負担は多くなる可能性があるので、生活費は高くなるかもしれない。やってみないとわからない問題も多い。また、人々の考え方は時代によっても変わるから、10年とか数10年といった時間単位で、地域の人々にとっての適正人口をやり直して考えるチャンスをもってみる。こうした試行錯誤をしていくことによって、先の自給率向上や、人口の大きさのもつ意味を皆が理解していくようになると思う。当初はこうしたことを人々が日常的に考えるような習慣作りに努めることで、そうした努力の中からさまざまな工夫も生まれてくる。早急に目標を決めてそれに向かって努力するといった行動は避けなければならない。
各地域の適正人口を合計した国の人口が国の適正人口ということになる。ある程度、国の適正人口の方向が固まってきたならば、それを視野に入れて、実際の人口が適正人口からずれている場合には、いかにして適正人口に近づけていくかを真剣に考えることになる。目標は100年、200年先の話にはなるが、目標年度を一応定めて、それに向けてどういった無理のない方法で人口を収斂させていくかを考えてみる。
人口問題は日本だけでなく世界中のすべての国々にとって共通の深刻な問題である。ただ、多くの国々は宗教と人種及び民族問題を抱えていて、人口問題を真正面から取り扱うことが難しい。幸い、日本は、他の国々に比べると宗教と人種・民族問題が少なく、人口問題を直接に考えられる極めて数少ない国の1つである。その日本で、「食料の自給」と「市町村規模の単位での住民の意思による適正人口の提案」の2つで人口問題を考えていく行き方が軌動に乗れば、それは世界の範となる可能性が高い。
先に述べた、人口の減少を避けたいという単純な考え方が残念ながら現在の日本のリーダーたちの考え方である。彼らの心配は、年齢構成のバランスの崩れることのようだ。つまり、年寄りが多くなって若者が少なくなってしまう現象である。これは過渡期には仕方のないことで、そうした年齢構成のバランスの崩れの影響をいかにして最少にするかということをこそ真剣に考えるべきだと思う。例えば、社会が年金受給者の割合が増えて、働き手の負担が過重になるというが、年をとっても元気で働ける人には、楽しく働く環境を作って働いてもらえばいい4)。それは、単純に定年年齢を伸ばすことではなく、定年後は、第2の人生で新しいことにチャレンジするという認識がもっと社会で一般化しても良いと思う。
参考文献 5‐1‐2(3)節
(1) 井上修介・高橋正征.2007.地域の食料自給率の重要性と高知県室戸市における魚介類の地域食料自給率の推定.黒潮圏科学 1:1‐16.
(2) 高橋正征.2007.地産地消を考える,22世紀の水産業 第3.部 水産業の未来に向けて,アクアネット,9月号,70‐71頁
(3) 山下惣一.1998. 身土不二の探求.創森社,東京.234頁.
(4) 高橋正征.1996.第二の人生を楽しむ.生涯フォーラム.社団法人社会教育協会,
No.1161:35.
(4)自然資源の統合的管理に必要なソフト資源のあり方
自然資源の中でも、石油・石炭・鉱物資源などは再生速度が極めて遅いので、利用していった場合には“遺産の食い潰し”になるが、バイオマス・水・空気・太陽光などは再生量や供給量を考慮して利用していくことによって持続的な利用が可能になる。バイオマスに対しては、最大の生産速度を維持するような管理も工夫できる。
ただ、最近の日本では1次産業である自然資源の利用の技術継承が必ずしもスムーズではない。農業・林業・漁業・狩猟などの歴史的な技術を持っている人がいなくなって、そうした技術が急速に失われている。技術は一旦失われると、復活することはほとんど不可能である。現在残っている技術を早急に洗い出して、その技術継承を工夫することが喫緊の課題である。現金経済の発達した現在の日本では、これらの伝統技術を継承して生業としていくことは困難なものがほとんどだから、関心を持った人がパートあるいは趣味で技術を継承していくことなどの工夫が必要である。
特に、自然資源の持続型利用にとっては、伝統的な利用法を基礎にすることが極めて重要である。例えば高知県室戸市には室戸岬の東側海岸に沿って、南から高岡、三津、椎名、佐喜浜の4つの大型定置網が数km間隔で設置されていて、明治の初め頃から100年余にわたって定置網を主力産業として各集落で数100人規模の人々が生活してきた。それぞれの定置網は50人規模で毎日作業が行われているが、急増した現金収入増に対応できないために、若者の就業が無く、今では60才を最年少にした年齢構成になってしまっている。従って、もう10年もしない内に大型定置網は就労者のいない状態になって消滅してしまう状況だ1)。定置網は、地先の魚類の捕獲法としては極めて優れていて、持続型漁業の筆頭にあげられる優良漁法である。かつての日本に存在していた地元の“魚介類が一番”と尊ぶ状況が復活すれば、よそからわざわざマグロ・サケ・エビを取り寄せないでも、地元の(つまり定置網で獲ったような)水産物を中心に利用する生活が復活する。伝統技術がまだ息絶えないでいるうちにそれらを継承していく努力が、自然資源の理想的な利用を目指す意味でも現代の私たちの喫緊の課題である。
参考文献 5‐1‐2(4)節
(1)高橋正征.2007.機械化で明暗を分けた室戸と知床の定置網漁業.22世紀の水産業 第3.部 水産業の未来に向けて,アクアネット,5月号,74‐75頁.
5‐1‐3 自然資源の変化に即応できる社会能力
農村には農地や多様な生態系そして農村景観などの地域に固有の自然資源があり、農業者など地域住民の共同的な活動によってそれが維持保全されてきた。しかし近年、都市部を中心とした産業の集積と高度化等が進行するなかで農村人口特に若年層や働き手の流出が続き、それに伴って農村地域における活力や地域資源の維持管理能力の低下といった事態が見られるようになった。他方、ゆとりや安らぎを求めるような国民の価値観の変化や環境保全に対する関心の高まりが、豊かな自然資源に恵まれた農村地域での生産及び社会活動を、その多面的機能を十分に活かした環境保全をより重視したものに転換させることを要望している。平成19年度から実施される「農地・水・環境保全向上対策」はこのような要望に応えるものであろうが、人口減少局面への移行、団塊世代の大量定年退職などの社会構造の変化、あるいは都市住民のふるさと暮らし志向の高まりなども踏まえ、都市と農村との交流の一層の活発化への配慮もまた求められよう。
農林水産省が行った市町村の農政担当者を対象としたアンケート調査1)によれば、全体の6割の市町村が「農村には以前よりは活力が無い」と解答している。また、これらの市町村が期待する地域活性化対策としては、人材育成、雇用機会の確保、地域特産品の開発などが挙げられているし、地域が活性化している市町村ではその要因として産直の実施やリーダーの存在などが挙げられている。このように地域の活性化には、農業と関連産業や異業種との連携、地域特産品等の開発、そしてリーダーの確保が鍵を握っていると見られるが、様々な資源が存在する農村では、人材を確保して自らの主体性と工夫とによってその活用を図ることが望まれるのである。また都市住民には、「農産物直売所での農産物の購入」、「観光農園の利用」、「農山村の風景を楽しむ」など、農村の景観や自然、季節性や地域色豊かな料理や産物に強い関心がもたれている2)。農山漁村の良好な景観の形成・維持を積極的に図るため、地方公共団体景観農業振興地域計画や景観計画などの策定への取組みを促進すべく、平成16年(2004年)12月には「景観法」が施行されたが、地域の人々の主体的な取組みを通じて、地域資源を活かした都市農村の交流を促進し、地域の活性化を図ってゆくことが重要であろう。
現在、地域活性化に取り組む活動主体の多くは市町村と第3セクターであり、集落や農林漁業者のグループ等の組織もその一翼を担っているといわれるが、その活動を支えるための行政の支援、例えば人材や資金の確保、施設整備への助成等が重要な役割を果たしているのが実態であり、財団法人日本農業土木総合研究所の調査3)によると、都市農村交流活動を行う団体の48%が行政との連携の必要を強調している。他方、内閣府の「地域再生に関する特別世論調査」(平成17年9月)によると、地域活性化の活動主体として「住民一人一人」とするものが最も多く、住民の地域活性化活動への参加意識はかなり高いといえようが、農林水産省「農林業センサス」(平成12年)の結果は、地域活性化活動の中核的な役割が女性や高齢者によって担われていることを明らかにしており、農村における社会構造の実態が示されているといえよう。
近年、農村では女性による起業数が増加傾向にあり、その7割はグループ経営であるが、個人経営の比率も次第に高まってきているという。このような女性の起業活動は、農村での所得拡大のみならず、社会参画を更に進める契機ともなっている。また、農業経験のある高齢者に対しては、地域問題についての相談役、地域の文化や伝統の継承者等としての役割が期待されているのみならず、女性とともに生産・加工・販売などの活動に加わっている。若年層の流出などの農村社会構造に変化に対応した活動様式が定着しつつあるとも言えよう。
このような農村地域での生産活動や社会活動の新たな展開は、交通手段や各種メデイアの発達によって促進されている。しかし、立地条件による差異の存在は否定し難く、生活基盤や情報通信基盤の整備によってその格差を縮める努力が求められるとともに、都市農村間など地域間の人・もの・情報などの交流をより活発にすることが重要であろう。
5‐1‐4 地域社会の統合的管理
高齢化の進展は全国的にも生産年齢人口比率の低下をもたらしているが、農山村地域での低下傾向は都市圏に先行して進んでおり、特にいわゆる「全部山村」4)では人口減少率も高く、2030年の生産年齢人口の割合は50%を下回り、65歳以上の老齢人口は40%を超えると予測され、集落機能の低下や不在村者保有森林の増加が一層進行するものと懸念されている。一方では中高年層を中心としたいわゆるUターン率も高まっているし、Uターン者を受け入れた市町村を対象とした調査5)の結果からは、それぞれの地域がUターン者に農林水産業の担い手や地域づくりのリーダーなどとしての役割を担ってもらうことを期待しているものと考えられる。また「農林業センサス付帯調査
農村集落調査」(2005年)の結果によると、過去5年間に農業集落内に転入したもののいる集落数は全体の57%、農作業に従事する転入者のいる集落の割合は49%となっている。更に、転入者のいる集落の方が地域活性化の諸活動がより活発に行われているともいわれ、集落活動の活性化にUターン者が深く関わっていると考えられる。他方、大都市圏でも20歳代から60歳代までの幅広い年齢層の4割が「ふるさと暮らし」を志向しているといわれ、特に50歳以上層の過半数は「農村での悠々自適の生活」を望んでいるという。また、都市住民の中には、都市と農村とにそれぞれ住居を設けて往き来をする2地域居住に対する関心が高まっているともいわれている。
しかし、「ふるさと暮らし」を現実のものとするためには、居住のための条件、例えば土地や家屋の入手可能性や医療機関の整備状況などについて情報提供に、地元が如何に配慮するかが重要であろう。農村地域での生活環境施設の整備は着実に進んでいるといわれているが、汚水処理施設など一部に整備が遅れている面もある。農村地域の特徴を活かした快適な生活環境を都市住民に提供するためには、遅れた生活環境施設に対する投資を先行させなければならないという問題もあろう。しかし何れにしても、農村地域の特色すなわち都市では得られないものが都市住民によって魅力とされるならば、その特色あるいは魅力的なものを知ってもらうことが重要であろう。またそれとともに、田舎暮らしの現実の厳しい面も理解してもらう必要があろう。そのためには諸々の情報提供が先行しなくてはならないし、人々の交流に先立つ情報の交流に工夫がなくてはならないであろう。
これらの情報交流は、地域外からの参入者が新たな魅力ある地域作りにその社会経験や知識を活かすための必要条件でもある。魅力的な地域を創出するためには、農村集落の一員として生産活動や社会活動の一翼を担うべき新たな参入者が、自らの経験や知識を活かすべき場を考えることも必要であろうし、それが自らの経験や能力を地元の人々に理解してもらう契機ともなろう。
地域の活性化には、上述のように、地域資源活用のための人材及びその組織化がなくてはならないが、それは地域に賦存する如何なる資源を如何に活用すべきかの具体的な計画を伴ったものとなろう。勿論、それぞれの地域にはそれぞれ特有な問題があり、また行政的に進められている市町村合併などによって新たにもたらされた問題
‐ 施策の重点化などがもたらす地域間格差の拡大、集落組織などと行政との心理的距離の増大、等
‐ に対する懸念もあるが、それぞれの地域の特色ある資源を活かして地域のブランド化を図るような、それぞれの地域特有の工夫があり得るに違いない。しかし、現在わが国の農村でほぼ共通する問題として重視しなければならないのは、先ず農地利用率の低下傾向を如何にして押さえ込み、土地資源の活用化を図るかということではなかろうか。
過去における種々な投資によって生産力を高めてきた水田は、現在需要の減退や労働力不足等の理由によって遊休化が進んでいる。高度な栽培技術を体得して長年稲作に従事してきた農民には、良質米の生産からの転換は必ずしも容易なことではないかもしれないが、情報の収集や新たな人材の確保によって、需要拡大が見込まれる商品、特に関連産業部門での需要に対応する商品の生産拡大を志向することも必要であろう。最近、バイオ燃料の需要増大を契機とするトウモロコシなど穀類価格の高騰が、穀類需要の食料と燃料との競合として問題となっている。環境に優しいといわれるバイオ燃料に対する需要の拡大が石油価格の高騰によって後押しされているためであるが、その環境に優しいというバイオエタノール生産技術の新たな開発(従来のものに比べて生産性が4倍にも高められたという6))は、稲わらや間伐材を原料にしたエタノール製造事業の拡大強化につながるものと考えられる。
何れにしても、新たな人材や組織、そして新たな技術を導入することによって、遊休化した農村地域の土地資源の活用と地域経済の活性化を図ることが、今求められているのである。その為には、農業の活性化・競争力強化には意欲ある優秀な農家への農地の集中・大規模化、そしてコスト削減を可能にする仕組み作りが不可欠であろう。わが国農家の77%は兼業農家である。その多くは機械化が進んだ米作りに携わっている。農業以外に安定収入を確保しながら、農業を続けることによって農地の相続税の優遇を受けることができる。経済的理由から農地を売却せざるを得ない状況にある農家は殆どないであろう。また、郊外型店舗や公共事業などへの転売期待なども農地としての規模拡大を妨げている。1970年の農地法改正や1993年の農業経営基盤強化促進法なども、農地の流動化・集積に大きな効果があったとは言えない。日本農業の競争力強化には、法的措置も含めて農地問題の解決に取り組む必要があろう。
参考文献 5‐1‐3~5‐1‐4節
(1) 農林水産省「食と農、多面的機能の発揮等に関する調査」(平成15年3月)
(2) 〈財〉都市農山漁村交流活性化機構「都市住民のニーズ把握定量調査」,(平成15年3月)
(3) 〈財〉日本農業土木総合研究所「都市と農村の共生対流に関する検討調査」,(平成16年3月)
(4) 市町村全域が「山村振興法」により「振興山村」に指定されている区域
(5) 国土交通省「中高年者のUJIターンに対する意識調査」
(6) 日本経済新聞 2007年9月7日
5‐2 自然資源の統合的管理に必要なソフト資源のあり方
5‐2‐1 社会システムの考え方
基本的な社会の基盤として21世紀の戦略目標としての考え方:
- 価値観の転換(Shift in the Value System)
- 制度の変革(Reform of Institutional System)
- 技術の革新(Innovation of Technology)
の3つがお互いに融合し動的に社会システムをデザインする仕組みが必要であると考える。社会システムを支える基盤を資源(ハード、ソフト)と考えるが、実社会システムとしては、「資源」だけではなくその「マネジメント(ガバナンス)」(資源の育て方、使い方)と表裏一体と考える。例えば、エネルギーを考えると1次エネルギーとしての自然資源と社会システムとして利用する2次エネルギーのようにさまざまに形を変えて利用される。さらに、原油価格の高騰のような状況からバイオ燃料が価格競争力を持つと穀物からの2次利用として利用されると自然資源の利用形態は大きな影響を受ける。これらをすべて指摘利益の追求を目的とした市場原理にまかせることからそれらを総合的にマネジメントしガバナンスに結びつけるシステムの構築が急務である。また、ガバナンスを司るために「情報の非対称性」を防ぐためにもそれらにふさわしいICTをベースとした「情報」を付与する。
- 「天然資源の力」=「資源」× 「マネジメント(ガバナンス)」×「情報」
- 「ストック」としての資源ばかりでなくダイナミックな「フロー」としての資源の概念を考える
- 資源を第1次産業、第2次産業、第3次産業といった利用形態別の視点から産業横断型での社会システムとして考えそのためのシステムの構築を行う。
- 時間軸の考え方の相違を総合的に考えるシステムとする。
- 短期的時間軸 主として経済活動等
- 中期的時間軸 主として生活やコミュニティ活動等
- 長期的時間軸 主として環境や生物学的視点等
(1)実現すべき社会システムの基本方針
これらの基本的考え方を社会システムの基本方針としてまとめると下記のようである。
a.資源のライフ・サイクル・アセスメント(LCA)
ストックとしての考え方とフローとしての考え方の融合
b.資源の可視化
資源は存在や採取するためのさまざまな制約要素や利用の形態によりさまざまである上お互いが、相互に連関しているためマネジメント(ガバナンス)するためにはさまざまな指標の上に可視化出来ることが望ましい。また、価値観の転換(Shift
in the Value System)、制度の変革(Reform of Institutional System)、技術の革新(Innovation
of Technology)などにも柔軟に対応可能なことが肝要である。
c.資源の時間軸とメタモルフォーゼを考えた社会システムの実現
資源の考え方としては時間軸が重要であるが社会システムとしてマネジメント(ガバナンス)を行う場合には、社会の変容に柔軟に対応できるシステムが必要である。
システムの実例として、最新の情報社会におけるTrusted Networkを上げる。
社会基盤としての情報システムをネットワークを中心として考える考え方で
イ)セキュリティ基盤‐安全性
‐盗聴の防止
‐改竄(ざん)の防止
‐反復の防止‐複写データの再利用防止
ロ)アイデンティティ基盤
ハ)サービス基盤‐正確性
‐リライアビリティ(信頼性の確保)
‐トランザクション(一貫性、一意性の確保)
の3つの基盤として考え分散型として動く社会システムを考える。現在の情報システムは、システム毎に、セキュリティとアイデンティティ(原始的なIDとパスワード)及びシステム(アプリケーション)を構築しなくてはならない。このような、すべてが閉じたシステムから分散協調できる仕組み(連携できる)に変わろうとしている。例えば、アイデンティティの基盤としては、次の5Aが重要であるが最初の1つめのAすら実現していない。
‐認証(Authentication) 利用者をユニークに特定するための情報
‐認可(Authorization) 利用者に与えられる権限情報(情報へのアクセス・操作許可)
‐属性(Attribute) 利用者の個人属性(所属、役職など)
‐運営・管理(Administration)
‐追跡・監査(Audit)
このように、社会システムとしてはすべてを一元化したクローズなシステムから他との柔軟な連携・協調を視野に入れた柔軟なシステムが必要である。また、
- 価値観の転換(Shift in the Value System)
- 制度の変革(Reform of Institutional System)
- 技術の革新(Innovation of Technology)
に柔軟に対応可能な短期・中期・長期にわたり持続可能なシステムが必要と考える。
(2)社会システムの基本的な考え方(自然資源の持続型システム)
a.原資源(素材)からリサイクルされるまでをLCAとして実現する社会システムとする。
‐加工、製品、消費、リサイクル
‐環境負荷、経済価値、廃棄物等の情報と連携
b.リサイクルされたときから次のサイクルが開始するが資源の状態が可視化できるようにする。
c.第6次産業と同じように資源+情報+マネジメントシステム(ガバナンス)を実現する。
注:
第6次産業 第1次産業+第2次産業+第3次産業 1+2+3=6 1×2×3=6
農業中心に加工、サービスまで加味したビジネスモデルを意味し生産者(資源)から最終消費まで見えるビジネスモデルに参加する。
d.自然資源を次の4つの観点から考察する(名称は要検討、総合国力参考)
- 「市民生活向上力」、「経済価値創造力」(以上2つが「内なる力」)
- 「国際社会対応力」(「外への力、外からの力」)
- 「資源・環境負荷力」生産力+負荷力 再利用・再生産時の資源・環境負荷も考える
‐注:「市民生活向上力」国民の福祉水準に関わる諸指標を体系化した「社会指標」(social
indicators)と類似した視点
‐「経済価値創造力」 「競争力」(competitiveness)と近い概念 たとえば、World
Competitiveness Yearbookを公表しているIMD(International Institute for Management
Development)によれば、国の「競争力」は「企業が競争力を支える環境を創造し維持する国家の能力」と定義
。ここでは、資源が多様に変容して最終的に再利用されるまでの経済価値を考える。
‐「国際社会対応力」 国際政治学上の「国力」を基礎とした概念であるがステークホルダーとしての国際影響を考慮して資源の位置づけを考える
‐「資源・環境負荷力」生産力+負荷力(社会全体への)再生産+環境負荷をトータルで考慮する。資源とあるのは、一つの資源が利用される場合他の資源に影響を及ぼす(例:加工やエネルギー等の複合要因)ことや再利用される場合を考慮する。
(3)ストック型のシステムとフロー型(持続型、分散強調型)のシステムの融合
ストック型からダイナミックなフロー型のマネジメント(ガバナンス)への移行を社会システムとして導入する。
- 例:魚の採取(資源+ガバナンス(環境・エネルギー))+輸送+加工+廃棄物(処理)ステークホルダー+経済価値+国際社会
- リアルタイムでの天然資源連関(例産業連関図(閉鎖型))を考える(開放型システムとして)
- 資源の時間軸は短期、中期、長期的な視点が必要であり時間軸も考慮したダイナミックな連関システムを考慮
- これらを集中型のシステムとしてではなく分散型(ネットワーク型)のシステムとして考える。
- 各ステークホルダーがその立場と視点から可視化できるシステムが望ましい。(透過型(トランスペアレント))
- 情報を連携するためのシステム(例:XML利用のWebサービス)
例えば、穀物を生産しそのまま食用にする場合は、輸送や加工を考えても有効に活用可能であるが、家畜の飼料として利用する場合には、牛肉で8%、豚肉で15%、鶏肉で25%のリターンしかないといわれる。しかも、これらのリターンの中には、輸送や冷凍・冷蔵などの保存、加工の消費については含まれていない。天然資源の多くはこのように最終消費されるまでにさまざまな変容を遂げたり、加工されたりする場合が多いと考えられ総合的視点が重要となる。実際の消費傾向予測では、2020年までの成長率は1982~94 年成長率の約半分・・・近年の急速な消費量増加と、肉食普及による消費の伸びの飽和が要因であり、途上国での消費量が増加しており全世界の食肉の62%、生乳の60%を途上国が消費している。ただし1人当たり消費量は先進国の方が多い。一方、生産成長率予測では、世界平均:食肉1.8%、生乳1.6%。食肉生産量は消費傾向とほぼ同様に推移している。しかし先進国、途上国別には、下記のようである。
- 先進国:食肉0.7%(豚肉0.4%~鶏肉1.2%)、生乳0.4%
- 途上国:食肉2.7%(牛肉2.6%~鶏肉3.0%)、生乳3.2%
1.社会のソフト化に対応した総合的なシステムの必要性
就業者の3分の2以上、GDPの70%以上が第3次産業に依存している状況とグローバルな協調システムの必要性から持続型社会での資源の多様な利用と最適な利用を考える。
図5‐2‐1は各国GDP産業別寄与率、図5‐2‐2は1人当たりのGDP、図5‐2‐3はGDP当たりの1次エネルギー供給の各国比較である。
1次エネルギーは石油、ガス体エネルギー、石炭、原子力、再生可能エネルギー、水力、地熱などで、2次エネルギーとしては、電力、ガス事業、熱供給、石油製品などである。図5‐2‐3からは、資源の活用の効率性や有効性により社会システムをマネジメント(ガバナンス)して行かなくてならないのとシステムとして考えるときには効率性も考えた共通性のある指標が必要となる(グローバル・ヘクタールのような)。
図5‐2‐4は、参考のため日本の最終エネルギー消費の図である。
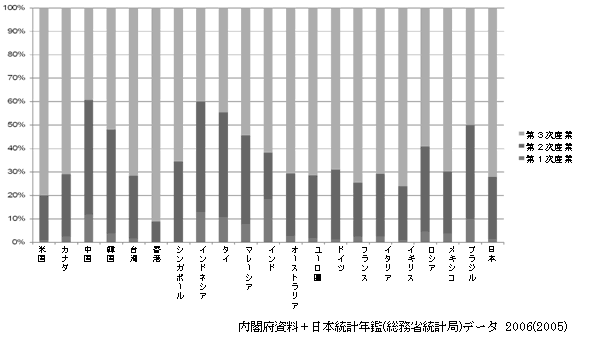
図5‐2‐1 各国GDPの産業別寄与率
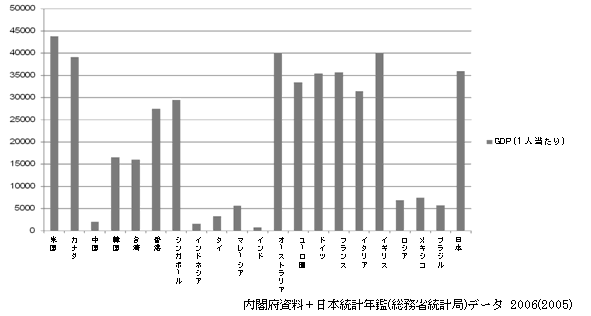
図5‐2‐2 1人当たりのGDP
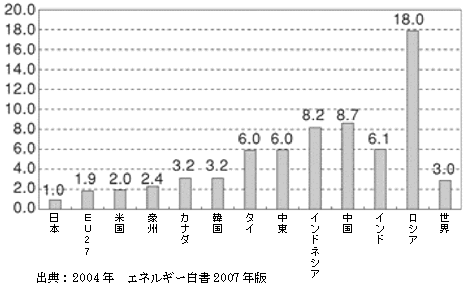
図5‐2‐3 GDP当たりの1次エネルギー供給の各国比較
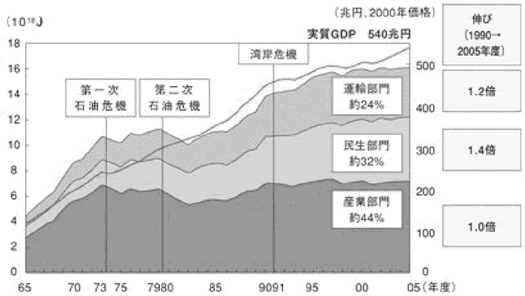
図5‐2‐4 最終エネルギー消費と実質GDPの推移
これらをみると産業部門ではエネルギーの効率的な消費が行われているが、民生部門と運輸部門において大きな伸びを示していることがわかる。自然資源を考えるには、社会システムの中での利用と個々の部門の最適化が必ずしも全体の最適化にならないことに着目して社会システムを考える必要がある。
5‐2‐2 モデルと計測手法と考え方
資源を念頭に置いた社会システムのモデルとして国力を中心とした考え方と、環境指標を中心とした考え方について述べる。
(1)総合力としての国力の概念
1.国力の概念
最近では中国が「総合国力」という用語の下で指標体系を構築し、計測を試みている(浦野,1997)。しかしその構成要素を見ると、NIRA型総合国力とはまったく異なる概念であり、以下の理由からむしろ伝統的国力概念に近いことがわかる。
第1に、「経済力」や「国防力」のほか、「文教力」や「協同力」など多数の分野を網羅しているという点では確かに「総合的」ではあるが、国家の3つの「顔」を総合的に把握しようとするものではなく、「国際国家」の能力という観点に重点を置いて体系化されている。その意味で、おそらく経済企画庁における「総合国力」の研究の延長線上にあると思われる。
第2に、軍事的な要素が重視されている。「国防力」を「直接軍事力」と「間接軍事力」に、前者をさらに「核力量」と「平常力量」に分けた上で、例えば「平常力量」に詳細な検討が加えられている。
以下総合国力の記述は、NIRA型総合国力の研究による。NIRA型総合国力の研究は、少子化により人口が減少することを想定した研究である。
「外交の背景となる国力とは、軍事力、経済力、技術力、文化など様々な要素から成り立つ。・・・(「国力」の再認識)・・・まず第1に拠って立つべきは「技術力」である。さらに、わが国として、世界標準たり得る仕組みやルールを「構想する力」を涵養しなくてはならない。・・・」(外務省,
1999)
「わが国は、科学技術が経済力の増強のみならず国力の維持・強化に不可欠であり、世界の発展を牽引するという認識の下、科学技術基本法の制定以降、特に科学技術の振興に強力に取り組んできたところである。・・・(1)研究基盤の強化による国力の充実
将来の知識の源、国の発展の礎となる基礎研究を更に強化する。・・・」(総合科学技術会議,
2003)
2.伝統的な国力概念
実際、学術研究のレベルでは、「国力」(national power, national capabilities)の概念は国際政治学において発展してきた。伝統的な国力概念は、国際関係をパワーポリティクスと規定し、究極の力である軍事力とその背景をなす地理・人口や経済力を基礎としたものであった。その代表がモーゲンソーによる「国力」概念である。モーゲンソーは、力の資源として、地理、天然資源、工業力、軍備、人口、国民性、国民の士気、外交の質、政府の質を挙げている(Morgenthau,
1948)。
ここで、伝統的な国力概念を計測する試みとして、クラインの国力方程式を見よう(Cline,
1975)。そこでは、国力Pは以下の式で定義される。
P=(C+E+M)×(S+W)
Cは基本要素(人口、領土)、Eは経済力、Mは軍事力、Sが戦略目的、Wが国家意志である。
「人口減少によって我が国の国力が著しく低下する」という懸念は、もし人口が著しく減少するという前提を置けば、クラインの国力方程式から一目瞭然である。一国の経済力がGDPによって端的に測られるとすれば、生産性(1人当たりGDP)を一定とする限り、人口の減少に比例して経済力が低下する。軍事力は現役兵力数や軍事費で測るのが分かりやすい。ここでも、人口に占める兵力数、あるいはGDPに占める軍事費の割合を一定とすれば、人口減少は比例的な軍事力の低下をもたらす。もちろん、一人当たりの生産性や軍事的負担を引き上げれば別だが、それには自ずと限度があるだろう。これに人口減少による直接的な影響を加えれば、領土に係る部分を除きいずれも比例的な国力の低下をもたらす。まさしく「人口が半分に減少すると、国力が半分になる」のである。
伝統的な国力概念は、軍事力を究極の力とし、国内資源がそれを支えるという総力戦の時代に相応しいものであった。だが、相互依存関係の強まった今日の国際社会では後述するようにいわゆる「ソフトパワー」が重要になっており、国際政治学上の国力概念も多様な要素を含むものとなっている。また、現代においては、たとえ軍事力を中心に据えた国力概念を考える場合でさえ、人口そのものに大きな役割を見出すことはない(最近における軍事力中心の国力概念についてはRAND,
2000)。
さらに重要な点として、人口減少の影響を論ずる際に、国力を国際政治学上のそれに限定する必然性がない。こうした問題意識から、以下では21
世紀に相応しい「総合国力」概念を構築し、それをもとに人口減少の影響を検討する。
「国力」とは、国家が、ある目的をたて、それを実際に成し遂げていく能力及びそれにあたっての資源、組織、意志などを指すものと考えられる。」(経済企画庁,
1994, p.109)
これを踏まえ、同報告書では、「国際貢献力」、「基礎的能力」、「対外交渉能力」の3つの側面からなる「総合国力」を考えているが、これはまだ国際政治上の国力を捉えようとしたものであった。
「国の能力」の「3つの側面」を一体として捉えたものを「総合国力」と定義する。
- 「市民生活向上力」:国民1人ひとりが市民社会の一員として豊かな生活を送れるようにする国家の能力。「福祉国家」としての力量を計測する。
- 「経済価値創造力」:企業活動に好ましい環境を与えることを通じて1人ひとりの生活を豊かにする国家の能力。「市場国家」としての力量を計測する。
- 「国際社会対応力」:国際社会において、人類の平和と共生に貢献するとともに、自国民の利益を守るために発揮する国家の能力。「国際国家」としての力量を計測する。
「総合国力」=「市民生活向上力」+「経済価値創造力」+「国際社会対応力」
NIRA型「総合国力」は、その3つの側面が異なる分野の既存概念と重なる部分を持つことから、学際的、包括的な概念である。
「市民生活向上力」には、国民の福祉水準に関わる諸指標を体系化した「社会指標」(social
indicators)と類似した視点がある。
「経済価値創造力」は、いわゆる「競争力」(competitiveness)と近い概念である。たとえば、World
Competitiveness Yearbookを公表しているIMD(International Institute for Management
Development)によれば、国の「競争力」は「企業が競争力を支える環境を創造し維持する国家の能力」と定義されている。
「国際社会対応力」は国際政治学上の「国力」を基礎としたものである。
「総合国力」の主な構成要素の分野としては、「人的資源」、「自然・環境」、「技術」、「経済・産業」、「政府」、「防衛」、「文化」、「社会」が考えられる。上記の「3つの側面」にはそれぞれこうした要素が含まれうる。こうした関係は、以下のように表示すれば理解しやすい。
| 市民生活向上力 | 経済価値創造力 | 国際社会対応力 | |
|---|---|---|---|
| 人的資源 | |||
| 自然・環境 | |||
| … | |||
| 社会 |
これらの分野に分類される要素の一部をグループ化して、「ネットワーク力」、「情報力」、「バイタリティ(活力)」、「モデル提示力・ルール形成力」といった区分(これらは後述の「ソフトパワー」に関連する)を設けることもできる。
このうち「バイタリティ」は特に定義が困難であるが、人口減少がしばしばバイタリティの喪失と結びついて語られることから検討が必要である。そこで、ここではキャンベルの考え方にしたがって整理しよう。すなわち、個人レベルでのバイタリティ=生命力は、「将来の利益のために現時点で犠牲を払うこと」を必然的に伴う。よって、「国のバイタリティ」も何らかの形でこの意味を含むはずである。加えて、これが国家についていえるためには、個人と国家の利益が一致しているとの感覚を必要とする。こうした条件に合致する指標が「バイタリティ」の度合いを示す(Campbell,
1997)。
「モデル提示力・ルール形成力」もわかりにくい概念であるが、これは主として国際政治上の「国力」の一種である「構造的な力」に相当する。「構造的な力」は「関係的な力」と対比され、グローバルな政治経済の構造を形成し決定する力である(Strange,
1988)。
国際国家体制が国際ルールに基づく世界へと移行するにしたがい「構造的な力」の重要度は増す。
ところで「総合国力」の各分野は、「資源」とその「ガバナンス」(資源の育て方、使い方)に分解できる。あるいは、個別の指標について、「資源」と「ガバナンス」のどちらかに分類できる。「資源」と「ガバナンス」の両方が合わさって「能力」が発揮される。
「各分野の国力」=「資源」×「ガバナンス」
人口などは典型的な「資源」であり、容易に増加させることはできない。しかし、人口をどう使うかは工夫次第の面もあり、「資源」に制約がある状況では「ガバナンス」の改善が国力強化の鍵となる。
3.ソフトパワー
国力の要素について、ハードパワーとソフトパワーに区分されることがある。ソフトパワーの提唱者であるナイは、ハードパワーを「強制する力」や「買収する力」、ソフトパワーを「魅了する力」とした(Nye,
2004)。すなわち、「アメとムチ」に相当するものがハードで、そうした誘因なしに相手を自発的に自国にとって望ましい行動に向かわせる力がソフトとされる。この整理によれば、たとえば上記8分野のうち「文化」、「社会」に関する項目の多くはソフトパワーに含まれる。
この場合、ハードかソフトという区分は、量的か質的か、あるいは有形か無形かという区分とは一致しない。古典的なモーゲンソーの国力概念に「国民性」、「国民の士気」などの質的、あるいは無形と考えられる要素が含まれることからも、ナイのいうソフトパワーはこれらの区分とは無縁であることがわかる。そもそも量的か質的か、といった区分は視点によって変化するものであり、分析上の有用性は乏しい。たとえば、「知的水準」は通常は人間の「質」と捉えられるが、知識の「量」と捉えることもできる。「資金」は紙幣の束を想像すれば「有形」であるが、電子マネーを引き合いに出すまでもなく信用力に着目すれば「無形」である。ただし、人口減少についての分析との関係では、力の要素が人口規模に関連するかどうかという区分は重要であり、それをあえて「量的」な力の1つとして考えることは意味があろう。
ところでナイのソフトパワー概念は国際政治上の「国力」の要素を念頭に置いており、NIRA型総合国力指標が捉えようとするものより狭い。「魅了する力」という概念をそのままNIRA型総合国力に持ち込むと無理が生じてしまう。たとえば、「市民生活向上力」において「魅了する力」とは誰を魅了するのか、何のために魅了するのかが明らかではない。むしろ、21世紀に相応しい国力強化戦略を考えるという我々の目的に照らせば、NIRA型総合国力においては「21世紀型ソフトパワー」を定義しておけば足りる。これは、「最近重要度が増してきた力の要素」を意味する。「21
世紀型ソフトパワー」には、当然ながらナイのいう「魅了する力」が含まれるが、それに加えて人的資源の「質」や先端的な技術力も含まれる。
「21世紀型ソフトパワー」は世界共通の概念であり、先進国を中心として多くの国はこの力を強化しようと考えているはずである。しかしどの国にも歴史的に形成された得意分野、不得意分野がある。例えば日本は「環境」「先端技術力」「治安」などに関連したソフトパワーが強いが、国外との「ネットワーク力」や「モデル提示力・ルール制定力」は弱い。このように「21世紀型ソフトパワー」の中で日本が強いものを合わせて「日本型ソフトパワー」と呼ぼう。具体的には、日本が単独3位以上の指標を選ぶことが考えられる。その上で、1つの提案として、「日本型ソフトパワー」の維持・強化に努めつつ、それに関連した分野にも少しずつ幅を広げながら国力を強化していくという戦略が浮かび上がる。
ところで、何が日本の強みか、ということに関して、国内と海外で若干の認識ギャップがある。NIRAのアンケートで相対評価を聞いた項目のうち、「ソフトパワー」あるいはそれに準ずる分野では、国内では日本が弱い(7位)と思われている「情報力」が海外では2位であり、他方、国内では3位とされた「国際貢献力」は、海外では6位であった。最近、日本は資金面のみならず人的にも国際貢献に努力しているが、海外からの価は冷ややかであることがわかる。個別項目では、たとえば「大衆文化・スポーツの魅力」で内外のギャップがある。国内では中程度(5位)と思われているが、海外では8位と極めて評価が低い。アニメやストリート文化に集中投資する戦略は必ずしも賢明とはいえない可能性がある。
次ページから、指標の概要である。すなわち人的資源、自然・環境、技術、経済・産業、政府、防衛、文化、社会の8指標である。
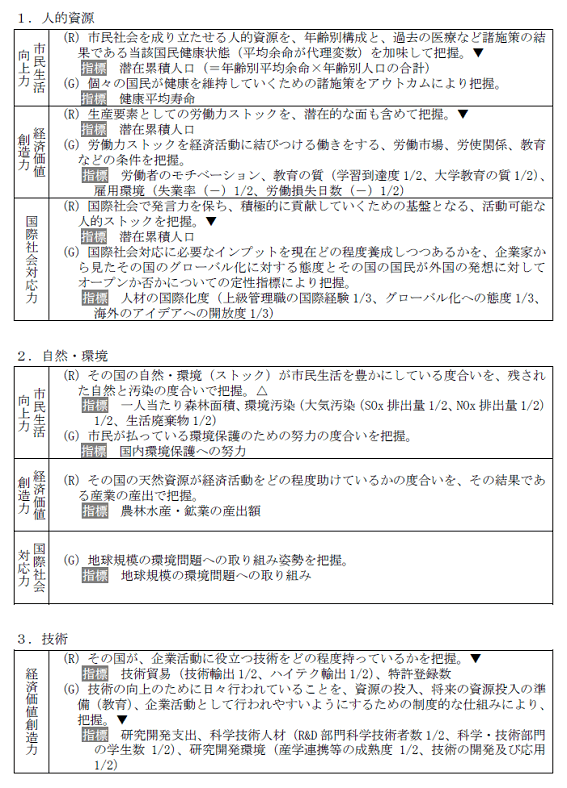
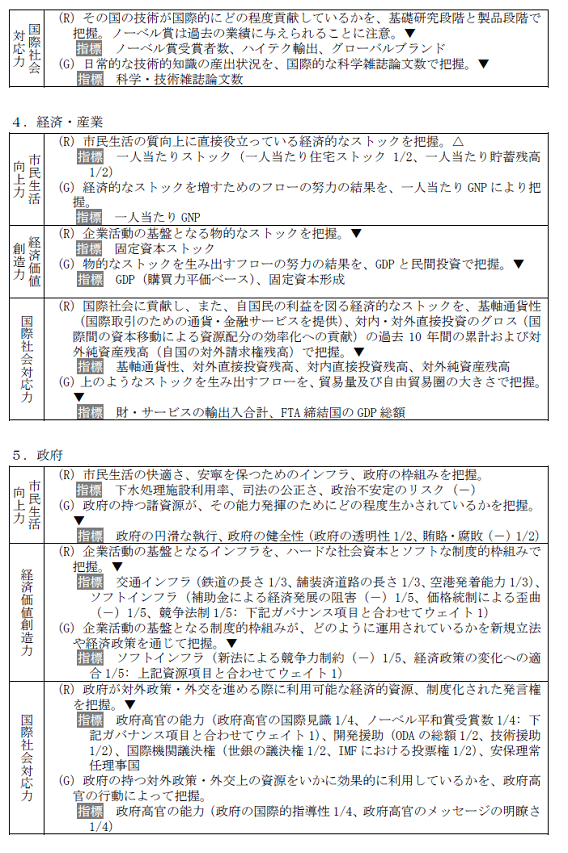
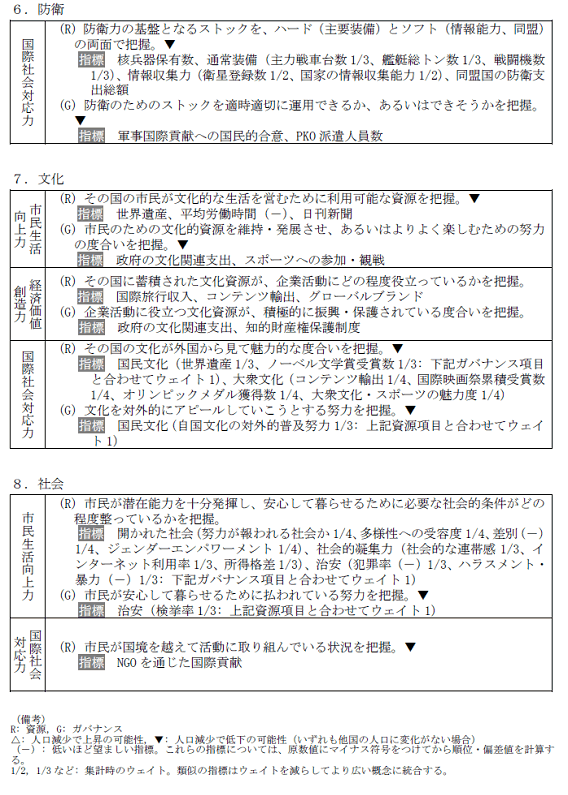
5‐2‐3 自然環境の有限性と公平な分配に着目した指標
(1)自然資源・環境の有限性と公平な分配に着目した指標
環境への負荷を物的な計測単位に投影して、負荷量の持続可能なレベルを算出し、1人当たりの割当量を公平に分配するという試みである。先進国には急進的で受け入れがたい部分もあるが国によって大きく異なることを数量的に示めそうとした点と全地球的な容量に着目したことは評価される。
1.マテリアルフロー勘定(Material Flow Account)ドイツ ヴッバータール研究所
持続型社会を目指して資源環境の有限性を重要視した考え方で経済活動と環境の間の物の流れ(マテリアルフロー)として包括的に捉え様とする考え方である。
自然環境から人間活動への資源の投入量(インプット)
人間活動から自然環境への廃棄物の放出量(アウトプット)
人間活動全体での物資の通過量(スループット)物的なマテリアルフロー勘定(Material
Flow Account、MFA)
投入量には資源が地球から採取され経済活動に投入されるまでの余剰のフローを含める(エコロジカル・リュックサックと呼ばれる)
単位サービス当たりの物質使用量(Material input per unit service MIPS)
(シュミット=ブレークら)単位資源消費量の考え方
経済活動に投入される資源量DMI(Direct Material Input)と隠れたフローの和TMR(Total
Material Requirement)
日本のTMR46トン(1人1年当たりのフロー)でドイツ、米国などと比べてかなり小さい
日本DMI輸入の寄与30%、TMR約50%(1997)
この考え方は、単位資源量当たりの豊かさを4~10倍にすることを目標とし、そのために移動などのエネルギー資源消費量を1/4から1/10にすることにより実現させる。
2.エコロジカルフットプリント分析(Ecological Footprint:EF)カナダ、ブリテッシュコロンビア大リースら
「人間活動の足跡(踏みつけた面積)」の大きさ 資源の供給元及び汚染の吸収源としての緩急をすべて面積に換算し、それにより環境負荷の大きさを測るという考え方である。
エネルギー消費(化石燃料消費に伴って排出される炭酸ガスを固定するために必要な面積)、土地の占有(都市用地など、人工的に改変された土地)、果樹園、耕作地、牧草地、林地を含め、水資源の消費量に応じた海洋の面積等
カナダ人のEF4.3ヘクタール、世界平均 1.8ヘクタール(インド 0.1ヘクタール)
3.エコスペース概念
オランダ 自然環境研究諮問員会(RMNO)、ヴッバータール研究所、地球の友オランダ等の提唱で地球上の資源の1人当たりの利用可能量を算出する。項目は機関毎に異なる
例:化石燃料、淡水資源、非再生可能(鉱物)資源、農地、木材資源の5分野物質、エネルギー、水、土地、土壌の5分野等機関によって項目は異なる。
(2)環境資源指標
環境資源の指標に関する研究及び検討は各国で活発に行われている。
1.環境資源勘定(Environmental and Natural Resource Accounting)
- 国民経済計算体型SNA(System of National Accounts)との関係を考慮
- 貨幣勘定(Monetary Account)と物的勘定(Physical Account)に分ける
- 貨幣勘定 グリーンGNP(GDP)従来の経済勘定から、汚染防止の支出などの環境関連項目の抽出・分離、汚染や資源の消耗、劣化を貨幣価値に換算してGDPから差し引いて修正した指標
- 物的勘定 鉱物、森林、水、土地などの自然資源についてストック(ある時点での埋蔵量や蓄積量)及びフロー(ある期間における消費量や変化量)を物量単位で体系的に記述
2.主要国における指標開発動向
米国:持続可能な発展に関する大統領諮問員会(President's Council on Sustainable
Development:PCSI)、省際作業部会(Inter‐agency working group for indicators
of sustainable development)1997年450の指標から32を選定
イギリス:省際作業部会 1996年報告 重要課題の対象分野を21のグループにまとめた。経済(10)、交通の利用(4)、余暇と旅行(2)、国際貿易(1)、エネルギー(8)、土地利用(9)、水資源(6)、森林(5)、漁業資源(3)、気候変動(4)、オゾン層の減少(4)、酸性沈着(3)、大気汚染(8)、淡水(8)、海水(6)、生物と生息環境(11)、土地被覆と景観(8)、土壌(2)、鉱物の採取(6)、廃棄物(7)、放射能(3)
5‐2‐4 最新事例
(1)(事例1) 生きている地球レポート(2006)
WWF(World Wide Fund)、ZSL(Zoological Society of London)、Global Footprint
Networkが行っているレポートを取り上げる。
世界の生物多様性の変化の状態と、人類による自然資源の消費の結果生じる生物圏への圧力について述べたものであり、2つの指標を中心にまとめられている。
1つ目は地球の生態系の健康度を示す「生きている地球指数(LPI:Living Planet
Index)」、2つ目はこれらの生態系に対する人類の需要の程度を表す 「エコロジカル・フットプリント」である。
WWFインターナショナル事務局長のジェームズ・P・リーブは、このレポートの序文で「フットプリントを大きくしている最大の要因は、エネルギーの生産と利用の方法にある。
エネルギー需要を満たすために化石燃料への依存度が増加し続け、気候変動の原因であるCO2(二酸化炭素)排出量は全世界のフットプリントの実に48%、およそ半分を占めていることが、本レポートには示されている。また本レポートを読むと、人類のフットプリントを減らすには、現在の経済開発モデルの中核に切り込むことが必要であることがわかります。本レポートでは、エコロジカル・フットプリントと、人間開発の度合いを測るものさしとして知られる国連の人間開発指数(HDI:Human
Development Index)を比較し、現在私たちがいわゆる「高度な開発」として認めているものと、世界が目標に掲げる持続可能な開発とは、大きくかけ離れていることを示している。各国は、自国民の生活を向上させる過程で持続可能というゴールを無視して、いわゆる「超過」状態に陥っています。地球が持続できるよりも、はるかに多くの資源を消費している。このままでは、貧しい国々が発展する力、豊かな国々が繁栄を維持する力が出せなくなる。」
1.LPI「生きている地球指数(LPI:Living Planet Index)」
LPIは、地球の生物学的多様性の動向を測るものである。世界中の魚類・両生類・爬虫類・鳥類・哺乳類のうち1313の脊椎動物種の個体数をもとに、陸域・海洋・淡水に生息する生物種別に指数を算出。その3つの指数の平均を求めて、総合的な指数を算出したものがLPIである。
図5‐2‐5は陸域・海洋・淡水の脊椎動物の個体数の変動を示しており、1970年から2003年の間に29パーセント低下したことを示している。
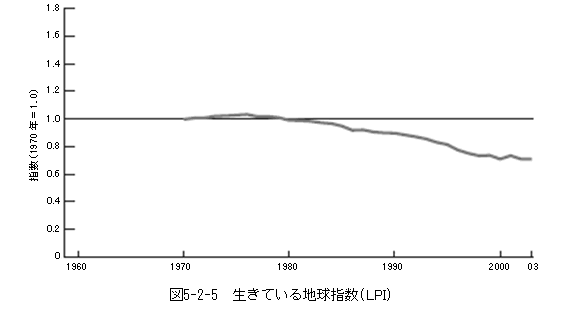
2.取水量
図5‐2‐6は1960年から2000年の間に淡水の使用量は倍増したが、1人当たりの平均使用量は変化していない。世界の取水量のうち、約70パーセントが農業、約20パーセントが工業に利用されている(FAO 2004年、Shiklomanov 1999年)。
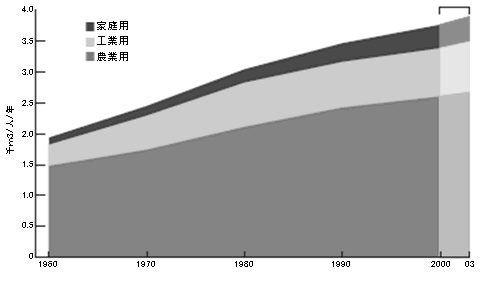
図5‐2‐6 部門別にみる世界の取水量
3.エコロジカルフットプリント
生物圏における生産力が、人間による消費と廃棄物生成のペースに追いつけないと、生物多様性は損なわれる。エコロジカル・フットプリントは、このことを、生態学的な資源やサービス、つまり食料や繊維や木材の供給、建設用地、そして化石燃料の燃焼によって発生するCO2を吸収するために必要な生物学的な生産力のある土地と水域の面積で表すものである。地球の生物生産力は、人類の需要に対応するために利用できる耕作地、牧草地、森林、漁場などを含む、生物学的な生産力のある地域の総面積である。淡水の消費量はエコロジカル・フットプリントとしてではなく、このレポートでは別項目として取り上げている。
図5‐2‐7は人々が生物圏の生産能力をどれくらい消費するかを概算した「人類のエコロジカル・フットプリント」であり、図5‐2‐8は2003年のグローバル・ヘクタールを定数を用いてフットプリントを算出した。

図5‐2‐7 人類のエコロジカル・フットプリント
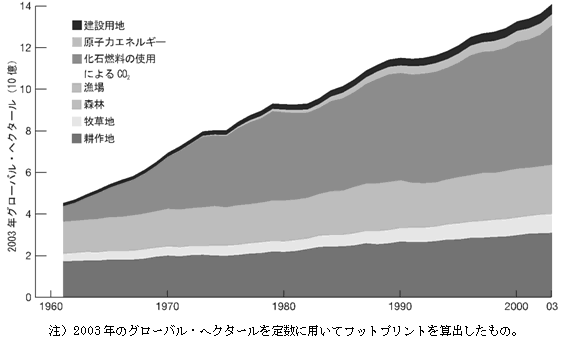
図5‐2‐8 構成要素別にみるエコロジカル・フットプリント
「構成要素別にみるエコロジカル・フットプリント」である。図5‐2‐9は人口100万人でデータが入手可能な国を対象とした「国別にみる1人当たりのエコロジカル・フットプリント(2003年)」である。
さらに表5‐2‐1はフットプリントの総計が大きい国とのデータをまとめた「生態学的な需要と供給」である。表5‐2‐2は陸生・海洋・淡水の各生物種の減少傾向をまとめたものである。
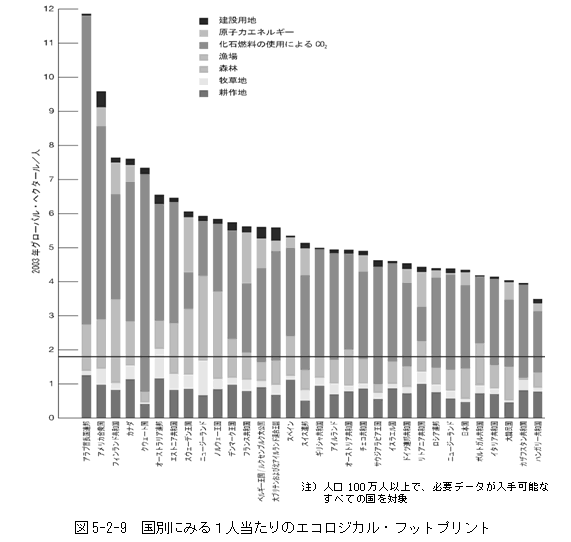
表5‐2‐1 生態学的な需要と供給
| 国\項目 | エコロジカル・ フットプリント 合計 (gha 100 万 ) | 1 人あたりの エコロジカル・ フットプリント (gha/1 人当たり ) | 生物生産力 (gha/1 人当たり ) | 生物学的 余力 / 不足 (-) (gha/1 人当たり) |
|---|---|---|---|---|
| 世界 | 14,073 | 2.2 | 1.8 | -0.4 |
| アメリカ合衆国 | 2,819 | 9.6 | 4.7 | -4.8 |
| 中国 | 2,152 | 1.6 | 0.8 | -0.9 |
| インド | 802 | 0.8 | 0.4 | -0.4 |
| ロシア | 631 | 4.4 | 6.9 | 2.5 |
| 日本 | 556 | 4.4 | 0.7 | -3.6 |
| ブラジル | 383 | 2.1 | 9.9 | 7.8 |
| ドイツ | 375 | 4.5 | 1.7 | -2.8 |
| フランス | 339 | 5.6 | 3.0 | -2.6 |
| イギリス | 333 | 5.6 | 1.6 | -4.0 |
| メキシコ | 265 | 2.6 | 1.7 | -0.9 |
| カナダ | 240 | 7.6 | 14.5 | 6.9 |
| イタリア | 239 | 4.2 | 1.0 | -3.1 |
1 gha (グローバルヘクタール):平均的な生物学的生産力を持つ土地 1 ヘクタールに相当する
表 5-2-2 陸生・海洋・淡水の各生物種の減少傾向
| 陸生・海洋・淡水生物種 | 内容 | |
|---|---|---|
| 陸生生物種 | 温帯及び熱帯陸生生物種の指数 | 1970 年から 2003 年の間に、熱帯陸生生物種の個体数は平均 55 %減少した。温帯陸生生物種の数はほぼ安定している。 |
| 生物群系別にみる生息地の減少 | 1950 年以前に農業に適した土地のほとんどが農地に転換され、それ以降大幅な生息地の消失が起こっていない地中海性混交林と温帯混交林地域を除き、 1950 年以前に生息地の多くを失った生物群系では 1950 年から 1990 年の間も急速に生息地の消失が進んでいる。 | |
| 生物地理界別による農業転換による生息地の消失 | 生息地の消失ペースは熱帯で最大となっている。オーストラリア界では新熱帯界と同じ速さで農地化が進行しているが、 1950 年時点での農地化レベルは比較的低かった。 | |
| 海洋生物種 | 北極海・大西洋及び南極海の指数 | 1970 年から 1998 年の間に、南極海の海洋生物種の個体数は 30 %減少した。一方、北極海・大西洋は全体的に増加傾向にある。 |
| インド洋・東南アジア沿岸海域及び太平洋の指数 | インド洋と東南アジア海域では 1970 年から 2000 年の間に平均 50 %以上が減少した。一方、太平洋の海洋生物種は安定数を維持した。 | |
| 地域的にみるマングローブの面積 | 1990 年から 2000 年の間にアジア地域のマングローブの4分の1が失われた。同じ期間に、南アメリカでは半数近くのマングローブを消失した。 | |
| 淡水生物種 | 温帯及び熱帯地方の淡水生物種の指数 | 1970 年から 2003 年の間に、温帯地方と熱帯地方の淡水生物種の個体数は 30 %減少した。 |
4.人間開発指数HDI
「生態系の支える環境収容力の範囲内で暮らしつつ、人間生活の質を向上させる」(IUCN他1991年)ためには、持続可能な開発が必須である。
持続可能な開発に向けての各国の進捗度は、国連開発計画(UNDP)の人間開発指数(HDI)を豊かさの指標に、フットプリントを地球に対する需要の指標に用いて測ることができる。HDIは平均寿命、識字率、就学率、そして1人当たりの国内総生産(GDP)から算出される。UNDPでは0.8以上のHDIを「高度な人間開発」としている。一方、地球の生物生産力を総人口で割った1.8グローバルヘクタール/人よりもフットプリントが小さければ、地球規模では持続可能なレベルであるといえる。
5.コストの持続可能性
5つの要因が、地球規模の超過の限度、もしくは国にとってはその生態学的赤字を決めることになる。このうち3つの要因がエコロジカル・フットプリント、つまり生物生産力への需要を形作る。その3つの要因とは、人口規模、その人口での1人当たりの平均消費量、そして消費ユニット毎の平均フットプリント強度である。
イ)人 口
人口増加は緩やかになり、最終的には、子どもの数を減らすことを選ぶ家族を支援することで、減少に転じることもできる。女性に対する、より良い教育、経済的機会、保健医療の提供は、有効性が実証された3つの方法である。
ロ)1人当たりの物とサービスの消費量
消費量を削減する可能性は、部分的には個人の経済状況に依存している。最低限かそれ以下の生活を送る人たちが、貧困から抜け出すために消費量を増やす必要がある一方で、より裕福な人たちは消費量を減らしつつ自分たちの生活の質を良くすることができる。
ハ)フットプリント強度
物とサービスを生み出すのに使われる資源の量は、大幅に減少できる。これには、製造現場や家庭において、無駄を最小限に抑え、リサイクルと再利用を増やしてエネルギー効率を上げるということから、低燃費の車や多数の商品の運搬距離を減らすことまで、いろいろな方法がある。産業界は、資源効率と技術革新を促進するという、明確で長期的な政府の政策に、消費者の圧力に対するのと同様に必ず反応する。さらに2つの要因が、生物生産力(供給量)を決定する。それは、生物学的に生産力のある土地の利用可能な面積と、その土地の生産力(生産量)である。
ニ)生物学的に生産力のある土地
生物学的に生産力のある土地は、拡大することができる。注意深い管理により、劣化した土地は再利用できるのである。利益は持続しないかもしれないが、台地の形成は歴史的な成功を収めてきたし、灌漑も限界耕作地の生産性を高めてきた。とりわけ優れた土地管理は、生物学的に生産力のある土地が減少したり、都市化や塩類化、砂漠化によって消失したりしないことを保証するはずだ。
ホ)ヘクタール当たりの生物生産力
ヘクタール当たりの生物生産力は、生態系のタイプとその管理方法の両方に左右される。農業技術は生産性を高めることができるが、生物多様性を減らす可能性もある。エネルギー集約型農業や化学肥料への強い依存は、生産量を増やすかもしれないが、増やした投入量に伴うフットプリントの増大という代償を払いながら、土壌をひどくやせさせ、最終的には収穫量は減り始めることになるだろう。
淡水供給の確保のため、河川流域や湿地帯、分水界を保護し、また健全な森林や漁場を維持することによって、土壌を侵食や劣化から守り、生物生産力を保つことができる。気候変動の影響を抑え、緩和することもまた、収穫量を維持するのに役立つ。生態系を劣化させる恐れのある有害化学物質の使用をやめることも同様である。
6.取水量に関して国別に見る1人当たりの年間取水量
世界には3,500万立方キロメートルの淡水があるが、その70パーセント近くは氷冠であり、約30パーセントは地下水である。残り1パーセント未満の淡水が、地球上の湖、河川、小川、湿地帯を満たしている。毎年約11万立方キロメートルの雨や雪が地上に降り注ぎ、植物がそのほとんどを吸い上げた後で、約4万立方キロメートルの淡水が海へと流れ出る。この流水が世界中の再生可能な淡水資源の総量であり、農業用水、工業用水、家庭用水の供給はすべて最終的にこの流量に依存している。世界の年間取水量は、およそ4,000立方キロメートルで、流量の約10パーセントに相当する。
淡水は地球規模では乏しい資源と考えられていないが、その多くは、地理的に入手することができないか、年間を通して利用することができないものである。人類が容易に入手できる水資源の年間総流量のうち、54パーセントが家庭用水や工業用水、そしてもっとも重要なこととして、灌漑に利用されている。
淡水資源は、世界中で公平に配分されている状況からはほど遠く、多くの国では淡水生態系に負荷をかけずに継続的に利用できる量以上の取水が行われている。広く用いられている水ストレスの指標は、利用可能量と取水量の割合から算出される。
(2)(事例2) EPI(Environmental Performance Index)2008
Yale Center for Environmental Law & Policy Yale
University
Center for International Earth Science Information
Network (CIESIN)
Columbia University
In collaboration with World Economic Forum Geneva,
Switzerland
Joint Research Centre of the European Commission
Ispra , Italy
EPIは、エール大学環境法政策センターを中心としてコロンビア大学、ワールド経済フォーラム、ECの4者が協力をして環境パフォーマンス指標を作成した。最新のデータは、2008年1月末に公表され従来の同種の研究の欠点であったデータの時系列での取り扱いやデータのギャップ、出典などを吟味して指標を策定した。特に
- 人間の健康に与える環境ストレスの減少
- 健全で活力のある環境システムのための天然資源に対する提言
に焦点を合わせている。
特徴的なのは、基本データが公開されていることでデータの出典も明記されている。
全体の構造は、下図のように大きく環境ヘルスとエコシステム活力に分かれている。
日本は、スコアー84.5で21位である(図5‐2‐10参照)。
なお、EPI指標詳細を図5‐2‐11、指標重み、データソース一覧を図5‐2‐12に示した。
これらの内容を見ると日本は環境が人間の健康に及ぼす負荷としての「環境衛生」では疾病が招く環境リスクの低さ、水が招く健康リスクの低さ、大気が招く健康リスクの低さでは3番目の項目がやや低いが高得点をとっている。

図5‐2‐10 EPIランキング
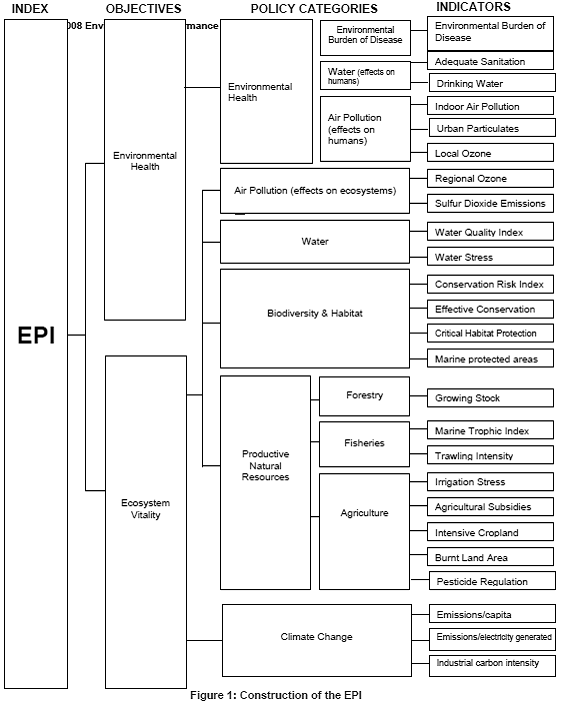
図5‐2‐11 EPI指標詳細
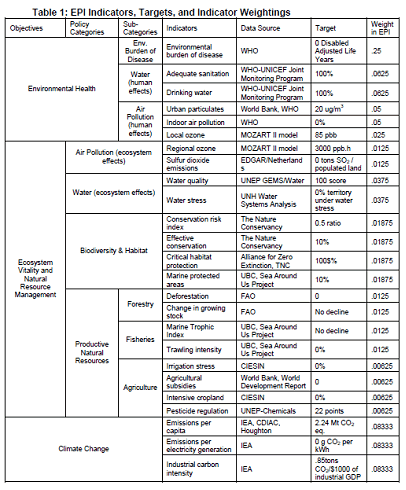
図5‐2‐12 指標重み、データソース一覧
一方、生態系の活性度では「種の多様性・生息地環境」の項目で低いスコアがつけられており、気候変動のスコアがやや低いこととともに総合評価を落としている。
総合点では、米国(39位)はスーダンより下でありオーストラリア(46位)など生態系の点数が低い。一方、中国(105位)やインド(120位)などは生態系の点数が低くOECDの加盟国が上位4分の1に入っているが生態系部門ではばらつきが大きい。上位を占める、北欧の国々は、広大な国土の割に人口密度が低く好条件であるが、環境対策が世論と産業界に浸透している点も見逃せない。人口密度の高い国は、ブルンジが132位であるのにドイツは13位であり人口の過密さが環境負荷に与える影響は大きいが政策や合意形成により乗り越えられないことはないと考えられる。作成者側も記述しているようにランキングが重要ではなく、これまでより優れた政策を選び、限りある資源を有効活用し、さまざまな要因について理解を深めることが重要である。
(3)(事例3) 国連Millennium Ecosystem Assessment 2005年3月
国連Millennium Ecosystem Assessmentでは、下記4つのシナリオに基づき生態系と人間生活について2050年をターゲットとして推計を行った。
1.4つのシナリオを作成。
イ)世界が結束・・・各国が貿易や経済自由化を通し連結。生態系問題には受身の姿勢。貧困・不公正の低減に強い措置をとり、インフラや教育など公共財にも投資。経済成長は4シナリオ中最大、人口増加は最低のシナリオ
ロ)力による秩序・・・安全・保護に関心を置く地域重視の社会。地域市場が最優先で、公共財投資には無関心。生態系問題には受身の姿勢。経済成長は最低(特に途上国では低い)、次第に悪化。人口増加は最大のシナリオ
ハ)モザイク適合・・・地域の流域単位の生態系が政治的・経済的注目を集める。地域機関が強化され地域生態系管理戦略が共通化。生態系管理に積極姿勢。経済成長はやや低いが次第に増加。人口成長は「力による秩序」と同程度のシナリオ
ニ)テクノガーデン・・・地球規模で連携する世界。環境にやさしい技術に大きく依存。生態系は高度に管理・機械化。生態系管理に積極姿勢をとり問題を回避。経済成長は比較的高く上昇傾向。人口成長は他のシナリオの中程度のシナリオ。
その結果下記のような推計結果が得られた。
2.推計結果
イ)生態系の転換・・・21世紀前半に生態系転換が急速に進展
- 10~20%の草原・森林が2050年までに他の利用に転換。農地拡大、都市/インフラ拡大等が要因。
- 生息域や地域固有種の喪失・・・温帯混合林、サバンナ、低木、熱帯雨林、熱帯林で最も進展。生態系転換率は将来シナリオにより変動(特に人口、豊かさ、貿易、技術における変化)。
- すべてのシナリオで、地球環境での生息域喪失は固有種の多様性低下を加速すると予測。その結果、生息域の地域住民が生活できなくなり転出。
- 種の平衡数が減少し、生息域喪失が地球全体での喪失に拡大・・・植物種の平衡数は1970~2050年の生息域喪失により10~15%減少。
- 淡水生物種が急速に減少・・・気候変動、取水過多、富栄養化、酸性化、非固有種の侵入等による複合影響。河川の魚類喪失は熱帯・亜熱帯の貧しい国に集中。
ロ)生態系機能の変化と人間生活
- 人間による生態系機能の利用が大幅に増加。機能が量的・質的に悪化。漁業、乾燥地農業、水質、文化的機能に影響。
- 栄養失調が依然存在・・・栄養失調の子供の割合は「力による秩序」シナリオで10%増加、それ以外のシナリオで10~60%減少。
- 気候変動による淡水資源の変化・・・降雨量増加→洪水頻発や、降雨量減少→水不足(中東や南欧など)。取水量が先進国では減少、アフリカや途上国では増加。
- 環境問題に受身の姿勢をとるシナリオでは、途上国で淡水資源がもたらす機能が悪化。積極姿勢をとるシナリオでも悪化傾向がみられる。
- 魚類・魚加工品の需要増から地域漁業が衰退する危険性が高まる。
- 土地利用変化により生態系のCO2吸収機能に影響。地域によりCO2、CH4フラックスが増加。
- 乾燥地域の生態系・・・変化に脆弱。地域のアダプテーションや保全活動が機能喪失を緩和。
国連Millennium Ecosystem Assessmentでは、2100年までの推計やビジネスに影響する6つの環境リスク(1.水不足、2.気候変動、3.生息域の変化、4.生物多様性の喪失と外来種の侵入、5.海洋漁業の乱獲、6.栄養過多)について、
- ステークホルダーからの圧力
- 企業イメージと環境取り組み
- 原材料の入手可能性
- 事業上の影響・効率
- 新ビジネス創出のチャンス
- 新ビジネスのための新技術
検討を行っている。
参考文献 5‐2節
(1) 内藤正明、加藤三郎編(1998)「持続可能な社会システム」,地球環境学10,岩波書店
総合研究開発機構(2004)「NIRA型総合国力指標」
(2) WWF,Zoological Society of London,Global Footprint Network(2006)“Living
Planet Report”, WWF International,Gland, Switzerland.「生きている地球レポート」
(3) Yale Center for Environmental Law & Policy,Center for International
Earth Science Information Network(CIESIN)(2008)“2008 Environmental Performance
Index”,Yale University,Columbia University.
(4) Millennium Ecosystem Assessment (2005)“Millennium Ecosystem Assessment
Synthesis Report”
お問合せ先
科学技術・学術政策局政策課資源室
-- 登録:平成21年以前 --