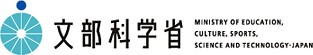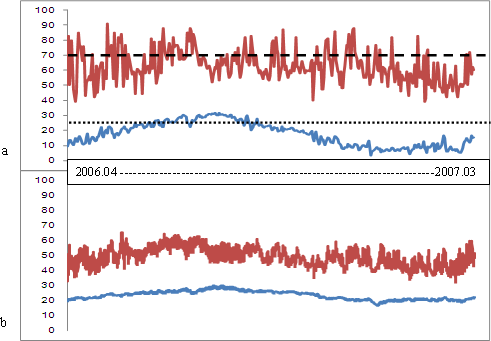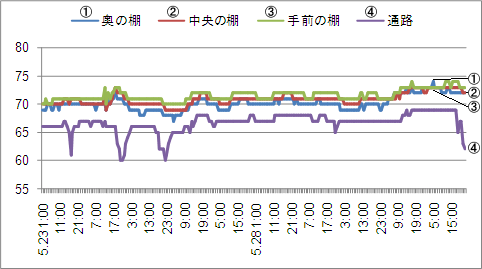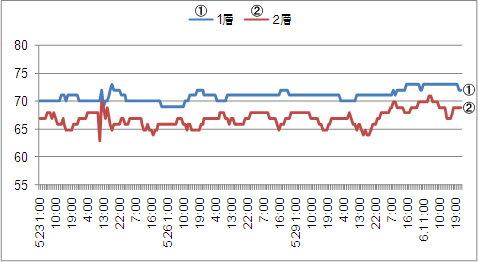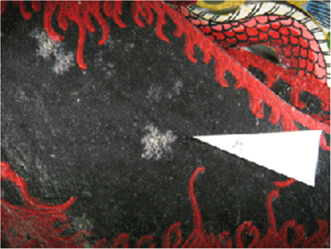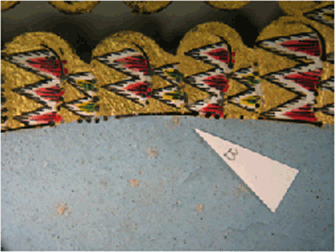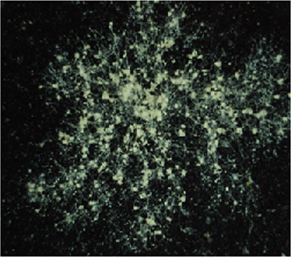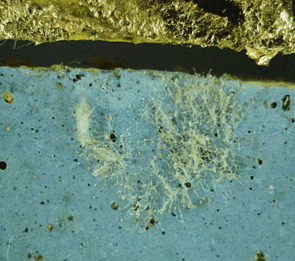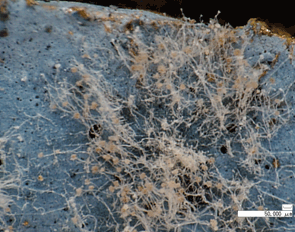1.カビの発生しない環境づくり
博物館や図書館等では、近年、予防保存(Preventive Conservation)の認識が高まっており、問題が発生してから対処するのではなく、被害を生じさせないために日常的に何をしたらいいのかという点に意識が向いてきている。その端的な例が生物被害対策における、総合的有害生物管理(IPM:Integrated Pest Management)(注1)の考え方[木川ほか2003]である。
カビの発生しない環境づくりにおいても、予防保存が基礎となる。そして、そのための活動は単に保存担当の職員だけでなく、館の職員全体が自分のこととして認識することが生物被害を未然に防ぐため、そして、たとえ被害が起きても早期発見で被害を最小限に抑えるためには重要である。被害が拡大してからの対処では、人手も時間も余計にかかることになり、最終的には経費が高くつくことになる。
- (注1)総合的有害生物管理(IPM:Integrated Pest Management)
- 農業の分野から始まり、近年文化財の分野にも広まった生物被害コントロールの方法。化学薬剤だけに頼らず、複数の防除法を合理的に組み合わせることで生物被害をできるだけ回避し、制御する。
1−1 定期的清掃
IPMは、問題を発生させる要因となるものを避ける、取り除くことから始まる。カビの発生しない環境づくりでは、ホコリや汚れをためないことがこれにあたる。日本では、建物内に入るときに靴を脱ぐ習慣があるため、部屋のなかにホコリや汚れを持ち込むことは一般に少ない。しかし、博物館や図書館等には靴のまま入館しているのが現状である。少なくとも収蔵庫や書庫などに立ち入るときは、上履きやスリッパに履き替える、靴カバーをつける、入口に粘着剤付き除塵マットを敷くなどの対策をとると、ホコリや汚れの持ち込みを大幅に減らすことができる。
また定期的に清掃を行うことも重要である。展示室や閲覧室など、ひとの出入りがある空間は、原則として毎日清掃する。資料に直接触ることがなければ清掃業者に委託する選択もあろうが、収蔵庫や書庫においては、その中に収蔵しているものを一番理解している内部職員が清掃を行うことが望ましい。毎日の実践が難しい場合は、週1回、月1回というふうに周期を決めて、忘れずに実行するようにしたい。展示ケース、収蔵棚、書架などの下は、人目につきにくいだけでなく、清掃を業者に委託している場合には清掃対象箇所に入っていないことがあるので注意する。定期清掃の最後に、周辺にある資料への目視点検を習慣づけると、カビの早期発見に役立つ。
基本的には、高いところから低いところに向かって清掃を進めていく。棚の天井面、天井灯のシェード、ダクト上部など上から順に、清掃用ワイパーなどを用いてホコリを取り除いていく。掃除機を使用する際には、HEPAフィルター(注2)付のものにする。掃除機を使用するときには、ノズルを操作して掃除を行うひとと、掃除機本体を持つひとの2人1組で行うと、掃除機本体やコードを資料や棚にぶつけたり、吹き出しの排気を資料に直接あてたりという事故を未然に防ぐことができる。また高所に掃除機をかける場合には、ひとりが掃除機を持ち上げて支えてあげることで、安全に作業ができる。
定期的に清掃を行っていれば、市販の住宅用洗剤などを用いなくても十分に清掃できる。市販品は成分が明記されていても、その濃度や割合までは詳しく表示されていないので、資料のある空間での使用は勧められない。水拭きの必要があるときは、しっかりと絞った雑巾を用い、すぐに乾拭きすることを徹底する。
掃除機や掃除用具は、資料管理の重要度、すなわち空間の汚染度に応じて、使い分けることが望ましい。なお、作業にあたる人は、作業着、ホコリよけの帽子やスカーフ、マスクを着用する。
- (注2)HEPA(High Efficiency Particle Air Filter)フィルター
- 粒径0.3μm(マイクロメートル)の粒子に対して、99.97パーセント以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa(パスカル)以下の性能をもつフィルター(JIS(ジス) Z8122より)
1−2 清浄な空気環境
定期的に清掃を行うことで、室内環境を清浄に保つことが前提となるのはいうまでもないが、外部から汚染物質が入るのを防ぐには、空調ダクト内にHEPAフィルターを設置することも有効である。
室内を清浄に保つには、室外からの塵埃の侵入を避ける必要があり、隣接空間との境の扉については確実に空気が動かない閉まる構造とする。空調が重要な資料を収納する空間は、周囲に対して正圧となるよう送風機等を調整する。
室内の汚染物質の除去には、空気清浄機が有効に働く。空気清浄機は、本体内のファンで空気を吸い込み、フィルターを通して空気中の汚染物質を除去し、きれいになった空気を部屋に戻す役割をする。多くの製品は、まずプレフィルタで比較的大きなゴミやホコリを取り除いている。また、1990年代中頃からHEPAフィルターの使用も一般的になってきた。電気集塵式とよばれる空気清浄機は、放電を利用し、微小なホコリを帯電させたうえで、それを反対の電荷の電極で集塵している。日常の手入れとしては、空気清浄機の吸い込み口周辺はホコリがたまりやすいので掃除機でこまめに吸い取ること、フィルターが目詰まりしないように定期的に清掃したり交換したりすることである。
1−3 温度・湿度のモニタリング
カビの発生しない環境づくりは、対象となる場所の環境を把握し、その特徴を捉えることから始まる。南北に細長い日本列島では、温度や相対湿度は場所によって異なるうえ、四季を通じても変化する。そのため年間を通じた、温度と相対湿度の測定と記録が大切になる。
また単に温度・湿度のモニタリングにとどまるのではなく、定期的にモニタリング結果を、学芸員や司書など資料の管理にあたる人だけでなく、施設を管理する人、空調がある場合にはそれを監視し調整する人、これら異なる部門の人々と共有し、常時、速やかに連絡を取り合う体制を整えておく。そうすれば、たとえ空調機の故障などの緊急事態が発生したとしても、その部屋の立ち入りを全面禁止するなどの処置がすぐに取れるので、最悪の結果は避けられる。
<自記温湿度計>
温度と相対湿度の変化を、継続的に同一紙面上に記録する器械が、自記温湿度計である。記録紙の上半分は相対湿度、下半分は温度を記録するようになっている。記録紙1枚には、ドラムの回転速度を変えることで1日、7日、または31日分(機種によっては3か月、半年、1年分にも対応)の温度と相対湿度を記録することができるが、無人地帯の長期観測ではない限り、7日など短期間周期で使用するのがのぞましい。というのも記録紙交換の際に温度・湿度をチェックすることができ、異常の早期発見につながるからである。記録紙を交換するときには、紙面の底辺がまっすぐ回転ドラムの下辺にあたるように設置し、全体にたるみがないように固定する。
自記温湿度計の設置場所は、空気の流れや直射日光があたる場所はさける。位置としては、資料の周辺環境を測定するのが目的なので、対象物の高さに近いところを選ぶようにするが、あまり低い場所だとホコリがつきやすい。入室したときに目につきやすい場所に設置すると、記録紙交換時以外でも目視点検の機会が増える。
温度の受感部は、熱膨張率がちがう2種類の金属の板をはりあわせたバイメタルでできている。温度が変化すると、熱膨張率の小さな金属のほうに曲がる性質を利用したものである。湿度の受感部には、毛髪が使用されている。大気中の湿度が変化するに従って、毛髪が伸縮する性質を利用している。毛髪部分にホコリがつくと、吸湿され、正確な測定にならないので、清潔に保つようにする。
温度に較べるととくに湿度に測定誤差が出やすいので、定期的に較正を行うことが、正確な測定につながる。自記温湿度計は、記録用のペンを固定してから動かすようにする。また移動後すぐに較正するのではなく、その環境にしばらく慣らしてから行う。較正は、アスマン式通風乾湿球湿度計(注3)を用いると容易に行える。手巻きか乾電池で一定速度の風を湿球に送り、乾球と湿球の温度差を読み取り、附属の表から相対湿度を導き出すようになっている。湿球は、清潔なガーゼを純水または脱イオン水で濡らして包む。測定にあたっては、手の温度や息で測定を狂わせないように、装置の向きに注意するとともに、金属部分には手を触れないようにする。
- (注3)アスマン式通風乾湿球湿度計
- 温度と湿度測定の基準となる計器。2本の温度計のうち1本はそのまま(乾球)、もう1本は感応部をガーゼで包んでしめらせた状態(湿球)とし、一定の速度で風をあてて測定する。温度は乾球から読み取る。湿度は、乾球と湿球の温度との差から求める。
<温度・湿度データロガー(注4)>
温度および湿度を測って記憶するデータロガーの利用は、記憶したデータを直接コンピュータ上でグラフ化できる解析ソフトが充実してきたこともあり、ますます普及している。データロガーは自記温湿度計に較べると小さく、持ち運びも容易であるため、ひとつの部屋内での複数箇所測定、保存箱内などの小さな空間内の測定にも対応できる。
このように便利なデータロガーであるが、その記録は前もって定めた、ある一定間隔ごとに測定した温湿度の「点」の記録であり、全体を通した「線」の記録ではないことに注意したい。ある測定時間と次の測定時間との間で突発的な異変があったとしても、それは記録に残らない。この点に留意した上で、用途に応じて自記温湿度計とデータロガーのいずれを用いるのか、あるいは、併用するのかを決める。
データロガーを使用するときには、年に1回は一箇所に集めて、それぞれの測定値とアスマン式通風乾湿球湿度計での測定を比較してみるとよい。測定値に開きがある場合には、 0.5度、
0.5度、 2パーセントというふうに各データロガーにシール等を貼って記入しておく。わずかの差ならば、温度や湿度の推移を相対的にみるには差し支えはないが、あまり差があるような場合にはメーカーに較正を依頼する。
2パーセントというふうに各データロガーにシール等を貼って記入しておく。わずかの差ならば、温度や湿度の推移を相対的にみるには差し支えはないが、あまり差があるような場合にはメーカーに較正を依頼する。
- (注4)データロガー
- 各種データを計測・保存する計器。ここでは温度と湿度のデータロガーを指す。
1−4 温度・湿度データの記録と解析
<年間の推移>
一般にカビの発生しやすい資料の場合、温度25度のとき、相対湿度が70パーセントだとカビは数か月で繁殖し、75パーセントを越すとその速度は急激に早まり、90パーセントではわずか2日で目に見える程度まで繁殖するといわれている[Michalski2000]。
図1aは、大阪の2006年4月から2007年3月にかけての温度と相対湿度(気象庁データ)の推移である。年間の温度は、春から夏にかけてゆるやかに上昇した後、秋から冬にかけてゆるやかに下がっている。一方、相対湿度は、年間を通じてほぼ60パーセント以上と高い。なかでも6月後半から7月にかけては、温度25度以上、相対湿度70パーセントを超える日々が多く、カビが発生しやすい環境になっている。
一方、図1bは、部屋のなかの温度と相対湿度の推移である(部屋には空調設備はないが、周辺の部屋からの空調の影響を受けている可能性はある)。建物の中では、外気の温湿度の変動が大幅に緩和され、夏季でも数値的にはカビが発生しにくい環境になっている。しかし、これはあくまでも空気の循環の良い場所のことであり、空気が滞留している場所では、局部的に固有の温湿度環境(マイクロクライメート)が形成される。一般に資料の密集している場所は、空調の有無にかかわらず、空気が滞留し湿気がこもりやすく、カビが発生しやすい。
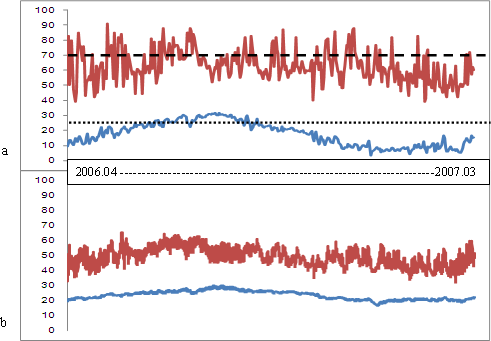
図1 年間(2006年4月〜2007年3月)の温度・湿度の推移
〔a 大阪市(気象庁データより)、b 部屋の内部〕
<マイクロクライメート>
建物の空調は、通常、部屋に何もない状態で設計されている。しかし実際は、部屋の中には棚や書架が配架され、さらにその中には資料が収納されるので、空調の効果が棚の内部まで達しているとは必ずしも限らない。図2は、部屋の中の開架式棚の中央部分と、通路部分での相対湿度を比較したものである。この部屋では棚の位置に関係なく、棚の中央は通路に較べると相対湿度が5パーセント程度高くなっており、開架式にもかかわらず、棚の内部で空気が滞留している傾向が読み取れる。
また、同じ部屋でも測定する地点の高さにより、温度や相対湿度が異なる場合がある。図3は図2と同じ部屋での測定結果であり、積層棚の下側にあたる1層と、上側の2層、それぞれの相対湿度を比較したものである。空調の吹出口と吸込口はすべて天井に集中しているため、空気の還流を考慮し、積層棚の床材は丸孔を開けた構造になっている。温度は1層、2層とも20度と比較的低かったが、相対湿度はこのように1層では常時70パーセント前後と高湿度の状態が続いた時期があった。そのため、2層では異常はなかったのだが、1層の一部でカビの発生がみとめられた事例である。その後、除湿器の数を徐々に増やしながら経過観察を続け、湿度の高い季節には継続的な使用を心がけるとともに、天井に集中していた空調の吹出口の一部を1層まで延ばす工事を行い空気の循環を改良した結果、温度、相対湿度ともに落ち着いた状態になっている。
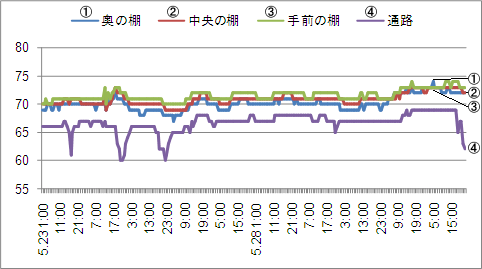
図2 開架式棚内部と通路での相対湿度の違い
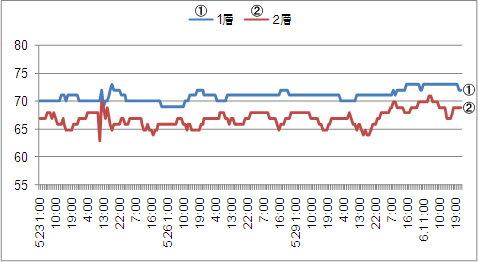
図3 測定地点の高さによる相対湿度の違い
これらの事例でわかるように、温湿度のモニタリングにあたっては、測定地点によって得られるデータが大幅に違ってくる。空調設備のある部屋にはその制御のために温湿度センサーが設置されているが、センサーの設置場所での計測は必ずしもその部屋の現状をあらわしているとは限らず、温湿度の制御が適切に行われていないケースも散見する。一般に、湿気は下にこもりやすいことを念頭に、データロガーを複数箇所の場所及び異なる高さに設置し、その部屋における温湿度の分布をつかむことも必要であろう。その結果、床からどの高さまでは湿気がこもりやすい要注意場所なのかなど、すぐに活用できる情報が自ずとみえてくる。
なお、資料の保管について言及すれば、一般に周辺環境が不安定なところは密閉型の棚や箱を利用すると、周辺環境の急激な温湿度変化をある程度緩和することができる。逆に、周辺の温湿度環境が落ち着いている場合には、開架式の棚、通気性のある紙製などの収納箱を利用すると、資料を安定した環境で保存できる。収納箱の利用は、資料を汚染物質やホコリから守るとともに、資料に直接触る回数を減らす効果があり、推奨できる。ただし、箱にいれてしまうと人の目がとどきにくくなるので、カビ発生などの異常が起きても発見されにくいため、定期的な点検を心がけたい。
1−5 滞留しない空気の流れ
空気が滞留しているかどうかは、同じ部屋の複数箇所の温湿度モニタリング結果を比較すると見えてくる。通常の収蔵庫や書庫内では、微風速計を用いても空気の流れを測るのは困難な場合が多い。というのも、微風速計のそばに人がいるだけで温度が上がり、風が発生してしまい、正確な測定ができなくなるからである。東京文化財研究所では、色のついたビニールひもを手で細かく裂いて棚の縁に配置し、その動きを撮影することを推奨しているが、安価で簡便な手法といえる。
空気の滞留を防ぐには、空気の流れをつくる必要がある。カビが発生していない清浄な環境であれば、扇風機などでゆるやかに風を送るのも効果がある。しかしカビが発生している場所であれば、単に送風するだけではかえってカビの胞子を散らしてしまうことになる。カビの発生源を見つけ出し、そのものを隔離するとともに、周辺の棚などをアルコール消毒した後、カビの胞子を取り除けるHEPAフィルター付の空気清浄機を活用して空気を動かす。
空気が滞留している場所は多くの場合、湿度が高くなっている。効率的に除湿するには、除湿機を長時間稼働させる必要があるが、その場合は、一定の水位に達すると自動的に機械が停止するようになっているか、あるいは、ホースなどを介して既存の排水口につなげられるかなど、回収した水の排水方法を確認しておく。機器がない場合には、単によく乾かした新聞紙を敷くだけでも湿気を吸い取る効果はある程度なら得られる。
展示ケース内など閉じられた空間では、調湿剤の利用も効果がある。適正な使用量は製品によって異なるので、取扱説明書に従って使用する。通常の展示ケースは完全な密閉空間でない場合が多く、調湿剤を使用しても、周辺環境と大幅に異なる湿度を維持することは難しい。調湿剤を入れたから後は何もしないというのではなく、経過観察を怠らないようにする。なお、調湿剤は、なるべく表面面積が広くなるように設置すると効果が上がる。
1−6 資料の点検
カビに限らず、異常の早期発見につながるのが、日常の資料点検である。博物館等では通常、開館前に展示場の巡回点検を行っているが、このときカビや虫害にあいやすい資料の目視点検を平行して行うのも一案である。ただし、資料の内側や裏側など目視点検だけではすまされない箇所は、週1回、月1回など、定期的に時間をかけた点検を行うこととし、むやみに資料に手を触れる回数を増やさないようにする。
収蔵資料の量によっては、悉皆調査による全点定期点検が不可能な場合もある。そのようなときは、少なくとも貸出や閲覧など活用の前後には必ず点検するようにしたい。そして、漆器収蔵庫のように湿度を高めに設定している部屋だけでも、定期的に点検する体制を整えておくことである。なお、貸出にあたって、先方の収蔵環境に関する情報を、施設や設備に関するファシリティーリポートとともに提出してもらうことは欧米の規模の大きな施設では一般化しており、日本でも実施している機関がある。貸出す側と、借用する側の双方が、資料にとって良い環境をどのようにしたらつくれるのかを考える契機となるので、広まってほしい慣習である。
日本では、古来、「曝涼」という習慣があった。温湿度の安定している時期に、資料の点検を行うのであるが、これは被害の早期発見だけでなく、資料周辺の空気を移動させることになるので、空気の滞留しない環境づくりにも一役買っていた。閉切りにしている収蔵庫や書庫では、少なくとも年1回、温湿度の安定している時期に、目通し、風通しの機会を設けることを心がける。
近年、虫トラップを利用した生物生息調査を実施している施設は多い。粘着トラップやフェロモントラップを一定期間設置し、そこに捕獲された虫の種類と数を調べるのだが、調査結果からチャタテムシ目やシミ目の捕獲が多いときは、その周辺にある資料や空間の点検を徹底することを習慣づけると、カビの早期発見につながる。というのも、これらの虫目は高湿度を好むため、カビ発生の指針となるのである。
点検を博物館や図書館等の職員だけの力に頼るのでは、やはり限界が出てこよう。資料の身近にいる案内係や警備員、さらには閲覧者や利用者が異常を発見したときに、その情報をくみ取る体制を整えることも重要である。閲覧や展示は、ある意味で資料点検の好機と捉え、資料に接するすべての人々の力をお借りするという謙虚な姿勢で臨みたい。
2.カビの発見
2−1 目視観察
資料に、直径3〜5ミリメートル程度の白っぽい(写真1a)もしくは色のついた(写真1b)斑点があらわれると、カビの発生を疑うことになる。カビは、集中して表面を被うというよりも、最初はポツポツと間隔をあけて発生する。その形態は、目視だけでも、あまり嵩だかくないもの、フワッとしたふくらみのあるもの、という違いが見て取れる。カビが活発に繁殖しているときには湿っぽさとともに特有の臭いがあるが、斑点状に発生している程度だと、あまり臭いを感じない。
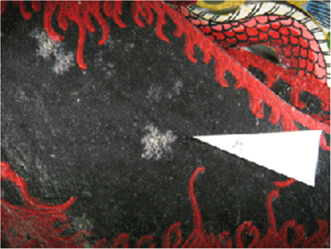
写真1a 影絵人形の表面にみられた白い斑点(直径約7ミリメートル)
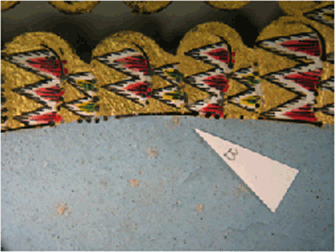
写真1b 影絵人形の表面にみられたベージュ色の斑点(直径約3ミリメートル)
カビの発見にはペンライトのような点光源を使い、斜めから観察すると陰影が生まれ、透明な菌糸体であっても見やすくなる。LED光源の白色または青白色は、透明な菌糸体でもやや吸収されていくらか蛍光発色が生じるため発見には有利である。
2−2 倍率を上げた観察
斑点状に見えたカビを、実体顕微鏡などで拡大してみると、白い糸状の菌糸が放射状に綿のような塊をつくっている。ときには、菌糸の先に色のついた胞子がみられる。目視で白っぽく見えるカビは、ほとんどが菌糸であるか、あるいは胞子の色がうすい(写真2a)。色のついたカビは、胞子の色によるところが大きい。とくに胞子が密集しているところは、全体が盛り上がり、フワッとした形状に見える(写真2b,c)。
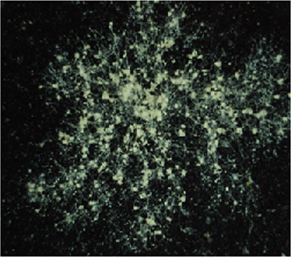
写真2a
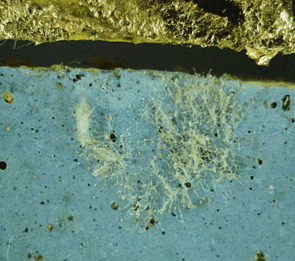
写真2b
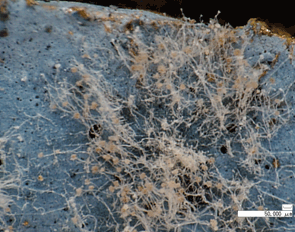
写真2c
2−3 カビと間違いやすい例
カビと間違えやすい事例として、無機塩類の結晶成長であった場合と、樹脂強化処置資料における樹脂成分の結晶化、ダニ等微小動物であった事例がある。
白っぽい物質が付着しているとカビとの判別が難しいことがあるが、倍率を上げて観察すれば、菌糸の有無によりカビがどうかの判定ができる。ときには細い針状の結晶が白いカビのように見える場合がある。このような結晶の大半は水溶性であるため、付着物の一部を採取し、プレパラート上で純水1滴の横にふれさせるようにおいてみる。水溶性の結晶であれば、溶解するのが観察できる。
クモの糸、イガの繭などが付着しているときにも、カビと混同されやすい。カビかどうかが疑われるときは、まず倍率を上げて観察してみることである。
ガラスや陶器など、カビの栄養源とならないような材質であっても、手の汚れやホコリがついていれば、そこからカビが発生することがある。カビであるかどうかを、資料の材質から判断することはできない。
3.カビ発見後の対応
3−1 カビ発生資料の隔離
カビ発生が確認された資料は、被害を広げないために、早急に未発生の資料から隔離する必要がある。隔離とは、カビ発生資料のある空間と健全な資料が存在する空間との空気交換が行われない状態にすることであるが、資料の状況や量、館内の空間的余裕や空間状況によって、対応できる方法は異なってくる。しかし、いずれにせよまず着手しなければならないことは、迅速に空間分離を行うことである。
空間分離のための道具には、カビの胞子を通さない遮断材を用いる。蓋付きのプラスチック容器などが望ましいが、これらが即座に用意できない場合は、厚手(0.1ミリメートル以上)もしくは2〜3枚重ねたポリエチレン袋や、厚手で頑丈なダンボール箱(防水性のあるものが望ましい)など、手近にあるものを応急的に用いて隔離しても構わない。理想的な材を探して時間を費やすよりも、まずは遮断することが先決である。カビ発生資料が動かせない場合や量が多い場合は、未発生資料を別空間に移すことも一方法である。
なお、隔離の際にカビ発生資料を動かすことにより、胞子を飛散させることは避けなければならない。飛散の危険が考えられる場合には、カビ発生資料のまわりから健全な資料を遠ざけた上で、カビ発生資料の上から容器を被せて密閉させる方がよい場合もある。また、資料に触れる場合には、手袋などを用いて直接カビに触れることのないよう注意すべきである。
隔離した後、処置を行うまでの間に配慮すべきことは、資料のカビを不活性化させることと、カビ発生資料の保全のために適切な環境を保持することである。
不活性化とは、カビ発生資料を置く空間の湿度を、カビ胞子が発芽する湿度以下に下げ、これ以上カビが広がらないようにすることを言う。ただし、対象資料は基本的に保存環境に配慮しなければならない文化財であるため、不活性化のために急激に温度・湿度を下げることは適切ではない。また、「別空間」ならどこでもよいわけではなく、少なくとも施錠可能な部屋など、資料の安全性を確保できる空間でなければならない。
また、仮置き期間であっても当然、当該資料に好ましい温湿度を保つ必要がある。しかしながら、容器などの小空間に半ば密閉した状態で湿気を含んだ資料を入れておくと、資料から放出された湿気で空間の湿度が上がる危険性が高い。容器内に調湿剤や和紙など湿気を吸着する性質のものをともに入れておくことにより湿度を制御するとともに、定期的に空間内の温湿度を点検して、異常を察知できる体制を整える必要がある。これら封入の調湿剤や和紙などは、吸湿して機能低下が認められれば、速やかに新しいものに交換すべきである。段ボール箱や紙箱を用いた場合には、箱自身にカビが繁殖する危険性も考えて、観察を行わなければならない。データロガーや示湿紙(簡易な紙製の温湿度計)などを一緒に入れておくと、容器内の湿度の異常が把握しやすくなる。アクリルなどの透明な容器は、ケース外からの資料観察を容易にする点で優れており、点検の際に蓋を開けて容器内の空気が外に出る危険を減らすこともできて便利である。
以上の対応は、あくまでも処置を施すまでの仮のものであり、この状態で長期間放置しておいてよいものではない。一刻も早く処置の方針と方法を決め、処置を施す必要がある。
3−2 カビ発生資料周辺の点検
資料にカビが発生したということは、その空間にカビの胞子が比較的多く存在すること、カビ発生に適合する条件が整っていることを意味する。胞子の観点からすれば、同じ空間にある資料は等しくカビが発生する可能性を持っているため、理想的には、同一空間にある資料は全点点検すべきである。しかし、それが難しい場合には、少なくとも、予測をつけて危険性の高い資料を優先的に点検する。まず、後述する「カビの生える環境となっている場所」にある資料。そして、カビ発生資料と同じ材質の資料や、材質的に湿気を帯びやすい資料などである。そのためには、日頃より各収蔵品の被害分析および予測(各資料がどのような素材で形成されており、その性質上、どのような虫・菌害の危害を被る可能性を持っているか)を行っておくと、それに応じた迅速かつ有効な点検が可能となる。ただし、カビの栄養源にならない素材であっても、付着した汚れやホコリからカビが発生する可能性もあるので、あくまで優先順位上でのことである。
点検方法は、まずは資料の肉眼および顕微鏡などを用いた目視観察である([基礎編]3−2、[実践編]2−1、2)。資料の発するカビ臭もカビ発生予測の参考にはなるが、厳密にはこれだけで判断の材料とすることは難しい。
目視以外の方法としては、カビ発見の直接の手がかりにはならないが、カビ発生空間の各地点における湿度や空中浮遊カビ数の細かいチェックを行い、危険箇所を特定する作業は、今後の発生予防の点からも有効である。部屋の四隅や棚下・棚裏、外壁に面する箇所や空気の滞留しやすい箇所など、管理湿度を逸脱しカビが生えやすい環境になっている地点を割り出して、その付近の資料を重点的にチェックすると共に、環境改善を図ることも重要である。これらの点検については、湿度の細かい測定や、地点を分けての空中浮遊カビ測定([基礎編]3−1、[実践編]1−3、4、5)などが有効である。
3−3 カビ被害状況の把握
カビが生えた場合、まず第一にその緊急度を判断する。被害状況範囲(被害程度と面積)と程度(胞子の有無、着色の範囲など)を記録し、被害状況写真と資料の収納状況、施設平面図などを準備する。同時に、環境条件の把握として温度湿度設定値の確認と計測、滅菌綿棒による付着菌の採取を行い、保存科学の専門家など、カビの処置や環境改善のための相談先に提供する基礎資料・情報を準備する。
資料や作品への微生物被害を目視で判断するのは難しい。コロニーがある程度育っている場合にはルーペでの観察も容易であるが、10〜20倍の拡大鏡があるとたいそう有効である。
3−4 カビ発生原因の解明
資料や作品に対してその後に適切な保存対策を取る上で、出現した微生物の特性を調査し、特質を明らかにすることは重要である。微生物はその限定された空間の環境条件に適したものが著しく繁殖してくるため、その微生物の特質を明らかにし、問題となる環境条件を排除するように対策を取ることが、繰り返しの被害を避けるための第一歩となる。しかし微生物の種類は多様であり、長期保管においては、必ずその環境に適した微生物が生育してくることは避けられないため、最終的にはあらゆる微生物が発生しにくい環境に空間を制御するのが最善である。すなわち相対湿度は60パーセントを超えないように、また空間や資料周りを清浄に保つことが重要である。カビ発生原因は、これらの条件から外れたために起こると考えて良く、水・栄養の供給源を見つけることが発生原因解明の近道である。
<カビの調査>
文化財に被害を及ぼしている原因カビを知るためには、直接、付着カビを採取する必要がある。また滅菌綿棒は乾燥に強いカビを主に採取している点に注意が必要で、乾燥に弱いカビを採取したい場合には湿らせて用いる必要がある場合もある。また菌糸のみを採取して、うまく培養できない事例も多い。逆に、同時に存在する可能性のある塵埃などを一緒に採取すると、例えばハウスダスト中には1グラムあたり 〜
〜 個のカビがあるといわれており、培養するといろんなカビが生育して、被害を及ぼしているカビを判断できない場合もある。
個のカビがあるといわれており、培養するといろんなカビが生育して、被害を及ぼしているカビを判断できない場合もある。
<水の供給源の発見>
周囲に対して低地にある、地下水位が高い、斜面を切り出した整形地にあるなど、もともと施設の立地条件が悪いと、湿気だまりが施設内にできやすい。施設外周を周辺環境から切り離す必要があるため、防湿能力を増強するよう見直す。
周囲の排水が悪く雨水だまりが建物近傍にあると、施設内に湿気だまりができることが多い。まずは、雨水やエアコンの外調機からの排水等を樋で適切に処理するなど、水回り処理を改善する。建物外周の地表面を締めて雨水が地表面を流れて溜まらないようにする、また建物が周囲に対して高い位置になり自然に排水がスムーズになるように改善するなど、周囲の水回り処理に注意する。
外壁を貫通するダクト周囲のパッキングの不備で、施設内で漏水や湿気だまりが生じることがある。扉などについては、可動部に影響が出ない範囲で開口部分を狭めるとともに、清掃頻度を見直すなど人的管理を見直す。開口部分を狭めるための道具として、櫛・ブラシ状のものや、発泡素材で作られたものなどが市販されている。常時可動しなくても良い場所については、シールテープなどで目止めすることも検討すると良い。
外壁等の亀裂からの漏水など、予見しにくく監視しづらい事例もまれに生じる。外周周りに新たに設備(階段など)をボルト等で取り付けるためにあいた穴やひびわれ、屋上の樋の落葉による目詰まりで屋上がプールになった事例、やや大きな揺れの地震の後などに生じた窓周り金物の不整などから漏水が生じ、発見が遅れてカビ被害が発現することも多い。亀裂の発見には床壁等の汚れシミなどを目視で調査する他、温度伝達の差から生じる温度分布を可視化する熱赤外線画像撮影なども応用できる。
<環境制御の不備の発見>
断熱の不整の発見は重要で、例えば窓など、外部からの影響を受けやすい部分は常に湿気がたまりやすく、カビ等被害を受けやすい。隣接する空間があるか外壁かによって外部からの影響は異なり、外壁となっている壁の内側に近接して棚がある、また資料を立てかけたなどの理由で、その場所がカビ被害に見舞われる事例も散見される。隣接する空間の環境制御条件が著しく異なる場合には、空間内に湿度勾配ができることが多い。季節ごとに空間内に温度分布ができていないか、データロガーによる測定や熱赤外線画像撮影などの方法でチェックすると良い。
空調のある施設では環境条件を平均化させやすく、人の入室・作業などの影響をある程度の時間内で解消できるよう設計されている。室内の送風を妨げるような資料の配置などがないかどうか管理する。
空調のない施設では環境条件に分布が生じやすく、おのずとカビ被害が発生しやすい箇所が固定されてくる。人の影響も強く現れる傾向があり、入室人数・時間・作業内容などにも十分に注意して、すみやかに影響が緩和されるように管理方法を常に見直す必要がある。
新鮮外気の導入は、人の入室のある空間では必須であるが、外気には多種多量のカビ等が含まれており、重要な資料の収納されている空間へ新鮮外気を導入する場合には必ずHEPAフィルターを介して供給する。外気を温度調節しないままに供給すると、内外の環境条件の差によっては高湿度となる場所が室内にできる。例えば冬季の外気温は室内より低く、冷気のあたる場所で結露が生じカビ被害を引き起こす。夏季の外気の温度と相対湿度は高く、一般に室内温度の方が低いため、ダクト等送風装置近傍に湿気だまりが生じたり、結露することも多い。新鮮外気はHEPAフィルターで処理すると共に、温度・湿度を調整して室内に供給する。温度湿度を調整できない換気のみのダクトは、内外の環境条件が著しく異なる冬季・夏季にはダンパーで閉めることができるように改善する。
<環境調査>
温度湿度記録は、各室1箇所は計測すべきである。中央など開放的な部分での計測(床からの高さ約120センチメートル)がその室の平均的な状態を示しており、代表値として記録・保管する。環境制御の不備を見つけるためには、室内の2箇所以上で計測する。データロガーを使用する場合には5分に1回以上の計測頻度で、変化を見つけられるようできる限り連続して計測する必要がある。
計測を開始してから1年程度は、各室の代表値と隅で環境条件にどの程度の違いがあるかを見つけるために、各月に1週間程度、1室内の多数箇所で環境計測を行うと良い。隅での計測では環境条件のむらが高さ方向に生じることが多いため、床からの高さ約30センチメートルと約120センチメートルなど、2箇所で計測できると良い。多数の計測が難しい場合には、代表値に加えて、その室内で相対湿度等の影響を受けやすい資料や作品で重要なものが収蔵されている場所の近傍で計測し、その相違について年推移をあらかじめ把握する。
温度分布の不整の発見には、熱赤外線画像撮影を利用すると面的な温度分布が容易に視認できるようになる。微風速の測定は難しく、空気だまりを計測で見つけるのは困難である。給気口と排気口の位置関係から空気の流れを読みとり、その経路上に著しく通風の妨げとなるような作品や資料、棚等を配置しないことが肝要であろう。
カビ被害の早期発見には空中浮遊カビ数の測定も有効であるが、人の作業の影響を受けるため、定期的に始業時に行うなど、計画的に計測監視する必要がある。
3−5 環境整備
施設外周の整備がもっとも重要で、まず始めに施設周囲を目視で点検し、樋・雨水受けの状態、建物近傍に水たまりはないかなど、水周りの始末状況を確認するとともに、ダクト周りの藻類などの汚れの著しい繁殖、扉など開口部まわりの汚れの状況などを確認しつつ、水回りの不備に係わる情報を収集し、すみやかに改善する。
施設内で高湿度となる場所を見つけた場合には、空間全体が高湿度である場合には除湿器を使用する。タンクが満杯になった状態で長時間放置すると、かえってその周囲が高湿度に見舞われるので適切に管理する。1台の除湿器でカバーできる範囲は送風の及ぶ範囲に限られるため、空気の採り入れ口に向かって室内空気を動かせるように送風機と組み合わせると良い。
3−6 カビ発生資料の処理
カビの発生した資料はまず隔離して、被害の拡大防止を図る。コロニーだけではなく胞子が結実した状態では持ち運ぶことによって被害が拡大することが多く、その場で「すみやかに除菌する」のが最良である。一般的に資料は経年劣化を受けて表面形状が複雑である場合が多く、除菌だけでは十分な処置とはならず、環境を改善していかない限りカビ被害が繰り返されることになる。
表面が堅牢な資料の場合には除菌可能であり、その場合には以下のように処置を進める。
- 1)汚染が拡大しないように作業区画を廃棄可能な素材で仕切る。
- 2)記録写真をとる。
- 3)セロテープ等でそっと胞子を散らさないようにサンプリングし、のちに専門家と相談する試料とする。
- 4)吸引できるように掃除機や空気清浄機などを近傍に静かに配置し、アルコールで取り除いて色落ちなどの問題が起きない資料に対しては滅菌綿布や綿棒にアルコールを浸して局部的に取り除く。色落ちの心配がある場合には、吸引できる機器の近傍で、やわらかな筆等ではらう。大気の除湿を進めるとカビの活性が落ちる場合が多くカビが払いやすくなるが、乾燥した胞子が飛散しやすい状態にもなるので、除湿器等で周辺を積極的に除湿する場合には汚染区域の区画化を進め同時に大気清浄化を計画する必要がある。
- 5)顕著な被害状況ではなく除菌(物理的に除去)することを選択した場合には、除去作業をしても大丈夫かどうか、カビの種類を確認するとともに、十分に保護具を備える。病原性のないカビかどうかを第一に確認する。体の弱った状態で起こる日和見感染(注5)にも注意が必要である。カビ胞子は殺菌してもアレルゲンであるので吸入量をできる限り抑制することが必要である。スタッフが普通に出入りする場所や,ほかの文化財が保管されている場所をカビで汚染したりしないよう,作業用のスペースを確保する。殺菌剤は,エタノールも人体毒性があり、その他の薬剤は人体に有害性が高いものが多いので,取り扱いには十分注意する。
ガンマ線照射による殺菌については、あらゆるカビ・バクテリアを殺菌する条件で照射した場合にはセルロース素材の劣化が起こることがわかっており、資料の殺菌に利用する場合には注意が必要である。洪水で多量の資料が被災した場合など、短時間に多量の資料を滅菌する必要がある場合には有効と考えられている。
現在進行中の虫害がある場合には、優先して個体数を減らす処理、忌避処理などをおこなう必要がある。虫はカビをまき散らし、また死骸はカビの栄養分となる。
- (注5)日和見感染
- 通常の健康なからだでは病気を起こさないような病原性の弱い微生物、たとえばカビの一種でも、からだの抵抗力が低下した場合に感染症を引き起こす場合がある。感染経路により肺炎、皮膚炎など、発症部位は多様である。
3−7 用具の廃棄
カビの検査や処置等に使用した用具等を廃棄する場合には、カビ等微生物の取り扱い手順、消毒等に化学薬剤を用いた場合にはその特性に配慮し、法律や地域の条例等に則った手順での廃棄が求められる。
作業中に使用したマスクや手袋など、繰り返し使用するものは、洗濯したのち十分に日光にあてて殺菌消毒する。拭き取り除去したカビ等によりその他の環境を汚染しないように、拭き取りに用いた布等は厚手のポリエチレン袋を二重にした袋に入れ、しっかり口を絞め、すみやかに焼却処分の手配をする。滅菌のためのオートクレーブ(注6)処理ができる事業所等に処理を依頼するのが最善である。
カビの検査のために培養した場合には、人への微生物被害を防止するため、オートクレーブ滅菌処理が必要である。カビの検査については、培養以降の各手順については、微生物取り扱い訓練を受け、専用の施設等を備えた専門検査会社などに委託すること。
使用にあたり、あるいは保管している薬剤について、急性毒性に加えて引火性についても注意が必要である。化学物質安全性データシート(MSDSシート)(注7)を取り寄せて、保管や廃棄上の注意を熟知し、化学物質リスクに対して準備する。また、薬剤廃棄にあたっては廃棄物の処理および清掃に関する法律を遵守して対応する。
- (注6)オートクレーブ
- 高温高圧の飽和水蒸気で微生物を殺滅するために使用する装置。高圧高温の耐圧釜。2気圧、121度、15〜20分の条件で行われることが多い。
- (注7)化学物質等安全データシート
- 化学物質の適切な管理を促進するため、その化学物質の性状および取り扱いに関する情報を事前に提供することを義務づける。MSDS(Material SafetyData Sheet)制度(経済産業省)において提供される安全情報。現在、対象化学物質として計435物質(第一種指定化学物質354物質、第二種指定化学物質81物質)が指定されている。