- 現在位置
- トップ > 政策・審議会 > 政策評価・独立行政法人評価 > 政策評価結果(評価実施年度から探す) > 文部科学省事業評価書-平成23年度新規・拡充事業等- > 1-4.学習者の視点に立った総合的な学び支援及び「新しい公共」の担い手育成プログラム【施策目標2-8、4-1、5-1、6-1】
1-4.学習者の視点に立った総合的な学び支援及び「新しい公共」の担い手育成プログラム【施策目標2-8、4-1、5-1、6-1】
平成23年度「元気な日本復活特別枠」要望額: 133,129百万円
(平成22年度予算額:93,917百万円)
事業開始年度:平成23年度
事業達成年度または定期評価実施年度:平成23年度
主管課(課長名)
高等教育局学生・留学生課(松尾 泰樹)
関係課(課長名)
初等中等教育局高校教育改革PT(袖山 禎之)、初等中等教育局特別支援教育課(千原 由幸)、高等教育局国立大学法人支援課(杉野 剛)、高等教育局私学部私学助成課(小山 竜司)
事業の概要等
1.事業目的
「学習者の視点に立った総合的な学び支援及び「新しい公共」の担い手育成プログラム」
意欲と能力のあるすべての学生・生徒が経済的理由により修学の機会を奪われることのないよう授業料の減免や、奨学金事業の充実を図る。
- 高校生に対する給付型奨学金事業の創設
全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、低所得世帯の生徒に対して授業料以外の教育費負担を軽減するため、給付型奨学金の制度を創設する。 - 学部・大学院段階に応じたきめ細かい支援策
経済的な理由で学業をあきらめることがないよう、無利子奨学金の大幅拡充、授業料減免や学生の経済的支援体制の充実など、大学生等の立場に立った段階に応じたきめ細かい支援を実現する。
2.事業に至る経緯・今までの実績
【高校生に対する給付型奨学金事業の創設】
高等学校については、平成22年度より、いわゆる高校授業料の実質無償化が図られたところであるが、高等学校の学校教育費に占める授業料が公立高校では36万円中12万円、私立高校では78万円中32万円であり、授業料以外にも大きな経済的負担がある。
高等学校における教育に係る経済的負担を軽減して、すべての意志ある生徒が安心して教育を受けられる仕組みの構築が必要である。
なお、特定扶養控除見直しに伴って負担増となる家計についても併せて対応する。
【学部・大学院段階に応じたきめ細かい支援策】
学生の教育費負担軽減策としては、奨学金事業の充実や実質的給付型支援である授業料減免の拡大が必要であり、平成22年度予算においても必要な経費を盛り込んできたところである。
大学生等の立場に立った段階に応じたきめ細かい支援を実現し、意欲と能力のある学生・生徒が経済的理由により修学の機会を奪われることのないよう更なる充実が必要である。
- 無利子奨学金事業の大幅拡大
平成22年度予算においては、奨学金希望者の増加に対応するため、事業費総額で対前年度580億円増の1兆55億円、貸与人員で対前年度3万5千人増の118万人の学生に奨学金の貸与が出来るよう充実を図った。
しかしながら、無利子奨学金の貸与基準を満たしながら貸与を受けられない者が存在しており、その解消や、平均的な学生が貸与を受けられるよう、学力基準を緩和するなど抜本的拡充を図る必要がある。
併せて、優秀な学部学生を対象とした新たな返還免除制度の構築や大学院生の業績優秀者返還免除制度の拡大、大学院生への予約採用方法の見直しを図り、大学生等の立場に立った段階に応じたきめ細かい支援を実現する。 - 授業料減免等の充実
- 国立大学の授業料免除枠の拡大
平成16年度の国立大学の法人化以降、平成21年度までの授業料免除率は5.8パーセントで据え置いていたが、平成22年度予算においては、意欲と能力のある学生が経済状況にかかわらず修学の機会を得られるよう、平成31年度までに、学部・大学院生の15パーセント(全額免除5パーセント、半額免除10パーセント)に授業料減免を実施することを目標として授業料免除率を6.3パーセントに拡大し、これにより、予算上の免除人員は対前年度0.4万人増の約5.5万人となった。(なお、員数は全額免除:半額免除=1:2として推計したもの)
また、平成21年度の授業料免除実施状況を調査したところ、免除実績は283億円となっており、各大学に配分された予算額を超えて授業料減免を実施している。 - 私立大学授業料減免等補助の拡充
平成18年度から私立大学等が行う授業料減免等に対する補助を開始し、平成21年度の実績では、補助対象者数が約2.7万人となっている。平成22年度予算においては、意欲と能力のある学生が経済状況にかかわらず修学の機会を得られるよう予算を倍増(20億円から40億円へ)させ、補助対象者が約3.3万人になることを見込んでいる。
- 国立大学の授業料免除枠の拡大
3.概要
【高校生に対する給付型奨学金事業の創設】
全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、低所得世帯の生徒に対して授業料以外の教育費負担を軽減するため、給付型奨学金を支給する都道府県に対して、所要額を交付する。
【学部・大学院段階に応じたきめ細かい支援策】
経済的な理由で学業をあきらめることがないよう、無利子奨学金の大幅拡充、授業料減免や学生の経済的支援体制の充実など、大学生の立場に立った段階に応じたきめ細かい支援を実現する。
- 無利子奨学金事業の大幅拡大
教育の機会均等の観点から、貸与人員を拡大するなど、奨学金事業を充実し、教育費負担の軽減を図る。特に無利子奨学金について、貸与基準を満たしながら貸与を受けられない者の解消や平均的な学生が貸与を受けられるよう、学力基準を緩和するなど抜本的拡充を図る。 - 授業料減免等の充実
- 国立大学の授業料免除枠の拡大
今後3年間で学部・大学院修士課程に係る授業料減免率を過去最大水準(12.5パーセント)まで段階的に引き上げ、さらに大学院博士課程については国際競争力の一層の強化を図るため、学部・大学院修士課程の2倍(25パーセント)まで引き上げる。
平成23年度の運営費交付金の算定に当たっては、免除率を6.3パーセントから8.4パーセント(学部・大学院修士課程)、12.5パーセント(大学院博士課程)に引き上げる。 - 私立大学授業料減免等補助の拡充
私立の大学等が経済的に修学困難な学生を対象に実施している授業料減免等への支援を拡充する(平成22年度:3.3万人(約1.5パーセント)から、平成23年度:約4.1万人(約2.0パーセント))とともに、学生の経済的負担の軽減のための支援体制を学内に構築している大学等に対する支援を新たに行う。
- 国立大学の授業料免除枠の拡大
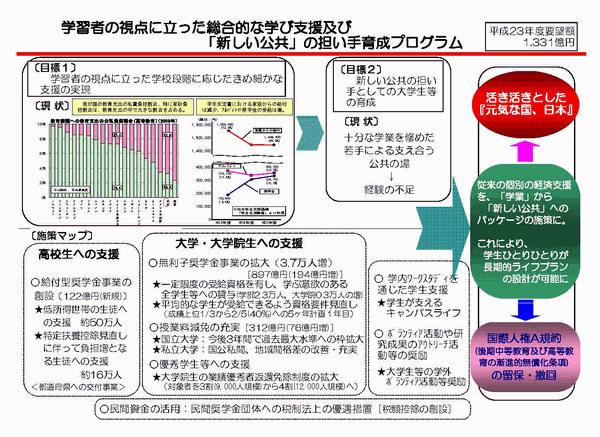
4.指標と目標
【高校生に対する給付型奨学金事業の創設】
指標
都道府県において給付型奨学金が実施され、低所得世帯の生徒等に対しての支援が実施されること。
目標
すべての都道府県において給付型奨学金が実施されること。
【学部・大学院段階に応じたきめ細かい支援策】
無利子奨学金事業の大幅拡大
指標
無利子奨学金の貸与基準を満たす貸与希望者に対する貸与率
目標
無利子奨学金の貸与基準を満たす貸与希望者全員に貸与を行うこと。
授業料減免等の充実
(国立大学の授業料免除枠の拡大)
指標
各国立大学における授業料減免の実施状況
目標
各国立大学において、意欲と能力のある学生が経済状況にかかわらず修学の機会を得られるよう、授業料減免を実施すること。
(私立大学授業料減免等補助の拡充)
指標
- 各私立大学等における授業料減免の実施状況(対象人数)
- 学生の経済的負担軽減体制の整備状況
目標
- 各私立大学等における授業料減免の実施の拡大
- 学生の経済的負担軽減体制の整備
事業の事前評価結果
A.必要性の観点
1.要望パッケージ全体としての必要性
日本国憲法第26条において「すべて国民は、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する」とされており、さらに、教育基本法第4条第3項において「国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない」こととされており、政府が責任をもって積極的かつ確実に取り組むことが必要。
また、新成長戦略においては、質の高い人材層を形成する観点から、学生に対する経済的支援の重要性について指摘がなされている。民主党マニフェストにおいては、「大学生、専門学校制などの希望者全員が受けられる奨学金制度を創設します。また、大学の授業料減免制度を拡充し、教育格差を是正します。」とされているところである。
2.行政・国の関与の必要性
- 高校生に対する給付型奨学金事業の創設
本事業は国から地方自治体への交付金として行うが、地方自治体の単独事業として実施することとした場合、各地方自治体の財政状況や取組姿勢によって地域格差が生じる可能性があることから、国の関与が必要である。 - 学部・大学院段階に応じたきめ細かい支援策
「1.要望パッケージ全体としての必要性」で述べたとおり、「国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない」こととされており、政府が責任をもって積極的かつ確実に取り組むことが必要である。
3.関係する施政方針演説、審議会の答申等
- 新成長戦略(平成22年6月18日閣議決定) 第3章(6)雇用・人材戦略
- 菅総理大臣指示書(平成22年6月8日)
- 高校無償化法案に対する附帯決議(平成22年3月12日(金)衆議院文部科学委員会)2、5
- 平成22年度税制改正大綱(抄)(平成21年12月22日閣議決定)
- 民主党マニフェスト2009、2010
- 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際人権規約(いわゆるA規約)第13条 2 (a)~(c)
B.有効性の観点
目標の達成見込み
高校生に対する給付型奨学金事業の創設は地方公共団体より、その創設について要望等が提出されており、必要性に対する認識を同じくしている。
また、大学生等への総合的な経済支援プログラムの展開については、本事業の実施により、無利子奨学金の貸与人員の増が見込まれるとともに、授業料減免についてもその実施がより一層積極的に行われるものと見込まれる。
C.効率性の観点
1.インプット
【高校生に対する給付型奨学金事業の創設】 12,186百万円
低所得世帯(年収350万円未満)の生徒に対する給付… 対象生徒数:50.3万人、年額:18千円
特定扶養控除見直しに伴って負担増となる生徒に対する給付… 対象生徒数:16.1万人、年額:24~62千円
【大学生等への総合的な経済支援プログラムの展開】
- 無利子奨学金事業の大幅拡大
無利子奨学金の大幅拡大(3.7万人増):89,706百万円 無利子奨学金貸与人数:34.9万人から38.6万人へ(3.7万人増) - 授業料減免等の充実
- 国立大学の授業料免除枠の拡大 25,425百万円
授業料免除枠対象人数:3.7万人から4.8万人へ(1.1万人増) - 私立大学授業料減免等補助の拡充 5,812百万円
授業料減免の充実:3.3万人から4.1万人へ(0.8万人増)
学生の経済的支援体制の構築:667百万円
- 国立大学の授業料免除枠の拡大 25,425百万円
2.アウトプット
教育にかかる負担を軽減し、すべての意欲と能力のある学生・生徒が経済的理由により修学の機会を奪われることなく教育を受けられる仕組みの構築が進展する。
今後の方針及び外部評価・有識者委員からの指摘等
計画のとおり実施していくことが適当。
お問合せ先
大臣官房政策課評価室
-- 登録:平成22年09月 --